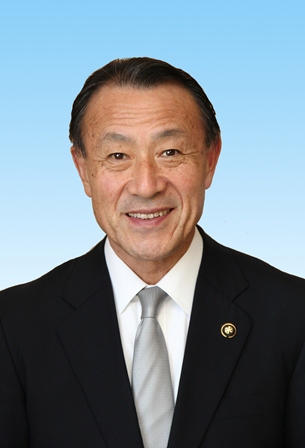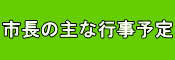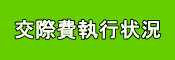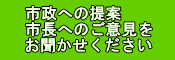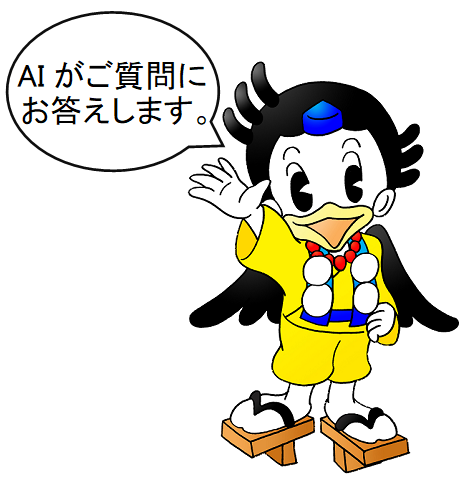市長の部屋 4月号「台湾企業経営者ら60人が市を視察に」「将来の進出をにらんで」 世界的な半導体企業の熊本県への進出に始まり、福岡市には半導体関係の拠点が集積。北九州にも後工程のトップ企業が進出の準備と、台湾からの活発な動きが九州経済をけん引しています。併せるように台湾の中小企業団体が九州進出を目指して、豊前市に台湾ビジネスサービスセンター(TBSC)を開設しました。4月14日には、これを記念する式典に参加するメンバー60人が市に来訪されます。九州への進出をにらんでまず豊前に、という動きです。 拠点となるのは豊前市関係人口交流拠点施設ZigZag2階のサテライトオフィス。そこに設置されたTBSCの事務所に、台湾出身の地域おこし協力隊員の陳沛樺(ちんはいか)さんが勤務しています。陳さんは「日本人でも難しい」といわれる日本語検定N1の資格保持者です。市役所付近で見かけたらみなさん気軽に声をかけてあげてください。 中小企業団体である中華民国全国商業総会は台湾最大の商工団体で、日本商工会議所に相当します。会長は、元国会議員でホテルなどを経営する許舒博(きょしょはく)氏。政治力あるリーダーで、TBSC事業に関して連携する協定書に署名しています。今回は経営者ら総勢60人で、短時間ですが豊前市を視察されます。市内に60人もの来客を受け入れる相応の宿泊施設がないのが残念ですが、同じ台湾資本で30人規模の宿泊施設が近く市内に開業します。 台湾から九州進出に関心をもつ中小企業は多くあるようですが、日本での経営のために商法、会計、労務部門の専門スタッフを個別に雇うのは経費面だけでもハードルが高く、進出は難しいのが現状です。そこで、商業総会で事前に希望する企業の経営内容や経営姿勢などを厳しく審査し、パスした企業だけがTBSC事務局に送られてきます。TBSCは市と協力して進出希望企業の相談に応じて、経営計画書類などを地元の専門家などの協力を得てチェック。入国管理局に経営管理ビザなどの申請や経済産業局、労働局等への届出などを手伝います。 これまで2社が商業総会の内部審査を終え、企業のオーナー、幹部社員などがZigZagを訪問。関心を持つ企業との相談会や企業訪問をしています。このほかにも数社が名乗りを上げており、今回やってくる60人の訪問団からどれだけの企業が進出を具体的に進めるか、注目するところです。 こうした台湾からの企業誘致が具体化してくると、事務所オフィスや工場などの用地がもっと必要になります。合河の旧卵の里に準備を始めた工業団地だけでなく、他の工業団地造成や活用策を地元のみなさんから意見を集めている将来の学校跡地利用も考慮に入れなければなりません。 また、このような企業で働く人たちを、語学も含めて教育する場が求められます。旧築上館跡を改築した後に、人材育成専門の民間企業が入ります。民間の力を借りながら、豊前市の総合力で経済活力源となる企業を迎え入れたいと思っています。これが、市の人口減少に回っている歯車を逆回転させることにつながるはずです。 |
||
過去の市長の部屋 |