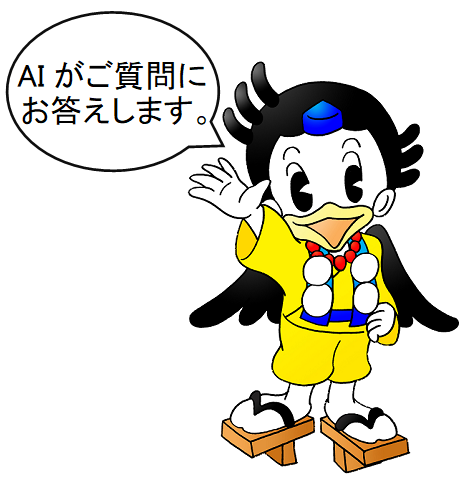友枝 高彦(ともえだ たかひこ)【1876(明治9)~1957(昭和32)】
◆教育者・思想家 類まれな国際感覚で外交に活躍
|
高彦は上毛郡大村(現;豊前市大村)の大庄屋の家に生まれ、豊津中学を経て進んだ第五高等学校(現;熊本大学)で、校長であった嘉納治五郎に感化され「魂の親」として終生敬慕したといいます。その後、東京大学へと進み哲学・倫理学を学びます。 1904年(明治37)には日露戦争開戦にあたり政府からイギリスに派遣された末松謙澄に秘書として随行し、日英同盟という大事なパートナーであるイギリスに日本の正当性をアピールし、併せてヨーロッパの情報収集に当たりました。イギリスに滞在した2年間、高彦は自由主義、民主主義についても学び、このことが後の思想形成に大きな影響を与えます。 1910年(明治43)再び3年間の留学を命じられ、シカゴで社会倫理学をベルリン大学、ライプチヒ大学でドイツ哲学を学び多くの学者とも交流します。 こうした経歴を活かし、帰国後は東京文理科大学の教授となり、多くの学生を指導します。一方でドイツとの国際文化交流に奔走し、ドイツでの講演などに尽力しました。 戦後は社会道徳協会を組織するなどして永年の薀蓄を活かし、社会への還元に尽くしました。幕藩体制という武士以外は様々な権利を否定された時代、常に民衆の側に立ちその苦難を救おうとした友枝家の伝統がこうした生き方に影響していたのかもしれません。 ※末松謙澄は行橋出身のジャーナリスト、後に政治家となった人物です。伊藤博文に重用され中央政界で活躍する傍ら、地元の門司港開発にも尽力します。また、晩年は周防・長門の維新史「防長回天史」の編纂に取り組み、歴史家としての側面も併せ持ちます。
|
|
|
友枝家屋敷地 |
正面から(終戦直後のスケッチ) |
|
※江戸時代の行政区画で友枝手永は現在の豊前市大村周辺にあたります。その記録である「友枝文書」は近世の農村の様子を知る上で貴重な資料として知られます。 |
|