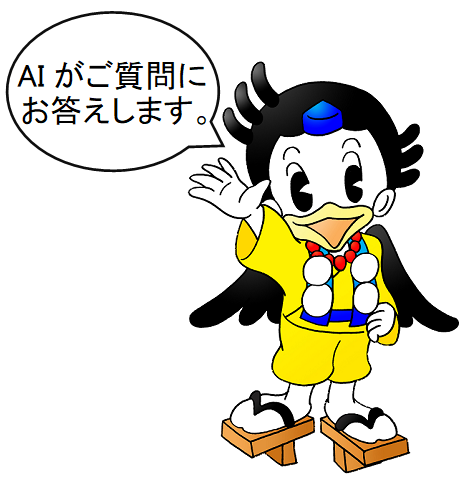議事録(平成22年3月9日)
| 平成22年3月9日(2) 開議 10時00分 ○議長 秋成茂信君 皆さん、おはようございます。 只今の出席議員は14名であります。それでは、これより本日の会議を開きます。 なお、一般質問については、3日間を予定しておりましたが、議運の協議の結果、2日間に変更いたします。 それでは、日程第1 一般質問1日目を行います。順次質問を許可します。 最初に、新世会の質問を行ないます。今本文徳議員、お願いいたします。 ○5番 今本文徳君 おはようございます。今日は、私たち新世会が一番バッターでございます。 野球で言えば、一番バッターの品格の素晴らしい大リーガーの鈴木選手ですね。 イチロー選手でございますので、先鋒でいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 今回、新世会につきましては、私が3点を予定しております。. 1番の品格という問題は、日本の議会の中でも、こういう素晴らしい質問はめったにないと思っておりますので、品格の問題を質問させてください。 2番目が、この市の玄関前にもありますAEDの問題です。3点目が、1週間前に厚労省が出しました公共施設及び飲食店等における完全喫煙の問題の3点でございます。 それから、山崎議員さんから、農山村関係の問題を1時間予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 私は議員になりましてから、市民の代表としまして、主に教育の問題、福祉の問題、心の問題を質問させてもらいました。今回は品格の問題です。非常に難しいですね。 何故、僕が今回、品格の問題を質問する理由は、今年に入ってから新聞等で、大相撲の問題がありましたですね。これは昨年も話したんですが、朝青龍という非常に強い横綱がやめましたね。その理由が、大相撲の場所中に酒をいっぱい飲んで喧嘩したんですね。 その経緯で各新聞社と国民が怒りまして、品格の問題があがってきました。品格ですね 難しいんです。品格、品位の問題。これは私が何時も言いますが、これは道徳の問題とも関係があるわけです。道徳というのは、一生かかって自分の行動を反省していくと言いますかね。品格の問題で横綱はやめたんですね。 また、やめた後が悪いんですよ。ハワイに行って、あの格好で遊び放題ですね。 1億2000万人の日本人を愚弄したんですよ。品格の問題で非常に僕も憤慨しています。 2番目が、またありました。オリンピックで日本の恥ですよ。あの國母選手、あの服装の格好、髪の格好、行動、しかも東海大学生ですね。これが大きく問題になったですね。 品行の問題で。オリンピックというのは、国旗を背負って世界の国の人が集って競うんですよ。しかもユニホームを着てですよ。先頭に団長さんが来まして、世界の皆が見ておるんですよ。あの選手の態度を見てください。僕は涙が出ましたですよ。国会でも問題になったですね。ああいう選手をどうして出したのかという。品格の問題、品行の問題で2点あがってきました。他にもあります。 国会を見てください。ヤジは禁止はされませんが、野党はヤジばかり。恥ずかしいですね。与党はお金の問題、いろんな問題で中身が無いじゃないですか。品格がないんですよ。最低なんです。だから僕は今回、品格の問題を質問します。これは結論はないんです。 ないけれど、お互いに、ここで論議することによって、公の市民に訴え、特に公務員、教職員に対して反省をしてほしいと思っております。私からは言えません。 そこで質問いたします。まず1番に、私は3人に質問します。市長さん、教育長さん、課長さんの代表である総務課長さんですね。まず、品格ということ、私は、釜井市長は素晴らしいと思うんですよ。豊前市はじまって以来の最高の品格を持っておりますね。 そこで釜井市長さんに自分の考え、市長としての品格とはどういうふうなものであるかを、ご答弁してください。お願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今本議員のご質問、ご指摘、特に品格の問題は、主体的な問題、客観的な判断、年齢の問題、そして若い人、中年、お年寄り、いろいろなタイプ、また、微妙ですけれども男性と女性の問題、これもあると思います。その中で、豊前市長としての品格は何だろうかと。 これは3万市民の幸せのために身を挺して、どのくらいやるのか。そして、また今までのことを踏まえ今の今を見、未来をどうするかということが、豊前市長としての品格。 また加えて、今から、地方自治体1つだけではなかなか難しい。いろいろあるけれども、築上郡とどう手を握っていくか。中津、行橋のほうにどう広げていくか、ということも豊前市長としての客観的状況の品格だろうと思います。まず、以上、お答えいたします。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 2番目に教育長さん、お願いします。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重髙岑君 おはようございます。教育の関係から申しますと、人は教育によってつくられると言われております。その教育の成否は、教師にかかっていると言っても過言ではないと思っています。子ども達や保護者はもとより、広く社会から尊敬され信頼される教師でありたいものであります。そのような教師の条件には、様々な要素があると思いますが、大きく要約しますと、次の3つがあろうかと思います。 1つは、教職に対する強い情熱として、教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感、常に学び続ける向上心を持つことが大切であろうと思います。 2つ目には、教育の専門家としての確かな力量として、教師は授業で勝負すると言われますが、子どもの理解力、児童・生徒の指導力、集団指導の力、学級づくりの力、学習指導や授業づくりの力、教材解釈力などがあげられます。 3つ目ですが、総合的な人間力として、教師には、子ども達の人格形成に関わる者として、豊かな社会性や人間性、常識と教養、礼儀作法をはじめ、対人関係能力やコミュニケーション能力などの人格的資質を備えていることが求められていると思います。 私は、教職員の指導をする立場にありまして、今申し上げましたようなことを自らの課題として、日夜精進をしていきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 おはようございます。ご質問にお答え申し上げます。まず、人として公務員としての品格について、どのように考えているかということでありますが、昨今、公務員の不祥事が続いておりまして、ややもすれば法スレスレト言いますか、法にふれたり、法にふれなければ何をしてもいいというような一部風潮がございまして、厳しく市民をはじめ多くの国民から、公務員のあり方について失望を受けております。こういった問題について真摯に反省をしていかなければならない。また、私どもがそういった側にならないように、日々、日常努力していかなければならないのは言うまでもありません。 そこで品格の問題でありますが、今日、日本人の中に謙虚さや礼儀正しさ、或いは、服装の問題等で、ややもすれば何をしても許されるというような風潮があるやに聞き及んでおります。やはり日本の中で長く培われてきました謙虚な気持、或いは、礼儀正しい行動をするということが、まず、品格の中での基本ではなかろうかと思っております。 また、公務員として人として、遵法精神を大切にしていくということも大事であろうと思っております。今日、道徳観が失われ、家庭崩壊や青少年の凶悪犯罪、或いは、親が子を殺す、子が親を殺すといったような犯罪の背景には、日本人の中で培われてきましたこういった謙虚さや法を守っていく精神、或いは、優しさ思いやりといった礼儀正しさというのがなくなっているのが、背景ではなかろうかと考えております。 私どもも、そういった大事にされてきました先達の生き様を十分に生かしながら、日々公務員として、日常の業務に生かしていかなければならないと考えておりますので、今後ともご指導をよろしくお願い申し上げます。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 私から反論はいたします。これは今言ったように非常に客観性で難しいですね。 品格というのは、その人の立場もあるでしょう。市長さんは市長としてのですね。 或いは、総務課長さんは公務員のトップとして、課長として、そのとおりでございます。 私は、品格の勉強を、この半年間ずっと勉強したんです。品格には、内面的な品格と外面的なものがあると思うんです。哲学だから難しいです。内面的なものは、ゆりかごから墓場までずっと行くんです。私はぎゃっと生まれて71歳になりますが、71年間の中に品格が入ってきている。僕はありませんけれどね。 今日は、白いカッターを着ていますよ。意味があるんですね。ファッションでは赤もピンクも着ますよ。しかし公の席で品格を言うときには、自らの姿勢を正しまして、やはり白いカッター。珍しいですね。手も綺麗にしておりますよ。内面的な思考から外面的にいくんですよ。一般市民、我々は外面的なところを判断するんです。ああ、あの人は先生としてマナーが悪いね。言葉遣いが悪いね。言動が悪いね。こうくるんですね。 しかし、人間というのは、内面的なところの品行と外面的なところをいくんですね。 そしてずっと一生かかってできるんです。小学校で指導する道徳と同じです。難しいです。 かのインドのガンジーが言った言葉があります。マイライフイズマイメッセージ、インドの一生、私の一生は私の1年間、一生の間のメッセージを見てくださいと訴えているんですよ。一生かかっていくわけですよ。そして死んだ後に形成していくんです。 学校の先生は死んだら勲章もらえます。よくできましたねと。私はもらえませんけれどね。はっきり言いますけれどね。過去の言動が悪かったから、今は反省しております。 一般の市民が思うのは、外的な面を見るんですよ。あまり言いたくないけれど、よく耳にするんですよ。これは結論はないと思う。ファッションと品行とマナーの問題は難しいから、僕は結論は出しませんが、ここで議論することによって、皆さん達に反省してほしい。まずファッションの問題からいきましょう。 豊前市にはいませんが、私は過去にひげをはやしていました。しかし、学校におる間ははやしていませんでした。辞めてからはやしました。公務員をしておりましたからね。 学校や公務員の職場で鼻ひげをはやしたり、顎ひげをはやしたりするのは、品格の問題でどうであろうかという問題です。日本人の文化から見たときにですよ、その辺が1つ。 それを皆が言うんですよ。ある学校の先生は鼻ひげがはえとる。顎ひげがある。先生おかしくないですか。いや僕はそれは言えません。品格の問題ですからね。その辺について後で、その問題については、これはファッションの問題だから難しいですよ。教職員や公務員の男性が、顎ひげや鼻ひげをはやすのはどうだろうかという問題です。 市民の方々は、やはりちょっと不満を持っています。それから、女性のほうは非常に厚い化粧をしたり、いろいろあるんですよ。そういうファッションの問題ですね。 茶髪はいませんが髪を真っ赤にしたり、金髪にしたりする問題、やはり公務員として、その辺について結論はいりませんが、そういうものがどうであろうかということを、1つ質問したいのですけれどね。今度は、相本課長さんの方から、ファッションと品行の問題について、次に、教育長さんに、お願いします。すみません。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 ご指名ですので、お答えさせて頂きます。個性の問題もあろうかと思いますが、公務員という公の立場では、やはり全体の奉仕者でありまして、市を代表するような、いろんな各界、階層の方々とお会いしなければなりません。対象者に不快感を与えない中庸の精神は肝要と思いますので、相手に不快感を与えないような服装や、清潔感を出していくということは、まず相手に悪い印象を与えないためにも重要ではなかろうかと考えております。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重髙岑君 今、課長さんがおっしゃいましたように、学校の教員であれば保護者、或いは、児童・生徒の前に立って指導していくわけでありますので、ひげをはやすとか、或いは、髪を長くするとか、頭の毛を染めるとかということにつきましては、私は望ましいこととは思っていません。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 私から後は論評いたしません。この品格の問題は、宗教と関係があるんですね。 回教徒が一番厳しいですよ。私は海外旅行しますが、東南アジアに行きますと、男女でも手を組んだら駄目ですね。厳しいんですよ。女性は顔を隠すんですね。浮気したらムチの刑があります。日本の文化は仏教との兼ね合いがありますので、やはり日本人の文化を守るように学校現場でも、是非指導してください。市役所の中でもお願いします。 強制はできませんので、私もそういった意見は言いませんので。 それから、もう1つ、これも言いたくないんですが、たばこを職員が廊下で吸うんですね。昨年ありまして、ある職員がベランダでたばこをのんでいた。ある人が来て議員さん何時かというんですね。どうしたんですかと言ったら、たばこをのんでいるじゃないか。どこですか。グラウンドで吸いよるというんですよ。今勤務時間かと言うもんだから、私は確認しますと言ったんですが、職員がたばこをのむのは反対しませんが、市民が見て、廊下を行きよったんですよ。たばこをのんでいるので怒って、こら、貴様、何しよるかのかと、私に議員さんどうしたんですか、たばこをのんでいるじゃないかと。今勤務時間かどうかと怒られまして、私は後で聞きますと言ったんですけどね。喫煙するときは、やはり市民が見ますと休憩時間か、勤務時間かわからないですね。 市民は勤務中というから、何かいい工夫があれば、休憩中でたばこを吸っていますと分かったほうがいいような気がしますが、出来れば、そうしたほうがマナーの問題でいいような気がします。勿論この問題についても2番で質問しますが、たばこを吸う人たちの配慮を考えて吸う時間を考えてやらないと、市民からすぐ出ますので、何かありましたらお願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 市民からみますと、高い給料を貰いながら、仕事を放棄しているという印象を与えて、不快感を与えるのは事実でありましょう。そういった問題につきましては、所属長連絡調整会議でも論議いたしまして、どのような形で喫煙の問題と仕事の問題をクリアしていくかということについて論議して、近いうちに議会に、どのような対策を考えるかについてご回答できますように努力していきたいと思っております。次回の議会には、きちっとした方向を示していきたいと考えていますので、今暫く時間を頂戴したいと思います。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、私からのお願いですけれども、フロアーに喫煙所を設けていることを、ついでに説明してください。総務課長。 ○総務課長 相本義親君 議長から説明せよということであります。今回、1階のロビーに子供さんや、お年寄りの方もいますし、たばこの煙で害を受ける市民の方もおるということで、完全に密封式の喫煙所を少しコストをかけまして、他の方に煙の害がいかないようにということで、吸う方のみで、強制排気で、外に煙が出せる施設を完備しております。ただ、ここで勤務時間中に職員がたむろすることについて、市民的共感が得られるのかという問題については、今本議員の警告、或いは、市民の警告だと受け止めておりますので、たばこを吸う者達とよく論議して、市の職員としてふさわしい、市民から共感を得るような行動をしていくように論議をしていきたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 この問題で質問しませんが、國母選手の問題のときに、ある団体のトップが言いました。この品格というのは、その自分の仕事、自分の地位、自分の役目に合った服装、行動をするのが、一般的な品格であろうと言いました。私もずっと勉強したんですが、こういうのがあったですね。普通よく使う馬子にも衣装というのがあります。悪い意味でね。 これはいい意味ですよ。馬子にもワンポーという言葉があります。難しいですね。 漢語ですね。馬子にもワンポー、悪い言葉は馬子にも衣装ですね。この馬子にも衣装というのは、やはり、その人の今までの一生懸かってきた今の地位ですね。市長さんであれば、市長さんにあった服を着るのがいいんじゃないかという意味なんですね。 だから市長さんにあった言動をとるのがいいんではなかろうかということです。 そうしますと、さっき言われた課長さんにも私の質問したとおりです。学校の教職員についても、やはり馬子にもワンポーという言葉があるんですよ。1回辞書を見て、是非、指導は難しいと思いますが、今本議員が、こういう質問があったことを言ってください。 そしたら後は自分の判断です。自分で判断できなければ駄目なんです。 僕はそのために今日、ここで質問したので、強制はできませんから。だから、私が鳴らした警鐘を豊前市民に皆に伝えてもらって、各自が反省して素晴らしい豊前市をつくってほしいんです。これで1番の問題を終わります。 2番の問題に入ります。これは非常に大事な問題、また命に関係する問題ですね。 私はよく仕事をするものだから手を怪我してみたりします。今、豊前市の玄関前に赤い機械が入っています。AEDですか、あれがあるんですよ。1週間ぐらい前の新聞を見たんですが、日本中で今15万台入っている。ほとんど利用していないというんです。2.1%、あれ使うのが。聞いたら殆どの市民が知らないですね。なんというんですかということです。電話がかかってきたので、今日、僕はこういう質問しますと言ったら、それは何ですかと言うんですね。 現在、豊前市内では、この機械は何台配置しているのか、担当課長さんお願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 AEDという英語で言いますから、よく分かりにくいと思いますが、自動体外式除細動器というのが日本名の呼び名ですが、不幸にして心臓が停止した場合、この機械を使いますと、心臓がまた動き出すという救急救命のために重要な機械でありまして、豊前市が管理しております市所有の機械が29台。その他に、九州電力やJA福岡豊築、恵光園、病院では重岡さん、或いは、花岡さんという病院が、この機械を持っていると聞いております。この機械の設置場所につきましては、インターネットや、いろんな情報で提供していますが、この他にも、個人で所有している所があるようですが、今のところ問い合わせしても、公開して頂いているのは市が29台、その他、九州電力が2台、JA豊築、恵光園、2医院が設置しているという報告を頂いております。 実数は、これよりもう少し多いのではないかと考えております。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 平成8年から豊前市で29台ありますが、不幸にして、これを使った事例があるかどうかですね。お願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 私ども調査いたしまして、市内でということで限定しますと、昨年1件、この機械を使った事例があります。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 全国でも2.1%ですね。これが一番課題になっているのが、新聞見ても多くの市民が関知してないということです。これを、どういう人達が使えるように人材育成をやっているかという問題が1つと、1年間の点検料、バッテリーというようなのがあって、点検料は高いことを言うんですね。その辺の1年間のコストと言いますか、点検料、交換料あたりの問題と、どういう範囲で、例えば、課長さんは皆な使えるかどうかですね。 私は機械も何も知らないんですよ。僕もあそこで検証したいんですよね。だから現時点で、どういう範囲の人材が、これをマスターしているかどうかという問題と、お金の問題をどうぞ、お願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 まず、どういう者が、この機械を使えるようになっているかと。この機械はしゃべりまして、蓋を開けると使い方を機械が説明します。ただ、そうは言っても、やはり心臓が止まっている人に対して使う機械ですので、機械がしゃべると言っても、一定の講習がないと、なかなか使いづらいだろうということで、今のところ、市の職員は強制的に嘱託を含めて、市役所に勤務する場合は、2年から3年に1回は、この機械の使い方の講習を受けるようにしておりまして、私も3回受けております。 職員については、1名も受けてない者はいません。消防団については、2年に1回、必ず義務付けをしております。その他に、どういう広がりを見せているかについての関心があるのではなかろうかと思いますが、大体、広域消防が講習をやっておりまして、年間少ない年で320名ぐらい、多い年では500名ぐらい毎年、希望者に対して講習を京築広域圏消防本部が責任をもってしております。 学校の教職員等についても機械が配置されておりますので、関心を持っていただいておりまして、この機械の使い方について、講習会を開いていると聞いておりまして、かなりの市民が、毎年この講習を受けていただいて、使えるように日々の訓練をしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 それから、コストの問題でありますが、この機械は、電池と、パット電極のものを貼るわけですが、一度使いますと消耗品ですから、交換しなければなりませんが、メーカーによって違いがありますが、大体1万5000円ぐらいで、電池の寿命については2年ぐらいで交換しなさいと。もっと長いものもあるようですが、目安としては2年。 それから、AEDの機械については、メーカー保証が5年間で、その間にトラブルがあればメーカーが責任を持ちます、という補償がついていることも付け加えたいと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 機械があっても利用しないほうがいいのはいいとは思います。特に高齢化が進んでおりますから、一般市民にも是非こういうものがあることを、もう1回公開してほしいと思っております。言葉が難しいですね。英語ばかりで、もうちょっと簡単な言葉があればいいと思いますが、知らない人たちが聞いたらなんですかという事柄ですね。 これを使用していて事故があっても刑事罰にならないわけで、保証が入っておりますからね。それを使っていて失敗しても刑事罰には対処しないとなっていますから、是非、活用しないように、一生懸命頑張りたいと思っておりますが、万が一の場合は活用できるようには是非しておいてください。やはり命は大事ですからね。 その次の問題も難しい問題です。私はたばこは吸わないですよ。昭和52年にやめました。それまでは毎晩、机に座っていて40本、50本吸いよったですよ。その代わり朝の1時、2時まで机に座っていますから、手が真っ黒やったですね。風邪を引いて、それからたばこやめたんです。そうしますと、海外旅行に行っても、たばこの煙が入ったら死のうごとあります。受動喫煙とか言うんですけれどね。 質問したいのは、1週間前ぐらいに厚労省が出した要請文の内容、公共施設や飲食店等においては、すべて禁煙せよという内容について、どういう内容だったのか。それを受けて、市はどういうことを考えているのか、ご答弁ください。担当課長さんお願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 公共施設における完全禁煙について、厚労省から健康局長の通達で、2月25日付で文書をいただいております。今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。 全面禁煙を行っている場所では、その主旨を表示し、周知を図るとともに、来客者等にも理解と協力を求めるなどの対応をとる必要がある。また、少なくとも、官公庁や医療施設においては、全面禁煙をすることとなっています。また、特に屋外であっても、子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である、とこのような指導をいただいております。 今後、豊前市もこの通達を受けて、どのような対応を取るかというご質問ですが、今後全面禁煙をするべき施設、或いは、区域を明確に市民に分かりやすく説明する必要があると思っておりますので、どの施設をどのようにしていくかについて明確にしていきたいというのが、1点でございます。 それから、受動喫煙による健康への悪影響等の情報を提供していく必要があろうかと思っております。市民の中では、こういった問題について、十分に正しい理解のない方もおられると思いますので、こういった問題の情報提供を市がしていく必要があろうと。 教育委員会とも連携しまして、健康教育、喫煙防止教育を今後、積極的に取り組んでいく必要があると考えております。完全禁煙については、すみやかに行動に移す必要があろうと考えておりまして、実施計画をつくりまして、議員の皆さんのご意見も頂戴しながら国の指導を受けて、市内でどうするかということについての方針を、早急に確立していきたいと考えております。 ちなみに、全施設禁煙ということで、公共施設は、原則的に室内では吸わないようにということでしているわけでありますが、今のところ、一部の施設で市民の利便性のためにロビー等で吸うような施設もありますので、こういった問題は、個別にどのようにクリアしていくのかについて明らかにしていきたいと考えております。 今暫く時間を頂戴したいと思います。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 今、質問しましたが、受動喫煙による健康の害はどういうのがあるか。これを福祉担当の課長さんに、もしご理解があれば、お願いします。 ○議長 秋成茂信君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 厚労省の文書による受動喫煙による健康被害ですが、呼吸の問題、心拍の増加、血管の収縮等に関する治験が示されるとなっておりまして、慢性影響として、肺がんや循環器系の疾患、発がん性の分類において、たばこは最も発がんを誘発する原因の1つである、と厚労省から示されております。また、低体重児の出産の発生、要するに、子どもさんが余り大きく育たないという問題もあるという研究報告をいただいております。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 たばこを吸いますと、がんになるのは自分の責任ですけれどね。周りが非常に困るわけなんですね。周りの人達の20~30%が肺がんになってしまう。心臓病になるんですね。心臓病になると、大体、半分が肺がんになってくるんですね。狭心症の人とか、心臓病の人たちは、大体肺がんが多いですね。悪循環するんですね。たばこの影響は非常に多いと思うんですよ。脳梗塞とかですね。私が言いたいのは、やはり、たばこをやめますと自分も長生きします。周りの人も長生きします。そして国民保険料が安くなるんですよ。 そこもあります。これは是非やってくださいよ。 そのためには、できないかも分かりませんが、自分の案ですよ。来年度から職員を採用するときの条件として、たばこ吸う人は採用しないと、市長どうですか。これもアイディアですよ。いいことはやらなきゃ駄目ですよ。どうですか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 ほかは明快ですけれど、なかなかこれは難しいですね。私は全く吸いませんが、子どもはものすごく吸います。健康の問題を含めまして、日頃は答弁は明快ですが、ちょっとこらえてください。 ○議長 秋成茂信君 今本議員。 ○5番 今本文徳君 日本では、5~6年ぐらい前に神奈川県が実施しておりますね。県知事がかわりましたがね。県知事さんが、アイデアをもった人がかわりますとできるんですよね。 皆賛成しておるんですよね。住民も賛成しているんですよ。だから是非、豊前市も、たばこを皆吸わない町で、国民保険が安くなる町にね。 それから、台湾に行っても、たばこは全部禁煙ですよ。日本は条例が甘いんですよ。 外国は罰金でもって押えている。日本人は品格、品性があるから罰金をしないんですよ。台湾にいきますと、飲み屋に行って、たばこ吸いよったら密告される。飲み屋さんも営業停止ですよ。住民の我々も罰金が来るんですよ。それはよくないかも分かりません。 外国でマナーが守れるのは、罰金ということがあるから本当はよくないですね。 そういう国は、民主国家ではありませんが、我々は皆長生きするために、たばこを吸わないように是非してほしいと思っておりますので、私は今回も教育問題、これずっと品格に関係あるんですね。2番目に言った事柄も、即3番目のたばこの問題とか、そういうところがすべて品格が関係してきておりますから、私は、これからも教育の問題、福祉の問題に視点を置きながらしようと思っております。小さなことは勉強しておりませんので、いろんな問題を勉強しておりませんから質問できません。しかし福祉の問題、教育の問題につきましても、経験と実践もいっぱい持っております。そういう問題で、また質問しようと思っております。今日した事柄はすべて結論は出ませんが、一番大事な問題ですから、心に銘じて、そして肝に銘じて、一生懸命実現するようにしてほしいと思っております。 これで私の質問を終わります。 ○議長 秋成茂信君 次に、山崎美議員。 ○7番 山崎美君 おはようございます。2番目のバッターとして、今日は、政権が8月の衆議院選挙で民主党にかわりまして、9月16日から新政権のもとで、いろんなマニフェストに載った取り組みを掲げて、今いろいろな問題が出てきております。その中で、今日は、六次産業化という言葉が最近、よく新聞、テレビ等で報道されております。 その中身について、まだ私も現実は読みきっておりません。このくらいの資料があるんですね。多分、担当課長も市長も、これはまだ読まれてないだろう。私も全部は見ておりませんが、この中に則って、今まで、私が農業問題に取り組んできた流れの中と、新しい今度の六次産業化の農業問題、特に農業、林業、漁業、農業委員会についての質問を時間の許す限り、今本議員が私のために早く終わって、長く取っていただいたということでありがたく思っております。 まず、新しい政権の中で、特に、事業仕分け、見直しが、当初からテレビ等で報道されております。その中で、まず一番にお聞きしたいのが、各地方自治体、事業を何ヵ年計画ということで組んでおると思います。その中で事業仕分け見直しで、特に、農業関連に関係する影響する事業が多分あるだろうと思っております。他の部署もあるだろうと思いますが、計画に則った中で事業を計画した中で、影響ある事業があれば教えていただきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 ご質問にお答えします。影響する事業につきましては、本市で取り組んでいます農業関連事業での仕分けで、4事業が対象となりました。第1として、転作助成金として受けていました産地確立交付金、水田等有効活用促進交付金、需要即応型水田農業確立推進事業等が廃止となりましたが、平成22年度から、新たに増設されます戸別所得補償モデル対策へと移行したため影響はないと思われます。 本事業は、自給率向上のために水田の作物を生産する農業者へ、主食米と同等の所得を確保する対策として、自給率向上事業と農家の恒久的赤字に陥っているコメに対して補填する対策として、コメのモデル事業、コメ戸別所得補償モデルとなっています。 本制度への対応は新規事業であり、農家に対して個別相談会を開き、助成金が有利に受けられるように指導・対応したいと考えております。 次に、中山間地域等直接支払制度と、農地・水・環境保全向上対策は継続されることになりましたが、双方の市町村に対する事務費が削減となります。また、農地・水・保全対策は、事業の1割程度の削減となります。対応は、農家の組織に対する活動内容を精査しながら影響が出ないように指導したいと考えております。 次に、農地有効利用支援整備事業は、200万円以下の小規模の工事が対象となっていましたが、これは廃止されました。本市では、小規模な事業に対して、補助金が受けられると計画的に事業実施を予定していましたが、廃止されることとなり、事業の遅延が懸念されます。 以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 当然、この事業は新しく入ってくる事業、それから継続的な事業、大きく言いますと、農道の整備事業、それから、里山のエリア事業、それから、耕作放棄地再生事業緊急対策とか、鳥獣害の対策が、国から地方へということになっております。そういうものは全く影響はないですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 まず、1点目の広域農道につきましては、現在、京築広域農道アグリラインを計画しておりますが、本市については完成しておりますので、完成的な農道については、影響はないと考えております。 それから、農地有効利用の問題については、新しく今年1月より党から連絡がありましたところによりますと、協議会をつくって、そこで利用者に対する助成金をということにつきましては、私ども農林水産課と農業委員会と協議しながら、新しい制度に臨むという準備はしております。 それから、耕作放棄地と獣害防止でありますが、まず、耕作放棄地の事業については、現在、耕作放棄地対策協議会を立ち上げたところですので、新年度から新しく取り組むということを考えていきたいと思っております。事業は農林水産課がするようになると思います。それから、獣害対策については、今、非常に豊前市内でも、全国的にも大きな問題となっておりますが、これについては協議会をつくって、しっかりした方向性を示していきたいと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 直接、影響がないということと、新しい事業の中で取り組むということであります。 但し、今、私が農業関連を言いましたが、農業関連以外に多分影響する事業があるだろうと思いますが、それは当然、いろんな所から情報提供なり、お聞きしたいと思います。 それと、さっき言いました耕作放棄地の対策協議会をつくると。これは早くから言われている、今つくることではないんですよね。いろんな所から環境問題で取り沙汰されているときから、早くから、こういう問題について、どのように行政が指導しながら、それとJAを巻き込んだ中で、農家との連携をとりながらやっていくのか。 大体、私に言わせると、豊前市は何時も遅れている。当然、ほ場整備も今年度、角田の所が立ち上がりますが、もう余所は、ほ場整備が終わって、今の新しい政策の中で、いろんな事業に取り組みながら農家所得を向上するため、自給率をあげるために取り組むんですよ。だから、その10年から15年遅れた分を一気に取り返さないと、余所の地区には対応できないですよ。そういうところを十分踏まえて、今後、早急に早目、早目の対策を打つべきだろうと思っております。本題に入ります。 通告いたしました新しい事業で、戸別所得補償制度の事業ですが、今回は2本立ての柱の中で取り組みますが、30何年来の生産調整をやってきましたが、これは生産調整がなくなった。もう自由ですよ、という取り組みの中で、私は今度の民主党の政策はモデル的で、長続きするとは思っておりません。何故かと言うと、そういう予算については、ファントムの1基入れなければ、そういう事業の予算が組めるでしょうが、あくまでモデル的にやってみると。私が一番心配するのは、多分、課長も分かっていると思いますが、何のために生産調整をして自給率、バランスを図ってきたかと。 当然、これからは2本立ての柱の中で生産調整、昔はペナルティとかありましたが、今殆どペナルティがない、野放しと、言葉は悪いですが。そういう指導も途中はやってきましたが、もう、なあなあになってやってきてない。新しい事業がはじまった、その新しい事業に飛びついたということで、今までの正直に一生懸命にやってきた農家が馬鹿を見る。 1つの例を言いますと、新潟の大垣地区は、全く生産調整をやってなかったですね。 何故かというと、その地区については、コメが全部高く売れとった。ですが、今度の施策で当然、農協の集荷率はあがります。課長は分かると思います。ミニマムアクセスでコメは輸入します。それでなくてもコメが余っています。そういう中でコメの価格が、多分1万円切るだろうと。これは5~6年前から言われているんですね。これが現実に、この施策については私は大反対です。ですが、当然、民主党がやってみることですので、今の政権がモデル的にやってみて悪かったら来年はどうなるのか。 ですが、今、一番農家が不安を抱えているんですよ。今、集落座談会の中で全く見えない施策の中。ただモデル事業をやりますよ。水稲をつくって麦をつくったら1万5000円ですよと。転作すれば3万5000円、麦、大豆をつくれば3万5000円、プラス麦つくれば5万円ですよと。そして飼料米については8万円ですよと。大きな目玉商品がありますが、現実に試算をしてみると、農家の手取りがどれくらいになるのか。 コメが下がったときも、どれくらいになるのかという試算をしながら、今の集落座談会に説明しているとは思えないですね。ただ、今の説明の中では、はっきり見えない部分がありますので、ただ私は行政として、そういうものを先々を見た中で、どういう取り組みをやるのか。当然、生産調整しなくても結構です。コメも検査して今自由に売られます。 そういう売られる時代の中で、行政の立場として、当然これに農協が入ります。 農協も、もう少ししっかりしていただかなければ、本当に今の農業はやっていけなくなる。農業だけではないですね。当然、漁業も林業も。そこで実際に、まだはっきり見えない所ですが、豊前市としての指導の仕方、取り組みの仕方、今の座談会の中で、どのような説明をやっているのか、どのように取り組んでいくのか。もし、こうなった場合は、こうやりますよ、という所まで踏み込んで計画を練らないと、本当に日本の農家は駄目になると私は思います。 そこで、農林課長、昨年からいろいろな経験をしておりますし、自分も1つの地区の中で農業部門に取り組んでおりますので、行政としての対策なり、取り組みなりの心組みをお聞きしたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁 ○農林水産課長 奥本隆己君 今度の新しい事業につきましては、1つ目の柱として自給率向上事業、これは転作事業が移行したということであります。水田の作物を生産する農業者に対して飼料米として同等の所得を確保するという事業であります。 次に、2つ目としては、コメのモデルタイプ、これは1万5000円を支給するということでありますが、これは赤字に陥っているコメに対しては補填する事業で、この事業については定額部分と、差額を補填するという2つの事業があるわけですが、豊前市としては、本事業を最大限に活用するためには、今、集落座談会で、JAと農林水産課で全集落回っていますが、その中で非常に農業の経営形態が個別に違うものですから、各地で開催しながら申請書の作成の指導を行い、豊前市としては、水田農業推進協議会で取りまとめて、福岡農政事務所に申請すると。集落座談会で周知を図っていますが、なかなか分かりにくい所がありますので、3月18日から、各地で再度、地区の説明会を開催し、更なる周知をしたいと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 いろんなパターンがあります。活用自給率向上事業、水田のね。この前も説明がありました。私も資料を持っています。この中で一番所得率のいいやつ、何か分かりますよね。 麦と大豆しかないんですよ。飼料米とコメ粉の取り組みを、私は昔から言っておりましたが、これは限度があります。飼料米も相手があってのことですので、ここ豊前市は養鶏業者があります。これは設備がないから全く駄目なんですよ。この飼料米については、個人ごとの契約になっております。窓口が農協なり市になっていますが、飼料米は本当はぽっとみたらに飛びつくんですね。8万円プラス1万5000円で9万5000円もらえる。 ですが、この中で昨年、2地区つくりました。それが50円だったのが今度半額になった。いくら8万円もらっても、麦つくって9万5000円もらっても、元の単価が下がれば経費を引くとマイナスになるんですよ。やはり一番確実な手取りがいいのは麦と大豆なんですよ。だから、そこを十分農家に説明して、当然、今、麦・大豆をつくっている所は営農組合、もしくは認定農業者、大型農家の方がつくっております。 もし、今度、生産調整しない方についても、モデル事業じゃなく2本立てですので、麦ができれば地場産を使う、今、学校給食もいろんな地元のものを使って、熊本県は、特にコメ粉、そしてパンをつくって学校給食に出していますが、また、この次には、給食関係にも入りたいと思いますが、そういういろんな取組みを、早め早めに余所はしているんですよね。だから、豊前市は豊前市の地域性もあると思いますが、これということに決めて、多分、もう麦と大豆しかないですよと。 だから生産調整しながら、コメの過剰米が発生した場合に、米価の下落が必ず予測されますし、必ず下がるだろうと、絶対というふうに私は思います。今回の施策の中で。だから、岡垣町が今まで全く転作しない方が、今度の説明会に全員の方が来て取り組むというようなことが、農業新聞等に載っていました。 そういう面を汲んで、いろんな地域性も考えながら、まず、豊前市の農業の自給率向上、今度の新しい事業の取り組みの方向性を出して行っていただきたいなと思います。 一応モデル事業については、これで終わります。特に、これは農家所得の向上対策ですので、十分考えていただいてお願いしたいと思います。今、農家数は1207戸あります。 第1種が10%、第2種が約60%、70%が殆ど1種と2種の農家だと。だから豊前市は、1に農業だという地域性を昔からの流れを見ながら取り組んで頂きたいと思います。 2番目に質問いたします。営農組織認定農業者、担い手支援の対応ということで出しております。その取り組みを教えて頂きたい。豊前市は、営農組織は今18組織あります。 機械利用組合が3組織と、種子の組合が1組織、認定農業者39人、特に認定農業者のメリットが全くない。ただ行政と県と普及センターと農協で、いろんな指導をしておりますが、認定する場合ですね。よく市長と、新たな認定農業者第何号ということで市報に載っていますが、本当の認定農業者の支援がないんですよ。ただ認定農業者ですよと。 条件的に認定農業者になれば、貸付にしても、いろんな事業に乗られますが、それが現実に乗られてない認定農業者が多い。殆ど乗られてない。1割ぐらい乗っているか分かりませんが、今まで認定農業者はかなり減っていますよね。 認定はするけれど再度認定がされてない。というのは何故かというとメリットがない。 何も支援がない。何のために認定するんですか。やはり農業の維持、それから荒廃田と、いろんな面で荒さないように管理していただくというのが、営農組織なり認定農業者に与えられた使命だろうと思います。それを行政が支援しなくてどうしますか。全くメリットがないんですよ。メリットがあるということであれば、その対策なり、どういうメリットがあるのか教えていただきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 奥本隆己君 最初に、営農組合認定農業者、担い手支援についての対応を、お答えします。 まず、営農組合への支援は、現在、管内の営農組合数が14組織、機械利用組合が3組織、採種組合1組織の18組織となっています。管理面積については100ha、関係戸数263戸の構成となっています。営農組合の経営支援は、転作助成金の最大の活用の取り組みの指導を面的集約等考えて行っています。それから、水田経営安定対策の加入等の指導もしております。県の普及センター、JAグリーンセンター、市農林水産課が連携を図り、営農組合の組織への支援を行っています。現在、夫婦木営農組合が、法人化に向けて指導勉強会を行なっており、平成22年4月に予定しております。 次に、認定農業者の支援につきましては、豊前市では、認定農業者の会アグリネット21を組織し、現在39名の会員がおります。支援の対策としては、担い手経営展開支援リース事業により、農業機械のリース事業や助成、活力ある高収益型園芸産地育成事業により、施設の整備や農業機械導入等に対して助成を行っております。また、農業経営体成資金を活用される方への利子助成事業も行っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 助成事業の支援をしていますと言いますが、認定農業者は何戸ですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 39戸です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 39の認定農業者の中で、何戸、今、課長が言われた事業に取り組んでおりますか。 支援をしましたか。いいです。 課長ね。営農組織の場合は分かるんですよ。認定農業者、何人かしていますが、これは分かりますが、なかなか認定農業者のメリットというのは、極端に言えば、農舎を建てると農協に行ったら、認定農業者だけれど貸してくれなかったと。なんで認定農業者、条件が整った中で、普及センターと市役所と農協が認定して、なんで貸さないんですか。 課長は分からないだろうと思いますが、私は産地育成協議会の中で、認定農業者を認定する以上、営農計画を出した中で、一生懸命農業をやるんだという農家のために認定するんでしょう。それを貸さないとか、条件はちょっと分かりませんが、当然それは行政と普及センターが認定した以上は、責任を持って最後まで面倒を見てやるのが、そうじゃないですかね。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 奥本隆己君 その件につきましては、何故できなかったかという理由については、私ども直接聞いておりませんので、それについては、また、その人のいろいろあると思いますので、その条件等を協議しながら、またJAに出向いて協議したいと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 当然、それは認定農業者だから、そういうものを申し込まれる。1個人では申し込まれないですね。そのために認定している。やる気のある人だから、そこは何故できなかったかということを本人にも、ただ貸してくれんやったということで本人はやめていましたが、認定農家を外れたということです。認定農家はこの倍あったと思います。 5年計画の中で殆ど外れて、メリットがないということでなっていたと思います。 だから、これから農村・漁村の六次産業化という一番大きなメインが、農林・漁業の持続的かつ健全な発展、地域経済の活性化ということで、課長、またインターネットで出してもらったら、これにいっぱい事業が載っているから。この中から、少しずつ全部が全部該当しませんが、福祉も1回これを見とってください。 どんな事業が今からの農業、本当ですよ。それは工場誘致も大切か分かりませんが、日本は農が基本になるということを、後である事例を出しますが、そういうものが該当するように、やはり認定農業者についても、これから本当に頑張っていただくために支援をしていただきたいなと思いますので、当然、協議会がありますので、ただ豊前市だけが認定農業じゃないので、上毛町も吉富町も築上町もありますので、その中で十分、認定農業者に認定する以上は、メリットがあってこそ持続的な農業が維持できるだろうと思いますので、折角やる気がある人が、手をあげたら駄目でしたということにならないようにお願いしたいと思います。 それから、3番目、野菜農家、果樹農家、なかなか今、こういう時代で輸入物からいろんなもので、野菜も単価が下がるし、果樹もつくれば余るというような時代の中で、何かはじめての園芸振興のために、中身は何が何ぼというのは分っていると思いますが、園芸振興のために野菜・果樹農家と私は書きましたが、園芸振興を図るために、何が一番必要で、市として、何がどういうものを農家のために支援し指導していくのか、根本的なものをお伺いしたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 果樹、それから野菜の振興につきましては、現在、取り組んでいますが、今から六次化ということを見据えた上で、そういうふうにつながる施策をしていかなければならないと。 現在、トヨミツヒメを売っておりますが、それからユズにつきましても、過去、第3次的なところまで、イチジク、ユズについては進んでおりますが、その他の野菜についても、豊築管内、豊前市でも、特有の産地化を図りながら農業所得をあげていくと。また、コストを下げる上で協働的な利用を使いながら、しながらしていくということで、現在のところ豊前市では、レタス、イチゴ、スイートコーン、なばな、ブロッコリー、ナス、そういうものを主に野菜としておりますが、果樹については、イチジク、ユズをメインにつくっていきたいと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 今言われましたように、いろんな野菜があるんですね。昔は築城のレタスと言ったら日本一、どこに行っても負けなかった。ですが今は衰退しております。今、築城の面積より豊前の面積が多いんです。今、豊前は19町、築城は14町、全体で約45町のレタスですが、あの頃の単独の築城が頑張ったというのは、そこにいろんなものがあったんです。 当然、今は農協が合併しております。行政は合併しておりませんので、この食い違いじゃないけれど、そういう考え方がちょっと違ってきているのじゃなかろうか。 当然、各市町村長の会合もあろうし、全体の課長会があると思いますので、その中で、これから本当に野菜、果樹を伸ばすと思えば、加工センターが必要であろうと。 何故かというと、秀品というものについては、東京とか関西方面に送っていますが、B品というのは地元で、その後のC品というのは殆ど捨てている状態です。捨てているという言葉は悪いですが、そのB品、C品を一定の業者名前を言ってもいいですね。 向野さんに頼んだり、川底柿グループに頼んだり、そこで加工して道の駅、それから、いろんなイベントの中で売っているんですよ。特に、加工品は評判がいいんですよね。 トヨミツヒメも今推進していますよね。これも加工してジャムにしたら非常によかったということで、福岡豊築のラベルで、今出して新聞に載っとったですね。ですが限られてくるんですよ。だから、当然、豊築管内、行政がですね。市長、いいですか。 各町と話しながら、この六次化産業化の中で、加工センターをつくって、各地区、西、東から豊前市が中心になって捨てるもの、勿体ないですね。農家が、いくらかでも収益性があがるようなものを、イチジクにしてもイチゴにしても、いろんなものを、各行政が出資をして事業を農協と連携をとりながら、当然、農協も負担するべきと思いますが、その中で商品化をやるために、全国的にPRするためにも加工センターの建設、今ではないですが、先々には絶対必要だろうと思いますが、市長どういうふうにお考えでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 議員が言われた中で、京築管内を見ましたら、道の駅が豊津、築城、豊前、新吉富は成功しておりますし、今度の行橋市の市長選で、八並さんの道の駅をつくるという大きなテーマを書いておりました。あれは、おそらく東九州高速道路のサービスエリアを指しているだろうと思っております。苅田町におきましても、海の駅をつくろうという中で、なかなか議会と円満にはいってないようですが、苅田町も目指しています。 そこで何時も言われているのは、道の駅の先輩、成功はこっちのほうだと。一緒にしながら、広域圏事業にしたらどうだろうか、という提案を新川町長がしていますので、今言われた件について、農道も終わり、ほ場整備も目処がついて、今度、溜池等の農業関係の組織も再出発しまして、事務所は豊前市内にありまして、市役所のOBの山下というのが事務局次長になっております。 こういうことですので、将来を見た場合、今、議員が言われた件もやっていく必要があるだろうと思っております。4月にみやこ町の町長選が終わりました後、そういうことを含めてご相談していこうと。六次産業化、この件も先取りのテーマを出す必要がありますし、みやこ町の町長選が終わった後に、再出発の組織の2年目ですから提案していこうと思っております。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 市長、前向きな答弁ありがとうございます。これは絶対必要です。何時もブランド化、オリジナルブランドと何時も言っていますが、本当のブランド化になってないですね。 実際、地元のものは地元で売る。いろんなイベント関係でもですね。一番いい例がカラス天狗など見てください。農協は何か出して、していますか。ミカンですよ。普通だったら加工したやつをJA福岡豊築ですが、ミカンを2箇所しか置いてないですよ。 いろんなイベントの中で、地元の野菜は殆ど出てない。これは運営委員会の中で問題じゃないですかね。何のためにイベントをやっているのか。車を上に置いてみたり、わざわざあんな所に車を置く必要がありますか、カラス天狗の中で車を4、5台置いて。 そういう所を考えていただけなければ、農家の方は本当に不満を持っているんです。 不安と不信感を。何をしてくれるのだろうと。そこまで考えていただきたい。 後、新しい初年度に取り組む農家の支援ということで、当然、農協資金の営農資金とかありますが、行政独自のかなりかかるんですよ。これは、ほ場事業にも乗る部門もありますが、ほ場事業にも乗らない部分がありますので、当然そういうものについては支援するべきであろうと。一時油が高騰したときも、JA単独で助成金を出しておりますよ。 だから、そういうものも少し検討しながら、前向きな方向でそういう支援策を、ただ県の事業、国の事業じゃなくて、豊前市独自の支援の気持がなければ本当に伸びていかないですね。農家1人では何もできないですよ。やる気があって、JAがあって、行政があったらできるんですよ。それと国と県の事業があれば、市長どう思いますか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 カラス天狗祭りも長い歴史がありました。最初は、どげちこげち物産展、野菜を私当時売りまして今1件もないですね。そういうところか、或いは泥臭いのがなくなったか。 ただ、そうは言っても、いろんな打つ手が、やはりカラス天狗祭りのイベントを20数年しているから、他の町より知恵がわいたんじゃなかろうかと思っております。 問題は、野菜の関係はどうなのか。農協さんは農協さんの縄張りとかいろいろありそうですけれども、いろいろ言っても、1月4日の仕事始めは、豊前市と豊築農協と豊前商工会議所と新年の出発式をしておりますから、気持を新たにどうしたらいいのか考えていきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 そういうことで、いろんな面で不平・不満がありますが、それは担当各部署もありますし、本当に農協と連携をやっていかなければできないものだろうと思いますし、今まで個人で農業で走っていた方が、この事業でどのように変わるか分かりませんが、1年間、私はこのモデル事業を見てみたいなと。来年どのようになるのか、多分、予算が不足するのは間違いないだろうと思っております。次に入りたいと思います。 豊前市は、就農事業に長年取り組んでいますが、今の就業の取り組み方の現状を聞かせていただきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 奥本隆己君 就農の現状の取り組みについて、お答えします。新規就農者は、平成7年から21年まで14名が就農し、主に施設園芸に取り組んでいます。新規就農に関しましては、県と連携を図りながら進めております。新規就農者の受け入れとして、ソフト面では、新規就農相談会及び個別相談は随時、新規就農者研修交流会等行っています。 ハード面としては、活力ある高収益型園芸産地育成事業、新規就農定着促進事業等により、ハウス等施設導入に補助等に対する融資については、農業近代化資金、就農支援資金等について指導を行っております。現在、1人の就農者に対しまして、新規就農定着事業に取り組んでいるところであります。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 今、新規就農事業をやっていますね。14名ですね。現状、今定着した人が1名ですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 1名です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 事業をやってなんで1名しか残らないんですか。その原因は何ですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 奥本隆己君 就農に対し離農するということについては、現在、私どもが把握している分については精神的な疾患、それから連れ合いの病気、施設園芸のほ場の被害、施設園芸による農業所得の減少。それと離農した方々についても、私どもとしては、どういうことが原因なのかしていきたい。ただ農業は1人でするということが多いので、そこら辺のコミュニティ的なサポートが一番必要かなと私たちは思っていますので、現在そういう事業もやっていますが、なかなか実際、就農した方々は非常に厳しい状況にある中で、1人でやっていく不安もあるのじゃないかと私たちは判断しております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 新規就農は農業をやる気があってくる人ですね。14名の方が1名しかしてないと。 いろんな理由がありますが、新規就農の場合は、まず面接がありますね。そして、どのような環境状況かと、いろいろして最終的にその事業に取り組むのでありますね。 要はいろんな理由があって離れたというのは分かりますが、やはり十分な審査をして事業を組まないと、折角の事業が14名して、たった現状1名しか残ってないという結果になるんですよ。だから、本人のやる気もあるでしょうけれど、やる気があって来て、その事業を組むんですから、当然、支援、サポートするんですから、これは市だけに責任はないと思います。当然、普及センターにも農協にもあるだろうと思います。 ただ、今から、この新規就農事業、農協の農業塾、もう12回目を迎えて、かなりのやる気のある方が1年間勉強をやっています。その連携をとりながら、この事業ができないものか、お伺いします。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 先ほど残っているのが1名と、現在、就農に対して1名ということで、現在13名でございます。農協の事業ということでありますので、その事業についてはJAと・・・ ○議長 秋成茂信君 さっきと答弁が違うじゃない。山崎議員。 ○7番 山崎美君 新規就農は14名来て14名の方が就農やっているということですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、はっきりと。 ○農林水産課長 奥本隆己君 これは平成7年からということですので、それ以前がありますので。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 今、平成7年からと言ったですね。それ以前とはどういうことですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 平成7年前に就農している者もおりますので、そういう人達を含めてです。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 私が言ったのは、新規就農事業についてということだったので、要は事業を組んで、成果が100%効果が現れるような事業をやってくださいということを、お願いします。 さっき言いました農協農業塾で、この卒業生にも当然、新規就農事業が当てはまりますので、当然、農協と連携を密にしながら取り組んでいただきたいと思います。 それでは、農業問題で最後に、みのもんたのテレビでも非常に問題が報道されていますが、鳥獣害、特に、イノシシの被害が全国的に被害があるということで、怪我人も出た、死人も出たということで、毎日のように、この対策について農業新聞にも載っています。 国の事業仕分けの中には、鳥獣対策については、国から地方に移管するということが載っておりました。それで各県も市町村もこの対策については、かなりの力を入れてやっているんですよ。豊前市が、この前、被害の調査状況を調べましたね。その結果を教えてください。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 被害調査につきましては、今年度、市内の農家を対象に、農作物の被害の実態調査を行いました。総被害面積については39.4ha、内訳としましては、水稲が17.1、麦が1.1、大豆が2.6、ソバが1.2、その他、野菜、ミカン等で17.4haとなっています。調査の結果では、稲の作付け時期はシカが多く、出穂から成熟期はイノシシの被害が大きい。それから麦、大豆、ソバにつきましては、播種から収穫までのシカの被害が多くなっています。また、畑や果樹園ではシカ、イノシシの他にカラス、タヌキによる被害が多く見られました。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 今の調査で、被害額が分かれば教えてください。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 被害額につきましては、共済の価格を使いまして試算したところで、約2000万円前後じゃないかと思われます。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 私が管内調べたのが、これは統計事務所の中で、多分、共済組合だろうと思いますが、管内というか、この近辺で1億8000万円、これは豊前市でしょう。ただそれプラス2000万円ぐらいの被害かなと思うんです。何故かというと、08年度の被害が98件で39億円、イノシシが18億5000万円、鳥の被害が12億2000万円、シカが5億8000万円、その他2億5000万円と結果が出ておるんですよ。その中で福岡県が一番多いですね。11億5900万円。 佐賀県の武雄市がイノシシ課がありますね。そこが2億7000万円ですが、早くからイノシシ課をつくって対応をやっていると。福岡県の取り組みも悪いですよね。 宮崎県、鹿児島県は、鳥獣害対策に、朝、課長も述べましたよね。10年度予算でかなりの計上をやっていますね。豊前市も有害鳥獣駆除をやっていますが、その駆除と狩猟の捕獲数が断然、狩猟のほうが多いですよね。武雄市は、有害鳥獣駆除のほうが断然多いですね。捕獲数が少ない。 武雄市は、イノシシの被害が20年度が、駆除期間が1541頭、狩猟期間が611頭です。そのくらい違うんです。武雄市は、加工センターをつくっています。ご存知ですよね。みやこも今度オープンしたんですよね。少しずつ真剣に考えないと町の人はイノシシ、シカが可哀そうとか、可愛いですよと餌付けしていますが、本当に農家にとっては大変な生き物なんですよ。私が言いたいのは、今年度の予算が、あまり重きを置いてないというのは失礼ですが、そういう対策に本当に力を入れてないですよ。 それと共済組合だけで調べるんじゃなくて、統計事務所が共済額で出しますが、本当に豊前市が調べるなら、余所は調査員とかを置いて実際に調査をやっているんですよ。 これはあくまで共済組合とか、自分の家で調査したのも被害なんですが、そういうものは殆ど出てないですね。そのくらい多いんですよ。 私が、これを何故言うかといいますと、猟友会も高齢化なんですよ。課長よく知っているように、昭和53年は350~360人の猟友会員がいましたが、今は3分の1で135名。殆ど50歳以上が8割を占める。20歳が1人、30歳が4人、40歳は7人しかいない。これから、当然、有害鳥獣駆除をやると思いますが、定年されて60歳以上が約63%、この方で、こういう対策ができるのか、多分無理だろうと思います。 全国的にも、この前、兵庫県の豊岡市、テレビに出ていた。市が50名程度養成して、市が研修して、市が奨励して、そういう制度に取り組んでいるんですよ。何故かというと銃砲もなかなか厳しくなって、なかなか経費もかかって免許が取れにくいと。そういうものがあるので、やはり行政が駆除するために行政が養成して、行政で研修しながら、猟友会と警察と一緒になって狩猟していただこうという取り組みが始まっています。 今、豊前市の資料がありますが言いましょうか。20年度が有害鳥獣駆除170頭です。狩猟で取ったのが794頭、このくらいの差がある。有害鳥獣駆除には、多額なお金を使っております。県の補助金と市の補助金ね。このバランスがね。それと自分達で電柵や網やらしますよね。そういうものについて、今後、有害鳥獣駆除だけに頼ってはいけない。私はここが言いたい。 武雄市は、当然、有害鳥獣駆除でお金使ってもいいですね。そのくらい獲れているんですから、3倍近くですね。これから、当然、農家の方も一緒になってやってもらわないと高齢化、それから後継者の育成、これは自衛隊が1回すると朝日新聞に載っていましたが、まず無理ですよ。拳銃では撃たれないです、狩猟法がありますから。撃つ鉄砲が違うんですね。自衛隊で機関銃で撃つわけにはいかない。そうでしょう。犬がいないと獲れない。 自衛隊と警察で追ってもらいますか。できないですよ。不可能なことが朝日新聞に載っていた。本当に考えたら、今から農業は自給率を高めるということであれば、これを課題にしないと。鹿児島で電柵でも事故があっています。年寄りの方が亡くなっている。 雨降りの日に行って、あれも危ないですよ。今発光ダイオードといってライトを使ったイノシシの撃退機がものすごく好評があるんです。鹿児島で試験をやって現実にできている。 名前がピカちゃんといって、アルカリ電池で約4ヵ月で、約1個5000円だけれど、これは行政が全額助成するんじゃなくて、やはり農家の方も受益者負担しながら、そういう対策を一緒にやるということなんですよ。だから、そういうものを殆どいろんな所で、農業新聞を見てください。イノシシ、シカの関係は毎日載っています。 私が言いたいのは、これからの後継者、高齢化問題について、行政はどのように考えているか。それと有害鳥獣駆除のこれからの方針を、お聞かせください。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 対策につきましては、現在、各事業でほ場整備で中山間地域については、防護柵の設置を行っております。市も補助金規定がありまして、資材に対する補助、一定の面積を一定の受益者の中で補助金をやるという事業をしております。それから、獣害被害のケアについて、どうするかということでありますが、この件については、やはり銃器を使ってということが第一になるかと思います。それと、もう1つは、ワナ等の免許についても来年度以降、研修会等しながら、できるだけ事前講習をやって試験を受けていただくというものを指導しながら、高齢者が多くて猟友会のメンバーが減るということについても、何らかの形で増えていただくように行政としても支援していきたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 当然、課長が一番山奥と言えば失礼ですが、イノシシに遭遇しておりますので、一番分かることだろうと思います。それで有害鳥獣駆除の関係は、上毛町と築上町と合同の協議会の中で話し合いながらやっていますね。私はこの実績を見ても、これはボランティアなんですね。ボランティアでやっていますので、若い人も入ってきて、これは遊びじゃないですよ。皆さん、畜生撃って殺生してと言う人がおりますよ。 けれど、しなくちゃしないでもいいんです。やはり猟友会としては、そういうマナーに則った駆除は、農家のためにということでやっているんですから、そこを鉄砲撃つ人は野蛮な人とかいろんなことを言いますが、全然違うんです。本当に農家のためになっているんですよ。私は猟友会の事務局長をやっております。今、非常に運営上も厳しいんですよ。 今、法律が変わって申請が変わって大変なんですよ。私が思うには、ここで有害鳥獣駆除に補助金が県からきます。市も出していますが、猟期中の保障制度の導入は余所はやっています。市長、どうですか検討して、余所は機関銃で1頭捕ったらいくらとか、築城は上小山田地区の集落が単独でイノシシを獲ったら奨励金を出すという検討に入っているんです。総会で決まるんですよ。 そういう取り組みをしているのに、行政がしないというのもおかしいと思うんです。 私は5000円出せとは言いませんよ。やはり、そういうことによって当然、狩猟者は負担が今非常に多いんですよ。今、狩猟免許を受けるにしても3万円かかるんです。 大分県と福岡県で6万円、更新に行けば更新料が2万円、離島の人が受けられないんですよ。本土に行かないと射撃があって射撃に玉が当たらないと、許可がおりないというくらい厳しくなっている。こうやって厳しくすると鉄砲撃つ人はいない。そうするとどうなりますか。考えたら分かるでしょう。国道にイノシシとシカが走っていますよ。笑い事ではないですよ、本当に。宝福寺山にも今1頭おるんですよ。 皆さん笑っていますが、農家にしたら本当に大変なことなんです。被害があって子供さんが怪我したらどうしますか。そういうところまで考えていただいて、猟期中の捕獲補償制度の導入。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今まで、豊前市の50数年の歴史の中で、イノシシに対して壁をつくるとか、また玉代を出すと、こういうことをしたと思いますが、また県下累計の所もあるわけですので、検討させてください。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 前向きに十分検討していただきたいと思います。それから、当然、獲ったものをどうするかですね。みやこ町が加工センターを今度オープンします。この前テレビに出ていましたが、武雄市は早くからやっております。そのデーターもあります。みやこ町のこの前、猟友会も一緒になっての協議会をやっております。写真もここにあります。 課長、持っておれば市長、副市長に見せてください。当然、この加工センターも必要だろうと。私は前回、みやこハムさんに頼んだらという話もしましたが、猟友会も経営が厳しい中で、こうやって加工場ができて、これを商品にしてブランド化して売るということであれば、当然、狩猟の皆さんも収入が少しずつ入る。それが免許の切り替えに係るお金に負担したり、玉代に負担したり、そういうものに当てられるんですよ。 それで私が思うには、みやこ町は、みやこ地区以外の方は、みやこ町在住の狩猟者登録をされた方に限りますということです。今、豊築管内、築城、椎田、豊前、上毛、大平の中で、市長、新しい事業がいっぱいあるんですよ。今すぐではないですが、豊前市が当然、中心ですので、豊前市にそういうものを持ってきて、猟友会は豊築は1つですので、そういう加工センターをつくって、それをブランド化して、町おこし、村おこしと言うか、そういうものを起こしたらどうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今の今、現実にされている所が、卜仙の郷ですね。シカの刺身とイノシシのボタン鍋を営業しています。近隣で言うならば宇美町がイノシシのラーメンをしています。 地元のメーカーのみやこハムさんも以前、お話があったと思いますが、制度はそこまでいってなかったかと思います。みやこ町も考えているようでありますので、先ほどの話と同じになりますが、みやこ町の町長選が終わりましたら、どんなふうにしていますか、ということを聞きながら、制度をもってやれるかどうか。また業績の見通しも見ながらやっていこうかなと思っています。今、道の駅ではイノシシの料理はしていないと思います。 五木村に、この前行きましたら燻製をやっていました。簡単ではないけれども、1つの立地条件を生かしながら検討していきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 当然、みやこ町はみやこ町でいいと思いますし、豊前市、築上町、上毛町が、何故かというとメタセの杜と大平楽、卜仙とあるんです。そういうもので、豊前市が中心になって声かけして、予算組をしながら出資してやるべきであろうと。特に、10年度の都道府県の予算は、駆除や肉を利用するのが、こんなに大きく載っているんですよ。そのくらい取り組むんですよ、どこもね。 宮崎は、鳥獣害対策強化事業に2億9000万円、指導専門家180人とやっているんです。福岡県が、一番被害が大きくて他県は被害が少ないのに、このくらい力を入れているんですよ。山の状況とかいろいろ違いますが、このくらいやっていますよということをお伝えしたい。だから農家のことを考えてやっていただきたい。防御柵と言っても下から掘られたら一緒なんですよ。行って見てください。ネットは噛み切って破られて、どんどん入っている。本当ですよ。電柵は大人の方が亡くなった事故もありますので、行政が何処かの地区に1回やってみるとか、いろんな面でやっていただきたいんですよ。そういうことでお願いしたいと思います。もう7分しかないですね。 後、森林の関係に早急にいきたいと思います。森林整備は、再生の取り組みについての現状ということで、一応しております。課長、その認証制度の関係を含めた中で返答してください。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 林業の森林整備についての取り組みについては、現在、造林費、伐採費等の経費の増大、木材価格の低迷、急増する木材の輸入等により、全国的に衰退している現状であります。 本市では、主に国・県の補助事業を活用し、森林所有者の造林費の負担を軽減する施策を重点において、森林の整備を行い林業の振興に努めております。 また、京築地区各市町と福岡県、そして豊築・みやこの2林業組合で構成する京築地域森林・林業推進協議会で、市民・建設業関係者を対象とした地域材でつくられた住宅見学会を開催し・・ (「もう、端的に」の声あり)) それから、シイタケ等の特用林産物の生産面にも県の補助金を活用しながら、積極的に推進しております。今後につきましては、生産者、製材所、設計事務所、工務店、行政等の関係機関と連携しながら、推進体制を構築して消費者と一体となり、木材の消費拡大を図りたいと思っております。 それから、認証制度については、山に付加価値をつけるということで、現在、代表的なものは、国際認証機関に森林管理協会、日本独自の認証機関に緑の循環認証会議というものがあります。この認証森林に認定されるには、森林管理法、長期経営計画等、厳しい基準が設けられていますが、県及び近隣市町村森林組合と協議しながら検討していきたいと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 時間5分の中でいきます。整備は後でいいんですが、認証制度でSGEC認証マーク、このマークがつくと大体1割高いですね。だからこれはいろいろあるんですよ。 要はSGECマークとFSCですか、いろいろ審査があると思うんですよ。 今、財産組合の監査を私はしていますが、手を入れて現実あまり儲けてないですね。 だから、こういう制度も取り入れるべきなんですよ。それと今伐採した後にヒノキ、スギの木を植えていますが、あれは逆にシイタケの元のクヌギを植えたらどうですか。 今の代で植えて何年先ですか、孫の代でしょう。今シイタケがいいのは、中国の餃子の関係から、今、国産のシイタケの見直しが非常によくなっています。シイタケの栽培がキノコ栽培。要は08年の林業の産出額、栽培キノコが首位に立ったと。特に生シイタケが非常にいいということと、栽培キノコの中では、新潟、北海道、福岡県は3番目に入っています。新しくシイタケをしている方もおります。当然、今からキノコは国産でなければ駄目なんですよ。だからそういうものについても、ヒノキを植えなくて原木の地元のやつを、クヌギを植えさせたらいいじゃないですか。材木が安い中で、そういうマークもとりながら、材木を高く売って、その材木で地元の供給、今度、北高跡地でも行政が入札するときに、材木は地元のものを使ってくださいと。当然、森林組合でも森林環境税でいろんな事業があった中で、それを含めた中で、地元の林業を栄えさせてくださいよ。 2分しかないけれど簡単に一言。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 林業については、議員が言われるようにサイクルが非常に長いために、後継者、また林業につなげて行くというのは問題がありますので、シイタケを植えて、これこそ六次産業化ではないかと思いますので、是非、前向きに考えたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 山崎議員。 ○7番 山崎美君 1分しかありません。後、4番、5番があったんですが、この次に6月に回します。 市長、長野県の川上村の藤原村長さん、ものすごく有名な方なんですよ。 1戸平均2500万円実現と。この方は、何年も前から企業誘致を後にしたんです。 まず、農業を基本において、1戸当たり2500万円を実現しながら、それから企業誘致に係るということです。だから、そういうものを入れて、ここにありますので、後で読んでください。そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 これで質問を終わります。 ○議長 秋成茂信君 以上で新世会の質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 12時01分 再開 13時00分 ○副議長 中村勇希君 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行します。ぶぜん風の会の質問を行ないます。 最初に、岡本清靖議員、お願いします。 ○3番 岡本清靖君 午後から風の会3名の中、岡本が先にさせていただきます。 食事の後、皆さん眠くなる可能性が強くなり、また私の質問に対して眠くなるかも分かりませんが、自分も頑張ってやりたいと思っております。今日は3点の中からやらせていただきます。 まず、はじめに指定管理者ということであがっていますが、豊前市では指定管理者で団体が動いております。そういった中で、行政としては、指定管理者が多くなれば多くなるほど負担が少なくなる可能性があるので、そういった形で行政としては、指定管理者を達成していくのが筋ではないか、というような言い方になろうと思いますが、自分の地域として岩屋の活性化センター、公民館で指定管理者の所はありませんが、先々岩屋の活性化センターを指定管理者ということで考えておられるのか、そういった形で先々やってほしいという意向があるのか、お聞きしたいと思います。担当課長、お願いします。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 答弁書を用意していますので、読んでお答えしたいと思います。公の施設の管理につきましては、地方自治法第244条の2第3項及び豊前市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例に基づいて、指定管理者の導入が可能になっております。 具体的には、施設の現状など総合的に判断して、直営か指定管理者がいいのかを判断することとなります。ご承知のように、豊前市内には、11館の市立の地域の公民館があります。現在のところ、すべて市の直営で運営しております。 ご質問の岩屋活性化センターにつきましては、岩屋公民館として地域の中核施設という役割を担い、年間約8800人あまりの住民の方に、ご利用をいただいております。 こうした公民館施設につきましては、かねてより活性化の取り組みが求められておりまして、現在、策定中の豊前市生涯学習基本推進計画の中で検討中でありまして、将来に向けて方向性を出していきたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 やはり教育長が言われています生涯学習、いろんな面で地域との連携もとらないとできない。私は逆に指定管理者でないほうがいいんだけれども、先々その地域のいろんな面を考えますと、指定管理者でもってあればいいのかな、ということで質問させていただいております。最終的に、これから先、岩屋地域でのNPOという法人の立ち上げが、まだ認定されていませんが、先々認定があるならば、こういった形でなされていただければという、自分の地域の中の考えでありますので、そういった方向で先々それができれば、その地域の活性、また村起こしの感じでもってやらせていただければと思っております。 やはり最終的には、行政との関わりがありますので、やはり公民館の館長という形で、地域の中、そして行政との関わりがありますので、その面は、今から先、真剣に取り組みしなければいけないと私は考えておりますが、一応これだけお聞きしております。 最終的に、まず、教育長、やってほしいというのか、それとも、そのまま逆にはやらないでほしいというか、どちらの考えが強いでしようか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 今のところ、それを具体的に進めるという段階までには至っておりません。 そうすることが地域の活性化になるのか、或いは、地域住民のためになるのか、行政としての役割を果たしているのかとか、勘案しながら考えていきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 分かりました。私たち地域でも一緒になって考えながら、この件を進めていきたいと思います。続いて、第2の項目であります。 求菩提山史跡保存と観光についてであります。やはり求菩提山は、豊前の発祥の地であると私は考えております。豊前が生まれたのも求菩提山がありこの豊前市ができている。やはり観光施設としても豊前があり、いろんな面で観光があり、犬ケ岳がそびえている、その中でシャクナゲ、つつじもありますが、いろんな面でやはり土台として求菩提山を私はメインとしてあげていきたいと思っております。その中で、私が議員になってからですが、求菩提山の史跡の保存の関係で、整備の計画がなされておりましたが、その計画の流れは、どんなふうになっているか、お聞きしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 お答えいたします。求菩提山史跡保存と観光について、平成19年度に県の自然環境整備計画にビジターセンターとして要望し、平成21年度から25年度までの自然環境整備計画におきまして、インフォメーションセンターとして、平成24年度の事業で計画されております。計画では、場所は、求菩提駐車場の隣接地を予定しており、国・県が建物を建てるようになっております。しかしながら、現在、国の予算状況が不透明のため、計画は、現時点では白紙の状態と県からの回答を受けております。 今後は、国・県の状況を見守りながら要望していきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 今、課長は白紙と言ったんですが、それは地域保存の整備の中の白紙なんですか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 県はビジターセンターの計画をしておりましたが、県の予定では、平成24年度に計画があがっていたんですが、今回ビジターセンターの建設が、県から白紙という報告を受けております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 ビジターセンターというのは、観光の一番メインの案内所だと私は思っております。 そのために、豊前市の地域全体を見ても観光の所がいろんな所があります。その中で、やはり最終的にメインが求菩提山の史跡で、いろんな面で保存されながら、その地域の観光を逆にまとめていく中で、そのビジターセンターがどこにあってもかまわんと思います。その中に観光施設、ガイドさんを置かれて、豊前の中の観光を広げていく形だろうと思いますが、どこかにそのセンターをほしいと思います。そうなった中に、もしかしたら逆に地域としては、岩屋地区にそういった観光施設が、ビジターができるという前提で今申し上げた中で、それが逆に駄目という言い方を今されていました。 その中で、公民館をその中で併用することも考えたら可能ではないか、という考え方を私たちは持っていますが、そういったところはどんなもんですかね。ビジターセンターを観光施設を逆に公民館の中に入れるという形の考え方という。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 県からビジターセンターは、白紙という報告を受けたんですが、その件については教育委員会と十分協議したいと思います。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 やはり教育委員会と、まちづくり課と一緒になってしていただきたい。ただ、史跡保存だけじゃなくて、その地域の観光なんですよ。だから、教育委員会だけが史跡だけを考えるんじゃなく、お互いによくするためには、観光がつきものだと思います。だから、観光の方々と一緒になって、その地域の存続を考えていく、外部から多くの方に来てもらうという考え方をもたれて、大きい目でもって、広く視野を広げて観光に取り組んでいただきたいと思います。 今、北高跡地のほうが観光施設とやっていますので、逆にそっちのほうに目がいってしまったり、豊前市外に目がいってしまっている可能性があるので、全体的に多く、広く目を見つめて、そして、求菩提山ではなくて宇佐と英彦山、羅漢寺、求菩提山、そういった関連の中で、修験道が今まで一生懸命になってしてきた求菩提山があります。 その中で乳の観音様、千手観音、如法寺、いろんな関係がつながりがありますので、そういった所を互いに考えながら、観光の拠点をつくるなりしていただきたいと思います。 本当に、最後には観光ガイド、史跡のガイドをされる所が絶対に必要になると私は思います。それだけはちゃんと頭の中において、前向きの検討で、県がなんと言おうと、市が積極的にそれを進めていく気持でやってもらいたいと思います。分かりますかね。 最終的に、逆に最後に位置付けをする所、基地をする所をできれば近い所にしてもらいたいんですが、全面的な観光を考えると、やはりどこか中心にならないといかん。 それは市にお任せします。では、一応、観光的な所は終わらせていただきます。 また、後、豊前の特産、地域での継承についてでありますが、豊前市には、沢山の特産品があります。海から山のほうにもですね。いろいろあります。あげても本ガニから一粒ガキ、農業になったらイチゴ、ミカン、野菜、イチジク、シイタケ、お米、お茶といろんな特産品がありますので、そういった中で、これからの特産品が地域でそのまま継承される意向、午前中に山崎議員がいろいろ質問されております。その1つの特産品をどうして生かすかということを、行政側と一緒になって考えないといけないと思います。 ただ自分だけで活動しながらやっていこうというのは、本当に無理だと思います。 その中で行政の指導、そして手助けが逆に必要になるのではないかと思っております。 その中で、私が地元のことばかりで大変申し訳ないんだけれど、やはり地域を盛り上げて地域を潤う、活性化させるために私も出させていただきました。そのために地域のことで悪いですが、ここで言わさせていただきます。 そろそろ5月になります。5月にはシャクナゲの花も咲きます。そして観光シーズン、緑の芽がいっぱいふくらみ、そういった観光シーズン、山の登山者が多くなります。 そうした中で5月の新芽のお茶ですね。今、お茶の加工場がありますが、お茶の生産地があります。その中で加工する施設はどこにもありますが、最終的に、それを昔からの継承で、手もみ茶を継承できないかという考え方ですね。そういった中に、やはり行政の力を借りながら、その地域に拠点をつくりたい。産家地区、求菩提地区の皆さんは、そういった登山者に向けて昔から手もみしながら、こられた方々にお茶を振舞っていたといった継承が今なくなってきている。けれど、その地域が、これからそれをやっていこうという意気込みは伺えているだろうと思います。そういった中で、これは本当にやるべきじゃないかなと考えております。 この手もみ茶は去年、何人かの方がちょっとやっておられます。そうした中で自分の所に加工所がないことにはどうしようもできません。そうした中で、やはり1軒の家で手もみするわけにいかないと思います。やはりお茶は、その時期を通じて常にどっとん、どっとん生産されていますので、やはり大きな施設があって、そこに皆さんが持ち寄り、そして中で皆さんが体験もできながら加工もしていこう。最終的に仕上げていこうという、そういった施設がほしいと私は考えております。 そうした面で、地域の中で手もみ茶の加工場といったものを、行政側として考えていただけるものか、これから先になっても、そういう形であろうかと思いますが、今の現時点の考え方をお聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 岩屋地区では、以前は手もみ茶の生産が盛んであり、現在でも生産されている方がいると聞いております。現在では、地域での検証が困難な状況であると考えますが、観光の観点から申しますと、生産の時期がちょうど犬ケ岳のツクシシャクナゲの開花時期と重なりますので、地元のシャクナゲ祭りや登山客にPRすることで、観光につなげていくことができる可能性があると考えております。 また、可能であるならば、地元の方々の協力により、現在、空き家になっている民家等を活用しての手もみ茶の体験教室等を開催することにより、観光客の誘致や地元での手もみ茶の継承が可能と考えられますが、今後の調査・研究が必要であると考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 そうですね。空き家と今、課長が言われましたが、空き家を借りて加工するには、その住居の人が外に出られて、そのままいなくなっている空き家を借りたとしても、その中で加工施設をつくるためには、空き家を改造しなければいかないですね。そういった面でいろんな面があると思います。だから、1つの土地をどこか提供して、そこで加工施設をつくるということは、逆に莫大な費用がかかるだろうと思います。それもいい考え方だと思います。そうした中で、特産品の関係で、今、加工施設が出ましたが、先ほど山崎議員が言われた中で、いろんな面で加工施設がほしいだろうと思います。 先ほど山崎議員が言われたごと、A級、B級、C級があります。最終的に農産物の直売所にその品物を出したときに、私たちの所からも卜仙の郷に出させていただく、後JAのふれあい市場とか、道の駅に出させていただきますが、そういった中で悪いものを持っていったら売れないですよね。お金を下げてでも売れないですよ。 だから、それをどうやったら売れるものになるのか。人参にしろ、大根にしろ、二股になったものを持って行っても売れない。やはり真っすぐ1本になったものでないと売れない。そういった形を考えると最終的には、それを処分しなければ捨てたら勿体ない。 だから、それをどうやったらいいのか。そういったときの加工の施設、お互いに加工の施設は必要だろうと思います。だから手もみ茶だけではないですね。そういった中で、その加工が真空パックにされて薄く乾燥されて、そのまま食卓に戻ったときには、食卓でそのまま調理ができる、そういった施設なんです。だから生でそのまま出すんじゃなく、それを逆に悪いのを小さく切って乾燥させて、食卓まで届けるといった加工施設が必要ではないかと思っていますが、先ほど検討します、という言い方ですが、検討でなく前向きにめがけてください。 財務課長は、お金の面でいろいろと忙しいと思いますが、これは豊前市の発展のためですよ。地域の掘り起こし、豊前の掘り起しですよ。豊前市全体に野菜がありますので、そういった中で、そういった大きな加工施設を手がけてもらいたいと思います。 市長、その辺の意気込みをどんなでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 今回の関係でソバ打ちの予算、そして農家民宿の予算をはじめてあげております。 この関係は岩屋地区でありまして、従来から思っていたんですができなかったわけですが、ようやく踏み込んだと思っております。今議員が言われた件も、一緒に相乗効果でいければいいのじゃなかろうか。そのために、今年踏み込んでいきたいなと思っております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 今、市長がソバを言いましたが、私はあえてソバは出しませんでした。一応、今回の本題の中で、いろいろとソバが出ていましたので、私は言いませんでしたが、ソバも求菩提ソバとして自分達、営農組合1団体は営農じゃないですけれど、3つの団体で求菩提ソバをブランド化していこうという気持でやっております。だから最終的に、それを含めた中のいろいろな面での加工施設がいろうかと思います。市長ありがとうございます。 これからもよろしくお願いいたします。継承の関係は一応終わらせていただきます。 最後ですけれども、一次産業との共存ということであげております。前農林課長のときですが、田舎のほうではシカ、イノシシ、タヌキ、ウサギといった被害が存続しております。その中で県道沿いでシカの被害が起きているというのが、車との接触事故なんです。 そういった中で、道路標識を身近に県道を通る方々に促していただきたい。そういった形で私はずっと言っていますが、今の現況がどのようになっているか、お聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 県道の標識について、お答えいたします。県道32号線、犀川・豊前線の鳥井畑~産家間の道路上で、今言われるようにシカ、イノシシ、タヌキ等の接触の交通事故が起きているということで、動物の出やすい場所に、注意との標識をしたらということでしたので、県の京築土木事務所の道路課とも協議をいたしました。新年度予算において、地元と協議しながら、数箇所において設置するという回答をいただいております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 その設置の場所ですが、やはり豊前市の山手のほうに行けば、どこにもシカやイノシシが出ると思います。そうなると私の言っているのは32号線のことですが、全体的な所も考えてやってください。私たちが32号線を基準に言ったのが、寒田にあがる所、求菩提の頂上ぐらいの豊前と築城との境の32号線、そこには、あがりで2つぐらいありますが、自分達が住んでいる県道32号線の通り道で、自分たちが仕事に出かける途中のカーブには何もないですね。上にあっても通り抜けする方しか分からないようなことなんです。 普段から32号線は卜仙もありますし、卜仙ができて、今いろんなお客さんが上り下りしております。そういった方々にも、ここには動物が出ますよというものを掲げていただきたい。そうなると岩屋近辺までさがって貰って、それから所々にしてもらう。すると合河も入り口にしてもらうとか、山田なら山田でもしてもらう、角田でもしてもらう。そういう標識の仕方で考えてもらったらなと私は思っております。そういう形でちょっと。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 議員が言われましたように、鳥井畑からちょっと範囲が狭いということですが、そういうことも含めて、再度、県の京築土木事務所と協議しまして付ける位置等、また地元に聞かないといけませんので、出やすい所、一番危ない所を聞いて、つけると聞いておりますので、それも含めて検討していくように県と協議して実施するようにいたします。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 それでよろしくお願いいたします。 次に、一応、加工施設がここにあがってきますけれども、山崎議員と一緒の関連があります。一次産業ですので、漁業、農業、林業、皆が入っておりますので、私は林業に関連した中でシカ、イノシシがどうして民家におりてきたのか。農家の作物を食べだしたのか。 荒しだしたのか。これは行政の考え方、やはり考えてもらわないといけないと思います。 やはり森林のあり方が、最終的には問題になっております。やはり人工造林を増やしているということです。山の上までどっとん、どっとん、植林をしてしまって、やはりそこにクヌギ、ナラ、シイの木、そういった実のなる木がだんだんと少なくなってきております。そういった実を食べて、今までシカやイノシシは育ってきていると思います。 シカは大体、草食の関係ですから、そんなことはないだろうけれど、シカもやはり葉っぱも実も食べます。やはりだんだんと上が植林の関係で緑が逆に下葉がなくなり、下に全然そういった草食の関係がなくなってきている。そういった中で、やはり里山に出てくると思います。そういった関係を考えながら、これから林業を考えていってもらいたいなと。 そういった中で、先ほど言われました加工施設、みやこ町にも、この3月、私は4月が本格的なオープンと新聞で見たんですが、山崎議員は3月からと言われております。 そういった中で、やはり猟銃使用者の方々、皆さん見てそういった経費の関係、自分の使った経費がそこで浮くような感じ、そういった加工施設、イノシシ、シカ等加工される場所を私はしていただきたい。市長は先ほど答弁されましたので、それは深くは言いません。そういった形を、これからも考えていただき、やはり村の人が里山の人が住める、楽しくそこで過ごせる里山をつくっていただきたいと思っております。 逆に、ほ場整備の後が柵で囲まれております。逆に人間が囲まれているような感じになっています。動物のほうが外から見ているような感じです。そういった形式があります。 そういった形式も景観も、1つの考え方も考えていかなければならない。その景観の仕方も、これから考えながら、その周りの木の植え方も少しずつ考えてもらえたらなと私は思っております。 続いて、環境税が福岡県に導入されました。この環境税が導入された中で、国と県の補助もあると思います。森林に対して、今の森林組合が年度内ぎりぎりで、一生懸命沢山の仕事をされていますが、環境税と逆の補助の関係の割り当ての仕事の仕方はどんなふうか分かりますか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 森林環境税につきましては、100%補助金でございます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 それは分かります。その中で個人の山、そして市の財産、県有林といろんな所で今仕事されていると思います。そういった中で、国の補助の分で森林整備がされている。環境税は補助ですが、その割り当てというのは、そういうふりかけで仕事はどんな形でされているのか、お聞きしたいのですが。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 森林環境税の使途につきましては、基本的に民有林を整備するというものでありまして、15年以上放置された杉を植えた山という一定の規定がありますので、現在、豊前市の中で調査しまして、その山に対して協定しまして整備しております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 分かりました。この環境税も成人された方、一人ひとり県民税を払っている方が、皆さん一緒の金額で出させてもらっております。山の所有者と関係なく出してもらっていますので、やはり森林の整備の仕方は、これからよく考えてもらわなければならないかなと思っております。この環境税の使い方は、今言われたあれでありますが、国と県の補助の関係で、今、森林組合はいろいろ仕事をされておりますが、逆に山の整備ができていればいいという考え方で、今の林道が通っていろいろと周りから見れば、ああこの山は手入れしているな、そんな感じでよく見られる。それが本当だろうと思いますが、私から見れば逆に森林の整備の仕方というのは、考えなければならないなという所が1点あります。 それは近年、平成3年からですが、台風被害が出てきております。そういった中で昔の人の植林の仕方は、やはり外縁林は全部枝を残しているんです。中に風が入らないごとしているんですよ。今の1つの山が隣り隣りにあって、その中間が伐採されて切られたら仕方ないですが、植林して枝打ちをする、そして段々と間伐しながらする中で、外回りの木の風が当たる所が全然当たらないと言った見掛けは悪いかもわからんけれど、そういった森林の整備の仕方でないと、現在3月、そういった植林の仕方で森林の整備をされているけれど、もしかして9月ごろになって台風がきたら、いっぺんでさっと倒れてしまう。 そういった可能性が多くあると思います。だから、できるだけ風が入らないといった工夫は県の指導もほしいと思うけれど、やはり昔から山に携わった人たちの話も聞きながらそういった森林整備の仕方をしていくべきじゃないかと思います。 これは県の補助として周りが枝打ちされてない。これはどういうことか、これでは補助はやれないと。これは逆に間違っていると思います。山に外縁を1歩でも入った中は美しく手入れされているんです。そういった山の手入れの仕方でないと、これからの林業は確実にやっていけないと思っております。 それは木を製材しても悪いのは悪いです。けれど、これからの山を持つための人の知恵だと思っておりますので、そういったことを、森林組合と一緒に話ながら前向きで県ともお互い一緒だと思います。県もいろいろ勉強されている方がおりますので、そういう方々と一緒に話ながら、手入れの仕方を考えていただきたいと思います。 この前も求菩提山の第2豊築線を通らせてもらいましたが、その中で、やはり見掛けは美しい、最終的には、その下の辺は群生林でもって三椏の木が多いんですよね。 その木も森林の整備の関係で伐採されてしまっています。切断されて見掛けは全然なくなっている。ああいったものを逆に下葉で補佐して、間伐されれば下葉で日光が当たらないといった感じで、逆に出ているというのが一番いいんです。地面も乾かさないような仕方、常に水を含ませるような感じのつくり方でないと駄目だと思います。 そして逆には、あの三椏も資源なんですね。大事な今のお札は三椏の資源だと思います。ああいった資源を、ここでは有効されてないんだろうけれど、見た感じは切られてしまっている見方は、大変、私は残念に思います。 そういったところは、課長、お互い一緒になって話を前向きに、こういったことでは悪いじゃないかという言い方をしてもいいんじゃないかと思います。それで県から補助が出なかったら、それはお互いちゃんと話合いをすればいいことだろうと思うので、そういったところをお願いいたします。環境税の関係は、一応切らせていただきます。 最後に、農家民泊の件であげておりますが、私は昨年8月ぐらいに九重町まで農家民泊の関係で行かせていただきまして、11月にそういった中で県との話合いができ、最終的に岩屋地域で農家民泊をされたらどうですか、してくださいという言い方で、最終的に3月20日に、岩屋地区で7軒の農家民泊を計画されています。その中で農家民泊がいい悪いじゃなく、その地域が取り組むべき問題が、家庭の中で私の所はどうしてもできない。 あんたの所でしてくれと言われたけれどできない。どうしたんですか。家が散らかってしまって、周りがこんなに散らかっていたら人が来てくれても、こんなではどうしてもできん。あんたの所の家が美しいから、あんたの所でやってくれんかと、そういった話もあったような気がします。 それは私からしたら本当じゃないかなと思います。けれど本当にそこで行政との話合がその身近さ、福岡のほうから来られて農家の身近さを感じる。家が古くても散らかっていても、来たときに農家のありがたみを最終的に分かってもらって帰ってもらうのが、一番本当は楽しさがあっていいだろうと思います。 その中で、私は何回か財務課長にも言ったんですが、そうした中で折角来る中で、トイレ、洗面所は美しいほうがいいのか。そうした中で財政が助成できるのか、そういった中で言われました。その件で何回か言われたけれど、本当に最後まで問い詰めはしておりません。そういった中で、今度7軒が成功したらだんだん増えてくるだろうと思います。 そういった中で、自分の所で利用するリフォームは、いろんな面があろうと思いますが、どういった基準までぐらい助成ができるのか、財務課長分かったらお願いします。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 今回の件につきましては、県のアメニティー構想の中で豊前、築上、上毛、みやこを中心に沢山の農家民宿を将来つくっていきたいという中の、まず、モデル事業という形で今回取り組んだわけであります。今回25名ぐらいの方を福岡から受け入れをいたします。 皆さんマンション住まいということで、農家のあり方を知らないような方ばかりで、言われたように、本当の姿を身近に感じていただきたいという中での体験をしていただきたいと考えています。お風呂とかトイレの問題も、将来的には出てこようかと思いますが、現在、まず受け入れてみて、皆さん方に反省会をしていただいて、今後どういうふうにしたらいいのかということを、何回か重ねながら、将来的に市として支援できる部分があれば、そういう制度も検討されていくのではなかろうかと考えております。 現在、まだはじめての試みですので、何度かそういう経験をしまして、必要なものを行政として検討していきたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 農家民泊は、はじめての体験ですから、その人たち7戸の人の後の意見が大切だと思います。また財政的に風呂とかといったものは、遠くても卜仙でもできると思うので、そういった中で、そちらの風呂を使ってもらったりという考え方もあると思います。 これは奥さんが、うんと言わなければ絶対できないことでありまして、私が一人でやろうと言っても、家内が本当にやる気があって、いいよという言葉の出方、夫婦の話合が一番大切だと思います。そういった中で農家民泊を見ながら、今後どのような方向に進むのか、私も応援していきたいと思っておりますので、これから行政もよろしくお願いします。 最後に聞きたいのは、農林課長、先ほど山崎議員が言われた森林整備事業、シイタケとか、そういった面に対しての補助があるということを言われたと思うけれど、その中で植林する場合に、12月議会で、私はクヌギ苗をできるだけ植林したほうがいいんじゃないかと言ったけれど、クヌギの苗の植林には費用の補助がないと言われたですね。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 それは景観的にと私ども思っておりましたが、山に植林する分についてはございます。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 私が言ったのは、景観的な考えを持たれて、あの時補助がないと言われたんですか。 本当に植林を今からされるなら上まで植林されてもいいんですよ。シイタケ木を山の上につくるんです。そして下のほうにはヒノキ、スギでもいいんです。中間の里山でクヌギ系統を植える。クヌギというのは上から下に下ろすものですから、その途中でホダバというのが必ず必要なんですよ。そのホダバというのはシイタケ木を置く所、確保する所です。 上にヒノキ、スギ山があって、シイタケが下にある、けれど逆に上に持って上がる人はいないですよ。シイタケ木は伐採されたのが、そのまま下の森林整備されている中にホダバとして活用される。そういった形の流れが一番大事と思います。だから植林の中で、私ははじめ勘違いしましたが、補助があれば、そういった補助を活用してもらって、できるだけそういった方向でクヌギ、カシなど広葉樹を植えてもらって、これからの森林のあり方を考えていっていただきたいと思います。 私の時間が過ぎましたので、ここら辺でやめさせていただきます。 後、言いたいのもありますが、京築ヒノキのブランド化の関係も言いたいんですが、次の機会にいたします。これで私の質問を終わります。 ○副議長 中村勇希君 岡本清靖議員の質問を終わります。 次に、尾澤満治議員です。尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 では、3月議会の一般質問は、私は2点について質問させていただきたいと思います。 1点目は、教育問題です。今日は、たまたま県立高校の入学試験ということで、うちの子供も今日、朝、入学試験に行きました。昨日からじいちゃん、ばあちゃんが心配していろんな形で電話をしてもらったりとか、家族皆で、どうかうまく入試がいけるようにと、それが家庭の有難味じゃないかと思いまして、私も小さい頃、かなり親に心配をかけたんだなという形で、今日つくづく思ったんですが、この点で、前回6月議会にも質問いたしましたが、高校推薦入学について質問いたします。 1点目は、高校推薦入学の基準について、教育長から教えていただきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 答弁いたします。前回もお答えしましたけれども、同じようなことになろうかと思いますが、各中学校の進路指導におきましては、推薦入試のために、校内推薦委員会を設置して推薦基準を明らかにして、年度はじめの保護者会で、この基準を3年生の保護者にお知らせして、推薦入学を希望する保護者や生徒に対して行っております。 具体的には、1つは、志望校に対する興味・関心が高く、目的意識が明確であること。2つ目は、中学校3年間、全教科全領域で意欲的に取り組んでいること。3つ目には、3年間、中学生らしい行動ができていること。4つ目には、合格した場合、入学する意思が確実であることなどがあげられています。 校内推薦委員会では、生徒の志望書を精査の上、推薦について協議して、学校として成否を決定して保護者へ通知するような仕組みになっています。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 4つの項目があるということで、校内に推薦委員会を設置するということですが、この校内推薦委員会のメンバーは、前回、聞いていたんですが、校長、教頭、教務主任、進路指導主任、3年生の担当というメンバーでしているという構成を聞いていますが、間違いありませんか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 はい、そういうメンバーで構成していると聞いております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 その部分で、これは推薦をしてもらう保護者は、何時のタイミングで推薦していただくのか。学校側は3年生のときに保護者に通知されるのか、お願いします。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 先ほど申しましたように、年度はじめの保護者会で、その基準を3年生の保護者にお知らせしていると聞いております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 3年の年度はじめということですね。何故かというと、3つ目の項目の中に3年間、中学生らしい行動ができることということでした。この3年のときに言われても保護者は分からないと思います。1年生の入学のときに推薦を受ける方はこういうことだと。 3年間こういう教育、生活指導する者に対して、推薦が受けられるのだということを言わないと、3年のときに言っても遅いのではないか。1年と2年は終わっていますので、私どもとしては、1年生の入学のときに推薦基準はこうですよと、最終的に3年生の時には、言ってもらっても結構だと思いますが、1年生のときから言わないと、急に3年のときに言われても、推薦入学の基準に入らないのではないかと思いますが、教育長はどう思われますか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 議員がおっしゃるとおりでですね、やはり1年生に入ったときから向こう3年間のことを考えて、早めにお知らせしたほうが私はいいと思っております。そういうふうに中学校には話をしていきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 ありがとうございます。これは手帳の問題もありますし、1年の時からそういう基準が、こういうものがあるんだということを親御さんに周知していただきたいと思います。 今年あったのが、私は保護者から聞いたんですが、推薦入学を出したのに学校側に受けていただけなくて、推薦入学にならなかった経過があったということを教育長、聞いていますか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 推薦入学というふうには聞いておりません。専願と、そこだけ受けるということを担任は説明して、親は当初分かっていたけれども、後になって推薦入試というふうに取り違えていて、何か問題があったと聞いておりますが、はじめから推薦入試で推薦ができなかったという話は聞いておりません。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 私が聞いたのは推薦入学と、その前の子供さんも推薦入学で行かれて、次の子どもも推薦入学でいくということで、担任の先生に言っていたけれど、先生は勘違いしてないでしょうか、という形で言われた。勘違いではないでしょうか、ということが、私も言葉のあやで勘違いしてないというよりも、そのときは推薦ですかどちらなんですか、とはっきり言わないと勘違いしてないでしょうか、と先生から言われて、親御さんも憤慨されていたということであったんですが、私はその場にいないから分からないですが、親御さんから聞くには、先生から、そういう形で勘違いしてないですか、と言われたということは、今、教育長が言われた専願という形であれば、それを言えば、その時に誤解がとれたはずだけれど、それを言わずに、そのままずるずるといって推薦入学にしてる、してないということが起こったという経緯は、そのときの担任の先生が、はっきりそのことを言ったほうがよかった、誤解を招かなかったと思いますが、そこはどうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 やはり将来を決める入学試験ですので、丁寧な気持の伝わる説明をしていかないと、事務的に短い言葉でぱっと言ってしまったんでは、相手の保護者の心の中に落ち込まないという点もありますので、生徒に説明するのと同じように、保護者に対しても丁寧な言葉で丁寧に説明していくということは、必要なことであろうと思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 それと1昨年に、ある父兄に聞いた話では、推薦入学について受けたいという親御さんがお願いしたんですが、その方はかなり上位のほうでしたので、推薦入学を受けなくても、そのまま一般入学でいけるから、通れるからという話だったんですが、その人は受けなさいと。ラインの危ない人を推薦入学に回すんだからと、ある先生が言われたということですが、その推薦入学の位置付けというのを、先生達は何か勘違いされているのじゃないかという形を思うんですよね。通すための1つの材料として使っているのじゃないかなと。 昔、我々の小さいときは、頭がよくてスポーツもできた、そういう人達を推薦入学で入れていくという形できてたんですが、今、推薦入学がそういう形で、安易に厳しいところを入れていくような使われ方がされているのじゃないかなというふうに思われますが、教育長はどう思われますか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 推薦入試は、高校の活性化や生徒の個性尊重を理由に、学業やスポーツなどに秀でた生徒を対象に、県立高校すべての学校で行われていると聞いております。以前は、すべての高校でやってはいなかったんじゃなかろうかと思いますが、推薦のあり方が、中身が優秀な子どもを推薦するというのが原則であろうと思いますが、推薦の割合が、どんどん伸びて広がっていることは、私は賛成ではありません。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 1つ提案ですが、校内推薦委員会というのが、学校側で決められますが、その中に民間の方を入れて、校内推薦委員会のメンバーに民間人を入れるということはどうなのか。 民間の力で個人の情報は消していただいて、どういう生徒が優秀でいいのか、そういうところを先生だけでなく民間人の意見も入れながら、そのメンバーの中で推薦をしていくということはどうなのかということを教育長に、お伺いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 やはり365日と言わないまでも、3年間の多くの時間を生徒と先生で過ごすわけであります。民間人が1日、或いは、2日ぽんと入って、その子がどうあるかということについては、非常に判断が難しかろうと思います。教育現場には、その推薦に関することについては、そぐわないかなと思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 学校の中でということで、子ども達は365日じゃないけれど、ずっと休み以外は学校の中にいるので、分からないかもしれませんが、民間のいい所を採用できればしていただきたいと思っております。 それから、地元にある青豊高校、今、教育長も言いましたが、推薦入学、定数が青豊高校は320名の定数に対して去年も150数名、今年も150数名の推薦枠をいただいております。定数は128程度ということで、学校側は言っていましたが、オーバーして158名の推薦枠をいただいていると。今、佐賀県の教育委員会は、協議して推薦枠を減らすような動きが入っております。 何故かというと、学力をつけさせるためにも枠は縮小してほしいとか、枠が広がり過ぎて、生徒が学ぶことを軽視している状況があり、勉強しなくなっているという形。 それから、推薦高校であがった場合も2月ぐらいで大体はっきりしますよね。 それから、まだ一般入試が3月にありますが、それまでの間に学校の運営が厳しくなってくる。もうあがって入試を受ける子との差が歴然と出てきていると。そういう形で佐賀県は、推薦枠を減らす動きをしているということですが、福岡県をみても、青豊高校が推薦入学が一番多い所だと思います。私は悪いとは言ってないですが、推薦枠の中身というか、本当に優秀な子を入れていくことはいいことだと思いますが、安易に考えて推薦枠を使って入っていくことが、一番懸念されてくると思います。 本当に、一生懸命勉強しながら入試を受けることじゃなくて、若いときから楽な方向に行く部分が出てくるのじゃないかなという形が、見受けられる所が多いですが、教育長としては、県の校長の権限で推薦枠を取るということが決められていますから、教育長の方からは変えることはできないと思いますが、そういう形で推薦枠について、もう少し検討してもらうことはできないか教育長、どのように考えられますか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 推薦枠が広がるということは、私の考えですが、歓迎はできないと思います。 ある程度、厳しくして、やはり自分で努力して勝ち取るということのほうが、その子のためには将来のためにいいと思っておりますし、県立学校の校長のほうで推薦の割合を決めて、県教委と最終的に決めていくと聞いておりますので、市町村教育委員会のほうから、どうということは言えないと思いますが、1割、2割の程度であればいいけれども、現在は30%前後が推薦入試で通るというような状況にもあるようですし、少し割合が下げていったほうがいいなと私は思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 先ほど言いましたように、佐賀県は、教育委員会が20市町村あります。その中で18市町村が、この推薦入学の募集枠を縮小することに対して賛成という形で、各市町村教育委員会の意見を聴いた中で、賛成18で保留が1、判断せずというのが1という形です。 各市町村もいろんな形で、今さっき述べたように集中できない状況が起こる可能性があるということで、今、教育長が言ったような形で検討して、縮小するとういう形で各委員会の報告があがっておりますので、私も極力、子どもたちに一生懸命勉強していただいて努力次第で、どういうふうになるのかという形でやっていかないといけないと思います。 その中で、今年の高校の入試で、公立高校に入学する子が減ってきているのじゃないか。 私立高校のほうが若干、今年は人数が多くて定数枠も増やしていましたが、それでも定数割れした学校が結構あるので、教育長、そこのところを聞いていませんか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 ちょっと情報はつかんでおりません。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 東京とか都会のほうは、私立高校に行って公立高校には集らないという現象もありますので、公立高校も一生懸命努力してもらっているとは思いますが、学校教育に対して、これからも頑張っていただきたいと思いますので、本当に豊前市をこれから背負ってくれる金の卵、子ども達が勉強しやすい環境を我々大人がつくっていくのが、第1条件じゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、小規模特認校について質問いたします。昨年夏に、豊前市の教育委員会から合岩小学校、大村小学校が、小規模特認校に指定されたそうですが、指定した経緯、それからメリット及び豊前市の支援について、お伺いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 小規模特認校制度とは、少数ならではの特色を生かし、一人ひとりの子どもの個性を大事にした教育を行う小規模な学校に、市内の通学区域を越えて、どこからでも通学できる制度であります。指定した経緯につきましては、大村小学校のPTA会長及び校長から、教育環境整備の要望がありました。内容につきましては、児童数の減少により、同級生のいない学年、2人から3人の完全複式学級、集団力の育成、体育やクラブ活動に支障を来たしているなどがありまして、それを受けまして、豊前市教育委員会は、豊前市立学校通学区域審議会に対しまして、豊前市小規模特認校制度の導入につきまして答申をお願いいたしました。 審議会より、平成21年8月7日に、豊前市教育委員会より答申がなされまして、豊前市小規模特認校制度を導入することといたしました。メリットといたしましては、小規模ですが、多様な指導形態を組むことができ、習熟度別学習により、一人ひとりの子どもの学力の向上が見込める。或いは、異学年の交流ができ、児童全体がお互いに意見交換ができる。地域との合同運動会などを行っており、地域住民と密着している状況がございます。 市の支援に対しましては、現在、数年前から市雇用の非常勤講師の配置をしております。 また、市のホームページに掲載したり、各保育園や幼稚園の就学時健康診断の時などに、小規模特認校のことなどを紹介しております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 特認校指定の期限は何時まであるんですか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 特に定めていませんが、複式学級が解消できるような、児童が集るようなことになれば、その時点では考えたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 それでは、この前、大村校区民との懇談会、これは釜井市長に出席していただいて、私もオブザーバーで入らせて頂きましたが、この中で、大村小学校の特認校指定に関連する質問という形であげられた部分から、質問させて頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 1項目に、学童保育導入のお願いという形であります。大村小学校は、学童保育と言っても今、全校で21名ですか、そういう形で学童保育は県事業になりますので、福祉の関係でしょうが、1年生、2年生、3年生が10名以上いないといけないということで、それには到底、人数が足りなくて基準に満たないと思います。それを解除するということで、小学校6年生まで拡大していただけないか、という質問がありますが、これについて、市の特区として、小学校6年生まで入れて拡大できないか、教育長、回答をお願いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重髙岑君 学童保育につきましては、教育委員会の所管ではなくて福祉課でありますので、福祉課の課長から答弁をしていただきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 岩本孝子君 お答えいたします。放課後児童クラブの現状を述べさせていただきます。 現在、市内に7クラブ設置されておりますが、1クラブあたりの児童は、低学年児童を対象とする国の補助対象基準の10名以上70名未満としております。設置経過としましては、保護者、地元と協議を重ね、また、将来的な児童数等を考慮し、設置に至っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 1、2、3年生の低学年が10名以上ということで、大村は完全に入らないと思います。 今1年生も1名という形であるのであれなんですが、例えば、今、大村公民館がアンビシャス運動を水曜日と土曜日にやっています。それの拡大で、毎日アンビシャス運動をどこかでやるという形で、その拡大で市が運営費を補助していただくとか、例えば、地域の方が大村小学校の管轄では教育長もおられるし、いろんな有識者がいらっしゃいます。 先生のOBとか、そういう地域の方、それから、大村子ども神楽の指導者とか、かなりのいろんな人材がいらっしゃいますので、そういった地域の方に先生になっていただいて、公民館の中でアンビシャス運動を展開するという形の事業は、補助としてできないか、教育課長、お願いします。 ○副議長 中村勇希君 教育課長。 ○教育課長 戸成保道君 アンビシャス運動展開の中で、学童保育をというお話ですが、一応アンビシャス運動については、対象といたしまして、全学年対象ということになっておりまして、その中に子どもの居場所づくりということが基本になっております。それで学童保育との位置付けを考えますと、学童保育は子どもを保育すると、要するに、放課後から例えば6時までという形になっておりまして、アンビシャス運動の中の活動内容としては、若干、違いが出てきておりまして、先ほど申しましたように、例えば、大村地区では、週3回のアンビシャスをやっておりまして、大体5時ぐらいで終わっているとお聞きしております。 今、学童保育でやられている分は、指導者と補助員等を雇用して、その中で子どもさんを見るという形になっておりまして、アンビシャスは、その中でやっている活動としては、子どもの遊び方とか、伝統芸能というのを教えていくという立場がありますので、アンビシャス運動の中の広がりの中の展開というのは、若干難しいのではなろうかと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 保護者が学童保育がないということでしてましたが、今ないのが横武と合岩、大村の広域にまたがって学童保育をという話がありましたが、広域にまたがっていたら、なかなか難しいところがあるので、そういうところをどうか回避したいということで、金がなければ知恵を出してと、いろんな所でアンビシャス運動、それから、学童保育の変形的な新しい事業をつくっていただいて、子ども達をそこで5時、6時くらいまで見ていただくことができないのか、そういうところを再度検討していただけないかと思っておりますが、今、お母さん方も社会に進出していっていますので、放課後、見る人がいないので、ある所にということで、千束とか山田小学校に行く人が出てきているのじゃないかと思いますが、大村にあれば、少しでも回避ができるのではないかと思います。 そこのところはアンビシャスもできない、学童保育もできないということで、何のための特認校か、メリットがないじゃないかというところもありますが、特にメリットとして、市として新しい補助事業をつくることはできないのか、市長、お願いします。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 この流れを言いましたら、7月のときの八屋、大村区長会、新年意見交換会に私は出させていただいて、大村小学校は生徒が20人もおらんごとなるということでありましたので、それなら、ちょっと膝詰めで話しようということで約束していったわけですが、なんか正式な文章がきたりいろいろあったんですが、ともかく現実を言えば深刻な状況です。 今年で17名減ります。次に深刻なのは1年生から3年生が3人しかおらないですね。保育園、幼稚園はどうかなと。こういう状況で80年、90年続いた大村小学校が、存亡の危機になるのじゃなかろうかと認識したわけでございます。 その中で、2月の終わりに区民の人が全員に呼びかけて50人が集っておりまして、私としては、ともかく本年度は間に合わないけれど、来年にかけて一生懸命作戦を練ろうと言ったわけであります。と申しますには、大村におって大村小学校にいかん人もおるわけです。しかも大村小学校に近い地域の方もおりますので、是非、特認校になったら建前上、誰も来なければゼロですから、接触アタックをしなければならないと思っております。 その議論の中で必須条件としては、学童保育がないと来んだろうと、そうだなと私は思っております。今、市内で学童保育のないのは、横武、合岩、大村です。横武は子どもが77名、合岩は50名、大村は今年4月は17名ですね。こういう状況ですので、教育長も大村の方ですので、よく話をして打ち合わせをして、八屋の人でも大村に行けるように三毛門の人もいいと、行けるようになり実績をあげんといけないと思っております。 ともかく伝統のある学校が厳しい状況だと。それについて静観してはいけないなと思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 ありがとうございます。市長、力を入れていただいて、特に今の話では、市内にいる方が、大村小学校に行けるという考え方が1つあると思いますが、それ以外に豊前市以外の人にアピールしなければいけないじゃないかと。大村の土地に分譲地をつくっていただいて、この分譲で横武みたいな形で定住できる部分、団地という話がありましたが、団地は一過性の流れしかないので、定住できる人を増やしていきたい。 これが大村小学校だけのことではないと思います。豊前市のことを考えたら、人口増対策の中の大村小学校は、逆に言ったら1つのいいきっかけだと思います。そこをどう考えるか、本当に真剣に考えていかないと、豊前市は人口が増えないと思います。ここの成功例で、大村小学校を市が一生懸命やって人口を増やすことによって、豊前市も人口が増えていくのじゃないか。うちの子どもも大村小学校に行けと市長は言いますが、自分の卒業した学校に行きたいと思います。副市長もいらっしゃいますし、教育長も我が地元だと思いますので、ここを本当に生かすためには、いろんな対策を練ってやっていくことによって、天地山公園とか、素晴らしい環境のもとで子供を育てるのにいいと思います。 例えば、福岡とか北九州市で喘息になった子ども達をここに連れてきて、定住させていくことによって体もよくなってくると思うんです。そういう豊前市の最大メリットを使っていただいて、大村小学校が増えていけば、すごいなという形で、豊前市の中で取り合いしても一緒じゃないですか。それより大きく高速道路が出来上がれば、北九州市からでもいけると思います。お父さんは、単身赴任で北九州市まで仕事に行きながら、子どもは、ここでの素晴らしい教育のもとで育っていくということができると思います。 市長もこの前、来ていただいていますし、副市長も地元ですので、小学校の先生がホームページを使ってやっているということで、市もホームページを使って、どんどんアピールしていただきたい。学校の先生は一生懸命やっているそうです。大村小学校は縄跳びで、小さいときからすごい優秀な体育のある学校だとか、子ども神楽がある、そういういろんなメリットがあるので、それをホームページとかいろんな所に、全国にアピールしていただければ来てくれると思います。 また、分譲地、高速道路が通った後、いろいろな所で土地も研究をしている方もあるということも聞いていますので、そういう所を分譲地にしていただいて来てもらって、住まわれた方には、固定資産税を5年ぐらい減免していただいて、6年目からは固定資産税も市民税も入ってきますし、人口増対策にもなるし、本当に逆にデメリットをメリットにしていかないといけないと思いますので、ピンチはチャンスに変えていく、これは市の執行部の企画力というか、人口増対策のためにも、ここを変えていったらすごい豊前市はいい所だと思っていますので、ただ大村小学校のことだけではなくて、豊前市の人口増対策として考えていただければありがたいと思いますので、執行部の方よろしくお願いしたいと思います。 次の項目に移りますが、今、東九州自動車道の建設も一部工事に入りまして、着々と工事が進んでいるかと思いますが、豊前市のインターチェンジ、鬼木から国道10号線までの取り付け道路付近は、豊前市の今からの顔になる位置だと思われますが、豊前市として、このインターから国道10号線のアクセス道路を、どのようなビジョンを描いているのか、まちづくり課長、答弁をお願いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 現在、東九州自動車道はネクスコ西日本により、平成26年度末供用開始に向け事業中であります。また、国道10号線から豊前市インターチェンジまでのアクセス道路であります犀川・豊前線バイパスも、平成26年度末開通に向け、県が事業施工中であります。 高速道路やインターチェンジ開通により、インターチェンジ周辺及びアクセス道路沿道に、新たな市街地の形成が見込まれます。また、高速交通体系からみてインターチェンジ周辺は、工業団地や流通団地等の立地の適地でもあります。 平成15年に策定されました豊前市都市計画マスタープランでは、インターチェンジ周辺の土地利用計画については、豊前の新たな玄関口として、整備促進及び各種産業が展開できる新産業予定地となっており、市が積極的に土地利用を進めていく計画となっております。しかしながら、人口減少時代の到来、少子・高齢化の進展、更には厳しさを増す市の財政状況など、市を取り巻く社会経済情勢も大きく変化しております。 去る2月上旬、犀川・豊前線バイパス協議会委員の皆様に、周辺の土地利用計画の説明を行いました。農林水産課の方からほ場整備、まちづくり課からは、工業団地及び土地区画整理事業の2案の説明を行いました。10年後、20年後の豊前市の将来の都市像が如何にあるべきか、市民の皆さんの意見を聴き、また地元地権者の皆様が何を望んでいるのか。ワークショップ、或いは、アンケートなどを実施し、意見を吸い上げマスタープラン庁内検討会議や策定委員会において、インターチェンジ周辺の土地利用を検討していく予定ですので、ご理解をお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 地元の説明会が2月に行われていますが、地権者の反応という形で説明したということでありますが、インターチェンジ付近を見てみると、不健全な建物がかなり建ってくるということが考えられますが、規制は入られていますか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 現在では、何も規制は変わっておりません。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 道ができた後、いろんな建物ができる可能性がありますので、早急に規制しておかないと、後でいろいろ問題になると思うので、早急にその規制をしていただきたいと思います。 それから、今10号線の所はバリアフリー化と、中央分離帯が一方通行という形で行かれないですね。そういう部分で、地元の方々も早く抜ける道をつくっていただきたいと。 それでないと、一方通行で出るのに遠くまで行かないといけないという形であるので、この付近で先々道をつくる予定があるのか、お伺いしたいと思いますが。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 今年度と来年度で、都市計画マスタープランの見直しを行っております。その中で街路の見直しを行いたいと思いますので、また地元の皆さんと十分協議したいと思います。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 高速道路のインターが出来上がって、アクセスのインターから10号線までの路線は、かなりの方が企業の倉庫とか、いろんな形で道路の脇の周りに張り付いてくるのではないかと思っておりますが、豊前市の顔になる。おりてきて豊前市のどこに行こうかというところがありますので、ここに豊前市の観光案内所、アクセス道路をどう豊前市に入っていいのか、どこに行ったらいいのかというものの案内所を設ける予定はないでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 先ほど申しましたように、今インターからの取り付け道路が、豊前市の新たな玄関口、顔となると考えておりますので、そういう案内所も十分検討していきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 豊前市が前、遊・食・自然の里というキャッチフレーズをつくって、なかなかそのキャッチフレーズのもと、一部はカラス天狗祭りとかでは動いていると思いますが、再度、素晴らしい遊・食・自然の里のキャッチフレーズを使いながら、豊前に来て海産物も山の幸も食べられる素晴らしい町だという形と言えるようなまちづくりを、早急にビジョンをつくっていただいて、地元の方の説明にも、こういうふうに豊前市は考えているんだ、ということを言えるような地域の地元説明会、なかなか地元の方もビジョンが見えないから、折角ある資産をどのような形で利用していいのか分からない。 それから、豊前市のまちづくりが、どのようになっているか分からないから、地権者の方も、どういうふうにするか考えている状態の方もいらっしゃいますので、本当に親身になって豊前市のまちづくりを提案できるように再度協議して頂きたいと思います。 今回の2月についても、もう10月に1回、地元説明会をして、そのまま4ヵ月間ほどそのまま放置されていると思いますので、地元としては、どのようなまちづくりになるのか期待していますので、早目、早目の対策を講じていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次の項目に入ります。市民の方から、豊前市内の商店街に買い物に行くと、駐車場がなくて困るという電話をいただきました。早速調べてみましたら、一部の店には駐車場がありますが分かりにくく、置かれる台数も少なくしておりました。そこで調べている中で分かったことが、駅前の電車の見える公園は、できたときはかなりの人が見に行かれたと思いますが、今ではどのようになっているか、調査したことがありますか。 今、公園の中に遊歩道がありますが、ここには石がゴロゴロ出ています。お年寄りが歩けない状態で石がゴロゴロ出ています。キャッチフレーズでは、お年寄りや子ども達が、汽車が見える公園ということであったんですが、行ってみると石が出ているんですよね。 それが、そういう景観になるのか知りませんが、お年寄りとか子ども達があれは行けない状態なんですよ。あれは10年ぐらい前につくられたと思いますが、課長は見に行ったことはありますか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 見に行ったことはありますし、駅に行くときにあそこをよく通っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 歩いてみたことはありますか。 (・・・) 私たちも石に引っかかるような形が出ています。デザインかもしれませんが石が出ているんです。それと駅のホームから見ると、公園とJRの間に土地があって、ここは草ぼうぼうなんです。私達はこちらから見るかもしれませんが、JRから特急が停まった方が豊前のほうを見ると、草ぼうぼうの公園なんですよね。それを見たことあります。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 草刈は、定期的にシルバー等にお願いして刈っておりますが、たまたま草が伸びている時だったんじゃないかと思われます。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 いや、駅があって公園があって、その間にちょこっと両方ともフェンスを張っているんです。その間に土地がありますが、これはどちらの土地なんですか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 多分JRの土地だと思います。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 どちらでもいいんですが、本当に逆から見ると、豊前市もJRとしても、これは気にしないと。借りている以上は、管理はシルバーがしているか知りませんが、そこの部分は刈ってもらうような形でやらないといけないし、そこの所はそれでいいんですが、豊前市の顔となる所が、そういう形で汚くなっていると。 それから、歩道も石ころがごろごろ出ているという形なんです。現場に何回も行って現場を見て、どうなのかというところがあってしてますので、後の10年、20年の見直しを考えながら、公園は今使ってないですね。自転車が放置されていたりとか、ごみがあるんですよ。そういうところで、再度見直しをするためにも、それとJRの駅の駐車場が少なくて、夕方になると皆さん子ども達を受け入れるための車が駐車しているんです。 例えば、公園の横にJR側に少し土地があるので、駐車場を確保していただいて、JRを待っている方にも少し待ってもらって、公園を見るぐらいの余裕ができるような公園づくりをしてもいいんじゃないかなと。それで商店街にも近いから、止めて買い物をしてもらうとか、そういう形で電車の見える公園で、そういう形で今のニーズにあってない。 ただつくればいいという形でなくて、その後のメンテナンスをどのようにするかという形を考えていただきたいと思いますが、課長、どう思いますか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 夕方の駐車場の件ですが、これは近年、近隣市町村の高校に通学する生徒が多いため、夕方、北口は確かに、宇島駅前は車であふれている状態が見受けられます。 駅前には、その件に関しては、市営駐車場があり30分間まで無料ですので、市営駐車場の利用を指示していきたいと思いますので、その辺ご理解をよろしくお願いいたします。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 僕は駐車場を使うんですが、駐車場も結構、いっぱいに近い所が多いんですよ。 あそこまで行って駐車する人はいないと思います。余裕をもって公園かあるから、その公園で遠くから来てもらう人たちに対しても、市の土地ですから、そこをリニューアルして駐車場をつくっていただいて、公園に行けるような形をとっていただければ、僕は正解ではないかという形があります。駅の駐車場を使えということでなく、駐車場も使う時がありますが、結構いっぱいのときがあります。一部しかない。全部月極めで指定ですからね。 そこのところは、もう少し公園を見ていただきたい。つくっただけではなくて本当に公園を見ていただきたい。公園をじっくりと見て、自分達が利用して本当にどうなのかというところをしていただきたいと思います。 それから、平公園につきましても、今、中央公民館の裏側の駐車場が買収されて土地がなくなりました。今、中央公民館の駐車場は利用者が多くて、公民館長からもあそこには駐車するなという形で言っていますが、できましたら平公園についても、山手側のほうに土地がありますので、コンクリートじゃなくて、ちょっと固めて駐車場にできないのか。 そして、少しでも駐車場を公園に利用してもらう。子ども達を遊ばせる。ひいては商店街に買い物にも行けるような施策ができないのか。公園で駐車場がないというのは、天地山公園というのは駐車場があるから行くと思うのですよね。 今の2つの公園は駐車場を確保してないですよね。それ専用の公園に対しての駐車場はしてません。その近辺にあるからつくらないという形なんですが、もう少し公園を利用する側に立って駐車場完備をしていただけないかと思いますが、課長どう思われますか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 議員さんのおっしゃるとおり、平公園には駐車場がなく、市民の皆様にはご不便をおかけしている状況であります。平公園には、幼児や小学校低学年の子どもの利用も多く、公園内の一部を駐車場にして利用する場合、危険性も発生してくるので、図書館跡地と公園外の近隣の空き地の駐車場利用を検討していきたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 図書館は分かりますが、今度、道ができてから細長い土地になりますので、結構出にくいと思います。結構遠いんです。できましたら平公園でという形で、僕は設備投資するんじゃなくて、今ある土地で最大限に利用できるものはないのかなと、平公園も駐車場じゃなくて、今、ある程度、路盤を固めるのがありますよね。そういうものでカラー舗装していただいて、駐車ができるような確保ができないかと思っておりますので、ただ現場に行ってもらってみていただければ分かるかと思いますが、この2つの公園について、もう少し利用者の立場に立って、もう少し利便性ができないのか、検討課題にしていただけないかと思っております。 私の持ち時間があまりないので、最後に、総務課長に、今年3月で終わりなので、防災については、一生懸命やっていただいています。私も防災について、一生懸命勉強させていただいています。今の豊前市の地域防災計画というのをつくって見させていただきました。これのパブリックコメントについてという形でホームページに出されていますが、これで市民から意見がありましたか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 特段、意見という意見はなかったように記憶しております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 各素晴らしい風水害対策編、震災対策編、事故対策編という3つで計画を組んで、すごい形で見させてもらったんですが、この中で、防災訓練計画、我々もやっていますが、防災訓練計画というのがあって、この中の45ページにありますが、市及び県は災害対策本部の運営を円滑に行なうため、図上訓練を実施するという形で書いてあります。 図上訓練というのは、どういうことなのか教えていただきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 いわゆる地図等を使ってシュミレーションする訓練でありまして、具体的に危険箇所等を想定しまして、その想定に対して、市長を先頭に災害が発生した場合、具体的にどのような対応をするか。議員もご存知だと思いますが、うちはコンビナートを抱えておりまして、九電を抱えておりますので、昨年、九電の場合、図上訓練を導入しまして、市長、県知事の代理、それから自衛隊、海上保安庁の関係者が来ましてしたものであります。 その豊前市だけのバージョンも検討しますよということであります。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○6番 尾澤満治君 最後に、私も1月18日の総務委員会で、この前、独立行政法人防災科学技術研究所に行き研修を受けました。この中で、今ありましたように図上訓練というのが、eコミュニティプラットホームというのを前回も説明させて頂きましたが、これを使って防災訓練ができると。今、課長が言いましたように図上訓練というのは、この分ですごい機能をしております。 1つ目は、商店街のマップとかグルメマップ、環境マップ、防災マップ、犯罪マップ等の地図を作成して公開することができる。それから、一人でマップをつくるんじゃなくて地域のいろんな人が力を合わせて、地域やコミュニティ全体で協議するマップをつくることができる、そういうものがいろいろ作れるんです。こういうものをうまく使いながら各公民館で今やっていますように、防災訓練をしていただくような形でとっていただければありがたいと思います。 次の課長に引き継いでいただいて、そういう訓練を現地で本当にやらないと災害が起こったら大変なことになりますので、ないとは思いますが、ここは地震がなく、何もなくても、この前みたいに津波が横から来る可能性もありますので、そういう訓練を使っていただければありがたいなと。これは無料で開放していますし、情報は全部入れていますし、今度、防災マップができるんですね。そういうデーターを全部取り込めば素晴らしいものができると思いますので、これを利用していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、時間が延びてしまいまして私の質問を終わります。 ○副議長 中村勇希君 尾澤満治議員の質問を終わります。 次に、山本章一郎議員。 ○13番 山本章一郎君 残り16分、3本勝負でございます。今回、私が通告しましたのは、総合計画、行財政改革プラン、集中改革プラン、農村・農業について、新政権での国と地方の関係についてと、この大きな3つの項目について、お尋ねしたいと思います。 全部について質問したいと思ったんですが、時間の都合で、最後の新政権での国と地方の関係について、特に、中身は農政の仕組みがどう変わってきたのかということで、財務課長にお尋ねしたいところですが、新年度予算の編成も終わって議案として提案されていますので、委員会の方で仕組みがどう変わって積算根拠はどうなったと、かくかくしかじかで、何ポイントか、何%か、増額しましたという説明を委員会でいただきたいと思っております。それで時間の限り責任ある答弁をいただきたいと思いますので、簡単に答弁出来るほうから、お尋ねしていきたいと思います。 まず、最初に農村・農業について、その1つは、前議会で南部地区で取り組みました5年に1回の三大神楽祭りの開催についてということで、市長にお尋ねいたします。 前議会では、ちょっと微妙な所があるということで、的確な答弁をいただけないままになっております。それで重ねて質問ですが、今年、5年に1回の三大神楽祭りについて支援するつもりがあるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 今度は合河の担当でございました。ただ合河の方に聴きますと、ちょっと無理だということを言っておりましたので、22年度の予算にはあげておりません。こういうことでありまして、今、言えることはあげてない。ただ北高の跡に神楽殿もできるし、精神はついでいけるなと思っておるところであります。それ以上の話は今までのところありません。 ○副議長 中村勇希君 山本議員。 ○13番 山本章一郎君 是非、その精神を引き継いでほしいなと思っております。それで、ちょうど北高跡地の体育館が多目的なホールに変化します。これを機会にこけら落としとして、日本全国の神楽に集まっていただいて、京築の神楽を盛り上げるように予算化をしてほしいと思いますが、如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 ご質問ですが、一応、福岡県も神楽殿にしてくれるということでありますし、また11月にテストをやろうと、県知事も来るということでございます。それについて、質疑までにいきませんけれども、一応、本年度200万円の予算を組んでおります。 ○副議長 中村勇希君 山本議員。 ○13番 山本章一郎君 そういった機会、それから県の力を寄せ集めて、全国から神楽ファンを豊前市に集めてほしいと。その経済効果も著しいものがあるかと思っております。是非その開催については、私も全力を尽くしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次いで、農業について新しい農政、午前中、山崎議員の質問、それから、先ほどの岡本議員の質問の中で、コメの戸別所得補償、それから、主食用のコメをつくれない所に対する所得の話がありました。私も私なりに、自分所の営農組合の農作物を取り組めば一番所得が上がるのかを試算しているところであります。一番儲かるのは主食用のコメをつくる。これは現行の中で、全水田面積の60%しかできません。残り40%の水田をどういう取り扱いをするかということで、私の所は飼料用米をつくろうと思っております。 これと同時に大豆、麦、それから加工用米、麦をつくって、1年二毛作でやると、ほぼ同じぐらいの所得が残るかなと思っております。ただ営農組合には所得は残らない。 係る経費を引き、日当を引く、それから借入金を返済する、いろんな諸経費を引きますと、手元には組合としては利益が残らないのが現状です。これが主食用米を作付けしますと1万5000円の交付金がもらえる。これが純粋な所得だと思っております。 うちの営農組合の場合、約2町歩ぐらいが対象ですが、合計しますと30万円の所得が22年で営農組合に残るという計算を私はしたところであります。 そこで、お尋ねですが、この所得格差、年二毛作に取り組んで、主食用の国が保障するコメの所得と転作をやって二毛作であれば出来る所得差は、市が補填するべきだと思いますが、農林課長のお考えは如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 ご質問の所得格差の補償につきましては、現在のところ国の制度を活用して、最大限に努める営農組合もありますが、ここの営農形態が、それぞれ違うものですから、あくまでも私たちは、今の農業者に対して最大の組み合わせを提案しながら協議していくということで、現在のところは市がそこで補填するということは考えておりません。以上です。 ○副議長 中村勇希君 山本議員。 ○13番 山本章一郎君 私のもう1つの提案は、今、合河にあります卵の里の鶏舎から出るいろんな悪臭とか、ハエ、網の目をくぐるような虫の被害が多く聞かれています。これは全く改善策ができてない現状でもありますが、これをうまく逆に鶏糞を利用すれば、地域で取り組まれているような方法でやれば、これが解消できる。そういった所に市が独自の補填をしながらやっていけば、この2つがうまく解消できるのじゃなかろうかなと思っております。 今後の検討課題として考えていただきたいと思っております。答弁はいりません。 後1つ、農業の独自産業化ということで取り上げられました。これは午前中の山崎議員のやり取りの中で、市は全く何も考えてないというような現状かなと思っております。 今からの農業の担い手、これに取り組まなくては、地域の経済は成長はないと私は思っております。この点についても、十分検討を重ねてほしいと思います。 これで農村・農業については検討してくださいということで終わります。 そういった中で、先日、集落の中で会議を開きました。これから10年後この地域、この村はどうなるんだろうかという会議をしたところです。その中で人口のことについて、皆さんと協議いたしました。具体的にはアンケート調査しながら、今後、自分の家の中、年代がどうあって子どもが生まれてくるのか、このまま家族が1人減り、2人減りするのかということで、10年後を想定したときに、今から15%の人口が減るだろう、家族が減るだろうという答えが出たところです。これはあくまで想定ですので、実数とは少し違うかもしれませんが、これを豊前市全体に移し変えたときに、今2万8000弱の人口が、10年後には2万5000人になるということが、目の前に見えているという気がします。 そこで、市長にお尋ねですが、総合計画後期基本計画の中で、目標人口には到底及ばないと思いますか、この見直しは何時図るのか。今年から来年にかけて新しい都市計画を練られるでしょうが、その辺のことを少しだけ、お聞かせ願いたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 後期計画の方向を出したばっかりでございます。税率の件等も今議会に出しておりませんが、いろんな関係で挑戦していくということでありますので、あの設定は生かしていきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 山本議員。 ○13番 山本章一郎君 市長のマニフェストの中にも、豊築は1つというのがあったり、人口増を目指すということもあったり、いろいろあります。特に、その中で固定資産税の見直しもあります。 当然、収納率も高める、その先頭に立ってやるのも私だ、というマニフェストもありますが、そういったことはきちっとやっていってほしいなと思います。 それで通告しておりまして、質問の中に入らせていただきますが、今年で集中改革プランは最終年度を迎えますが、担当課長にお尋ねですが、3つのプラン、成果と課題もあると思いますが、簡単にお答え願いたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 成果については、私から申し上げたいと思います。豊前市行政改革大綱については、平成17年から平成21年までの5ヵ年計画を計画期間として、民間活力の導入や、定員管理、補助金等の整理・合理化などを中心に、本市の改革指針を示したものであります。 また、この大綱に基づきまして、取り組みを計画的に実施するために、集中改革プランを作成し、その成果についても、市民の皆様に広くご理解をいただくため、広報で毎年、公表しております。集中改革プランの項目の中には、計画に対して遅れている事業もありますが、目標以上の成果をあげ、21年度までの財政効果額は、当初計画に対して140%に達する見込みであります。以上です。 ○副議長 中村勇希君 山本議員。 ○13番 山本章一郎君 課題について、お尋ねしたいところですが、もう3分しかありませんので、すべて聴くことができないので、男女共同参画社会を構築していこうということで、いろんな委員さんのパーセンテージ30%、庁舎内では、課長さんの職を30%ぐらいに持っていきたいとか、副市長を女性にかえるとか、その他あるかどうか分かりませんが、そんな目標がありますが、今、教育委員さんは5人に1人で、5分の1で20%、先ほどから執行部席を眺めておりましたら、21の椅子があって、今、お三方だけ左側におりますが、これはパーセントに直すと15%、そこで総務課長にお尋ねしますが、行財政改革ということもあって、収入役の席をなくして会計管理者に。その当時は三役から事務方のトップになるからということで、三役と同じ扱いにするべきだという考え方があります。 今聞くところによりますと、会計管理者は女性職員で課長補佐級だと、最初の男性のときは課長級と聞きましたが、これは課長級を置くべきだと思いますが。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 男でしたら課長、女でしたら課長補佐という考え方で、基本的に決めているわけではございません。うちと規模の同じような自治体の今日的な状況、人員をかなり減らしておりまして、いろんな関係から現状になっております。また、管理職の登用等を見ても、目標の30%ほど遠いではないかというご意見だと思いますが、係長職につきましては、現在45ぐらいいっていると思います。おいおい半分近くが、女性のリーダーになることは間違いありませんので、今暫くご理解いただきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 山本議員、終わりましたか。もうゼロです。 ○13番 山本章一郎君 もうゼロ分になりましたが、まだ1分間だろうと思っておりますが、ゼロということでありますので、後、委員会でお尋ねしたいと思います。その時はよろしくお願いいたします。終わります。 ○副議長 中村勇希君 以上で、ぶぜん風の会の質問を終わります。 ここで議事運営上、暫時休憩いたします。 休憩 15時00分 再開 15時30分 ○副議長 中村勇希君 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続けます。同志会の質問を行ないます。 本日は、福井昌文議員が欠席しておりますので、爪丸議員のみの質問となります。 それでは、同志会、爪丸裕和議員、お願いします。爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 それでは、本日、最後の質問ということで、同志会を代表いたしまして質問させて頂きます。先ほど議長からも、お話がありましたように、我が同志会の福井昌文議員が、病気のため欠席ということになりましたので、質問項目の1番、2番、3番については、今回カットということで、4番、5番、6番の3点についての質問ということになります。 それでは、早速、高齢者雇用促進についてということで質問に入らせていただきます。 先日の新聞に、我が国の労働者人口が減少の傾向に入ったと、このような記事が新聞に報じられておりました。団塊の世代の方々が定年退職を迎え、当然のことと感じております。 また、更に、少子化が進む中では、雇用情勢は、今後益々悪化するのではないかと懸念いたしております。その点を踏まえまして、どのように解消しなければならないのかということになれば、当然の如く、やはり今、高齢者も健康な方々が多のいであれば、このような高齢者の方々にしっかりと働いていただくと。かつて松下幸之助さんは終身雇用ということも訴えられておりました。この点について、国だけの政策ではなしに、今、分権時代を進める上でも、地方自治体として、どのように取り組んでいくかということが、大きな課題ではないかというふうに考えております。 それと、先日、オーストラリアは、現在、高齢化率が13%、そして40年経ってもまだ22%なんです。そのような国においても、国をあげての高齢者の雇用促進ということで、しっかりした予算を組んでいるわけです。そういう点も踏まえて、執行部の今の市内の状況と、豊前市の取り組みについて聞かせていただきたいと思います。 まず、分かる範囲内で結構ですが、資料もここに頂いていますが、今、市内における高齢者、65歳以上の雇用の状況はどうなのか。そして、行政としての取り組みについて、まず、ご答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 岩本孝子君 お答えいたします。 (「雇用状況について質問したんですが」の声あり) ○副議長 中村勇希君 税務課長。 ○税務課長 石橋正昭君 お答えいたします。先日、議員から65歳以上の雇用状況についてということで、調査を依頼されまして資料を作成いたしました。過去5年間ということでありましたが、私の手元にあるデーターは、平成17年から20年にかけて4年間であります。 その中で、年金以外の収入のある方について調査いたしましたところ、給与収入等ある方については、全体が2234、その中の1637人が、平成20年度において収入があるという状況になっています。給与収入については、平成17年から4年間で、約600人ぐらい増えているということで、雇用状況は詳しく分かりませんが、収入の面から見ますと、こういう給与収入のある方が増えてきているというのが、一般的に言われるのではないかと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 それでは、福祉課長にお尋ねしますが、今、市内における高齢化率と高齢者の数、過去5年、分かればお答えいただきたいですが。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 岩本孝子君 5年間全部でしょうか。 (「分かれば」の声あり) 平成17年3月末65歳以上7719人、高齢化率26.75%。平成18年3月末7777人、27.22%。平成19年3月末7894人、27.88%。平成20年3月末8034人、28.51%。平成21年3月末8120人、29.03%。平成22年2月末8181人、29.39%となっております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 分かりました。ほぼ30%というような形になっているけれど、税務課長にお尋ねしますが、今、お宅の資料で、先ほど課長も言われましたが、給与収入について、17年度から20年度で確かに600人ほど伸びているんですよね。19年度まで横ばいで行きながら、一挙に20年度で450人ぐらい伸びているんですよ。450人あがっているけれど、高齢者の数については、そんなに伸びてない。100人ちょっとしか伸びてないですよ。 給与所得の方が、僅か1年の間にこれだけ伸びた、その要因というか、その中身について分かれば答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 税務課長。 ○税務課長 石橋正昭君 ちょっと詳しいことは分かりませんが、平成20年度におきましては、この数字データーから見ると増えているということになっています。詳しい状況は把握しておりません。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 疑うんじゃないけれど、数に間違いはないですか。 ○副議長 中村勇希君 税務課長。 ○税務課長 石橋正昭君 私のほうが電算のほうに依頼いたしまして、電算の持っているデーターから切り出していただいたところでございます。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○4番 爪丸裕和君 お宅のほうが、そういうのであれば、課長、ここで議論してもあれだから調べてみてください。高齢者の数がそう増えてないのに、ここだけなんで一気に増えたのかというのがそこに私は疑問がありますので、ここで議論しても時間の無駄になるでしょうから、これはしっかり、もう一度調べてみてください。 これが事実なら、いきなりポンと増えたような形になってくるんですが、これは給与所得の方は分かりましたが、福祉課長、シルバー人材に登録されている数は、過去5年、分かればお聞かせいただきたいのですが。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 岩本孝子君 お答えいたします。60歳以上の会員登録者は、平成16年366人、平成17年386人、平成18年372人、平成19年391人、平成20年399人、平成21年、現在414人となっております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 もう、この数字を見てもお分かりのように、実際に高齢者の数が伸びているのと比較して、雇用の情勢が伸びているということは感じられないわけなんですよね。 だから、労働人口は低下してくるわけです。そこで、これは企業の問題だとか、シルバーには市から補助がいっているでしょうけれど、市内の老人会等に働きかけて、健康な方はできればシルバー人材に登録して頂きたいとか、また農業をやるなら支援等も考えて、健康に働いていただくということを促していくことが重要ではないかと考えております。 この点については置いとって、後は、市内における企業の、これもやはり高齢者の雇用の状況等が分かる範囲内で結構ですので、まちづくり課長さんに、ご答弁をお願いします。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 市内の主な企業100社ぐらいですが、毎年6月に企業にアンケートをお願いしていますが、現在では高齢者に関しての項目は、女性が何人とか、外国人が何人雇用しているとか、そういうアンケート調査を行なっていますが、現在は65歳以上の高齢者については調査を行っておりません。来年からそういう項目を入れるか検討していきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 そのようなことも各企業にも、お願いしていただくというのも、1つの行政の仕事ではないかと考えております。このような状況を踏まえて、豊前市としての市の政策ですね。 豊前市としてどのように取り組んでまいりたいという考えがありましたら、お聞かせいただききたいと思います。その雇用改善に向けてですね。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 ちょうど、私も65歳を過ぎまして、元気さはちっとも変わらんなと思っております。ただ失礼な言い方ですが、70歳過ぎましたら、いろいろだろうかと思いますが、60歳になって退職して、豊前に帰る人が相当おるんですよ。やはり家にじっといても、何もプラスにならないし、少なくとも65歳までは働くべきであるし、健康のために。そのようなチャンスを与えるべきだと思っております。66歳から70歳、70歳以上の方は、今から模索しながら、どうしたらいいかを考えたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 後から、うちの会派の会長からも、お話がありましたが、会長は75歳ですかね。 後期高齢者、それでも、まで元気にやられていますので、だから65歳は釜井市長が言われたように、まだまだお若いんですから、そのような方々に、しっかりと仕事をしていただく場を提供するのも、行政の役割じゃないかと。それは企業の問題だとか、先程言ったシルバーの問題で片付く問題じゃないんです。それと質問の主旨を冒頭にも申しましたが、地方分権改革推進委員会の委員長で今、会長さんか顧問だったか、伊藤忠商事の丹羽宇一郎さん、この方の講演を私も聴いたことがありますが、我が国は人口の減少に入っているわけです。 世界の国々の中で、人口が減少して、経済成長を成し遂げた国家はないと言われているんです。だから必ず今からの日本経済というのは絶対、衰退していくんだと。特に、先ほど言いましたように少子化というのは、これを加速化させるわけです。これを打開するのであれば、やはり労働人口を増やすことが一番大きなポイントになってくるわけですよ。 この点を十分に市執行部は認識していただきたいと。雇用の低下というのは、言うまでもなく税収は落ち込みますよ。そして健康維持につながるかどうか、働いたほうが健康じゃないかというデーターも実際出ております。そういうことになれば、毎年1兆円ずつ膨らんでいる社会保障費は、ここでやはり歯止めをかけることもできるわけなんです。 地方分権の時代ですね。この辺から国じゃなしに今、地域主権だということも民主党は言っているから、そのような中で、今、豊前市として高齢者雇用問題について30%近いから、いずれ30%越えるでしょう、これは。その辺を見据えて豊前市としてのしっかりとした取り組みに期待したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、2点目の観光事業について、ということで質問に入らせていただきます。 12月議会のときでも質問していたと思いますが、まず、最初に、まちづくり課長。 JRのカキ小屋の成果を、これは実際に期間は3月14日まであるんですね。今ちょっと分かる範囲内で成果について、ご答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 只今の質問ですが、JR九州と豊築漁協と提携して企画したカキツアーの成果ですが、1月9日から4月31日まで、当初の予定は、まだする予定だったんですが、どうも漁協のほうでカキの在庫がないということで、4月いっぱいで打ち切ったそうでございます。 その期間ですが、主に北九州方面から約300人が、豊前海一粒ガキの炭火焼の体験をしていただきまして、その一部は割引料金で天狗の湯も利用していただきまして、大変好評だったと聞いております。今後も引き続き、JR九州と連携して取り組んでいきたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 これはカキが不作だったのかな。それとJRの今後の考えについてはどうなんですか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 宇島駅長に聞きましたところ、今回予定が早く終わったから、まだ今回の分析はできてないそうでございます。カキについては、例年どおりと聞いております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 じゃ見込み違いだった。300人が多かったという感じでいいかな。決して多いような数に思われないけれどね。JRとすれば来年度もやるという認識でよろしいかどうか。 ○副議長 中村勇希君 まちづくり課長。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 まだ未定ですが、こちらはJRにお願いしたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 カキは、ちょっとここで置いときます。同じく12月でも質問したと思いますが、岡本議員からもありましたが、豊前市のシンボル、文化財というのは、修験道求菩提山じゃないかと思います。この立派なものを生かした観光事業に真剣に取り組んでいただきたい。 市長、一緒だったけれど北島はるみさんですかね。岩屋の区長会長がステージで、なんと言われたか。まず岩屋があって、卜仙があって、求菩提資料館があって、そして豊前市があると言っているんです。そのようなまちづくりを目指してもらいたいわけです。 折角こういう立派な求菩提山があり、卜仙があり、あれだけの資料館があれば、そこをしっかりと、そこのところを前回も言ったけれど、点になって点と点が線になる。点から線、線から面にというところが、全く横の連携が取れてないというのが、私の率直な意見なんですよ。だから行政の縦割りで、文化財だったら教育課でいいじゃないかとか、卜仙なら指定管理者制度については、農林水産じゃないかとか。観光事業はまちづくりじゃないかと、そこの意見が全部ばらばらなんです。先ほどの意見にもありましたが、東九州自動車ができることにより、豊前インターから、すべて北側になりますが、蔵春園があり、千手観音があり、その次は如法寺です。そして求菩堤山があり、卜仙があるわけですよ。 この事業を日帰りの文化観光、温泉ツアーというような1つのものをつくっていただきたいということを、12月にも申していたんですが、その後の進捗の状況について、お尋ねします。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 13年前までに、市外の人が豊前市に来るのは20万人ぐらいでした。 12年前に道の駅ができまして、130万人の人が来ております。そして卜仙ができ8万人、資料館を含め15万人ぐらい来ていると思います。天狗の湯も10万人、汐湯も7~8万人、畑の冷泉も水汲みを入れましたら、かなり数万人来ていると思います。 それを今、言われたようにつないでもっていく。これは非常に大事でありますので、築上北校の跡地の件も、まち中に130万人来た人にも、また来てもらうということを考えるべきですし、また次の項目の質問の定住圏構想は観光のテーマであります。 福沢諭吉ばかりが、そのメインじゃありませんので、中津は福沢諭吉、それなら豊前は求菩提、道の駅、道の駅は中津はありませんので、そういうことで、向こうの方にも来ていただくという効果を具体的に発するべきだと思います。これは見本はありません、歩いて見本を示すという気概でいきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 観光入り込み客の数のことばかり言われますが、道の駅に立ち寄る程度の客が増えたに過ぎないのではないかと思っているわけです。課長に聞きますけど、卜仙の郷は経営の状況はよろしいものじゃないのではないかと見ているわけです。その辺は如何なものですかね。経営状況について、お伺いします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 卜仙の郷につきましては、平成10年にオープンしておりますが、それから、18年に指定管理者へ移行しています。過去5年くらいから見ますと、利用客については約8万6000人ぐらいが来ております。平成20年度末で約7万9000人になっております。 景気の低迷があって、全体的に利用客が少ないということが見られまして、対前年の状況から12月末で見ますと、落ち込みが若干出ております。それについても今、理事と職員も一緒になっていろいろ検討して、改善策をやるということでしてます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 課長、お尋ねしますが、経営上に債務が膨らんで経営破綻ということになったらどうなりますか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 この施設につきましては、山村振興運営組合というものを岩屋地区でつくって、約47名ぐらい出資してつくった組合ですので、経営について、そこで立て直さないと、この施設そのものが、山村振興という施設でありますので、破綻したらどうかと言われますと難しいところがありますが、そうなる前に行政ではなく管理者だから知らないということじゃなくて、私どもも一緒に入って経営を見ていくということで、今調整しているところであります。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 課長、そこなんですよ。だから破綻する前に手を打たなければならないから、右肩が上がっているなら、私もこんな質問はしないわけですよ。一番懸念している所はそこなんですよ。天狗の湯もあるし、畑冷泉もありますが、卜仙だけ何故位置付けているかと言ったら、先ほども言いましたように、折角の素晴らしい文化財があるわけなんですよね。 そことの折角のチャンスを生かしきれなかったら多分、将来は駄目だと思うんですよね。 京都の北のほうに綾部市という所があります。そこでの条例が、水源の里条例というのをつくって、ここは限界集落なんですよ。高齢化率は100%なんです。だから65歳未満の方はいないわけですよ。このままでは大変だということで、あらゆるものに補助金をつけるという条例の内容ですが、本市におきましても、犀川の水源になるのが上川底ですね。岩岳川の水源になるのが産家なんですよ。中川の水源になるのが櫛狩屋なんですよ。 角田川の水源になるのが畑、山谷です。この4つの集落の中で、一番チャンスに恵まれているのはここだと思うんですよ。この卜仙の郷、求菩提山があるんだから、そこをうまく生かし切れてないからやっているんですよ。 だから当然、卜仙の郷の指定管理を受けている側としても、当然、企業努力はやられているでしょうけれど、そこは折角の文化財になるのであれば、そこを何故うまく結びつけるような手助けを行政がしないのかなというのが、今回の質問の主な主旨なんですよ。 12月もお話しましたが、その後、お三方で話し合いされました。教育課長と農林水産課長とまちづくり課長で、如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 教育課長。 ○教育課長 戸成保道君 12月の議員さんの文化観光ということで、ご質問がありまして、その時点で、一応ガイドボランティアということでご質問頂きました。そのとき、お答えが不十分だったと思いますが、その分の補充ということでありますが、一応ガイドボランティアにつきましては、求菩提資料館のほうでやっております。 現時点で、会員が35名程度ですが、一応、史跡案内ということで3コース組んでおります。今で申しますと、求菩提1日コース、それから求菩提2時間コース、それから求菩提資料館から岩洞窟、如法寺、千手観音等の3時間のコースを組んでおります。 この分に史跡ボランティアにつきまして、このコースをやっていきたいということと、現在やっておりまして、ガイド実績は12回、資料館の案内は40回、資料館につきましては、先ほどお話がありますように卜仙の郷等のお客さんが、資料館等に案内されて、そのときに説明するということであります。 その時点で、史跡をどういうふうに活用するかという話がありまして、現在、まちづくり課と北九州地区の観光パンフレットを合同で作成中でございます。その中で、求菩提資料館を取り上げていただきまして、PRに努めるということと、今度、京築アメニティーの観光ガイドがあります。この中で、一応、観光行政等の連携を取りながら豊前市のPR、要するに文化観光にPRをしていきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 教育課長、1番の公募と思うけれど、今15名と言われているけれど、実際ボランティアガイドがおられるとか、全く市内でも知られてないと思うんです。となれば、市外から呼び込もうと思ったときに、それをどのようにして求菩提山に修験道がありまして、そこにはこのようなボランティアガイドの方がおられますとか、そういったチラシ等配布されていますか。出回っているのかどうか。全くそこの所が一方通行で、客にしてみたら分かってないのじゃないですかね。 ○副議長 中村勇希君 教育課長。 ○教育課長 戸成保道君 その点で先ほど申しましたとおり、市内の方がなかなか分かりにくいという点と、市外の方が分かりにくいという点で、ご指摘がありました点で、先ほど申しました、まちづくり課とのパンフレットの中に入れていきたいということであります。 それと、求菩提資料館の案内等、ホームページ等に、史跡ボランティアを出していきたいということで、おっしゃられるように、なかなかPRが足りないということは重々感じておりますので、これからも如何にPRしていくかということを考えていきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 まちづくり課はともかくとして、卜仙がなんか置いていかれたような感じですが、農林水産は、卜仙の郷を巻き込んだようなところで、どこかの旅行会社が受けるか受けないか1回話に行ってみたら如何ですかね。JRはJRなりにやったのが、これですからね。 JRがバスツアーなんかやるわけないでしょう、客が減るわけだから、だからここでウオーキングを入れて、このような商品ををつくったわけですよね。カキ小屋を。 それは旅行会社に行って日帰りバスツアーはどうですか、ということで、そこのところを3課がお互いに連携をとりながら、真剣に取り組んでいく覚悟がなければ私は出来ないと思うんですよ。奥本課長、やる気は如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 この件につきましては、実は先日来、卜仙の郷の役職員、全職員が集って研修をやりまして、その中で職員からもそういう声が出ました。是非お客さんが沢山来るような政策を私たちも頑張りますと。じゃどういうことができるのかということで、今、役員も一緒になって、まず企業をまわる、各旅行会社をまわる。それから、岩屋地区は景観条例を昨年制定しまして、この条例に基づいて、教育委員会と私ども農林水産課と今度、景観農振計画をうちが立てるわけです。それを一体としたもので、岩屋地区を保全しながら、地域の観光を目指そうという形を、卜仙を核にして入り込み客をつくっていこうと。 現在、求菩提資料館にも、卜仙のお客さんが沢山いくし、また資料館に来たお客さんも卜仙に寄る。それから、キャンプ場に来た人も、卜仙のバスで迎えに行って夜入浴していただくと。今回の民泊ツアーも、各家庭でお風呂に入るということもいいんですが、温泉体験入浴という形で、25名をとりあえず卜仙に連れて行こうという計画をして、皆が議員が言われるように連携をとらないと、なかなかできませんので、私どももはじめて分かってきたし、特に受け皿になっている指定管理者の皆さんも、そういう意識の改革を持とうということで、努力をやりましょうということになっていますので、ご理解をお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 そのとおりです。しっかり取り組んで頂きたいと思います。当然、横の連携を取りながら。ついでに今話が出ましたから、景観条例を制定して、豊前市も鳥井畑から上ですが、文化的景観を目指していると思いますが、その後の進捗状況は如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 奥本隆己君 昨年来、この景観農振については着手しまして、今年度一応つくり上げると。 現在のところ、実は国から昨年、特別に九州管内で1地区景観農振のアドバイザー派遣事業を受けてくれないかということで、国から直に3回ワーキングをやりまして、自分達が残したいもの、今後どうしていくかと。その中で棚田を保全する、また若干整備しないと農業ができないと。今の景観をつくった上での農業振興を図る、景観農振を具体的に実施して、一応3月末ぐらいをもって農政局まで協議に行くように準備しています。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 折角、条例の制定もいたしたことですし、やはり国もそのような声かけということであれば、国の重要文化的景観を目指すぐらいの思いで、それと何度でも言いますが、求菩提修験道と卜仙の郷と結びつけて、しっかりとした1つの旅行のセットプラン、商品をなんとか前向きにつくっていただくように期待して、この観光事業については終わります。 3番目ですが、定住自立圏構想です。これは中津までのバス路線については、西鉄、二豊交通が撤退ということになり、利用者にとっては、不便に感じている住民も少なくないのじゃないかと。こういう中で今回、定住自立圏構想、これは中津市と提携しまして、いよいよ4月から中津までバスが乗り入れされるということになれば、当然、豊前市内の方でも、市外の病院に特に通院されている方とか、また見舞いに行かれる方は、本当に助かるありがたい事業だと見受けている次第です。 そこでお尋ねしますが、このバス路線ですが、バスの停車場について答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 バスでございますが、当初いろんなご意見を頂きまして、市バスがありますので、乗り入れの提案をしたんですが、中津駅から私どもが最終目標にしております市民病院の間は、北部大通交通バスという大分交通の子会社が運行しておりまして、これとの競合がありまして、今日、競合路線の乗り合いバスがある場合については、そこの承認がもらえないと新規参入が出来ないという大前提があるわけであります。 そういうことで、どうしても大交のほうから、来られることについて同意できないということでしたので、その件については、残念ながらあきらめざるを得なくて、大交のほうに委託しまして、こちらのほうに足を延ばしていただくという方法を取ろうということで、中津市、私ども、大交と合意いたしまして、現在、4月下旬を目標に運行開始を目指しておりまして、基本的骨格は出来上がっております。 答弁が長くなるとお叱りを受けますので、どういう走り方をするのかと言いますと、豊前市役所を起点とします。終点は中津市民病院でございます。この間11.8kmありまして、まず市役所から駅のほうにおりてきまして市民会館まで行きます。 市民会館でUターンしまして、一木の八屋のバス停から、市民会館方面に行きまして、市民会館でUターンしまして、八屋の中野のバス停として、現在、市バスが走っています三毛門まで走りまして、現在、三毛門の郵便局があります。ここにバス停を設けます。 それから、残念ながら吉富については、今回、市長とも協議しまして門戸を開けたんですが、このバス事業について、吉富行政から支持と共感を残念ながらいただいてないということで、どうかして市としては門戸を開けまして、うちの副市長にも向こうのリーダーとも話し合いしていただきまして、いろんな努力をしたんですが、結果として合意に至らなくて、広津、直江という2つのバス停は、残念ながら現在通過という形になっておりまして、後は図書館前、中津駅前から要所、要所の病院がありますので、旧街道を走りまして川嶌病院前を通りまして、約20箇所のバス停を設けて走るようにしています。 図書館から東本町というのは、駅前になりますが、新総合庁舎の入口、これは要するに、ゆめタウン前になりますが、牛神、一ツ松、宮夫というのは川嶌整形の前になりますが、終点が中津市民病院前というようなバスルートで走るようになっております。 吉富あたりについても、病院がありますので、理解をいただければ、ここにもバス停を設けたいという方向で、気持は今でもありますが、なかなか残念ながら協議が不成立に終わっておりまして、現在のところ通過ということで、取り組んでいる次第でありますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 まず最初に1点が、豊前市役所から始発ということでしょうけれど、そうなれば、その時間というのはアクセスというか、合河からくだってきますね。その時間帯は考えられているのか、如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 新聞報道でも、ご案内しておりますが、片道4便、考えておりまして、朝、集中的に病院に行く時間帯に2便、それから昼からも走らせます。これは見舞い、或いは、いろんな病院の透析等の関係で、村上記念病院に行く市民が非常に多いと聞いておりますので、こういった問題を考えますと、透析は4時間ぐらいかかりますので、昼からも走らせる必要があるだろうということで、午前中は2便、昼から2便、中津の市民病院からも朝2便、昼から2便ということで考えております。 この接続でありますが、若干、調整上、岩屋線がやや有利です。時間的に接続時間がですね。議員もご存知と思いますが、うちのバスは統廃合の条件として、スクールバスの機能も持っていまして、登下校の時間帯を譲ることが出来ません。こういった問題で、完全に2~3分すれば乗れますよというダイヤではございませんが、時間帯によれば路線によれば10分ぐらいはお待ちいただくと。或いは、12~13分路線によっては待たなければならないという路線がありますが、大体、概ね10分以内を目標に調整してありまして、市民の利便性を図りながら、しかも豊前市バスは減便せずに接続していくということで、ダイヤを基本的に組んでいるところでありますので、また使う中で、いろんなご指摘を頂く段階がくると思いますので、その段階では見直しをかけていかなければと考えておりますので、今後ともいろんな情報の提供をお願いしたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 10分程度ならそう悪くはないと感じます。本題にいきますが、課長、吉富ですが、いろいろあったことが新聞等にも書かれているけれど、結論をいうと、吉富の了解がなければ自分達から見たら天下の公道ですよね。バスを停車してはならないという決まりがあるのかどうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 決まりはないんですが、やはり国としても関係自治体、結局、うちと中津の事業でありますから、吉富はこの事業に入ってないですね。参加、論議を呼びかけたんですが、加わらないということでしておりますので、この事業に入ってない自治体については、知事と許可を貰ってくれと。OKと、要するにバス停をつくることに同意しますよという、これは道義的にもらって頂きたいという国の指導があるわけであります。 そういう意味で、同意がほしいわけでありますが、今のところ吉富からしますと吉富、上毛がコミュニティバスを中津駅まで走らせています。これに経営を圧迫するという視点で、うちのバス事業を文書で、中津のほうに出してもらっているわけです。 うちのこの事業に対して、そうではなくて、うちの利便性向上のために大いに賛成ですよ、ということであれば、非常にうちとしても、積極的にバス停をつくるということについて、国にも上申できるのでありますが、今のところ競合路線で迷惑という文書を頂いておりますので、その段階では、じゃバス停をつくることによって迷惑を受けるんであればつくることは避けましょうと。 要するに、そのことをつくることによって客を奪われると、このような文書になっておりますので、残念ながら、じゃ客を奪わないようにいたしましょう、という判断をさせていただいている次第でありますので、お含みおきをよろしくお願い申し上げます。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 上毛町のほうは賛成だったのじゃないかと記憶していますがね。今言われた乗り合いのバスですかタクシーですか、そのコースというのは、こちらのコースは競合しているんですかね。如何ですか。コース自体は。如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 問題になっていますのが、広津という山国川の横に、昔からバス停がありますが、このバス停について、ここでうちのバスを4便走らせるわけですから、うちのバスに広津の市民が乗ると、乗り合い事業に悪い影響を及ぼすというのが、吉富の考え方のようであります。上毛町につきましては、議員もご存知だと思いますが、コミュニティ無料バスを現在上毛町が独自にもう1本持っておりまして、イオン三光に無料で住民が乗っていけるバス事業を持っております。イオン三光まで無料で行けるものですから、イオン三光から中津駅まで100円で行けると。ですから、このバス事業については、積極的に反対もしなければ賛成もしないというのが、上毛町の立場でございます。 吉富につきましては、そういう無料バスを持っておりませんので、この事業は、うちが走らせることによってバス停をつくると、お客を奪うような結果になるという指摘については、満更、おかしい指摘ではないと私どもも考えますので、それでは通過をさせてもらったら、そういうお客を拾うということにならないので、迷惑をかけないのじゃないでしょうか、というのが現在の設計の基礎でございます。よろしくお願いいたします。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 ちょっと聞いた話ですが、もと、その広津案は最初出ていたんです。ここで吉富のほうが直江にも停めてくれと要望したけれど、そこの所でいろいろもめたというような話も伺っていますが、その辺は事実かどうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 広津に停めることが、客の減少になるので直江までバス停をつくりなさいと、基本的にそういう要求です。その要求の背景を私どもが一番心配していますのは、バス事業というのは事故、トラブル等、いろんな問題を抱えています。そのような形でバス事業を斜めで見られますと、今後、要するに、この事業でいろんな要求が出てきて、巡回的に回してくれというような話になってきますと、どんどん事業が膨らむ可能性が出てくるわけです。 私どもは、そういう見方ではなくて、吉富の住民の皆さんも利便性の向上のためですから、大いに賛成ですという文書であれば、結局、迷惑施設という考え方でなければ、私どもも非常にありがたいのですが、この事業をすることによって、うちは迷惑だから、もう1箇所バス停をつくれ、もう1箇所バス停をつくれという話になりますと、吉富は非常に狭い地域ですから、私どもが聞く限りでは、役場前とか、もうちょっと上のほうまで走らせると、今コミュニティバスを走らせているのにも、肩代わりができるのではないかというような、そういう要求もあると聞いていますので、そのように拡大解釈をされますと、非常にこの事業の経営はうちだけではなくて、中津との共同運営でありますので、うちも尊い税金を投入しなければなりません。市民的共感が得られるのかと。 そういう税金を投入しない所の要求を、どんどん受け入れていくということになると、うちの市民的共感はどうなるのだろうという問題もありまして、今回については、残念ながら協議をあきらめて通過という形で判断させていただいたと。 この文書を見ていただければ、議員もどのような書き方をなさっているかということをご理解いただけると思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 尊い税金と言われましたが、それと住民の利便性と言われましたが、今、情報公開とか説明責任とか言われる中で、どの住民が聞いても吉富に何故停めないのだと、まず利便性の問題、それと税金と言われるのであれば、当然、これは豊前と中津を結んでいる負担金を大交に払うわけでしょう。じゃそうであれば、乗降客を増やすことというのは、最大のポイントなわけですよ。当然、バス停の箇所が多いほど利用者は多いから、その点から 言っても如何なものかと。 それから、課長が言われた文書を見てくださいと、いろいろなことが耳に入ってくるんですが、これは結論を言わせて頂きたいけれど、豊前市というのは、言うまでもないけれど、昭和30年に9ヵ町村合併してできたんですよ。もう55年ですか。その歴史があるわけですよ。そうでしょう。そのような中で、大きな問題を抱えてきとるわけですよ。 工業団地、能徳にしても東部にしても、工業団地建設、そうでしょう。それから、少子化に伴った小学校の統廃合、それから、火葬場建設、大きな問題を抱えてきて職員がすべて解決してきたわけでしょう。そのような課題というのを。 それだけ優秀な職員があり、そのとき釜井市長は4期目でしょう。4期目の市長と、一方、吉富町さんというのは7k㎡でしょう。そういう狭いエリアの中で、言うまでもないけれど小学校も1校、中学校も1校しかないんですよ。そのようなハード事業も何もやってきてない所の、そのような首長さんと職員さんと、なんで、むきになって戦わなければならないかということを私は言いたいわけですよ。 やはりある新聞にも書いていたけれど、住民を無視にしたような、住民の利便性を考えずに、行政同士の喧嘩につながっているんじゃないかということを申し上げたいんですよ。 1歩大人になって、やはりどちらが住民のためになるか、それは文書を見れ、というなら課長に見せていただきますが、もう少し大人になっていただきたいというのが、私の今回の質問の主旨なんですよ。市長に答弁をお願いしましょう。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 言われるままですが、もう1つ医療の問題があったんですよ。結論を言いましたら、中津に医療の問題を認めないと、だから豊前と上毛と自立してつくったということがあります。それが1つ。ただ、それは解決しましたので、後バスの問題、何時でも豊前市はいいですよ。大きな気持ですから。中津はまだ他人ですよ。中津のほうによろしくという挨拶をしていただければいいんですよ。後は、何時も、何時も大きな気持で、特に、広津には東病院があって出入りしています。先生も今言われたようなことだと思います。 どうかならんか。だけれども、これは1つ1つ道を歩いて行けば解決することです。 そうご理解をよろしくお願い申し上げます。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 釜井市長、あまり熱くならないようにですね。この問題については。それと今中津のことを言われたけれど、中津もそのような考えですか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 中津は早い時期にバス事業を開始するに当たって、地域公共交通会議を開かなければなりません。その中で、現在の吉富の対応では、残念ながら賛成できないということで、早い時期に。うちは待つまで待ちました。正直申しましてぎりぎりまでですね。 これ以上遅らかすと国が、このバス事業を開始するに当たって許可が出来ないという、ぎりぎりまで待ちました。副市長にも、中津にせめて挨拶だけ行ってくれませんかと、難しいことは言いませんと。お金を出せとも言いませんと。せめて中津市に、この事業について共感を示す態度を示していただきたいということで、お願いしてもらいましたが、そのことについては町長、直々に耳に入っております。でも結果として違う形になっております。このことが、今日の原因を生んでいるわけでありまして、私どもが、もしいたらないというご指摘をいただくのであれば反省もいたしますが、最後の努力までして、ぎりぎりまで待って、今日の結論になっていることについても、ご理解頂きたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 最後になります。そのような経緯も大体分かりましたが、やはり住民の利便性という一番大事なことを忘れずに、頭を下げたくなかろうけれど、そうか課長も定年だね。 市長、先ほど言ったように正副市長で、住民の利便性ということを念頭においていただき、また中津にもお願いしていただき、なんとか、吉富の直江に停めるなら、停めてもいいんじゃないかと思います。はっきりポイントになるのは広津ですもんね。東病院があるから。ここはなんとか停めたいのじゃないかというのが本音ですよ。 4月の運行は下旬でしょうけれど、バス停は何時でも見直しもきくでしょうから、前向きにご検討いただきますことをお願い申し上げ、私の質問をこれで終わります。 ○副議長 中村勇希君 以上で、同志会の質問を終わります。 本日の日程はすべて終わりました。よって本日はこれにて散会いたします。 お疲れ様でした。 散会 16時25分 |