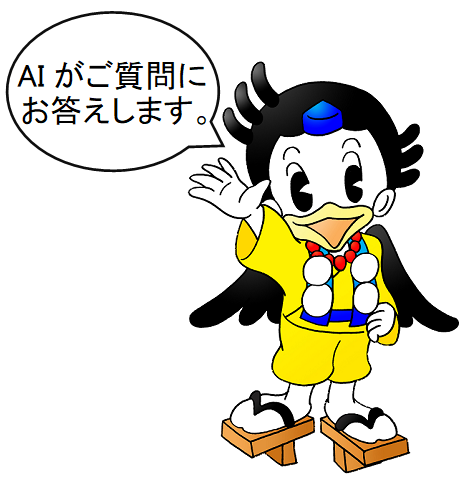議事録(平成21年3月10日)
| 平成21年3月10日(3) 開議 10時02分 ○議長 秋成茂信君 皆さん、おはようございます。 只今の出席議員は17名であります。それでは、これより本日の会議を開きます。 日程第1 一般質問2日目を行います。順次発言を許可します。 はじめに、尾家啓介議員。 ○15番 尾家啓介君 女性群が沢山いると気持ち良いですね。質問を始めさせて頂きます。 広域の自治体組織について、豊前市には、京築広域圏事務組合、京築地区水道企業団をはじめとして、近隣自治体と組合議会を構成する広域組織が数多くあります。 しかし、最近の新聞報道によりますと、京築地区水道企業団では、運営協議会で出資金増額の問題を賛成多数で了承する。吉富中学校組合議会では、執行部提案の条例案を否決する。1市2町清掃施設組合では、異例の一般質問と、その関連発言があるなど、ギクシャクした言葉が続いています。何故このようなことが続くのか、冷静になって事案を検証する必要があると思います。 組織を構成する首長がお互いに信頼しあい、意思の疎通を図ることが組織を構成する絶対条件です。お互いに信頼し合い、意思の疎通を図るという基本的なことに綻びがきているのではないかと思います。今後、定住自立圏構想も重要案件として浮揚してきます。 近隣の首長から信頼され、十分に意思の疎通が図れるということが、豊前市の市長になる重要な条件だと思います。近隣との広域組織について市長の見解を求めます。 2番目です。県営伊良原ダムよりの利水について。大阪府、新潟県、佐賀県、熊本県に続いて、全国知事会会長である福岡県の麻生知事が、国の直轄事業の事業費が増えたから、地方負担を増やすということには、反対の考えを表明して、県の09年度当初予算案には、計上を見送りました。その知事発言に関連して、伊良原ダムからの利水について3点質問します。 第1点、伊良原ダム建設の総事業費は、90年度585億円が、06年度に678億円に増額修正され、豊前市は7649万5000円の増額を要求されています。 県知事が直轄事業の事業費が増えたから、地方負担を増やすのは反対であり、予算にも計上しないと発言しているにも係らず、京築地区水道企業団の運営協議会では、吉富町長の反対を受け入れず、賛成多数で増額を了承しました。県知事が、わざわざ直轄事業の増額を地方は負担しなくて良いよ、予算に計上しなくて良いよと、指導的発言をしているのに、何故、県直轄事業の増額要求を首長の集まりである運営協議会では、反対意見を押さえ込んでまで了承する必要があるのか納得できません。説明を求めます。 企業団議会は、2月18日に、県と田川地区水道企業団との協定の改正案を可決しました。京築地区水道企業団には、加盟自治体への請求権が発生しました。吉富町長は、増額分は負担する考えはないと表明しています。吉富町の負担拒否を運営協議会では、どのように対応するのか、メンバーである市長の説明を求めます。 豊前市にも、水道企業団より請求書が送付されます。直轄事業の増額を地方が負担するのは反対であるという麻生知事の発言と、整合性がありません。私は増額分の予算計上には反対であります。最大限譲歩しても、吉富町の負担問題が解決するまでは、予算計上を見送るべきだと思います。答弁を求めます。 第2点、アロケーションの変更について。豊前市の責任水量は、1日当たり6470トン、負担割合は34.05%であります。豊前市の水道の使用料は、1日当たり5000トンから5500トン、単純に引き算しても、1日あたり1000トンの余剰水が出ます。 伊良原ダムの供給開始予定の10年後は、豊前市の人口は大幅に減少の見込みです。 当然、1日当たりの水の使用料も減ります。その上、豊前市には長い間、1日当たり5500トンの水を安定供給していた良質な地下水があります。耶馬溪ダム水系の受水開始以来、汲み上げ量は減っていますが、現在でも、1日当たり3000トンから3500トンの水は、長期的に安定的に供給することができると、水道の担当責任者は自信を持って発言しています。 豊前市は、身の丈の3倍のアロケーションを引き受けていることになります。 その結果、市民の方に高い水道料金を押し付け、豊前市財政の大きな負担になっています。身の丈に合った責任水量、アロケーションに変更することが、豊前市にとって最も重要な案件であります。しかし、4期目を目指す釜井市長の3つの挑戦等の約束の中に、豊前市分のアロケーション変更の必要性について記述がありません。責任水量アロケーションの変更は、必要ないと考えているのでしょうか、ご本人の説明を求めます。 第3点、平成17年3月より、旧犀川町、旧勝山町の加入により、豊前市のアロケーションは40%から34.05%に変更になりました。事業を立ち上げの最初より、平成17年3月までにアロケーション40%で、豊前市が負担した金額はいくらですか。 事業の最初より34.05%に変更後の差額の合計はいくらですか、工事別に知らせてください。また、減額された金額はどのように処理されて、今日、現在、どのようになっているのか、詳しい説明を求めます。以上、壇上よりの質問を終わります。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 尾家啓介議員のご質問、広域自治体組織、そして県営伊良原ダムの状況について、私から壇上から答弁いたしますが、2番目の関係で個々の件につきまして、上下水道課長、ないし財務課長からの答弁といたします。 尾家啓介議員のご質問、豊前市に対する心配、私に対する気持ち、感謝申し上げたいと思います。ということですけども、行政の運営は冷厳なる歴史の過程、冷厳なる事実、豊かな未来をもっていくことでありますので、考え方、やり方も相当違うなと思っているところでございます。それを前提にご答弁をさせて頂きます。 まず、京築広域自治体の組織でございますが、先程、書類を見ましたら、ごみ、し尿、吉富中学校、消防、20ぐらい、豊前市が組合長ないし局長でやっております。 以前はどうか分かりませんが、私になって、この12年、全てが円満にいっていると思っているところであります。その大きな理由は、3万弱の市でございますが、全て豊前市が責任を持って業務の内容、そして点検もしながらやっていると自信をもっております。 ご指摘の最近の中学校の問題、そして、ごみの問題でギクシャクをしているのではなかろうかというご指摘ですけども、そういうことはありません。 築上郡の町は、築上町と上毛町と吉富町とあるわけですが、そして京都の方は苅田とみやこ、行橋があるわけでありますが、豊前市として、何よりもやはり築上郡の方と手をつないで円満にいかなければなりません。ただ、言うべき点を言わずに遠慮してもいけません。昔から言うじゃありませんか、本当に仲良くすることは、喧嘩もすること、ということは喧嘩をするほど仲が良いということでありますので、今の現状は、そういう点が少し出ているのだろうと思います。 具体的に申し上げました吉富中学の問題は、吉富中学の理事の方とのご相談を、組合長である吉富町長がして頂くならば、こういうことにならなかったと思いますので、修正の提案で全会一致、吉富の町長の提案では賛成1人、後、全部反対したわけでございます。 その事実だけをお知らせしておきます。 ごみの問題は、これは異例の一般質問ということですが、そういうことではありません。議会運営委員会を開いて、そこで議長、委員の方で了解、この委員の方には上毛の方、豊前も入っています。一般質問が出ているが、議運でどうするかという取り扱いをした中で、全て豊前方式でいく、豊前方式はこういう方式ですよと、1人の質問は30分、関連質問は10分以内、どうですかということで、よございますということで質問したわけであります。この質問は、他の町を非難したわけではありません。 豊前市が鎖国だということを書いているから、これはどういうことですかと。 地域のリーダーとしてどうかということについてだけ質問があったわけでございます。 で、取る人にとっていろいろあろうかと思いますが、厳然たる事実に対して解明するのは、議員として当然のことであろうし、私としては、ごみは組合長、吉富中学は副組合長でありますが、別に口を挟む必要もありませんし、挟む気持ちはありませんでした。以上です。 次に、県営伊良原ダムの利水の件のご指摘を頂いておりますが、この関係は、運営協議会では、確かに、そういうような件がありましたが、ただ1年間5回の運営協議会をしておるんですよ。そして県も待っている、田川は既にサインをしているという状況で、もう近隣の町長、市長から、もう決めてくれと、いろいろあろうけれども、組織の運営というのは、やれるときは企画決定しなければいけないじゃないか、という指摘を秋ぐらいからされておりましたので、もうひと頑張り、県の方とお会いして、腹を割って話して頂くということをして、それを踏まえて運営協議会をしたわけです。 そこで、強引にしたことはありません。どうでしょうか。それは実際、手は挙げませんでした。傷が付かないように、本人の異論を聞きながら、他の方にご了解を頂いてOKを取ったわけでございます。決して、そこで私自身は、考え考え、譲歩に譲歩を重ねてやったことでございます。きちっと記録に残り、これから後は、その負担分をきちっと払って頂く。もう20年前から方向が出ている件を、行政の継続性をしながら論議をして、そこで了解をして、お金を払って頂くということになろうかと思います。 次のご質問で、アロケーションの変更の件でございます。この件について記録がないじゃないかということであります。書いておりません。これから一番大事なことは、伊良原ダムの建設について、今から言えることは、後は、いろんな関係で周辺の関係で、犀川、伊良原の周辺は今、方向は出ましたが、これからいろいろ、また流域等で起こるかと思いますが、これはやはり行橋や京都の方が地元ですので、責任を持って頂く必要があろうかと思います。 アロケーションの見直しにつきまして、何故、書いていないかということは、その前の水道企業団議会で、私、豊前市出身の議員も指摘しておりましたけども、どこもしております。ただ足りない町もあります。そういうことですので、豊前市が、これからアロケーションの見直しについて、増えることはないと思います。しかし減る可能性はあると思います。それは今、豊前が組合長でありますし、今度4月、5月改選がありますが、他の町の人はどうですかと、またご提案したいと思います。 今からのテーマは、伊良原ダムの建設をどうしていくか。そしてそれのアロケーション、そして流域の関係を、どう円満に方向を出して水を供給して頂くかであります。 豊前市としましては、13年前までは地下水に頼っておりました。値段もこの辺で一番安かったです。しかし、11年前から水道企業団の水を貰ってお金を払わなければなりません。地下水は今、豊前市の水道の5500トンの中で、もう半分は海水が入って使えないわけでございます。もう残るところは2000トンを切る状況でございます。 2000トンプラス3800トンで5800トンが、今の豊前市の水道の状況であります。これから先は、伊良原ダムの水、2600トンをどのくらい円満に話しをして低めるかということに加えるならば、6000トン強の水の状況で心配のない水の状況になろうかと思っております。 でありますので、供給の料金も経営努力で10円下げました。もう2回で20円下げました。これで豊前市も1500万円の料金を払わなくて良くなるわけでございます。 そういうことになれば、今198円が178円、恐らくそうなると他の自治体も取る所が多くなる。それがこれからのアロケーションの話になると思います。 加えて、伊良原ダムは行橋・京都でございますので、是非、今まで耶馬渓は豊前・築上が近隣でしたから、そういう線で未来のために、この江戸時代から干ばつの飢饉の状況の方向のために頑張っております。壇上からのご答弁、まず終わります。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長、答弁。 ○上下水道課長 川島和廣君 おはようございます。市長が今言いましたけれども、私から中身の数字的なものを詳しく説明したいと思います。県営伊良原ダムの利水について、お答えします。 京築地区水道企業団は、平成2年度に8市町村で設立、事業を開始しました。 平成16年に2町が加入し、平成17年度に合併により、7市町で運営することになりました。配分率、アロケーションは、各市町変更になり、豊前市は40%より34.05%、責任水量も7600?より6470?になりました。 お尋ねの伊良原ダム建設については、当初、平成12年度完成予定から、平成22年度、現在は、平成29年度完成予定と、変更になりました。 全体事業に対する事業の本年度末予定の進捗率は、24.1%、事業費は163億円で、主なものは付替道路、土地・家屋の補償が主なものです。事業の延長により物価の上昇分及び消費税率3%より5%に変更になりました増加等が負担金の上乗せになり、平成18年度に提案され、運営委員会及び京築地区水道企業団の議会で承認されたところでございます。 続きまして、アロケーションの変更についてお答えします。平成17年度の変更により、配分率、アロケーションが34.05%、責任水量6470?に現在なり、配水量5500トンでは議員さんが言われたように、約1000トン余る状況です。しかし、下水道の整備により住宅開発が進みつつあります。高速道路のインターより国道までのアクセス道路の開発、雇用促進住宅、上町南の団地が、今、2棟建築中であります。 青豊団地区域内の住宅等、水道水の供給が必要になります。また、工場等営業関係にも積極的に取り組み、現在、事業中の第8期拡張事業で給水区域を広げ、将来の水需要に対応します。これからも断水のない豊前市として、給水区域内の普及率の向上、より一層の効率化を推進し、経費の節減を図り、安全で良質な水道水を安定供給していきたいと思います。以上です。 ○議長 財務課長、答弁。 ○財務課長 池田直明君 それでは財務課から、県営伊良原ダムよりの利水についての3点目の質問について、順次お答えをいたします。平成17年3月まで、アロケーション40%で、豊前市が負担した事業費につきましては、18億611万8000円であります。 次に、アロケーション34.05%に変更したことによる差額は、事業別に水道水源事業が5513万3225円、広域化事業が2億1368万52円、合計で2億6881万3277円となっております。この減額された金額につきましては、年次計画によって17年度以降、債務の継承分調整として、本来、豊前市が負担すべき金額を他自治体が負担することによって、調整を行っているところでございます。 平成17年度から20年度までに8600万円が調整されまして、残金として、平成21年度以降、1億8281万3277円が、今後、調整されることになっております。 以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、自席から質問をさせて頂きます。まず、広域自治体の自治組織は、市長の言われるようにうまくいっていると思いますよ。うまくいっているけど、やっぱり豊前市が中心になってやらなきゃならんので、だから自分が運転していて100%正しい、相手からぶつけられたんだと思う交通事故でも、2割から3割は自己負担になるんですよ。 いわんや人間関係100%自分が正しいということはあり得ないので、やはり懐深くして意思の疎通を図りながら、うまく運営して頂きたいと思います。答弁はいりません。 伊良原ダムの件について、お尋ねします。確かに、伊良原ダムの増額の運営協議会は、1年間に沢山開かれておる。だけど麻生知事の発言は、最終回の前に発言があったんですよ。直轄事業の増額は負担せんでいいよと、予算に計上せんでいいよと、もう一番ドン詰めのところであったんでね、やっぱり、ものすごく事情が変化していた。その変化を利用したかどうか知らんけど、運営協議会の中で、そういう払いたくないという異論が出てきて、新聞報道の中では、調停案というのを行橋市長が発言したと書いてある。 それは今回はしょうがないかもしれないが、この次から払わないようにしましょうと、仲裁案というんですか、新聞報道にそういうふうに出ておる。今後は、負担増がないように付帯条件を付けてほしいと。ということは今後、要するに今後、払わんでいいよということは知っているんですよ、この本人は。払わんでいいよと言えることを知っとるんだけど、今度言うと問題が大きくなるんで、この次出てくるのは、今度は認めましょうよということだけれども、どうしてこれ言うんだったら、はじめから県知事がわざわざ言うんだから、払わんようにしましょうやというふうに言えばいいんだけど、これ役人根性だろうと思うんだけども、そういうふうに発言しとるんです。 私は、わざわざ麻生さんが財政負担になるから、直轄事業の負担分は払いませんというふうに、これは完全に指導的発言ですよ。そういうのをしとるときに、何故、麻生知事の支配下にある福岡県の直轄事業の増額分を払わければいかんのかと疑問に思うんだけども、その辺ご答弁願います。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 麻生知事の関係、県は一切そういうことはありません。ともかくよろしくお願いをしますと。田川も印鑑を押しているわけだし、今言われた件は、確か今全国の知事会長の立場、特に、新幹線等もああいうも状況がありますが、この関係と一切ありません。ともかくよろしくお願いしますということであります。そういうことで、何も予定通りお願いしますということです。行橋の提案は、行橋のそれを今回のことについては了解すると。これからのことについてということです。だからそれは運営協議会の中でも吉富の町長が言いました。行橋さんはうちと同じ考えですか、いえ違いますと。行橋はもう今回は今までの流れでありますから了解します。これからのことですということです。これからのことにつきましては、私も、今からいろいろな流域の関係を含めましてありましょうから、この線は強く頑張っていきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 では、今市長が言われるのは、運営協議会の中で、行橋も豊前も今度はしょうがないけど、これからは増額は認めないということでよろしいですね、これは答弁はいりません。 それと、もう1つは副市長。豊前市で合併協議会があったときに、議会から2人議員が出て合併協議会をしょっちゅうやったんですよ。その合併協議会がある前に、選出議員がどういう発言をしていいか、意思の疎通を図らなければならないし、統一してほしいというので、何回も議会で協議をやっている、会議の前に。 そうすると、今度、水道企業団の議会がある前にだいぶもめとるんよ、新聞報道によると。だから当然、豊前市からも3人議会議員が出ておるけど、議会の中で意思を統一してくださいと、そういう協議会をなぜ申し込まなかったんですか、議会に。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 水道企業団のことは、市長のほうで答弁をお願いしたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 では市長。 ○市長 釜井健介君 水道企業団の状況につきまして、議長といつも連絡をしておりました。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、議長と相談して、議会の中で協議会はやらんでも良いと市長は判断したと、そういうことでいいですか。 次にいきましょう。これは、もう1つ、吉富町長は新聞によると増額分を負担しないと、負担しなければ吉富の分は剰余金で対応したいというふうに企業団側の発言が新聞に載っておるんですが、剰余金で対応するわけですか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 議会の最終結果は、払わない吉富さんに払うように要請しましょうとなりました。 それまでの過程で、ではどうするかという運営協議会の過程で、吉富が払うまでは、当分、水道企業団がその分だけ抑えておこうという意見は出ました。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、財政課長にお尋ねしますが、さっき説明して頂いた豊前市の1億8281万3277円、吉富町の7058万7402円は、要するに企業団にある貯金ですよね。 企業団からの会計上、預り金。その剰余金というのは、預り金を言っておるんかね。 ○議長 秋成茂信君 財務課長、答弁。 ○財務課長 池田直明君 先程ご説明したものについては、債務の継承分ということで、過去、私どもが払い過ぎた分を、今後、払うべき自治体が負担するということでの、これは計算上の数字でありまして、実質この余剰金が発生しているということではないと考えています。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それはおかしいじゃないですか。要するに会計上は企業団の預り金にあげなならん。 この他の部分が入っておるんだから、余っとるはずだから。会計上余ったお金をどうするの、帳面づらだけで知りませんというわけいかん。帳面づらだけでも預り金になるはずなんよ。余っとるんだから。取っとるんだから、加入者側から。全額入っとる、入らんは別にしてね、計算上は。だから、そういうことは吉富側の余剰金で対応しますよということは、この預り金を当てにしての余剰金という意味ですかと聞いているんです。 それは分からんかね、推測でいいよ。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君。 推測では、ちょっと私どもは、中身は具体的に見ておりませんので判断はできません。 コメントは控えさせて頂きたいと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、アロケーションの変更について、お尋ねします。要するに豊前市は、1日当たり6470トンの責任水量を負わされて、必要量は5000トンから5500トン必要だと、1日当たり1000トンは確実に余ると。この状況は、これから増えるという水道課長の説明だけど、これは20年前ぐらいにつくった議案付属書類にも書いてある。 これからじゃんじゃん減りよるんよ。これから増える道理はないじゃないですか。 だから1000トン以上余るんですよ。その上、地下水は、その当時の技術から比べて掘削技術はものすごく良くなっている。だから豊前市は、その掘削技術を使わんだけで必要がないから。だけどあなたは3000トンから3500トンは出ると言っとるんだから、その水は使えば安くなるんだけども、今3800トン先に来とるから、それを先に使って足らない部分を地下水を利用して、今の水道料金になっている。そして、今度その上にまた3800トンプラスに2000何百トン入ってくると、地下水を使いよった分を外して高い水を入れるから、水道料金は上がっていく。そして人口も減っていくと、そういうことになると仮定はできるけど、あなたはどう思いますか。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 今、議員さんが言われたのは、区域の人口が減っているということでしょうけれども、豊前市全体が減少しつつありますけれども、区域内は、そう減少しておりませんし、先程、私が言いましたように、インターからのアクセスができれば、その付近の開発で雇用促進ですか、今あそこには水道は行っておりません。今、井戸水で賄っておりますので、それも賄えるようになれば、水道水は伊良原ダムが必要になってくるかと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 これは水道課長じゃなくていいよ。人口が結局、基なんですよ。水道水はね。 だからそうなってくると、この中の設立準備委員会の議案の中には、豊前市は、平成元年3月の人口は3万1541人としてある。それで行橋は6万6018人、苅田は3万3108人。この前の17年3月の国調のときは、豊前市は2万8104人。だけど行橋と苅田は増えとるんよ。行橋は6万6018人の平成元年から、平成17年3月は7万70人、苅田は3万3108人が3万4387人と人口が増えている。計画から上に上がっとるんですよ。豊前市だけは計画からずっと下がっている。だから京築水道企業団のアロケーションは、豊前市は、身の丈の3倍も引き受けているわけよ、どういう意味か知らんよ。 だけど苅田、行橋は身の丈と丁度同じか、身の丈以下の引き受けなんよ。この前、吉富に聞いたら、吉富も私はこれで丁度いいです、余るぐらいですと。だから企業団に加入している豊前市以外の各町村は、身の丈に合った計画で水量を確保しているわけです。 だから企業団に加入している運営協議会の中で、いくらアロケーションの変更を皆にお願いしても、豊前市は、赤字で困っているから何とかしてくれと言っても、他の所はアロケーションが身の丈にあった分だから、豊前市のを引き受けると赤字を引き受けると同じことだから、誰も引き受けてくれんですよ。これはものの道理。だから市長が今からアロケーションの変更をどうしてもやって頂かなならん。やって頂くためには、県を巻き込んで何か方法を変えなならんのじゃないかと思います。 今、下流の自治体に、お前の所に俺ん所が赤字だから持ってくれと言っても、なかなかうんとは言ってくれん。これが現実だと思いますよ。如何ですか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 昔の話をすれば、20年前、行橋、苅田も入りとうなかったと言うんですよ。そしたら組織はどこも成り立たんでしょ。それは尾家議員が心配して言われることでありましょうが、事実として改善するように努力をしていくと。 それと、今から一番大事なことは、伊良原ダムは京都郡にできるんです。いろいろなことは今から行橋・京都が責任を持ってやって頂くというふうになろうかなと思っております。だからそのときに、今言ったアロケーションの件も、再三見直しという線もできると思います。行政の運営は、皆お互いに4割犠牲をもって、泥を被ってやらんとできんと思いますから、それは豊前市の先輩がやった大きな功績だと私は判断して、これからもいくべきだと。これから、これを踏まえて言うべき点は言いながら改善していこうと思います。 ただ言えることは、全ての組織に良い話だけではなくて、広域事業については汗をかく、泥を被るというのは必要だろうと思います。水道企業団は、その1つの大きな証だろうと思います。ただ水が高い低いよりも無いのが一番困る、こういうことだと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 市長の言うように、この近辺のトータルを見ればそうなんですよ。だけど豊前市だけを見れば、豊前市だけを考えれば、これは伊良原ダムの水を貰うと、豊前市の財政は赤字になる、赤字が増える。赤字が増えれば市民の負担が増える、これは事実なんです。 だから伊良原ダムの水が来るまでに何か解決して、伊良原ダムから入ってくる2600トンだけは、県かどこかがもってくれるなり、加入の自治体が負担してくれるなり、何か方法論を市長に探してもらわなならん。再度そのご決意のほどをお願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 ですから、一番大事なことは、今までの水道行政、水道企業団の歴史を皆さんが抑えて頂きながら、足元で揺れないことが第1であるし、これから一番大事なことは県なんですよ。土木事務所が行橋が出張で、豊前が本事務所になりましたので、そういうことを踏まえまして、やはり福岡県と連携をとっていくと、いろいろ知恵を出すと、いろいろ可能性を追求していくと。この件はうちの市の使命だろうと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 最後に市長が言われた、県を巻き込んで県を調整させて、それで豊前市のこれを解決していく、これが本筋だと思いますので、それに全力を尽くしてください。 次に移ります。2月10日付、平成20年京築地区水道企業団構成団体出資金の納入について、3790万円。副市長、あなた判を押しとるけど、これは決裁をしたの。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 いたしました。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 内容を説明してください。どういう内容ですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、分かるの内容は。副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 出資者への事業費の3分の1でございます。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 事業費の3分の1を豊前市がアロケーションに従って払ったと、そういうことですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 そういうことでございます。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、今度の3790万円の事業費の総額を、時間の都合で私が言いますけども、1億3160万円、財政課長、間違いないね。1億3160万にアロケーションを掛けて持分が豊前市が3790万円、その中に調整というのが入っとるんよね。さっき私が預り金だと言ったが、この調整が豊前市は600万円、苅田が560万円、吉富町450万円、築上町70万円、この調整というのは何ですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 先程、財務課長が説明申し上げました2億8000万円の調整分でございます。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 要するに、あなたが言う2億8000万円というのは、2億6881万3277円、これが調整分ですよ。これは豊前市の財産よ。その豊前市の財産を使うときに、使う前に、これこれだからこういうふうに使わせてくださいと、当然、連絡があるはずなんですよ。 連絡はありましたか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 これについては、連絡はございませんけれども、こういう企業団で調整分の話し合いができておりますし、それに基づいて起案がなされましたので決裁いたしました。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 だから自分の財産を連絡なしに使われて、そういう答弁をしよったら困るんだけど、その上、今度、豊前市は650万円、それから使いますと。苅田は560万円、吉富は450万円、築上町は70万円使いましたとしとるわけよ。これはどういう基準で出しとるの。 全然、理屈で合わん。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。はっきり分かるように言って。 ○財務課長 池田直明君 これにつきましては、平成29年度までの歳出負担が決まっておりますので、それを年次計画に基づいて、私が先程申しました残高が、後1億8000万円ほどございます。 これを各年次計画に分けまして、計画で算定して割り当てているものです。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 だから、1億3160万円の工事費にアロケーションを掛けて、各自治体の現在のアロケーションを掛けて、各自治体の負担分を出したわけよ。だけど、それぞれ繰越金をもっておる所は、そこから一定分出して調整して減額しますよと。減額するときも当然、担当者は、今度、豊前市は500とか苅田は600とか勝手にするわけじゃない。何かちゃんと計算法式でやるはずなんよ。 40が34.05に下がった、そういう率でもって出すのは当たり前なんよ。 それを何か知らん豊前市は650万円、苅田は560万円、吉富は450万円、どんな計算法式で出しても、これは答えが出てこん。要するに担当者が勝手に650、450と書いただけの話じゃないの。大体、豊前市の財産を使うときに、相手が許可なしに650万円、勝手に差し引いて、こういう請求書を出して良いのか、どうかという問題もある。 だから、これはどういう意味なんですか。豊前市650、苅田は560、吉富は450を調整しておる。この計算様式は何なんですか。 ○議長 秋成茂信君 分かる人は、計算式を。はい、財務課長。 ○財務課長 池田直明君 今回のアロケーションの見直しの中で、一番率が下がったのは豊前市でありまして、一番多いのが豊前市が2億6800万円という数字でございます。逆に一番多くなったのがみやこ町で、負担が4億9200万円という負担が、新たに増えたわけです。 吉富町は8300万円と、各自治体によって、その調整分の額が違うわけです。大小があるわけです。そういう中の案分で豊前市の調整分が比較的大きな数字になっているということでございます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 あなたの説明が全然まともじゃない。按分率でやっとるんでしょう。だから豊前市は2億6800万円というけど、原資は苅田は9500万円、吉富は8300万円、その原資から調整額を出しとるわけよ。そうすると按分しとるなら、何故、豊前市が650で苅田が560で吉富が450の案分率が出るのかと聞いているんです。小学生でも分かるよ、こんなことは。どういう基準で出しとるの。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 そこまで詳細な説明は受けておりませんが、全体の額については、先程、説明したとおりに残高があるということで把握しております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 要するに副市長、財務課長は相談を受けてないんよ。企業団からこうしますよと報告がない。した後は、あなたたちが決裁しとるだけ。言葉は悪いけど、ここは企業団の話じゃないよ、全国で労働組合から市役所、県庁、会社、銀行、皆不正がある、公金横領の。 いろんな所である。こういうのは共通点がある。人事の交流がない。それで金繰りを任せっぱなしにしておる。この企業団の会計は典型的なものです。これが不正があるとは言わないけど、これは不正がある場所と同じシステム、同じことをやっておる。 大体、豊前市の財産をいくら使ったと、事前に報告があってしかるべき。それを何かわからん尺度でもって引いとって、後から請求書で出して、ぽんと判んこを押して良いものかと。それ副市長、どう思いますか。 ○議長 秋成茂信君 副市長。 ○副市長 後小路一雄君 一概にそうとは思っておりませんけども、この内容等につきましては、今後、よく企業団に照会をして精査をしていきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 少なくとも豊前市の繰越金を、調整金があるなら調整金を使うときは、事前に豊前市に相談して、今度アロケーションでこれくらい工事費が出ると、だからここで調整をこのくらいしますよと、了解を得た上でくるのが当たり前と思う。事前も何もないで、これ一本できて、後、何も報告がないでどうしようもないじゃないですか。 その辺、副市長、財政課長に業務命令を出して、企業団の局長に調査するようにお願いいたします。如何ですか。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 運営委員会の前に課長の組織であります幹事会があります。市長が企業長ということで、私が幹事長をしているんですけども、その中に、今から財務課長も加わってもらって、取り組んでいきたいと思っています。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 あなたが言って良かった。私はそれを言おうと思った、一番最後にね。だから当然、幹事会の中にあなたが行って、持って来て分かりませんと書類だけぽっとあげても意味がないんで、だから当然、財政課長が入るのは当たり前だと思っていたんです。 だから、これから財政課長に入ってもらいますけども、いわゆる豊前市の調整金を使うときは、事前に豊前市に相談して了解を受けて上で使うんだということは、ちゃんと決めて頂きたい。これはどうですか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今言った件は、各市町の財政関係も入れてしていきたいと思います。その旨、また水道企業団の事務局と相談していきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは、市長。最後に3期12年間ご苦労様でした。これから4期目を目指すんでしょうけども、身体に十分気を付けて、脇を固めて頑張って頂きたい。終わります。 ○議長 秋成茂信君 尾家啓介議員の質問を終わります。 次に、渡辺一議員。 ○11番 渡邊 一君 こんにちは。尾家さんの熱の入った質問、本当に詳しくよく勉強していますね、感心いたしました。私は、ごく基本的なことの質問をしたいと思います。 通告書にありますように、農業振興地域整備計画について、お尋ねしたいと思います。と申しますのも、先週、私の友人が陳情に来まして、農地を宅地に変更したいと、ついては農振の解除を申請したところ、来年3月までは、農振除外の申請をストップしていますよということで、来年3月までは受け付けてもらえないという話がございました。 それで事情を聞いてみますと、彼は自分と同じ千束の野田ですけども、野田の方が、たまたま黒土に家を建ててあるものですから、その家が東九州縦貫道にかかったそうです。 東縦貫道にかかったものですから、立ち退かなければならないということから、どうせ立ち退くのなら、生まれて育った野田に帰りたいなということで、私の友人の土地に目を付けて、これを分けてくれということから始まったそうです。 来年の春まで待てばいいようなものですが、ご承知のように東九州縦貫道は、既に着々と進行しておりまして、個人的な用地の買収が始まっております。ご承知のように家の立ち退きは、立ち退いてしまわなければ、お金をくださらないそうです。これは当然だと思います。金は払ったは家は立ち退かなかったでは道路はできませんから、全部取り壊してから支払をするという決まりになっているそうです。ですから先に家を建てて、そして壊さなならんということから、要するに自分の宅地を早く決定したいということのようです。 それで、私はこれは簡単なことだろうと思いまして、臨時に随時、受け付けというんですか、これはしょっちゅうあることですからと思いまして言ったところが、これは来年3月まで一切受け付けないということなんですね。これは私は初めて聞きました。 2、3同僚の議員、特に、農業を一生懸命していらっしゃる議員さんにも聞きましたけれども、お2人とも知りませんでした。来年3月まで受け付けんということがあるものかと、大体、年に3回か4回はやりよるはずだからと、詳しい方は、そんな馬鹿なことがあるものかとおっしゃいます。それで、その辺のところが、何故、来年3月まで止めなきゃならんのかということが1つ。 もう1つ、この際ですから、何故、今この農振の見直しが必要なのかということを議論してみたいと思います。この演壇では、その2つをお尋ねして、後は自席の質問にかえたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 渡辺一議員のご質問の中で、私からは答弁書を一応予定しております。それを、まず読み上げます。後は、2番目の質問になるかと思いますが、農林水産課長からの答弁にして頂きます。農業振興地域の見直しについて、お答えをいたします。 豊前市農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興計画であり、本市においては、昭和63年に変更・策定されたもので、全体見直しを、平成20年度から21年度にかけて行っているところであります。この計画は、農業振興地域の整備に関する法律、農振法に基づき、農業の健全な発展を目指し、農用地の効率的な利用を図るため、10年先を展望した農業振興の基本計画となるものであります。 整備計画の構成は、農用地利用計画、農業生産基盤の整備開発計画、農用地等の保全計画、農業計画の規模拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用促進計画、農業の近代化、農業を担うべき者の育成及び確保施設の整備計画、農業従事者の安定的な就業の促進計画、生活環境施設の整備計画、森林の整備、その他、林業振興との関連等であり、今回の全体計画の見直しは、主に、2の農業生産基盤の整備開発計画から、9番目の森林の整備、その他、林業振興との関連の見直しを行うもので、工業団地等、個別の土地利用の変更については、随時見直しで対応しております。以上、壇上からの答弁といたします。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 山下 正君 今、渡辺議員のご質問のうち、東九州自動車道の代替地に関する関連と、後、見直しは何のためについてのご質問に、お答えいたしたいと思っております。 まず、東九州自動車道の移転補償交渉等により、代替地が農用地区域に該当した場合につきましては、現在、全体見直しをやっておるところであります。しかしながら、期間中においても、そういう部分があれば、福岡県の土地開発公社等と十分連携を取って、個別的相談には応じてまいりたいと思っております。また、具体的に転用の計画が今年、工事をしたり、個別的な事業につきましては、随時相談に応じてまいりたいと考えております。 また、県と全体の協議の見直し、以前であれば、今回の全体見直しの中にも組み込んでいけるのではないかと思っておりますが、県との協議が、提出後であれば、今後の随時計画の見直しというところに持っていって、見直しで対応したいと考えております。 また、見直しは何のためにするのかということですが、今、市町村の農業振興地域整備計画につきましては、農業振興地域の整備に関する法律におきまして、概ね10年後を見通して定めるものでございます。前回、昭和63年度の見直し後、市長も答弁しておりましたが、20年を経過しておりますので、農業を取り巻く現況等につきましては、大きく変化しております。今後の本市の農業の振興を図っていく上で、計画の見直しは、この時点で必要であると考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 渡辺議員。 ○11番 渡邊 一君 今の課長の答弁は、来年3月まで待たなくても受け付けます、というふうに理解してよろしんですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 個別案件が、そのように具体的に計画があれば、それは今回の全体見直しの中でも、検討していかなければいけないんではないかと考えております。 ○議長 秋成茂信君 渡辺議員。 ○11番 渡邊 一君 それでは、私が先程質問しましたように、東九州縦貫道のためだと。是非、受け付けてほしいということは、では受け付け可能だということでいいんですね。 ○議長 秋成茂信君 農林課長、はっきり言いなさい。農林課長、答弁。 ○農林水産課長 山下 正君 時期がちょうど、今の見直しの時期の最終公告の時期が8月か9月ぐらいになると思います。1月に受け付けた分がですね。その分をする前であれば、県協議の以前であれば、十分可能ではないかと思っております。しかしながら、除外の4要件というのがありまして、その要件に合致しているものでないと、逆に言えば、そこに1項目でも合致しないということがあれば、全体的な見直しもかなりの時期がずれてくると思っておりますので、その要件が確実に合致するという案件であれば、うちの方としても、それは受け付けてまいりたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 渡辺議員。 ○11番 渡邊 一君 何かちょっと奥歯に挟まったような答弁で、受け付けるのか受け付けないのか。 受け付けたって許可しませんよと言っているように見えるんですけれどね。 それで、ちょっと市長の答弁の中にありましたように、今、何故、農振計画を見直さなならんかということを、私なりに意見を述べてみたいと思うんですけれども、豊前市は、昭和63年に1度、農振をきちっとやったわけですね。それで農振地域をきちっと決めて、大きな仕事をしていったんですよ。 まず、ほ場整備が入りました。ほ場整備の産物を活かすために広域農道をつくりました。そして、それらを活かすためにカントリーエレベーター、面が広がったわけですから、中規模農家と言いましょうか、その育成のためにカントリーエレベーターをつくった。 それから野菜団地、平成農園なんかもやりました。そういうことで、野菜、蔬菜を阪神や東京市場に出すために急速冷凍施設、野菜を中間に眠らせて、新鮮な野菜が東京にも届けられるというような機械も入れました。そして、ほ場整備の面積を、この間、農林課長に聞いたんですけども、殆ど出来上がっていますよ。 ほ場整備は、計画面積が931.10haで、整備済面積が760.86ha、81.72%が、ほ場整備が出来上がっているというデータを頂きました。実際その通りだと思いますね。角田地区が新規で残っている。これが81haです。後、繰り越しで黒土西部第2地区で72.20ha。私が先程あげましたような、この地域の農業振興計画がぴしゃっとあったわけでなんですよ。だから農振地域の指定をして、その事業がスムーズにいくように、補助体制がとれるように頑張ってきたところだと思いますけど、この農振で今度は何をしようとするんでしょうか。 農地をまた新しく増やそうとするんですか。それとも何のためかよく分かりません。 特に、今、国の農政がフラフラフラフラしているときなんですね。何か絆創膏を付けて、農林大臣を首になった人がいたり、組閣の前に、農林大臣だけは勘弁してくれと言って断った大臣がいたり、そういう農政を残念ながら自民党がやってきました。 そして今、皆がやはり迷っているところなんですけれども、収穫量を増やして、減反政策をやろうじゃないかという意見と、これは減反政策をやめてしまったら、我々の所はやれんぞという意見が両方あって、農業専門の山崎議員から、何時も農業新聞を取らされているんですけど、この中でも、はっきり総合解説の真相という欄に、生産調整、要するに減反ですよね。一人歩きに困惑しているという、どうしていいか分からないという記事が出ています。そういう時期なんですよ。今、農政については。 それから、民主党もちょっと党首がけつまづいていますけども、自民党の農政とは何か大きく転換いたしまして、もう一度、減反政策をぴしっとやって、サンチャン農業と言いますか、昔そう言われました。家庭でできる農業を育成せんと、日本の農地は無くなってしまうんじゃないかという考え方もあるようです。それだけに、今ほど難しいときで国でも迷っているような、私は農業政策だと思うし、豊前市自体にとってみましても、自動車100万台、150万台体制で世界に冠たる自動車工業地域をここにつくろうじゃないか。今経済不況でちょっと頓挫しましたけど、逆に私は良い時期だと思っています。 公共事業を投資し易い良い環境になったんじゃないかと思っていますけども、そういう時期で、例えば、農振地域ではあるけれども、農業政策が何もなされていない黒土の南部とか、三毛門地域とか、これをどうかするというような農業政策があるんでしょうか。 それから、今言う、ほ場整備が残った地域が各地区にありますけど、ほ場整備に参加しなかったような農地を、この際、きちっと農振にかけて何かをしようとする大きな目的があるのかどうか。その辺のところを、市の農政として、お聞きしたいと思います。 どちらでも結構です。お聞きします。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 山下 正君 今の渡邊議員から質問を受けましたが、今は国の農政につきましても、農業につきましては、集約化と方向等、個別的に今サンチャン農業と言われていましたが、そういう方向等増えておるということは、ご承知のとおりだと思っております。しかしながら、今からの農政につきましては、集約化の方向でいく部分が大きいのではないかと。そのためにもほ場整備をかなりの部分の面積、農地につきましてはやってきております。 また、他の農地については、どうするかというようなことについては、そのために今回の全体計画の見直しの中で、マスタープランなりつくって、農地の利用計画とか、後は農業生産基盤を豊前市においては、どういう方向にもっていくかというような検討を、今回の全体計画の見直しでやっていきたいと考えております。 先程も申し上げましたが、昭和63年度に前の分の基本構想計画ができております。 それから20年も経っておりますので、農業の方向もやり方も随分変わってきていますので、現在の農業の方針とか、そういう部分を含めた全体的な計画をつくっていきたいということで考えています。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 それは本当に迷惑な話なんですよ、地権者にとってみたら。なるほどなという計画があって、はじめて農振に喜んで提供するでしょうし、また農業に従事する家庭が増えてくると思うんですけど、今から計画をそのためにするんですと。その前に、とにかく農地だけ縛っておこうという答弁にしか聞こえませんでしたけど、そういうことですか。 例えば、昨年の資料を頂きましたら、20年4月に協議会を開いていますよね。 このための協議会を。それから7月にも9月にも協議会があるんですけど、この協議会の会議の内容が分かったら教えてください。あなたが言ったようなことが議論としてあったのかどうか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 通常の豊前市の農業振興地域整備促進協議会につきましては、豊前市の土地利用の計画の変更ということで、農振除外が審議がされてまいりますが、平成20年4月25日に行われました促進協議会におきましては、20年度から全体見直しの基礎調査に入りたいということで、その結果を踏まえて、21年度の農振計画の全体計画の見直しを行っていきたいというような説明を行っております。 また、平成21年1月23日の促進協議会におきまして、今年、本年度行いました調査を踏まえまして、農振計画の見直しを、それに基づき行ってまいりますということで説明を行っております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員、分かりましたでしょうか。 ○11番 渡邊 一君 要するに、農業振興地域整備計画は、市長が答弁しましたように、農業振興地域整備計画の構成、要するに農振の中身は、第1に農用地の利用計画を立てるんだと。 2番目に、農業生産基盤の整備開発計画を立てますと。これはここに書いてあるんですが、それぞれ1番から、市長が説明したように9番のどこでもいいですから、こういう計画を立てて、この地域でどうするという具体的な話があるんなら教えてください。 これね、僕は何もないんじゃないかと思うんです。 例えば、5番目の農業の近代化、今イチジク、アマオウがどうだとか、平成農園でどうだとか、そのために何かをどうかするとか、それから、先程、野菜を遠隔地に出荷するための保冷倉庫をつくったりとかありますけど、そういう何かありますか、振興整備計画の中身が具体的に。そのためにやりますということでしたけど。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 山下 正君 今、渡邊議員が言っておりました中につきましては、具体的にマスタープランの中の計画で、地域の農業の振興の動向を踏まえた中で、ある程度、具体的にもっていくということで入っております。その農業振興地域整備計画の中につきましては、先程お答えしましたものと重複するかもわかりませんが、農用地の利用計画ということで、農地の土地の利用方針と、農用地区域の設定の方針とか、今5項目目に言われていました農業の経営の規模拡大、農用地の農業場の効率的かつ総合的な利用の促進計画、後は農業の近代化の施設の整備計画等、今後、具体的に協議の中で進めてまいりたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 別に課長をいじめる質問じゃないんですけども、これからの豊前市農政に向かって、どうあるべきか、どうすべきかということを、この際、皆で知恵を出し合わなければならん今の時期だと思うんですね。特に先程、私が言いましたように、市長も一生懸命推進しています。自動車産業の誘致をね。工業団地もつくらななりません。そういう意味で全体の見直し、例えば、今の工業団地の10号線より、その辺の農地を総合的にどうするか。 要するに、都市計画や何かと十分話し合いしながら、この辺はこういう形だから農用地から外そうじゃないかとか、それから黒土の南部ですか、今やっています西部第2とか、その辺の農地を、どういう形で豊前市としては育てていくのか。 例えば、今あなたがおっしゃるように5反町、なにか30町歩単位で米をつくれというような話があるんですね。だから豊前のほ場整備をするときにも5反町でやってくれと、最終的にはそういう要請も農林省からありました。ところが農業生産者の所に行きますと、豊前では5反町というのは、やはり地形にそぐわないそうですよ。私は百姓したことがないから分かりませんが、5反の広いのを一面につくりますと、水が当たらんというんです。 水を入れ出して、水口から要するにいっぱい水が当たるのに1日も2日もかかって、田植えが非常にしにくいとかいうことで、県や農林省と話をしまして、水のために間に畦をつくる。それで農作業をして、それで後で畝をつくるという方法を考えたりした、私も昔の経験があります。そのころは県会議員もしていましたから、そういう要求があって、県の農政担当の人たちと相談しながらやったことがあります。 ですから、今ほ場整備をやっている角田地区、黒土地区にしても、そういう大きな面積で米づくり麦づくりをやれと言っても、ちょっと無理なんではないかなと私は思うんですが、米づくりに対しても、今ないと思いますけど、今そういうものをしっかり役所の中で、都市計画その他との兼ね合いで大きく広く、農用地を決めていく時期じゃないかと思います。もし今しなければならないとすれば。でも農政はどんどん変わりますよ。 減反政策ももっと減反をやれという意見と、取っ払えという意見と両方あると思いますが、農業者自身が迷っているし、国も迷っているし、今、縛りを強くして地権者にご迷惑をかける必要は、私はないと思うんですがね。 なお私が不満に思うのは、その方もそうですけど、高速道路はそこ退けそこ退けでしょ。これは、ほ場整備をした所であれ何であれ、決まったらテコでも動かん。そして田んぼのど真ん中を突っ切ろうと、残った残地がいびつになろうと、一切お構いなしで、これは農振を外すだけではなしに、農転も認めているんですね。今から決めようとする中には、農用地区の除外の要件としてあるんですけども、土地改良事業が施行されている場合には、要するに、ほ場整備に置き換えていいと思うんですが、事業の工事が完了した翌年度から起算して、8年を経過している土地であること、ということは、ほ場整備をした農地なら8年経過していないと、一切駄目ですよというふうに書いてあるんです。 これは道路だけは関係ない。関係ないにもかかわらず、それは国策ですから我々も分からんことはないと思いますが、そのあおりをくって農地ではどうしても使えないような残地ができてしまった。家にかかって、今さら山田の鳥越の人が八屋に来いとか、市役所の前の優良宅地に来いとか言ったって、やっぱり鳥越で生活したいという人はおられるんですけど、残った農地に対しては、民間に対しては8年経ってないから一切駄目だと。 農地の転用を認めませんと今、言っているようですけど、その辺のところはどうでしょうか、間違いないですか、東九州道関連で。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長、答弁。 ○農林水産課長 山下 正君 今のご質問は、道路用残地農地等についての問題だと思います。東九州自動車道で用地交渉に際しましては、本体道路が通った残りの残地等につきましては、十分地権者に理解を得て頂くように交渉してくれ、というようなことで、福岡県の土地開発公社に申し入れを行っておりますし、また、その残地が水田として利用できない、低くなってできないということになりましたら、個々の事例、案件によるとは思いますが、そこの部分を埋め上げて、ある程度一定の高さにして、横の土地、横の田なり畑と同じように利用できないかというような協議は行っていってください、ということは開発公社あたりに、うちのほうは要望してまいっております。それについても、今後もお願いしていきたいと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 十分説得しなさいというのは、誰が誰を説得するんですか。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 福岡県土地開発公社が用地買収に入っておりますので、道路側の事業主体側が地権者を十分に説得してくださいと。納得するような格好で、用地買収は行ってくださいということで、お願いをしております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 市役所の農林課としては、土地を買うほうの公社と地権者が話し合いをしてくれと言うわけですね。その上で出てきたら受け付けんというのが、今度の事件なんですよ。 今の場合、家がかかった人ですからね。こういう場合、全然、受け付けないから、公社も困っているような感じですけどね。どうします、豊前市としては。これは県やら国に了解を取らなければいけない事項かな。随時受け付けてどうか判断するということは。 ○議長 秋成茂信君 内容は分かっているんでしょ。農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 今の東九州道関係につきましては、昨日も十分県とも打ち合わせをしてまいりまして、全体計画、今やっております時期に合えば、その中に入れていきたい、協議をしていきたいと考えております。その分につきましては、物件があれば、その案件ごとにうちのほうに相談に来て頂ければいいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 ということは受け付けるということの理解でいいですね。 ○議長 秋成茂信君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 受け付けてまいりたいと考えています。 ○議長 秋成茂信君 それから、その話に関連なんですが、先程、農地としては使えないような残地になってしまった。あなたは隣と合わせて使えないかと、そういう指導をするということで、2つお尋ねしたい。隣の農地と合わせたら、ひょっとしたら田んぼとして使えるかもしれないという所なんですが、それが高低差がある。1mから1m50あって、その農作業のならす費用はどういう形になるんですか。これは公社の話とは思うけれども、要するに農地を保護するという立場からすれば、どういう考え方があるんでしょうかね。 ○議長 秋成茂信君 分かる方、答弁して。農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 個別の案件につきましては、私のほうが、どこがその費用を出すというようなことは言えないと思います。また、そういう分につきましては、公社と十分に協議して頂きたいというところが私たちの本音だと思っております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 では、ちょっと見方を変えまして、誰もお金を出す人がおりません。そういう農地が残りました。隣と合流するために100万円も200万円もかかると。たった2畝か3畝しかないのに200万円もかけてしませんと、引き受け手がおりません。そういう農地は、これからどういうふうに考えて、これは厄介な土地が残ったんですよね。これは豊前市の農業推進を図る立場としては、これはどうすればいいんでしょうかね。 答弁はいいです。これは難しいですよ。私が考えても分からんもん。これは皆で考えなきゃいけん今。道路が通るときに、残ったその辺をどうするか。これは本当に個別に考えていかんと、大変、迷惑な残地が残りますよ。この計画をしっかり、ずっと道路の沿線を見て回って、どういう残地が残るのかということを、きちっと把握せんと、本当にほったらかされるですよ。ほったらかされたら、後からその辺の百姓さんが一番困るんです。 それをどうするかというのが大きな問題だと思うし、そして、これは大変、山下課長にはご苦労でした。もうそろそろご定年で、長い間ご苦労やけど、あなたをいじめるわけじゃなかったんだけど、本当に、この今問題で困っている方が多いんです。 ですから、できんやつはできんでいいんですけど、話を戻しますと、受け付けて検討だけはしてください。そして、これは農用地として本当に残したいから駄目ですよとか、それでも結構ですよという返事をしてやらんと、本当に困っています。来年の3月まで一切審議なしというのでは困りますので、その辺のところは、むしろ市長に答弁をお願いしたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 私も、東九州自動車道建設促進、豊前市の責任者でございますので、今議員のご指摘、即答はなかなかできづらい件でありますが、検討してみたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 検討じゃなくて、受け付けてくれますか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 相談を前提に受け付けていきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 それでは、これで質問を終わります。19分ほど残しましたが、そろそろ傍聴の方もお疲れでしょうから。課長、ご苦労さんでした。 ○議長 秋成茂信君 渡邊一議員の質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 11時38分 再開 13時00分 ○副議長 中村勇希君 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。鎌田晃二議員。 ○2番 鎌田晃二君 皆さん、こんにちは。それでは発言通告書に沿って質問させて頂きます。 まず、最初に、豊前市在宅介護手当支給条例施行規則第2条に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、類似する手当の支給を受けている者は除くとあります。 吉富町より豊前市に移って来られた方で、豊前市では、在宅介護手当が受けられなくなったとの相談がありました。吉富町の条例では、障害者のため手当を受けている方の介護者にも支給されております。在宅介護手当というのは、在宅で介護する方の援助が目的であります。1ヵ月15日以上、在宅介護した場合、支給の対象に見直すべきではないでしょうか。 次に、市営住宅入居について、お尋ねいたします。昨年6月議会で、母子家庭住宅困窮者が優先的に入居できるよう改善をお願いしておりましたが、その後、どう改善されたのか進捗を教えてください。 次に、昨年12月にヒブワクチンが我が国でも接種できることになりました。 ヒブワクチンとは、乳幼児の髄膜炎予防のワクチンで、年に600人くらいの子どもがかかり5%の方が亡くなり、25%に重い後遺症が残っております。子どもの細菌性髄膜炎の原因菌は6割がこのヒブです。その他、ヒブで引き起こされる病気は、突然、息ができなくなって窒息状態になり、死亡率も高い急性喉頭蓋炎や敗血症もあります。 このようにヒブが起こす病気は、進行が速く早期診断が難しくとても怖い病気です。 しかし、ワクチンによって確実に予防できます。20年前に導入されたアメリカなどでは、この病気は100分の1に減少して、もはや過去のものとなっております。 現在、アジア・アフリカを含む90ヵ国以上で、定期接種になっておりますが、我が国での導入は大幅に遅れ、この度ようやく発売されました。東アジアでは、北朝鮮と日本だけが接種をしておりません。ワクチン接種は任意ですので、全額自己負担になります。 4回の接種が必要で、1回が7000円から8000円、副作用も殆どありません。 欧州では、ほぼ全員が接種しており、日本でも荒川区や栃木県の大田原市で補助を決めました。豊前市でも、全額は無理だとしても、補助をお願いしたいと思います。 4番目として、妊婦健診検査におけるHTLV1、ヒトT細胞白血病ウィルス1.型の抗体検査の導入について、お伺いいたします。皆さんは、HTLV1ウィルスをご存知でしょうか。ヒトT細胞白血病ウィルス1.型とは大昔から存在し、縄文人が運んできたと言われ、後に弥生人が渡米し、南と北に分かれ、日本では九州、沖縄、東北、北海道に多いとされております。中津は特に多いと聞いております。 1985年にHTLV1に対する抗体が測定できるようになり、感染が確認できるようになりました。1990年の調査では、感染によるキャリアは、全国で120万人、世界では1000万人から2000万人と推定されております。ATLとは、このATLウィルスが原因で発病するT細胞白血病であります。発病の年齢は、平均55歳から60歳で、比較的男性に多く発生し、年間約1000人が亡くなっております。 鹿児島県では、白血病による死亡の60%が、ATLによるものだと推測されたことにより、1997年にATL抑制10ヵ年計画を制定しました。また、関連として、関連脊髄症とか、脊髄が傷つけられて麻痺が起こる病気と、これも関連しております。 自覚症状の段階は、徐々に進行が進む歩行障害、突っ張り感、足がもつれて歩きにくい、筋力の低下、大腿や腰周りに力が入らず、スムーズな動きができなくなります。 筋力の硬直やけいれんを伴い、自分では膝や関節を曲げることが困難となります。 歩行障害が進行すると、杖・車椅子が必要になります。併行して排尿障害や便秘などの症状があります。重症例では、完全麻痺、躯体筋力低下による座位障害で寝たきりとなります。HTL1の感染経緯は、輸血によるもの、性交渉によるもの、母子感染によるものが考えられます。このうち輸血による感染は、今から20年前の1986年11月から行われている献血時のHTLV1の抗体検査で、ほぼ100%阻止できるようになりました。 しかし、それ以前、輸血を受けた人は感染している可能性が残されております。 性交渉による感染は、女性から男性への感染率は0.4%と低く、男性から女性への感染率は60%と高い数値になっております。母子感染については、主に母乳による感染と考えられております。母乳を6ヵ月以上与えた場合の感染率は20%、短期間の授乳で5から7%、人工ミルクのみの場合は3から5%しか感染しないとされております。 鹿児島県では、検査で陽性となった方に授乳指導を行い、感染を抑制しています。 そして現在、このHTLV1に対する治療薬は開発されておりません。では何故このウィルスが全国に知られていないのか。いくつかの要因が挙げられていますが、1つには、患者が九州・沖縄に偏在しているために、一種の風土病と考えられていたためと、2つ目に感染しても発病は5%と低いことが考えられます。 現在は、全国に患者が広がっております。この病気の最も恐ろしいところは、潜伏期間が長いことです。30年から70年と言われています。自らキャリアであることを知らず、子どもを生み育て、数年後に自分が発病し、ばじめて子どもに感染させてしまったことを知らせるお母さんの苦悩は、言葉では言い表せません。もし妊娠中に感染していることが分かれば、母乳を与える期間を短くして、子どもへの感染が防げたかもしれません。 このようなことが起きないようにするためにも、豊前市においても、母子感染を防ぐために、すぐにでも妊婦健診のHTLV1の抗体検査を実施すべきだと強く要望します。 既に秋田県では、平成13年から大仙市をはじめ、36の市町村で、また栃木県の大田原市などでも、今年度から妊婦健診時の無料抗体検査をはじめております。 豊前市におけるHTLV1ウィルス感染者の実態は、どのようになっているのでしょうか。また費用はどのくらいかかるのでしょうか。またウィルスによる白血病、また関連脊髄症は何人いらっしゃるのでしょうか。市民への周知を図るとともに、相談窓口を設置し、きめ細かい対応をすべきと考えます。 最後に、宇島駅エレベーター設置について、お聞きします。市長は4期目の挑戦にあたり、10の約束の中に書いてありますが、エレベーター設置の展望をお聞かせください。 以上、壇上よりの質問を終わります。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 鎌田議員のご質問の中で、豊前市在宅介護手当支給条例施行規則につきましては、福祉課長、市営住宅入居については建設課長、ヒブワクチンの補助について副市長、妊婦健診検査の検査項目については、市民健康課長からの答弁といたします。 私は、5番目の宇島駅エレベーター設置について、お答え申し上げます。 まず、答弁書をつくっておりますので読まさせて頂きます。 宇島駅のエレベーター設置について、お答えします。JR宇島駅は、弧線橋となっており、高齢者・障害者等の方には、大変不便をかけている状況です。本格的な高齢化社会の到来を迎えて、公共性のある建物等を高齢者・障害者等が円滑に安全に利用できるように、平成18年に高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が制定され、その整備促進が急がれております。JR九州によりますと、JR九州は、平成22年度までに1日の乗降客が5000人以上ある全駅のバリアフリー化を達成する計画で、整備を進めているとのことです。乗降客が、今1日3600人の宇島駅につきましては、その対象になっていないということですが、高齢者・障害者等の利便性を考え、現在、JR九州と協議中であり、実現化に向け、強く要望していきたいと思っております。 議員皆様方のご支援を何卒よろしくお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 副市長。 ○副市長 後小路一雄君 鎌田議員のご質問でございますビフワクチンの補助について、ご答弁申し上げます。 ヒブワクチンは議員がご案内のとおり、細菌性髄膜炎を予防するワクチンでございまして、この細菌性髄膜炎とは、インフルエンザB型菌炎や、肺炎球菌などの細菌が脳に感染する重症の感染症で、我が国では、年間600人から1000人に近い子どもたちが感染していると推定されています。その中で約5%が死亡、約25%に重い後遺症が残ってしまう病気だとも言われております。 ご案内のとおり、このヒブワクチンは、昨年12月19日から日本では販売になっておりますが、現在では、予防接種法に基づく国の定期接種に該当しておりません。 医療機関での接種料金は、1回に7000円から8000円に設定されており、しかも年齢によっては、3回から4回の接種が必要であり、総額で2万円以上の費用負担が必要となります。また、任意接種のために副作用の障害に対して、国の補償制度もありません。 こういうことでありますので、今後は国への要望も含め、県内の医師会、市町村の動向を参考に、この助成について検討してまいりたいと思います。以上です。 ○副議長 中村勇希君 福祉科長。 ○福祉課長 戸成保道君 それでは、豊前市在宅介護手当支給条例施行規則について、お答えいたします。 在宅手当につきましては、平成5年度より実施している事業でございます。目的としては、在宅において長期間にわたり、寝たきり状態等にある人の介護者に介護の労をねぎらい、経済的な軽減等を図るために支給している手当でございます。 介護されている人の条件といたしまして、在宅で3ヵ月以上寝たきり状態で、65歳以上の者、在宅で3ヵ月以上寝たきり状態で、心身障害者である者、在宅で3ヵ月以上、認知症状態である者で65歳以上の者及び豊前市重度身体障害者医療費支給に関する条例の第2項第1項に規定する者、重度心身障害者であるが、特別児童扶養手当等の支給に関する条例に類似する者は除くとなっております。 在宅介護手当で65歳以上の要介護者については、国や県等の公的な手当がなく、そのために市が援助する意味で支給している手当でございます。在宅介護手当は、在宅で1ヵ月15日以上、介護した者に月2万円を3ヵ月に1度支給しております。 在宅介護手当等の制度がある他市町村を見ますと、大体、寝たきり状態が6ヵ月以上で月1万円、状況によっては2万円や、年間の上限を10万円としている市町村もあります。6ヵ月以上寝たきり状態で、65歳以上で介護度が3もしくは4以上の者と規定されているものが多く見受けられます。各地とも、その地域の状況により条例を制定しているため、バラつきが見られますが、豊前市においては、他市町と比べても取り立てて支給基準が低いとは思われませんので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 建設課から、市営住宅の入居について、鎌田議員のご質問にお答えします。 議員から、先の議会で市営住宅の入居に対し、ご質問がありましたので、県下66自治体の入居方法について、実態調査を実施いたしました。その結果、抽選のみが68%、選考のみが2%、選考と抽選の併用が21%でありました。 また、本市のここ2年間の抽選状況をみますと、応募は建替え後の住宅である本町団地、新町団地、上町南団地の3団地に偏っており、倍率は5倍から16倍となっております。 他の団地については1倍、2倍程度であります。また抽選会当日、公募で当選しなかった方に、申込者がいなかった団地につきまして、その場で入居等を募りましたが、結局、申込者等はありませんでした。申込者の要望に合う団地でないと選択しないというような結果が出ている実情があります。 なお、平成21年度の公募から入居資格のうち、所得基準が一般世帯で引き下げられ、申し込み可能世数はいくぶん減少することが予想されます。入居者を決定する仕組みを検討する良い機会と市としてもとらえており、今後、母子世帯、高齢者、障害者、就学前の児童を扶養する世帯等を対象に、抽選での倍率、優遇措置等を検討していきたいと考えております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 ○副議長 中村勇希君 市民健康課長。 ○市民健康課長 福田信順君 妊婦健康診査の検査項目の中のT細胞白血病リンパ腫について、お答えいたします。 妊婦健康診査の検査項目につきましては、妊婦健康診査公費負担の拡充が、20年度から議論されているところであり、21年度に向けて、県の保健医療介護部健康増進課が連絡調整をいたしまして、県の医師会との会議が数回実施されました。 その中で、委託単価を含めて検討が重ねなられました。その結果、検査項目は尿化学検査、血液型検査、抹血液一般、不規則抗体、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウィルス抗体検査、貧血、グリコース、血糖値、超音波検査、保健指導となっております。 今回の検査項目の内容には、成人T細胞白血病リンパ腫は入っていない状況です。 この病気については、日本に約100万人の感染者がおり、発症者は年間約700人と言われております。発症率は極めて低く、2000人に1人の患者が発生する程度です。沖縄、鹿児島、宮崎、長崎にキャリア、無症候性感染者が多く、国内の約3分の1を占めるとの報告があります。母子間の母乳を通しての感染、性行為による感染、輸血による感染があります。性行為による感染は、感染してから症状が出るまで30年から70年と言われ殆ど症状が出ないそうです。輸血感染もチェック検査で現在は無くなったとのことです。 それで、妊婦検査で希望すれば費用は1000円から2000円程度で受けられるということと、中津市は非常に多いということですけど、豊前市が特別多いという調査結果は出ておりません。以上です。 ○議長 秋成茂信君 鎌田晃二議員。 ○2番 鎌田晃二君 それでは、自席より質問をさせて頂きます。最初に、在宅介護手当について、お尋ねいたします。豊前市在宅介護手当支給条例施行規則第2条には、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当受給者には、在宅介護手当は支給されません。先程言ったとおりです。この件に関して調査しているときに、生まれつき知的障害1級で寝たきりの子どもを育てているお父さんと出会いました。子どもさんの成長も止まっているそうです。 介護のため会社も辞めざるを得なかったそうです。6畳ほどの店を出して、2畳ほど仕切りを設けて商売をしながら、寝たきりの子どもの介護をしております。週に2回、施設に通わせ、3時には迎えに行かなければならないという状況です。奥さんもパートを探すのが難しい状況です。この方は、特別児童扶養手当を受けておりますので、在宅介護手当は受けられません。その不況の中、商売もそれほど儲かってはいないということです。 この扶養手当と在宅介護手当というのは違うと思うんですが、福祉課長、どうでしょうか、意味合いが違うと思うんですが。豊前市の場合、この両方を支給できないということになっておりますが、吉富のように重複して支給しても良いのではないかと思いますが、如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 在宅介護手当の分を申しますと、今おっしゃられるように特別児童扶養手当等に関する法律ということで、豊前市は規定されておりまして、特別児童扶養手当、もしくは障害児福祉手当等貰っている分は対象外ですよということになっております。 その分で、先程申しましたように、介護手当については、国・県の法的な手当がある場合には、一応ご遠慮して頂くと。大体65歳以上の寝たきりの方につきましては、公的な手当がありませんので、市のほうが月に2万円出すようになっております。 基本的に在宅介護手当の全体を見てみますと、今、私が申し上げたとおりに、各町村によってかなりバラつきがあります。その点を考えますと、その状況に合わせた形、例えば人口規模とかによりまして、大変申し訳ございませんが、一応そういう手当を貰っている方は、豊前市の条件に合わせて勘弁してもらっているという状況でございます。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 人口の規模とか言ったら吉富のほうが少ないんじゃないですか。それから、先程、手当を受けている方には遠慮して頂いていると。私が申したのは、この手当というのが、在宅介護の労をねうものではないと、私はそういう具合にとらえております。 この特別扶養という形の、この扶養というのは養育のための手当でありまして、在宅介護をねぎらうだけの手当というのは別になっております。だから、例えば中津はしているとかしていないとか、どこどこがしているとか、していないとか、そういうことを言うんではなくて、良い所に合わせると。福祉のまち豊前市なんだということを合わせるべきじゃないですか。 それから、この支給、例えば、今、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害手当は、何人の方が受け取っておりますか。それから、その中で在宅介護を15日以上受けている方は何人いますか。それから、その方々に在宅介護手当を支給するとすれば、市の予算はどのくらい必要ですか、お答え下さい。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 児童扶養手当の関係につきましては、今受けている方は36名、児童福祉手当を受けている方が14名、特別障害手当を受けている方が15名となっております。 現在、介護手当の受給で申しますと、19年度実績が1580万円であります。 12月現在の介護手当の受給者は金額は出ませんが、現在62名の方が受けられておりまして、この分が大体2万円をすれば1400万円ぐらいかと思います。特別児童扶養手当、障害者手当の中で、寝たきりという方に一応なっておりますが、大変申し訳ないですが、その分の実数につきましては、正直申し上げますと、予算等はどのくらいになるかということは、今のところ把握ができておりません。以上です。 ○議長 秋成茂信君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 福祉課で把握ができないというのは、あってはならないと思います。前々日でしたか、皆さんで一緒に調べたときに、課長、大体10人という数字が挙がってまいりました、職員の方からね。この中で特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給者の中で、寝たきりで15日以上介護している方は、大体10名ぐらいだとお聞きしました。 この10名に、在宅介護手当を吉富は1万円、2万円と区切っているようですが、この10人の方に支給を豊前市でするとすれば、月にいくらぐらいの費用がかかりますか。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 10人の方で計算いたしますと、月に2万円ですと月に20万円ということで、全体ですれば240万円ということになります。以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 月に20万円、もし1万円とすれば10万円ですね。10万円から20万円の支出になるということですが、それだったら福祉に、あそこはしている、してないとかじゃなくて、良い所の施策に合わせる豊前市ということで、実施してもらえませんでしょうかね。 これは市長の決断、課長に言うと、上の人に聞かないと分からないと言われましたので、上の人というのは市長でありますので、決断をして頂きたいと思います。 よろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 検討していきます。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 何時も答えは検討するということで、何時も何もなっておりませんので、是非、市として10万円から20万円の支出になるかと思いますが、是非これはお願いしたい。 本当に考えて頂きたいと思います。 続きまして、市営住宅入居について、お尋ねをいたします。豊前市市営住宅の管理条例には、本当にこれは県営住宅もそうですけれども、困っている人から入居させる。その数が募集の戸数よりも増えた場合に抽選する、これが条件であります。 しかし豊前市は先程、課長の答弁がありましたように、余所の市もあると思いますけれども、戸数以上集まったらランダムに、そのまま抽選するというような安易な方法が取られてまいりました。それで昨年5月に、子どもと2人で車の中で寝泊りしている母子の方が相談を受けて、結局、市は何もしなかったわけです。もう8ヵ月も経っておりますので、よろしくないんじゃないかと思います。 公営住宅法の25条第1項に施行条例第7条の規定により、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的にしておりますとなっております。母子家庭が公営住宅に入居する場合には、豊前市では、もっと母子家庭にやさしい措置はできませんか。 県営住宅では、母子の方はくじを2回引けます。さらに県は7月より困窮者ポイント制というのを導入して、2回追加して抽選をするようになりました。これは豊前市も資料を取り寄せて研究してもいいんではないでしょうか。課長、どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 今回の鎌田議員のご質問にありましたように、アンケート調査をいたしました。 その結果、抽選で住宅判断、困窮度合いに応じて配慮している、配慮していないというのを調査した資料の調査内容によりますと、配慮してないというのが56.6%です。 配慮しているというのが30%、また多数回申し込みについても配慮してないというのが56%、配慮してるが18%あるわけですが、豊前市も今議員が言われるように、この機会をとらえて、言われた母子家庭だけでなく、高齢者、障害者、就学前の児童を含めて、今言われたように2回なり3回引くなり、そういう方法を今から検討していきたいということを考えております。 また、優先入居、ポイント制という話になりますが、ポイント制の検討も必要と思いますが、この中で大事なことは、結局どこを基準に置くかといった場合に、保有資産とか、いろんな問題の申告制度とか、個人のものまで入っていくような状況もある可能性、どこまでが困窮しているのか、そこの問題もあるので、これは慎重に考えて、また公平にしなければいけませんので、選考委員会等も設けて検討していく課題だと認識しております。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 それでありますから、県の資料を4月からなりますので、取り寄せて検討して頂きたい。先程の検討委員会というのを、去年6月質問して7月の時点では検討すると、未だにされておりませんので、是非お願いしたい。 それから、さらなる提案と言いますか、別枠で母子世帯などの福祉目的の住宅募集という形も良いと思うんですね。ちょっと書き留めておいてください。今ある抽選とは別に、母子家庭とかいろいろあると思うんですが、そういった福祉目的の住宅募集を行ってはどうかということが1つです。自治体によってはされています。 それから、先程、課長が言われましたように倍率優遇、2度の抽選を設けるとか、またこれは磯永議員も言われておりましたが、多数回に落ちた落選者を救済していくといったことも良いと思います。母子家庭に限らずですね。それから公営住宅には、一般住宅と特定目的住宅とがありますが、豊前市では特定目的住宅等ありますかね。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 豊前市は特定目的住宅はございません。一般住宅のみです。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 これは提案ですけれども、母子世帯向け住宅とか、例えば、この特定目的住宅というのはいろいろあります。老人世帯向け住宅とか、心身障害者向け住宅とか、生活保護受給者向け住宅とか、DV被害もそうです。広島等では、原爆者向けの被害を受けた方の住宅もございます。こういった形で今、上町団地の改修をして、これに充てるとか。 また中村雇用促進住宅が、もし買い上げということになりましたら、課長もちょっと、そういうことを話されておりましたけども、これをこの特定目的住宅に充てるようなお考えはないでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 上町南団地には、1棟目には2戸、2棟目にも2戸、福祉住宅を充てるようにしていますし、雇用促進につきましては、今いろいろ雇用促進機構と協議をしております。 また若者も住めるような住宅とか、いろんなことがあると思います。そういうことを含めて検討していきたいと考えています。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 豊前市は福祉に本当に頑張っているということを、お願いしたいんですね。 公営住宅法にこうあります。公営住宅は、地方公共団体が住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に設置している住宅であるとあります。本当に困っている人のために助ける本気の改善を課長、よろしくお願いいたします。 続きまして、ヒブワクチンですが、先程お聞きしましたけれども、国への要望をしながら検討していくというお返事を頂きました。自分の近くにもいらっしゃったんですが、風邪かと思っておったら何か髄膜炎になってしまって、障害が残ってしまったと。 この病気は、お医者さんが7割ミスするそうです。風邪と間違えるそうです。そして手遅れになって亡くなったり、知的障害になる患者さんがいらっしゃるということです。 これは北朝鮮と日本だけという恥ずかしいことではなくて、国が遅れているんであれば、豊前市でも頑張っていくという取り組みを是非お願いしたいと思います。 それから先程言いました妊婦健診の4番目、項目検査ですが、あまりいないのではないかという話をされていましたが、これはやはり検査して頂きたいですね。検査費用が1000円から2000円と言っておりましたけれども、もしお母さんが自分がキャリアであった場合は、子どもさんに母乳を少なくする。3ヵ月以内だったら本当に感染率が少ないですから、そういったこともできますし、またエイズとは違いますので、広報等で周知・告知を徹底すれば、誤解も生まれないのではないかと思います。 そして母乳で育てなくてミルクで育てれば殆ど100%、子どもが生まれたときに血液で感染するのを除いて、100%感染は防止できます。今、母乳も冷凍保存したり、温度を上げたりもできますので、完全にお母さんが選択できるし、私もお袋が早く亡くなって、ミルクで育っておりますが立派になっております。これはお母さんが後で本当に嘆くことのないように、是非、検討をお願いしたいと思います。 最後に、宇島駅エレベーターの設置について、お伺いいたします。私は今、宇島駅エレベーターの設置の署名活動を始めました。まだ500人ほどの署名しか集まっておりませんけれども、その際いろんな話をお聞きします。母が高齢で階段を上がるのにも時間がかかり、乗り遅れて次の電車になることが度々あると。中津の川島整形で足の手術をしたけれども、駅の階段の上り下りでまた悪くなった。車椅子の方は、今3名利用されております。車椅子を乗せるリフトが怖いと言うんですね。エレベーターがあれば旅行とか、外出する回数も増えるのにというご意見を頂きました。中津駅を利用されている方も沢山おります。とにかく1日も早くエレベーターを付けてほしいというのが皆さんの声でした。 私は2月12日に、宇島駅に車椅子の方と視察に行ってまいりました。駅正面の階段は削られて段差がとられているんですが、それでも5センチくらい残っているんですね。 引っかかってものすごく危ないということです。使用する人の立場に全く立ってないというのがやはり行政ですね。 駅からホームまでリフトを使って移動するのに、45分かかると言うんですね。だから駅員が時間外のときは、あそこは1人しか付いていません。そうなると駅舎に鍵をかけて現在対応しております。こういった意味でも、是非エレベーターは必要だと思います。 海側の方にも降りられるようにもしたいとか、いろんな意見が出ております。 駅舎は古いから建替えるとか、エレベーターをすれば、今の建替えなければもたないんじゃないかとか、いろんなことが言われていますが、このエレベーターの工事費というのは、どのくらいかかるでしょうか。 それから、交通バリア法により国・JRの支援は受けられないのか、お聞きします。 5000人以上というのは、もうお聞きしましたので。 ○副議長 中村勇希君 副市長。 ○副市長 後小路一雄君 エレベーターにつきましては、昨年7月から、私どもが数点の要望をしております。 まず、市長から答弁がありましたけども、JR九州は、平成22年度までに5000人の利用客について、バリアフリー化をするということで、当初は、非常に否定的でしたけれども、最近、協議・要望を重ねていくうちに、消極的から非常に柔軟に協議をして頂けるようになりました。議員が今申されたようなリフトの件、エレベーター、障害者のこと等、全て私の方から説明を申し上げて要望しております。 エレベーターの価格ということですが、今その協議の中で、いろんな形態がありまして、今月末くらいには、ある一定の方向が出ろうかと思います。JRも先週に実測に来ておりますし、それで22年の問題もありますけれども、これは国の補助事業になるわけですが、私どもの単独でということも含めて要望しましたが、やはり最少の経費で最大の効果をということになりますから、是非、JRに国の補助事業にのせて、22年とは言わずに前倒しでお願いしたいということも、お願いをしております。 というような状況ですので、エレベーターが幾らかということに関しましても、いろいろとありますので、今、価格は申し上げることはできませんけども、私のほうも東芝のエレベーターがありますし、そういうことも含めて協議をしている状況でございます。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 交通バリアフリー法が2006年に新バリアフリー法にかわりましたね。ここはどう違うんですか。また、この交通バリア法の5000人以上の乗降客がなくて、国の補助を受けた所はあるんでしょうか、お聞きします。 ○副議長 中村勇希君 副市長。 ○副市長 後小路一雄君 バリアフリー法の詳しいことは承知しておりませんけども、トイレとか段差とか、いろいろ含めて計画をしておるようであります。それから、もう1点は、単独でやっておる団体はあります。それは補助はございません。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 私が調べたら1件あるんですね。和歌山県の田辺市、JR紀井田辺駅というのは、豊前市はさっき3600と言いましたが、駅長に聞いたら3700だそうです。 それで、このJR紀井田辺駅というのは3900人の乗降客ですね。殆ど変わらないですね。けれどこれが通りまして、JRが3分の1、国が3分の1、県と市が3分の1の負担で、来年3月に完成予定になっています。これはいろいろ田辺市役所に電話しまして、何故こんなことができたのかということを伺いました。やはりもう粘り強い陳情、それから新バリアフリー法というのが、ちょっと変わっているんですね。 何に重きを置いたかと言いますと、結局、市町村が作成する基本構想の指針を、まず大事にして、なお且つ重点整備地区といった項目が入っております。ということは、ここも都市化計画じゃないですが、北九州にも近いし、そういった意味も込めて要請していけばいいんじゃないかと思います。 このJR紀井田辺駅というのは、工事費が2億5000万円、障害者用の多機能トイレの設備費が6000万円、これは全部3分の1ずつの負担でできるようになりました。 いろいろ私はしつこく聞いたんですよ。そしたら問題の二階経済産業大臣が動いておりました。和歌山県出身です。そういったことを使ってでも、エレベーターを安くあげようということをやっておりました。 是非、豊前市もどんな手を使ってもいいから、エレベーターを障害者や困った方のためにつくって頂きたい。笑っていますけども本当ですよ。そして先程言いました、いくら工事がかかるか分からないという話がありましたけども、まず障害者の方、お年寄りの方も本当に困っていらっしゃる。これを向こうに下ろすとか建替えるとか、そういったことじゃなくてエレベーターだけでも先に設置する。市の予算を取って設置する。駅長に聞けば6000万円か7000万円で、今の後ろ側にエレベーターだけだったらできるだろうという話を聞きました。 ここだけでも市長、どうですか、今日は、かなり傍聴の方も来られています。 やっぱり4期目は釜井市長でないと駄目だというような返事を頂きたいと思いますが、如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 行橋・中津は高架になっているんですね。我が宇島駅は、高架はなかなか厳しい。 そしたらやれるところは何だろうかと。今まで駅と係わりがあるのが3つありました。 汽車の見える公園、これはJRは金を出しておりませんけども、いろいろ整備をしました。そして駅の前の整備は国の予算がありまして駅の協力を得てしました。 もう1つのトイレは、JR宇島駅さんの持ち物でありますから、全部JRにして頂きました。今の話のエレベーターの件は、やはり現実の選択として、一番無理をしてでもやらなならん所だと思っております。先般、東京に行きました旭桜会の三毛門の人ですが、ちょっと来てくれと。何かと思いましたら、俺は宇島駅に降りようと思ったら上がりきらんと。中津に降りよってすかんと。是非せんかということでございました。 そのときにパンフレットを見せましたら、おお書いとるのうということを言っておりましたので、是非これは至上命令、先程どんな手を使ってでもと、どんな手を使ってもいけませんけども、どんな手を使う気持ちでもやろうと思います。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 具体的に何時というのは、今日は言えないですね。バリアフリー法というのもおかしな法律で、公明党の方からも5000人以下の所にエレベーターを付けるべきというのを働きかけております。5000人以上の乗降客と言いましても都会は学生や若者ですよ。 そういう人が5000人おっても階段で十分ですよ、エレベーターなんかいりません。だけど10人、20人の障害者の方とか、足の悪いお年寄りの方とか、この人たちが10人いれば、こっちに付けるべきというバリアフリー法を作るのが国の役目だと思います。これは市に言ってもしょうがないですが。 そういった意味で、今、市長の力強い絶対やると、それも早いうちに、是非、要望いたしますので、また、ずるずるずるずるなるのも嫌なんですけれども、本当に市長、いいですかね、お願いできますか。 (「はい」の声あり) 以上で終わります。 ○副議長 中村勇希君 鎌田晃二議員の質問を終わります。 次に、岡本清靖議員。 ○3番 岡本清靖君 皆さん、こんにちは。私は今度1年になります。1年間いろんな勉強をさせて頂きましたけども、やはり自分の田舎、岩屋町、そして合河南部地区の関係の話になろうかと思います。6月議会、12月議会に出させて頂きました質問と内容が、異なるところがありますが、よろしくお願いいたします。本日は3点について質問させて頂きます。 第1、農業の振興と荒廃対策についてであります。私たちは、今何を求めているのか。職を無くして生活はできません。職とは何を求めるのか。いろいろな農業施策をする中で、担い手農業者、認定農業者、営農組合等の分野の方々に分けられ、農業にいろいろ従事しております。豊前市内の平坦地では、いろいろな野菜、水稲、いろんな農業が施策されております。その中で転作地に野菜の系統、果物、大麦、大豆、花等がつくられ、山間地域では水稲。転作地には、そばやイチジク、野菜、景観作物、密源作物など作付けが行われております。 私たち中山間地域では、高齢化や過疎化が進行している中、後継ぎの人がいない悪条件に満たされております。今後、政策としまして、直接支払い、農地、水、環境保全の制度がありますが、どのような利点があり、どのような現地に適しているのか、お伺いします。 また、山あいでは獣害による被害で作付けができる状態ではなく、荒廃になりかねない田・畑が出ています。今後どのような対策を考えていられるか、お伺いいたします。 2つ目に、森林環境と生産性の向上であります。森林のもつ機能、働きは、私たちの暮らしに様々な恵みをもたらしています。二酸化炭素を吸収、地球温暖化を防止する、土砂の流出、崩壊を防ぎ、水を蓄え浄化する、やすらぎを与える、防風林の役目をする。 自分たちの住む木材を供給できる、山からの豊かな栄養分を含んだ水が流れ込む、川や海の生き物を育てる。森林の施業の仕方によっては、野生動物が今存在しておりますが、里まで下りて来ないのではないかと私は思っております。これが森林のもつ環境づくりではないでしょうか。行政は環境をどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 また、県産材、地元材のPRについて、森林組合等を交えて、どういった対応をしているのか、お伺いをいたします。そして所有者に対しても、所得向上につながる販売経路も模索をされているのか、お伺いいたします。 最後に、人口増対策であります。釜井市長、3期、いろいろとお疲れでございますが、今度4期目に挑戦、そして、そのままの真っ直ぐな姿でまいられると思います。 それについて、また人口増対策を私は言いたいと思います。 後期基本計画がなされている中で、基本構想、人が元気、まちが輝く、豊前から未来への風が吹く、とうたわれております。平成24年度の目標人口を3万2500としております。今まで行ってきた具体的な内容があれば、教えて頂きたいと思います。 また、今後の政策、目標について、お伺いをいたします。 これで壇上よりの質問を終わらせて頂きます。後は自席より質問をさせて頂きます。 以上です。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 岡本清靖議員のご質問の中で、農業の振興と農地の荒廃対策について、農林水産課長、農業委員会局長、そして、2番目の森林環境と生産性の向上について、農林水産課長の自席からのご答弁といたします。私のほうから人口増対策。 今、豊前市の人口は、平成21年1月現在、2万8078名。戸数は、今までで一番最高ですけれども、微減の状況で頭の痛いことですが、これに対しましては、後期基本計画の目標人口、そして目標政策を忠実に頑張っていく。また、減税等の方策をもちながらやっていこうと思っているところでございます。自動車150万台推進構想も頓挫の状況ですけども、しかし、これは必ずこの地域が、日本における自動車の生産地域には間違いありませんので、今から準備をしながらいこうと思っております。 また、福岡県の一番東端で非常に厳しい状況でしたけども、京築広域圏、また新しい総務省の自立圏をダブらせて、するどくやっていこうと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 それでは、岡本議員のご質問のうち、最初に、農業振興と農地の荒廃対策について、お答えしたいと思っております。 本市におきましては、中山間地域等直接支払事業及び農地、水、環境向上対策事業を合河、岩屋地区及び市内全域を対象に、事業を推進しているところでございます。 両事業ともに、事業対象地域の耕作放棄地の解消や、農業施設の良好な管理を、地域住民が協同で行なうことに対する支援が中心となっております。このような取り組みにより、農村環境が保全され、農業、農村地域がもつ水源涵養、洪水防止等の多面的機能を維持し、風景や自然を守り、農地の荒廃を防止するとともに、都市住民に対する余暇の提供が可能となっております。 次に、農業者の高齢化の問題でありますが、農林業政策の調査におきまして、過去5年間で、約473戸の農家が米・野菜等の農産物の販売から撤退しております。 農業者の高齢化や、農家数の減少の要因としましては、水稲をはじめとする農産物価格の低迷や、機械や資材等の経費の増大により、農業経営や若年者の就農が困難な状況になっているところであります。今後、高齢化による離農のため、遊休農地が生じるような場合につきましては、農業委員会等関係機関と連携の上、担い手への利用集積等を進めてまいりたいと考えております。 次に、有害鳥獣対策につきましては、市の単独事業としまして、イノシシ・鹿等による農産物の被害を防止するため、被害が顕著な地域につきましては、防護柵や電気柵等の設置に要する経費について、補助する事業を設けております。また、国の鳥獣被害防止の基準に基づき、被害防止計画を現在、策定中であり、農林業団体及び狩猟者団体等と連携し、有害鳥獣の個体数の調整、被害防除等の取り組みを総合的に進めてまいりたいと考えております。 今後の農業の経営対策については、農業生産基盤の整備を推進して、基幹的担い手となる認定農業者の育成・確保と、営農組織の設立や法人化の支援を継続するとともに、農業所得の安定確保を図るため、施設園芸や新規作物の導入、新技術の導入等による高収益型農業の支援や、女性クループ等による農産加工や、直売所向けの野菜・果樹の産地づくり、地域資源を活用した特産品の開発を、今後とも支援してまいりたいと考えております。 次に、森林環境と生産性の向上について、お答えいたします。 本市を含む京築地域については、京築ヒノキの産地として有名でありますが、近年の住宅建築工法の多様化による安価な外国産材の輸入により、国産材の価格の低迷に伴い、生産量、林業者ともに減少している現状であります。京築ヒノキを含む県産材の使用に対する補助金については、県建築都市部住宅計画課において、福岡県快適な住まいづくり推進助成制度により、住宅建築費用の一部、最高限度額につきましては、47万円程度が助成される制度があり、PRにつきましては、県のホームページに掲載されております。 次に、地産材の販売拡大につきましては、福岡県と京築地区の各市町及び豊築・京都の森林組合で構成する京築地区森林・林業推進協議会の地域材利用部会において、県産材を使用した住宅見学バスツアーの開催や、公共工事における間伐材等の利用推進及び新用途 の開発研究、地元材を利用した木工教室の開催、間伐材を利用した公共施設等への内部改装工事への一部材料の提供等を行い、県産材のPR及び販売拡大を行っているところでございます。 また、所得向上につきましては、県産材の価格の上昇が見込めない現状を踏まえ、国・県の補助事業、特に、荒廃森林整備事業を積極的に活用し、積み込み運搬時の高性能機械導入や、効率的な作業道の開設により、施業能力の向上や労働時間の短縮を図り、生産コストを削減することにより、林業所得の向上を図ってまいりたいと考えております。 次に、森林環境につきましては、豊前市におきましては、森林の整備をすることにより、山に降った水が農地に落ち、そして海に行くということで、やはり森林の整備につきましては、一番重要なことではないかなと考えております。そのためにも荒廃森林事業等の効率的な事業を推進してまいりたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長 木村泰暢君 岡本議員のご質問のうち、農地の荒廃対策と今後の高齢化対策について、お答えいたします。農地の荒廃対策としましては、農地パトロールを実施しているところであり、平成20年度調査において385筆、33.8haの耕作放棄地を確認しております。 調査後の対応につきましては、農業委員が直接指導を行う場合と、事務局から文書を郵送し、適正管理をお願いする等の対応をいたしております。 高齢化に対する対策についてですが、高齢等で耕作できない農地につきましては、利用権設定による担い手農家への貸借契約を進めることで、有効利用へ結びつけるよう図っており、その実績、件数、面積等は年々増加しております。今後も農地パトロール等を通じて、所有者のニーズの把握に努めるとともに、農林水産課と連携して、農地の有効利用を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 この農業、林業は皆つながりがあると思います。まず、農業の関係で高齢化している中、私たち田舎、中山間で人口が減っている中、今、農業委員会の課長が言われましたけども、利用権設定ということで、田舎まで来て田をつくられるという形はあまりできないんではないかと思います。やはり地域の方、近くの方で守っていくのが当たり前ではないかと思います。外から来て棚田を守り、ほ場整備をしていない所が沢山ありますので、そういった所の田をつくることは非常に困難だろうと思います。そういった中から、人口増対策が一番大事だろうと思います。 その中で、中山間地域直接支払等環境保全の問題を農林課長が言われましたが、環境保全、農地、水、少し取り組みが豊前市的には少ないんじゃないですか。そのところをお伺いいたします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 豊前市におきましては、現在、農地、水、環境保全向上対策事業につきましては、取り組みが9地域あがってきております。それにつきましては、田んぼの面積が1万4603アール、畑につきましては932アールということで、現在行われております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 その中で豊前市全体ですけれども、中山間では、どういったところが何箇所かあがっておりますか、お聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下正君 中山間地域につきましては、夫婦木地区と枝川地区があがってきております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 中山間地域をこれから守っていくために、こういった制度があるだろうと思うんです。それが中山間地域で2地区しかないというのは、行政側としては、どのようなお考えでしょうか、お伺いします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 農地、水、環境整備事業等につきましては、農地の所有者と、後、地区の住民等が一緒になって環境整備をしていくという事業ですので、そこの横の連絡を十分取って頂いてやっていくべきと考えておりますし、また今後につきましても、そういう部分については、うちとしても十分指導していきたいと考えています。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 この問題は長く言っても話がつかないだろうと思います。これ自体、地域の中に出向いてでも、制度があり補助があるならば、そういった利点を田舎の方にまとめてもらうというか、出して頂くような行政側の積極的な指導が大事だろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、荒廃の形を今言われましたけど、田んぼの荒廃は、できるだけ地元で対処しながらやっていきたいと思っております。できるだけ出ないような形を考えていきたいと思いますが、高齢化になっております。そして跡継ぎがおりません。段々と私たちの所も人口が減っております。今でも限界集落の状態になっておりますが、何もしなければ、もう崩壊集落と言っても過言ではないのではないかと思います。逆に行政からいろんな補助がなければ、岩屋、合河、山田も一緒だと思います。お互い一番詰めの所は、どこも一緒だろうと思いますが、農業はしなくても良いというような考え方になるかと思います。 そういったことがないように、中山間地域を、これからも大事に行政側としては見守って頂きたいと思っております。そして私たち岩屋の中山間地域ですけども、これも、だんだんと合河、岩屋が統廃合されました。そんな関係で人口も少ない中で統廃合されただろうと思います。これから、まとめた農業というものを林業も一緒ですが、積極的に行政の指導をよろしくお願いいたします。 それから、農業をする中で水も大事だろうと思います。森林がもつべき浄化された水が河川に流されておりますが、現在、自分たちの家庭排水が河川を汚しておりますので、そういった水で農業、水稲をつくるということは、安心・安全から考えても、だんだん難しくなるんではないだろうかと思っております。そういった家庭排水の関係で、今、東京の多摩川地区が一番初めだろうと思います。源流きらりというバイオ的な洗剤ではないんですけども、そういった菌種をバイオでさせて、河川を汚くしないというような形を今とっております。そういった形は、私たち中山間の田舎のほうで集落排水ができなければ、そういった問題もソフト面などで田舎の活性化、そして環境問題も兼ねて、こういった納豆乳酸酵母菌といった家庭でできます。こういったものを、1つの事業として取り組めれば、これから先、河川は下のほうは段々と浄化槽などいろいろできております。 田舎のほうは浄化槽が今入っておりません。そんな感じで、やはり源流から河川を守っていくのが、当たり前だろうと思っております。そういうことで、これから先もソフト面で、行政がこういう事業に取り組めれば一番良いのではないかと私は考えております。 これが今の源流きらりの原本ですけども、あと佐賀県の川内の村が前向きに取り組んでおります。そういった中で、風呂の水も6ヵ月間換えなくてもよろしいという言い方をしております。風呂の水6ヵ月間換えなかったらということを考えますと、ちょっとびっくりしますけども、20ccの原液を少しずつ入れて、毎日、毎日、たらしたら、中でバイオ菌がその中で増えて、全然汚くない、臭いもしないというんです。 そういった形を今とられております。そういったことで、これから田舎のほうに、こういったものを関係の機関であります皆さん方に、考えて頂きたいと思っております。 次に、林業のほうに移らせて頂きます。今、地産材の販売拡大のPRができているような言い方をされましたけども、まず、京築地区は1つですけども、人口を増やすためには、豊前市内でのPRが大事だろうと思います。豊前市内に、モデルハウスなんかを建てさせて頂き、そういった面で転入される方々を招き入れる中で、こういった家はどうですかということでPRをされたら如何でしょうか。 そういったことは外部でされているような課長の話でしたけども、やはり地元でそういったPRをして頂き、森林組合等と一緒になって、行政側に積極的に宣伝効果のためにも、取次ぎをするという考え方はありましょうか、ちょっとお聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 モデル住宅等につきましては、直接の補助は、今のところは財政的にも難しいのではないかなと考えておりますが、それにつきましては、勉強させて頂きたいと考えております。後、京築ヒノキのPR等につきましては、私も地域産部会に入っておりまして、今回、固有名詞を挙げたら悪いんですけど、宇島の漁業組合の本所にPRを兼ねて、京築産のヒノキの腰板というようなことで頂いております。 後は、各公共団体、病院とか、机とか、基礎という分については、目に見える所でやっていって頂きたいということで今PRをしております。 それと、ここの県産材等、地元の部材につきましては、今、建築工法が、軸組等につきましては合板材と言いますか、そういう部分でないとヒズミが出るということで、大きな住宅メーカーについては、ちょっと回避されているという面がございます。 県産材につきましては、内装等についても、今後は、豊前市の分については、豊前市で使って頂けるのが、一番望ましいのではないかと思っておりますし、また今後とも、それらについては検討していきたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 豊前市内のいろんな所の企業の中で、そういった形で、今、県産材が使われていると言われましたけど、そういった地元材の中で使って頂くには、どんどん積極的に声掛けしてもいいんではないかと私は思っております。そこの業者とのタイアップで、全部使ってくれというのじゃなくて、少しでもいいから、その家の中に使って頂くような感じで、だから椅子なんかでもPRになりますけども、そういったものをどんどんこれからもしていって頂きたいと思います。 また、地元材についてのアンケートや、そういったニーズ的なものは、して頂いたことがあるでしょうか、お聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 毎年、京築アメニティの開催時に豊築森林組合とか、ここの地域材利用推進部会の方で出店等をしておりまして、そのときに若干のアンケートは行ってきております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 はい、分かりました。できるだけ京築ヒノキじゃなくても杉材も一緒ですけれども、やはり地元材として、できるだけ多くの利用をして頂くように努めて頂けると思います。 それから、今、荒廃された森林環境ということであげられています。今、一番スギ花粉が飛んでおります。そういった中で、花粉症になられた方が一番多いと思いますので、荒廃されている森林を今から整備される中で、1回、山のサイクルをさせて頂くというか、そういった形で、杉材が試験場なんかでも花粉が飛ばないような品種が開発されていると思います。 そういった仕組みに、今から荒廃の中を段々と新しい木にリサイクルさせてもらって、そのリサイクルするのが、今、火力発電とかバイオ的な所に、いろんな面で利用させて頂くという面を利用しながら、森林の開発をして頂ければと考えています。 そうしたら、今の花粉現象されている人たちの保険の使い方が、だいぶ違ってくるんではないかと思います。やはり豊前市の税金面に対しても効果があるのではないかと、私は考えています。そういった保険税の形を逆に山のほうに持ってくるような感じ。そういった開発・施策の仕方もいいんではないかと私は考えておりますが、そんなところはどんなふうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 伐採した部分等につきましては、今後とも、今、花粉が飛ばない杉というような部分も出てきております。そういう部分に随時、変更していくべきではないかと考えております。 また、間伐材の利用等につきましては、今後ペレットとか、小さな部分にして発電とか、そういった部分に持っていければ良いと思いますが、それにつきましても、かなりの金額等がかかります。それについてはコスト等もかかってきますので、やはり小さい部分から勉強してまいりたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 今、言われましたけども、こういった考え方で、今、植え込みは杉材を植えてもいいんですけど、広葉樹、針葉樹、やはり昔の山に戻さないと、人工林が今増えていまして、獣なんかが、今だんだん里に出てくるというのは、昔の山が人工造林にかわってしまった形だろうと思っています。そういった中で山には食べ物が無くなる。昔のように椎の実、栗の実、ドングリや、いろんな実が落ちて、山で自分たちが生き延びてきたのが、だんだん里に下りてくるという形になっておりますので、そういった政策を考えてもらわなければいけないかなと思っております。それは、またよろしくお願いします。 後、企業の中でも雇用の問題があがっております。緑の雇用対策といったものの考え方はありましょうか、ちょっとお聞きいたします。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 直接の担当がまだ決まってないので、総務課が総合的な担当になろうかと思いますので、雇用問題につきましては、明日もご質問が出ておりますが、今日の市民の生活状況というのが非常に厳しい状況にあると。ご案内のとおりに、中山間地域におきましては、非常に厳しいものがあるということで、今プロジェクトチームをつくっておりまして、森林組合等ともタイアップしまして、一時帰休の方々とか、そういう方々の例えば、こういう機会に農業関係、林業関係あたりの体験型の職業適用訓練とか、そういうものに関心がある方の啓発とか、今回のこういった景気の中で考えていきたいということについては、私ども副市長をトップにします対策チームの中で、議論をしております。 本格的には、新年度の予算の中で、何等かの形で出していかなければならないと思っておりますが、今は関係機関と、どのような事業があるかということについてのヒヤリングや調整中ですので、今暫く時間を頂きたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 分かりました。私にも声をかけられました。林業では難しいですよという言い方、農業も一緒だと思いますけども、そういった中で、自分なりに農業、林業としても、毎日、毎日の仕事ではないんですけども、雨が降ったりいろんな面がありますが、そういった中で、林業に対して雇用対策関係があるんじゃないですかと言われたんですよ。 そういうことで雇用対策は私も分かりませんから、行政や森林組合に問い質してくださいと、一応そういった話をしていますので、こういった人たちが出てくれば、できるだけ早く、そういった雇用の関係を考えて頂きたいと思っております。 後、環境の関係ですけども、夏場、冬場でも森林には、田舎の方に登山者多くなります。憩いを求めて来られると思います。だから、そういった面で、県のキャンプ場の近所、そういった所に森林セラピーというか、そういった憩いの場を、もう少し大きく、遊歩道的なところで考えてもらって、その地域の河川の関係も一緒に含めて、そういった問題に、これからも取り組んで頂けたらと思いますが、どのようでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 今の議員ご指摘の森林セラピーについては、今、全国で約35箇所の森を森林セラピー基地と、森林セラピーロードとして、森林セラピー実行委員会等で認定されております。 福岡県につきましては、浮羽市と黒木町、篠栗町がその認定を受けております。 森林セラピーにつきましては、リラックス効果が、森林医学の面からも専門家に立証されておりまして、関連施設等、自然・社会条件が一定の水準に整備されているということで、求菩提の付近が一番絶好の候補地ではないかなと思っております。 それにつきましては、今後、十分勉強させて頂きたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 候補地と思っておりますじゃなく、候補地にして頂きたいと思っておりますが、その点はどんなふうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 求菩提を中心にして、今後、検討していきたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 では前向きの検討で、またよろしくお願いいたします。 最後に、人口増対策に移らせて頂きます。今、市長からいろいろとありましたが、これから人口を増やすためには、外からの転入者がないことには、今の妊婦さん、若い人が子どもを産んでも、今、何人の方が居られるか私も分かりませんが、転入者を総合的に考えなければいけないと思います。そういった中で、転入者を迎え入れる所がないと、家がなければ入ってこない。逆に市営住宅があっても、固定資産がとれない、では税金だけという形になります。 固定資産が取れるような1戸建で、そういったものを多く、下の方ではなく横武、岩屋、合河のほうに、そういった面をもっていってもらうという形で、人口対策をと思います。そうしないと、私たちの所もだんだん高齢化で、私たちも何時どうやったら動けるか分からない状態でありますので、これからの人口増対策、そして、その転入者に対しての優遇措置、税金の減免や新築建物をされる場合は、少しの補助を出すとか、保育料の関係の免除といった、どこにもない優遇措置を一定期間だけ出してもらったらと思うんですが、そういうところはどんなふうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 大体、お会いしましたけども、2階建ての建物には4戸あれば半分ぐらいしか入っていませんね。けれども1戸建の土地がある所は、貸家でも大体入っていますね。今言われました合河、岩屋は東九州インターの件も含めまして、そのときの可能性ももっておかなければならないということになろうかと思います。 何も手を打たずに人口は増えないよ、ということですので、今考えているように、税率を下げようと、これも豊前市40年できなかったことですが、これをするにあたっても、大変なことだけどもやってみようと思っています。細かい制度は、前の議会でも言いましたけども、築上郡のほうと最低のレベルを合わせていかなければならない。より良いものは残していくと、こう思っているところでございます。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 まず、人口増対策の関係です。先程、市長が言いましたけど、今後の対策として、どういった面で人口増になるか、そういったものの考え方があれば、お聞かせ願います。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 いずれにしても方法は3つしかない。1つは、働く場を引っ張ってくる。今いる所がもっと豊かになること。やはり職場、仕事場、収入によるところを潤すこと。 2番目が、働く場の居住地区になること。それは北九州に勤めたり、行橋に勤めたり、中津に勤めたり、だけど住むのは豊前だということだと思います。 3番目は、一番大事なことですけども、住む方にとってメリットが何があるかと。 今まで私が何回も言いますけども、この我々が住む地域は一番福岡県のはずれであったんで、デメリット的な件が多かったわけですが、今この自動車150万台、また、これから必ず県を越えてのいろんなことが起こりますので、しっかり福岡県の豊前、福岡県の築上郡ということを押さえながら、福岡県と喧嘩をするんじゃなくて、福岡県と協力をしながら中津・大分県と対応していくというようなクロス型の地域に漸くなったなと思っております。見込みはあると思っているのが3番目であります。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 今、市長はメリットがありますと言いました。私の今言った減免措置が、やはりメリットじゃないかと思います。そうしないと転入者が来て、自分たちのメリットとは何か。 普通どおり転入されても税金面が本当に良かった。何年間でも助かったというところが、一番あれだろうと思います。そういったところの考え方は、市長どんなふうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 そのためにはフィールド、土台がちゃんとせんと、お金も税収もないのに良いことのじょう言っても駄目なんですよ。今からの行政は、ある程度の税収を自分がもって、交付税がカットされてもやっていける。今、豊前市の自主財源率が、大体、4割5分ぐらいですか、45%といったら県下の市の中でも真ん中ぐらいです。ですから捨てたもんじゃないと思います。町村は殆ど2割ぐらいですね。ですから、半分ぐらいはいっているわけですから、後は半分で制度でやれば対応できます。だから自主財源率をもたなければ、なんぼ良いことを言っても駄目なんで、自主財源をもち、それが伸びる方向の中に、いろんな措置をするということでございます。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 それでは3期、いろいろとお疲れでした。今度は4期目、そういった形で自主財源の関係で、これから頑張って頂きたいと思います。 最後に、人口増対策。私たち岩屋地域、合河も一緒に、どん詰まりの所が、これから先の限界の集落になります。そういった空き家の所やらあります。そういった中にこれから先、外部から入られる方が、住めるような環境づくりを、これからも考えていって頂きたいと思います。そんなところはどうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 その中で一番大事なことは、外部の人が来ても気持ち良く迎えられる地域、ウェルカム。今、総務課で検討しております無理ない程度ですけども、区のある程度の統合、協力は、今青豊を入れて132ですが、その点もやれる範囲で協力してもらいながら、外から来てもウェルカムというような大きな気持ちをもつ地域に岩屋もなってほしいなと思います。幸い卜仙の郷は10年、前向きに来ました。これ1年でも悪ければ、私は首でここにいないかも分からんけれどね。大体、前向きにいっているなと思いますので、是非、大事にしながらいってほしいと思いますし、外から来る方をウェルカムしてほしいし、いろんな施策についても、大きな気持ちをもって頂きたい、これを要望したいと思います。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 では、しっかりよろしくお願いします。これで私の質問を終わらせて頂きます。 ○副議長 中村勇希君 岡本清靖議員の質問を終わります。 これより関連質問に入ります。関連質問は1人答弁を含め10分以内であります。 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 それでは、尾家啓介議員の水道の関連質問をいたします。まず、水道企業会計で、市長、ちょっと確認したいんですが、今トン当たりの単価は確か188円から10円カットの178円は間違いありませんね。これは将来、伊良原からの受け入れ体制が整ったときには、将来は135円になるという、大体予定ですよね。これはここ確認なんだけども、これも同じく125円ということなんでしょうか、そこをお願いします。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 先程の水道議会で通りました。188円を10円下げて178円。これは今回の豊前市の水道会計にまだ入れておりません。6月か他の町も入れた所もあるし、5月、6月の所もあるということでございます。ご質問の伊良原は、私がなる前から、管が2万トンの管でやっています。ですから、2万トンになれば135円か138円と聞いております。 今度10円下げたから125円ではなくて、やはり135円という予定です。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 午前中、尾家議員が発言されたとおり、恐らく7000万円以上の供給の増額ということになってきます。一般会計からの繰入れですが、明日、榎本議員もやるでしょうけど、一般会計からの繰入れが8000数百万円あったんだけれども、今、上下水道課長、確か7800万円ですか、昨年度はそのくらいだと思いますが、1億5000円から1億6000万円、今から不足ということになってくるわけでございます。 当然、この会計の中で一番ポイントになるのは、供給水量と単価なんですよ。その単価は10円下げたんだけれども、結局、伊良原が入ってきたとき、135円であるならば、将来やっぱり同じようなことで言いたいのは、負担増をどう乗り切っていくかというのが、経営企業の経営手腕と位置付けているわけであります。 そこで、どのように取り組んでいくのか、これは川島課長、何度もお互い議論してまいりましたが、まず1点目、8期拡張工事ですが、これは予算にも今度上がっているけども、大体いつまでやろうとしているのか。どの辺の路線で止めようとするのか。それははっきり言って投資効果の問題から言わせて頂きます。 これは補助事業だからやれという問題じゃないですよね。これは確か市のほうから3分の1ですよね、国が3分の1で企業が3分の1、確かそうでしたね。結局は、市が企業会計と市の一般会計を入れたときは、3分の2の持ち出しになっているんですよ。 それだけの事業をやって、山田地区なんかそうだけど、実際の効果は表れなかったわけですよね、ご承知のように。ただ、今、角田のほうは促進住宅ですか、学校と促進住宅までいきたいということは聞いていますが、この工事が完成すれば、一応、8期拡張工事は見直して、はっきりストップするのかどうか、その辺をお聞かせください。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 午前中申しましたけども、もう1つ漏れたところが、インターから国道までアクセス道路ができます。その付近に農地も農振から両側を外しているようです。だから、そこには工場なり営業所なり、住宅もかなり建つと思いますので、そこら付近は、道路ができ次第、8拡で入れたらどうかなと。先程、議員がおっしゃった雇用促進もそうです。 それと下水道整備区域に最近、開発がものすごく進んでおります。その中に入ってない所は、8拡で延長が短くても入れることができますので、なるべくなら8拡を使って、一般会計から出資金として頂く分については、約2分の1ぐらい交付金で返ってくると思います。うちが3分の1出資する分については交付金はありませんので、なるべくなら8拡を利用して整備していきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 その必要な路線はわかりますが、確認ですが、一応、角田、山田地区に対しては、今の雇用促進で終わりというような解釈でよろしいですか。そのままで結構です。 よろしいですね。 (「はい」の声あり) 今言われたように、確かに住宅振興地域、そのような所には、しっかり投資すべきと考えております。今、課長の答弁の中にもありましたが、やはり下水道の水洗化率と上水というのは、当然、比例しているわけなんですよね。だから今課長が申しました、そこでこれを確認しますが、今、上団なんかできることは、おそらく上水利用の効果が上がると考えられていますが、今、民間あたりが過剰じゃないかというぐらいにアパートがどんどん建ち並んでおります。そのような中でも、中にはボーリングなんかを掘ってやっているような所があるのかどうなのか。今、例えば会社の社宅で言いましたら、日鉄建材とか、九電とか、吉木に東芝がありますね。自前のボーリングなんかで賄っているというような所がありましたら教えて下さい。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 私が承知しているところでは、開発が1件、八屋地区、後はその開発等の申請時には、うちの課まで書類が回ってきます。その時点でお願いなり要望をしておりますが、しましたが、1件が開発で、どうしても井戸をボーリングした所がございます。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 条例の制定というのは難しいですか。ある一定のエリアについては、そこは駄目だというのは如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 ちょっと難しいと思います。汲み上げる量も工場等と違って微量ですので、その件についてはございません。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 分かりました。今、言われた水洗化率が確か60数%だったかな、あんまり記憶にないけど。その辺も踏まえて、いわゆる職員の努力が如何なものかと。何度も何度も足を運んで頂いて、極力、接続率向上に努めることが、上水の使用料のアップにつながると位置付けておりますので、その辺も、課長、おそらく私とあなたとの質問のやり取りは、これが最後になるでしょうが、しっかりそこのところを後に申し伝えていてください。 最後に、市長、先ほど豊前市の今の自前のボーリングは、2000数百トンと言ったけれども、私が上下水道課長から聞いた話は、4000トンぐらいはまだ使えるんではないかということなんですよ。それで当然、伊良原からの供給水量が増えることにより6470トンですよね。言ったら1万トンを超えるわけなんですよ。現行が5000そこそこだから半分ということになるんです。これはもうはっきり難しいことは分かるけれども、何度も市長にお願いしているんですけど、やはり近隣自治体に供給水量を少しでも多く引き取って頂くように、あまり頭を下げたくないというのもあるでしょうが、できましたら京築水道企業団中で、そのような外交的な努力もお願いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 ですから、もう固定してしまったわけではなくて、汗を流しながら、これは20年の歴史がある中で、調整・修正ということを腹を割って話合いしなければならないし、また今度は、京都郡の伊良原にできるんですから、伊良原の周辺の自治体が、一肌、二肌脱いで頂くということも要請しながら、今の話のことになろうかと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 しっかりとお願いします。終わります。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 午前中の尾家、渡邊、両ベテラン議員の関連の質問をいたします。 まず、先程、爪丸議員も言いました渡邊議員の関連の質問からいきたいと思います。 農振除外の件で、いろいろお話をされておりましたが、農振除外につきましては、市が窓口であって、最終的な部分については、県の判断だと思いますが、午前中の議論の中で、来年3月までは、農振除外を受け付けないよということで、渡邊議員が質問したと思いますが、その中で、条件さえ揃えば受け付けるというような話を、話のやりとりでしておりましたので、そこら辺ごろを、どういう条件が揃えば今の時点で受け付けるのか。 そして、農振につきましては、10年に1度の見直しという方針の中でも、昭和63年以降20年経って、今、農振の見直しをするにあたって、豊前市としての農振区域の中で、どういうビジョンをもっているのか。ビジョンをもたないと、農振に指定された土地につきましては、非常に手かせ足かせと、法でがんじがらめとは言いませんが、自分の土地であっても自由に使えないというデメリットもありますので、この見直しの中で豊前市として、どういう農振地域で、今後、農業政策をやっていくのか、そのビジョンをお聞かせください。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 それでは、農用地区域からの除外の要件ということで4点ございますが、まず、第1点につきましては、農用地区域内の土地を利用しなければならない必然的な理由があり、農用地区域以外の土地では、その目的が果たせない場合。次に、2番目に、農用地の集団化、農作業の効率化、その他、農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。 3番目に、農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。 4番目に、土地改良事業等を施行している場合については、事業の工事が完了した翌年度から起算して、8年を経過している土地であること、というような以上、4項目を全部満たす場合については、原則的にうちとしては受付を行ってまいりたいと考えております。 次に、整備計画の変更について、具体的なビジョンはあるかということでありましたが、具体的なビジョンについては、今のところありませんが、今後の計画の見直しの中で、十分、関係機関等と協議してまいりたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 では端的に言います。今の4つの条件を満たさなければ、今の時点では、農振除外の申請は受け付けないということですか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 受け付けても、もし同時に受け付けますと、その1件でも条件に当てはまらないということになれば、他の案件についても同じように、ものすごく時間がかかってくるということで、全体見直し等についても、全体に完了の時期が遅れてくるということですので、できましたら、今の4条件をクリアできるような案件ということで、受け付けてまいりたいと思っておりますので、それにつきましては、事前に農林水産課のほうに、ご相談に来て頂ければと考えております。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 これは返事はいりませんが、農振を見直すにあたりまして、確たるビジョンは、今から話をしますとかいうのは、非常に推進をするにあたり遅れていると思うんですよね。 今、まさにほ場整備が終わろうとして、今は減反化率はなんぼですか、46.数%、ほ場整備が終わって米はつくるな、アクセル踏んでブレーキをかけるようなものなんですよね。その中で農振の区域は減らすなということで、この農振の見直しをやっていると思うんですよね。それならば行政がちゃんとした考え方をもって、その地域の方々にお願いにあたるというのが筋だと思いますので、どうか、そのことを踏まえてお願いします。 もう1つは、尾家議員の関係で、私もやはり伊良原ダムができれば、今3800トンですか、後の2600トン、これは6400数十トンですよね。今、豊前市においては5000から5500、井戸水をあげなくても、今のままで推移したら1000トンほどお金を出して捨てる水が出てくるわけです。先程135円と言いましたから、1000トンになったら13万5000円ですか、これは毎日、毎日、捨てないといけないわけですね。 その中で、課長、尾家議員の答弁の中で、やはり水を使うには、水洗等の啓発をしていくということだったですね。今エリアの中で水洗化率はどのくらいありますか。 大西・永久も含めて、それに水洗化率に関わる推進はどうしていますか。人口を増やすのは非常に無理があると思うんです。後は区域内の水洗化率ですよ。それが一番の手だと思うんですが、そこら辺ごろの行政としての手立てはどうしていますか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 資料はここには持って来てないんですけども、農振については80%ちょっとまで届かないという数字ですけど、公共下水については74ですか、これは毎年、新しい加入区域が増えております。それも含めての74%ですから、私は増えた分だけは、当然80%ぐらいいっている、完備しているような状況だと思います。毎年、増えた分だけ、とにかく7月になれば新しい区域が増えますので70%割りますけれど、3月末になると70数%まで水洗化率を上げていますので、過去の分から含めますと80%はいっているんではないかなと思います。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 その水洗化率は加入率のことでしょ。要するに加入率と水洗化率は違うでしょ。 負担金を払って加入するわけですよね、それプラス水洗化率は、どれだけの件数を引き込んでいるかですよね。それを私は聞いているんですよ。その水洗化率が70数%もありますか、ないでしょ。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 大体、普及率というのは人口で全部出しております。例えば、アパート等は1箇所で6世帯ぐらい入っております。アパート全部がつながって頂けますと、相当の普及率になろうかと思いますので、マスの数は出しておりませんので、ご理解をお願いします。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 要するに、公共下水道につなぎ込んでいる件数が70数%もいっているわけですか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 それは出しておりません。普及率は全国的に人口割で出しておりますので、それでうちのほうも県・国に報告しております。 ○副議長 中村勇希君 磯永議員。 ○10番 磯永優二君 しかし出るじゃないですか。豊前市で公共マスをいくつつくって、エリアの中でどれだけ加入して、どれだけ水洗化率があるかというのは出るでしょうが。だから、その加入の努力はどういうふうにしていますかと聞いたんですが、これはもう時間が無くなりましたので、次の委員会でもしてください。 市長、やっぱり水問題は非常に大事だと思います。有り余る確保は必ず必要です。 しかし水の問題というのは、先程言ったように、今のままなら1000トンほど、買った水をわざわざ捨てなできんわけですね。まだ平成29年までかなり時間があります。 今、相手もおりませんので、必ずこの問題については真剣に考えてください。以上です。 ○副議長 中村勇希君 他に。渡邊一議員。 ○11番 渡邊 一君 私も同じく尾家啓介議員の伊良原ダムの件について、お伺いします。 私も前にも話したことがあると思うんですけども、伊良原ダムの水道企業団の理事長は、豊前市長釜井健介ですね、現在は。結局、将来のために水がめが大変大切だと、これは誰も思うんですね。しかし今生きている、今、暮らしている人たちに、その荷が余りにも大き過ぎたら負担しきれないというのが、今の話を聞いてみても、そのとおりだと思います。 それで不幸中の幸いというか、築城基地があるんですよ。その築城基地の交付金なり、そういう基地対策を利用できませんかということを、私は話したことがあると思うんですが、それについて水道企業団なり、築城基地、県なりと話をしたことがありますか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 おそらく渡邊議員が言われているのは、米軍が来たと、いろいろ迷惑をかけていると。それに当たって、今、関連自治体の中で行橋、築城、椎田だけが近隣で、あと我々の地域は衛星都市のような状況で直接に話はないので、そうじゃなくて、近隣の自治体、水道企業は入っている所に、基地のいろいろな関係の措置が、補助等が及ぶようなことができないかということだろうかと思いますが、そういうことでしょ。 (「そうです。」の声あり) 今のところは、それはありません。苅田は基地地域に入っておりません。後は全部入っています。ただ論議の中でもゼロということではなくて、筑豊地域は産炭地の関係の絡みもあるんですよ。京築地域は何の絡みがあるかと言いましたら、県はアメニティ構想等のいろんな動きがあるし、補助も増えているんですが、基地の関係は、1500戸ぐらい企業団の水を飲んでいます。特に、旧築城町は水が足りない、新吉富村も足りないというところなんですよ。その話はしたことがありませんけれども、今からだと思います。 ○副議長 中村勇希君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 ちゃんと認識していらっしゃいますよね。行橋にしても京都郡にしても築上郡にしても、基地としては無視できない地域だと。だから基地交付金もいっているでしょうし、いろいろ話し合いをせなならんところですから、何故それと話を早くせんですか。たまたま今防衛政務官という役職は、ここの出身の代議士がおるんですよ。話したことがありますか、彼と、水道に交付金がいくかどうかということについて。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 その件は、まだ話したことはありません。 ○副議長 中村勇希君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 先程、尾家議員がやかましく言いましたけれども、やかましく言うだけでは解決にならんし、どっかから金をつくらなしょうがないんだから、県とも打ち合わせしながら、何か知恵を出してくれと言っていましたよね。だから行橋の市長とでも、今度、行橋に渡そうかという話も聞いています企業団をね。ですから真剣に話してくださいよ。 真剣に話して、そういうルートを全部使わなきゃ。産炭地振興に交付金が出ていたんだから水道事業に。同じように私は出らんわけはないと思うんですけど、工夫と人脈ですよ。やる気はあるんですか、あんた。全然、今まで誰とも話してない。これ何遍か言ったはずですよ、ここで。真剣に水道の問題を考えてくださいよ。 市民のために、これから10年先、20年先、工業地帯をここにつくるために、どうしても伊良原ダムというのは必要なんでしょ。答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 大きな声を出してもどうにもなりません。それを前提のもとに、今の件は常識的には、なかなかそれは難しい面があると思いますが、これからどうするかと。ダムもできますので、それを含めて、では給水の関係はどうかとかいうことで、話をしてみようと思います。 ○副議長 中村勇希君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 難しいのは承知の上なんですよ。まず、行橋の市長やら、みやこの町長やらと話をして、そして1つにして、そしてぶつからな。幸い今言うように、防衛省の中にも、ちゃんとこの地域のことが分かった人間がおるんだから、そういうのをどんどん使って、この地域のために頑張ってもらいたい。そのために4選するんでしょ。もう一遍出るんでしょう。 はい、頑張ってください。 ○副議長 中村勇希君 他に。榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 鎌田議員と岡本議員の関連質問をさせて頂きます。最初に、建設課長にお尋ねしたいんですけども、市営住宅の入居基準を下げるということは、所得の少ない方が優先的になっていて、際どい人は今後、応募できないということですかね。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 国の基準が4月以降、今まで20万円が15万8000円ということで、応募する方が少なくなるということですね。そういう感じになります。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 結局、共稼ぎの方とか、ちょっと所得の多い方は、市営住宅に入れなくなるんですね。そんな方は、市営住宅に入れないから民間のアパートに入ったり、どこか探さなければいけないんですけども、ますます豊前市の人口は減っていくんじゃないかな。 そこで豊前市として、そういった所得の多い方々に対して、入居の対策とか住宅のそういった対策は、市長、考えておられますか。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 なかなか公営住宅で難しい面がありますので、雇用促進があるでしょ。それは市が買いますので、自由裁量でやっていこうと思います。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 公営住宅法の中に、条例の中にも優良住宅が活用できるようになっているんですよね。そういった雇用促進住宅を、もし買われるんであれば、公営住宅、市営住宅法の中にはっきりと、所得の多い方も入れますと。その部屋はそれなりの部屋を確保してやるという、市長の考え方の住宅政策は必要と思うんですよ。その辺で、やはり市長が音頭を取ってやらないと、担当課ではできない問題だと思うんですよね。その辺、市長、どうですか。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 今120のうち60入っているので後60余っています。皆継続をしたいような気持ちですので、今、議員が言われたようなことを含んで、前向きに行きたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 住宅政策については、よろしくお願いします。 続きまして、先程、市長の答弁から、宇島駅前の汽車が見える、そういったお話もありました。宇島駅は、ご存知のようにタクシーとか、いろんな車がお迎えとか、非常に交通が混雑しているというか、非常に危ないんですね。事故も起こったという話があります。 そのような意味で、宇島駅前、向こうの駐車場の裏側も含めて土地が空いていますよね。総合的に宇島駅前のそういった対策をする気はありませんか、お尋ねいたします。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 駅前の件で、東の方はなかなか伸びるのは厳しいけども、西の方は伸びる可能性があります。ビジネスチャンスを含めましてね。だから言えば空き地もあるし、土地もあるし、商工会議所に通じるところもありますので、今から伸びると思いますので、当然、市としてしなければと思います。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 今の関係は、明日またゆっくりお尋ねします。 それでは、もう1件、岡本議員の関係で、地域の活性化と緊急対策の関係の補助金1億3000万円の関連のことで、お尋ねしたいんですけども、先程、モデルハウスとか、それから古い家の空き家対策というお話が出ましたね。その事業にこの事業を載せることはできないんですか。その点をお尋ねします。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 相本義親君 できないことはないかと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 そうであれば、やはり知恵を出して、人集めのためにやるべきだと思います。 そういう意味で今後考えとってください。明日、そのことをよろしく。以上終わります。 ○副議長 中村勇希君 他に。鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 岡本議員の森林環境と生産性の向上と、尾家議員の水道事業にも関連すると思います。 私の前の川もそうなんですが、昔はドジョウがとれたり、サワガニがとれたり、いろいろな生物がおりましたけれども、今は全くおりません。それで先程、多摩川の家庭排水の件で、いろいろ提案されておりました。この河川保護という形で、豊前市の合併浄化槽等もされていると思いますが、例えば夕張市においては、水道事業によって破綻したと言われておりますし、今ある計画以外で、下水道の工事を課長にお聞きしましたら、あまりしないという話を伺いましたが、間違いないでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和廣君 公共下水は計画区域を決めて、その中で事業認可を取って国の認可を頂いて事業を行っております。計画区域以外は、また何らかの模様が変わったときに、皆さんにお諮りするんであって、今の時点では、計画区域以外はする予定はございません。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 都会では、住宅密集で下水道工事も採算が合うかもわかりませんけれども、豊前市のように1軒、1軒の家が離れている場合は、これは合併浄化槽を用いたほうが私は良いと思います。テレビに出ておりましたけれども、下水道工事を一切止めて合併浄化槽に切り替えた町が出ておりました。4分の1の費用で済むということで、財政が立ち直ったということで出ておりましたけれども、豊前市も、これからはそういった形をとって頂きたいと思います。 例えば、久留米大学の石井教授という方が開発されました合併浄化槽は、大体20ppm以下ぐらいの水を綺麗にして出せば、基準が通るんですけれども、この石井教授は1%未満の1ppm以下ということで、パフォーマンとして飲んだりしています。こういった形で、先程言いました川が生き返るような合併浄化槽を推進していって頂きたい。 国のほうも補助金については拡充されてきております。 それで、豊前市も、今、答弁頂いたように、これからは下水道工事は、密集地帯、今の計画以外は合併浄化槽の導入という形でしていって頂きたいと思います。 昔は、ほ場整備等によって溝が用水路とか、河川が真っ直ぐになって、あらゆる所で水が氾濫しておりますし、川が曲がって昔で言う石をついて、水がそこで吸収されたり、曲がって勢いがゆるくなったりして環境に良いということで、こういったことも良いかということもまちづくりの中で検討して頂いて。 北海道あたりでも昔、曲がった川を直線にして氾濫して、また曲げましたよね。 そういった形で、環境にやさしい豊前市づくりも、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 山崎廣美議員。 ○7番 山崎廣美君 渡邊議員と岡本議員の関連質問で、お伺いしたいと思います。 農林水産課長、農振除外の完了期間、3月31日までかかるのか。それと渡邊議員は、高速の関係で地権者、対象者のことで発言したんだろうと思いますが、その対象者が年内に契約する中で何人ぐらいいるのか、もし分かればね。 それともう1つ、この件について、農業委員会の委員さんは、もう多分、周知徹底はなされているんだろうと思いますが、そこのところをお伺いします。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 高速関係で、今、代替地等の関係が伴われることについて、自分の土地を4条で、これに関しては現在8名。そして農地をもっていない5条関係は10名、全体で18名程度が現時点では、そういう状況にあります。 ○副議長 中村勇希君 農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長 木村泰暢君 この件については、農業委員のほうは、まだ周知、理解は全部してないと思います。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○7番 山崎廣美君 期間、3月31日。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 現在、1月分の案件がまだ残っております。それにつきましては、一応3月31日を最大限の目標にして頑張っていきたいということで考えております。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○7番 山崎廣美君 その目標ですけど、それは多分、来年3月31日までにできますか。何故かというと、できない場合は、1年ストップじゃないで、来年6月の農振もかけられないということなんですよね。お伺いします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 一応、農振につきましては、全体計画の見直しが終わった時点で、随時見直しの分に入っていきたいと考えています。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○7番 山崎廣美君 見直し完了でしょ。だから今3月31日までと言ったじゃないですか。この完了がもし12月で終われば1月から受付はしますか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 早く終われば、その時点でも受付が開始できると思っております。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○7番 山崎廣美君 何故、私がこの質問をしたかというと、渡邊議員も地権者の方が、多分これは土地改良区もありますし開発公社もあります。道路公団もあると思うんですよ。当然、対象者については、今年度で契約する方は、当然、代替地が欲しいわけなんですよ。それで見直しは私は結構だろうと思います。ただ、そういう対象者の方に横の連携を取りながら、安心ができる、そういう交渉ができるような打ち合わせとか、横の連携が取れてないと思う。 今、農業委員が知らない、周知徹底ができていない。これは私はおかしいと思います。 昨年9月にそういうものを打ち出したときに、当然、農業委員会にもかけて、地元の農業委員は農地の管理もしながら指導する立場の人ですよ。それが全く知らないというのはどうかなと。そこを知らないと、やはり住民の方は不安なんですよ。開発公社や県の職員も、そこのアドバイスをしてやるという親切・丁寧な交渉の仕方をしないと、渡邊議員が質問したような意見が出るんですよ。 もう少し考えて頂かないと、当然、立ち退きされる方は代替地が欲しい。新たに建てる方は、今言ったように8年という期間があるんだけれども、あくまでも特例ですよ。 家がかかる方については、この特例が特例でないように、完了後の8年でしょ。実際は9年か10年かかるんですよ。今、角田地区は除外をしながらやっておりますが、今、山田とか黒土、千束はほ場整備後に道が走るんですね。だから当然こういう問題が出てくるから多分質問したんだろうと思います。そういう対応もスムーズにいくように考えるのが、行政の仕事だろうと思います。 それと横の連携がなされていない。そこははっきり、これからやってもらわないと。 それと磯永議員が言ったように、ビジョンというのは、当然、見直しをする前にこういう地区には、こういうものをというものを設定をしながら見直しをやるだろうと思う。 見直しをして、そこにもっていくものではないと私はそう思います。だから、そういうものを、もう少し横の連携を取りながらやっていくんだろうと私は思います。 後、農業委員さんの荒地の関係をお願いでいいですから、毎年、農地パトロールをやっていますよね。やった後でいろいろな協議をやっているだろうと思いますが、パトロールは毎年増えているんですね。条例は条例であるんですが、条例が条例になっていないから余程の指導をしないと、まだ増えますよ、はっきり言って。そこを十分に農業委員会だけでは駄目なんですよ。農林水産課、高速の場合は、建設課も一緒に、3つの課が一体となってやらないと、前向きにいかないんですよ。あっち飛びこっち飛び。 私が農林水産省に行ったら、転作は別、中山間地は別、大豆の事業、麦の事業、全部別々で職員が立ち替わり入り替わりで、こっちはもうパニックで分からないんですよ。 この前、研修に行ったときにね。だからそういうことのないように、私は、もう5年目ですが、横の連携が当初からなっていないというのは指摘しておりますので、やっぱり十分連携を取りながら協議をやって、何でも1つの物事に入る前は協議をやって、緊密な連携をとってください。 それと中山間地事業、課長は3月で無事定年されるんですが、当然、これは引継ぎとして、今、中山間地事業の中でも、特に農地、水、環境保全については、ほ場整備対象地区も地区外も全部対象ですが、地区外については、まず不可能なんですよ。誰がどう言っても、そういうものについては、条件的にね。特にお願いしたいのは、なかなか要綱がいろいろ大変で、緩和をして誰もが取り組みやすいものを、市から県、県から国という要望をされても私はいいだろうと。誰もが地域の皆が取り組めるような条件の中で環境整備ね。 それからいろんな問題で、その地域の村おこし、いろんな活性化に取り組むべきだろうと思っていますので、返答はいりませんので、特にそういうものをお願いしたい。 後、材木の関係です。地元の材木をということで、課長はカキ小屋の開店のときのテーブルは、あれは非常に使い道がいいですよ。私は直接テーブルを3台くらい頼んだんです。 だから、そういういろんな地元の物を使うんであれば、そういうものを宣伝して、多分皆さん、家でバーベキューをすると思うんですよ。1個、2個はいると思いますので、そういうものも、いろんなPRのやり方があるだろうと思います。だからいろんな面を含めた中でやって頂きたい。 それと市長、お願いしますが、市長も3月一杯ですが、また新たになられるだろうと思いますが、特に今の農業問題、自動車産業も厳しんですが、やはり第1次産業の見直し、国もこのように大きく掲げておりますので、その中で、やはり行政が前に立っていかなければ、ただ、担い手、営農組合だけでは前向きにいきません。だからそれを踏まえた中で、やはり1次産業の見直しと力を強く農業振興を、林業にしろ漁業にしろやって頂くことが、豊前市の全体の振興になるだろうと思って、お願いをして質問を終わります。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。 (「なし」の声あり) それでは、本日の一般質問はこれで終了します。 本日の日程は、全て終了いたしました。 これにて散会いたします。お疲れ様でした。 散会 15時23分 |