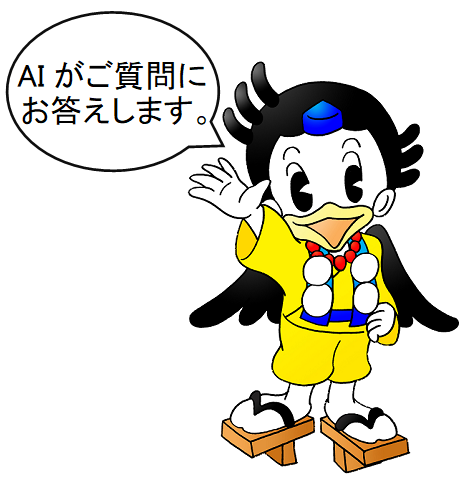議事録(平成20年9月9日)
| 平成20年9月9日(3) 開議 10時00分 ○議長 秋成茂信君 皆さん、おはようございます。 只今の出席議員は17名であります。それでは、これより本日の会議を開きます。 日程事項に入る前に申し上げます。昨日、設置されました決算特別委員会の委員長に、尾家啓介議員、副委員長に尾澤満治議員が決まりましたので、ご報告いたします。 それでは、日程第1 一般質問、2日目を行います。 まず、榎本義憲議員、お願いいたします。 ○4番 榎本義憲君 皆さん、おはようございます。只今より、私の質問をはじめさせて頂きます。 人が元気、まちが輝く豊前から未来への道が開ける、この言葉の素晴らしいことは、豊前市第4次後期基本計画のメインタイトルでございます。このことは市長もよくご存知だと思います。この素晴らしい言葉に反して、豊前市の人口は2万8000人を悲しいかな今年割ろうとしております。ここで何か手を打たなければ、豊前市は大変な状況に陥ると私は考えます。そこで、思い切った提案を市長にして欲しいというふうに思います。 そういった意味を込めまして、私は今回、質問をさせて頂きます。 第1点目は、税源移譲に伴う収税対策についてでございます。国の三位一体改革で、地方交付税や補助金が減ったかわりに、所得税の一部が個人住民税として地方に移りました。 そのことにより、収税対策にどれだけ力を入れるかによって、財源の差が生じ、自治体間で行政サービスの格差が生まれることになります。結果として、住民が住む市町村を選ぶといったような状況になると考えられます。このようなことから、収税対策にどのように力を入れていくかというのが、大事な課題になってくると私は思います。 そのようなことから豊前市は、今後どのような対策をされるのか、お答えをして頂きたいというふうに思います。 2点目は、市民が安心して暮らせるまちづくりについてでございます。 豊前市は、現在、区割りは大字によってなされております。区によっては、大字が入り乱れているために非常にわかりにくくなって、いろんな問題を呼び起こしております。 例えば、救急車を出動要請したときに、通報者が誤ったり間違えたりといったことで、なかなか現場に行き着かない。また、郵便物や宅配便が間違って配達されたり届かなかったり、そのような問題が起こっているというふうに聞いております。この問題を解決するには、新住居表示制度を確立する必要があると思います。市はどのようにお考えでしょうか、お答えください。 3点目について、お尋ねいたします。求菩提山の文化財の有効利用について、お尋ねいたします。求菩提山文化財は、豊前市にとりまして貴重な文化遺産であります。 この貴重な文化遺産の観光のために、豊前市に毎年3万人の方々が訪れていると聞きます。この観光資源を有効に利用することは、豊前市の発展、もしくは村おこしになるというふうに考えます。現在、文化施設の管理や公共施設の管理は、そして、またボランティアの育成、特産品の製造販売等々は、それぞれの団体によって別個に行われております。これを一括管理して行う、市総合サービスNPO法人の設立をされたらどうでしょうか。この目的は、市が指導力を発揮し、組織の強化と、若者が定住する施策の推進を行い、求菩堤山を全国的にPRするきっかけづくりにして欲しいからの願いでございます。 また、今後、求求菩提山の観光資源の活用について、豊前市はどのようにお考えでしょうか、その考え方を教えてください。 4点目として、6月議会で質問いたしました固定資産税の引き下げについて、再度お尋ねいたします。豊前市は、現在、固定資産税率は100分の1.6を徴収しております。 近隣の市町村においては、100分の1.4でございます。そのことは、合併問題での大きな阻害要因になっております。また、市内では、公共下水道の整備地区と整備されない地域との大きな環境サービスの違いがあります。この問題を解消するために、未整備地区について、固定資産税率を100分の1.4とする不均一課税を導入されたらどうでしょうか。その点について、お尋ねします。 以上、壇上からの質問とさせて頂きますが、私が質問したことが分からなければ、どうぞ反問して頂いて結構です。簡潔なる答弁をよろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 榎本議員のご質問の中で、発言通告で漏れている点もありますが、自席からと理解していきたいと思います。1番目の税源移譲につきましては、税務課長。そして、安心して暮らせるまちづくりにつきまして、住居表示等の件は総務課長。そして、他の点もありましたけれども聞かれてないようです。まず、今言ったような形で。求菩提山の文化財関係につきましては、教育課長ということにしていきたいと思います。 私は、壇上からのご答弁は、前回の質問に引き続いてのご質問でございます。 この件につきましては、今、真剣に執行部として検討しております。榎本議員のご指摘の件、ご懸念の件は分かると思いますし、それを踏まえながら、では、どういうことでいこうかという点を、今しているわけでありまして、今の今、この場で地域別に不均一課税すべきではないかというご指摘は承りながら、それも参考にしながら、近いときに方向を出していきたいと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 税務課長。 ○税務課長 仲敷国敏君 榎本議員の税源移譲と収税対策についてのご質問に対して、ご答弁申し上げます。 三位一体改革による国から地方への税源移譲により、平成19年度における現年度個人市民税の調定額が、平成18年度より2億8210万2000円の増となっております。 収入額では、2億7425万1000円、収入率では96.98%となっており、当初、新聞報道等によれば、全国的に徴収率が下がると思われていましたが、市民の皆様のご理解とご協力、また徴収職員の努力により、前年度より微小ではありますが上昇いたしております。 現在、収税対策係の体制は、係長兼務1名、係員3名、嘱託員2名、計6名で収納業務に取り組んでいるところです。平成19年度決算状況からみると、一般会計の歳入、約112億円のうち自主財源である市税が、約3分の1を占めております。この財源を維持・確保、更に、収税率増に向けた取り組み方法につきましては、次のような取り組みが必要と考えております。 福岡県では、住民税等の税収率向上に向けて、様々な取り組みを実施しております。 豊前市においても、この取り組みを取り入れながら、職員の徴収実務の向上に向けて、福岡県特別機動班職員の派遣を依頼し、合同の直接徴収、実務フォローアップ研修、または県の徴収事務研修生の派遣等を検討し、係内研修を行い、職員の徴収技術の向上に向けて努力してまいりたいと考えております。また、税務職員一体となって電話作戦、または、小学生や中学生に対し、納税意識の高揚について、税の教室等の開催が考えられ実施に向けて努力したいと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 おはようございます。榎本議員のご質問の中で、市民が安心して暮らせるまちづくりについて、中でも、住居表示の現状と課題について、ご指導頂いていますので、その点についての答弁をしたいと思います。 まず、この関係で19年9月議会に吉永議員が、そして、12月議会に尾家議員のご質問を頂いて、その中でいろんなご提言を頂いております。この関係で行政区の見直し、再編を速やかにやるべきではないかというご指導を頂いております。そのことを受けまして区長役員会と意見交換をいたしましたが、基本的に反対をする方は居ないわけですが、具体的になりますと、地域の伝統行事や、講組の関係とか、いろんな問題があるのではないかということで、かなり厳しいご意見を頂戴しております。 今日、そういったご指導や、ご指摘を頂戴いたしまして、現在、内部協議を事務方で進めております。失礼しました。榎本議員もおっしゃるとおりに、緊急車両の到達時間の問題や、郵便物の誤配の問題、豊前市に訪ねてきた新しく、はじめて来られた方々については分かりにくい等、今日課題があることは、私どもも十分理解しておりまして、現状の住居表示はかなり不便で、改善を図らなければということについては、私も大賛成でありますし、行政としても効率よい行政運営をするために、この問題は解決しなければならない問題であると考えているところであります。 全市で一斉にということになりますと、総論賛成、各論反対でなかなかうまくいきませんので、具体的にどのような形で手をつけていくのかについて、いろんなご意見も頂戴していきたいとは考えていますが、まず、海岸部のできる所から手をつけていくというのも大事ではないかと考えておりますので、議員の皆さんのご意見も頂きながら、区長会や地域住民の皆さんに、この種の問題についてのご理解とご協力を頂く方向を、具体的に足を踏み出していきたいと。具体的には、全市一斉に無理ならば、できる所からでも、この種の解決のために動いていきたいと考えていますので、今後ともご指導をよろしくお願い申し上げます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 教育課長。 ○教育課長 寺光正博君 ご質問の求菩提山文化財と関連文化財の有効利用により、人材育成について答弁いたします。その中で、最初に質問されました市総合サービス型と、NPO法人の育成についてですが、豊前市では、平成15年3月に、史跡求菩提山整備基本計画報告書を作成しております。その中で史跡の管理運営計画では、史跡管理のため、地元住民の協力は不可欠であり、住民や利用者が管理に参加できる体制づくりが必要である、というふうに書かれております。また、将来ビジターセンターの建設を予定しておりまして、求菩提山の歴史や自然について学べる啓発・人材育成の拠点づくりとするというふうになっております。 平成17年度から進めております求菩提地区の文化的景観保存管理計画策定の中で、文化的景観の構成要素であります棚田の保全をする手段として、地元住民や有志が参加するNPO法人等の設立も視野に入れ、現在、地元懇談会・説明会を開きながら検討しているところであります。 それから、2点目のボランティア育成、案内板の点検・整備についてでありますが、市内の文化財保護に関わる民間団体としては、自然と文化財を守る会と、史跡ガイドボランティアの会があります。自然と文化財を守る会の主な活動は、年2回、求菩提山の清掃登山を実施したり、文化講演会の企画、また、4月のシャクナゲ祭りに協賛して、里山コンサートの企画などを行っております。 一方、史跡ガイドボランティアの会の主な活動は、史跡求菩提山のほか蔵春園・千手観音・如法寺等の案内を行ったり、求菩提資料館の運営に協力したりしております。こうしたボランティア団体との協働を行うことで、その育成を図りたいと考えております。 それで、求菩堤山の案内板については、平成13年の国史跡指定以前に設置されたものが多いわけですが、平成16年度から国の補助を受けて順次整備を進めております。 具体的には、史跡見学の主要ルートを中心に、既設のサインの板面張替え・新設等を行っております。その他の文化財の案内板についても、できるだけ頻繁に点検して汚れ・破損を早期に見つけて対処するようにしております。 それから、豊前市の主な観光資源でもありますので、広報についても、市バスとPRについて、是非利用したいと考えております。そういう意味で、文化財と活用の広報についてできるだけ多くの機会を利用して行っていきます。 最後に、議員から発言のありました観光資源の活用については、まちづくり課の担当になろうかと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 それでは、順次、お尋ねしたいと思います。固定資産税率の引き下げについては、市長から今後、検討していくという回答でありますので、一生懸命努力して頂いて、豊前市が他の町村とより早く合併ができ、また、市民間にも不満が残らないようによろしくお願いいたします。 では、税源移譲の関係について、お尋ねします。担当課長から収税の取り組み等のお話がありました。より具体的に収税の取り組み方についての答弁がほしいと私は思います。 特に、個人住民税が多くなったわけですから、その収税は、非常に大事になってくると思います。現在、個人住民税は、殆どの会社では、特別徴収が行われていると思いますが、個人経営の会社や小さい商店によっては、普通徴収が行われているのじゃないかなと思います。基本的には、事業所は、特別徴収を行うのが地方税法で義務付けられていると思います。そういったことから、個人経営者に市長自ら先頭に立って、各事業所を回って、特別徴収をして頂けませんか、というお願いをしたらどうでしょうか、市長。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今日の新聞を見ましたら、行橋市・みやこ町が猛烈に言い方は悪いけれども、滞納している所を徴収しているようです。これは、ご提案の中で、先ほどの固定資産税率を下げた場合、必ず負担が増えるわけで、その財源を求めなければなりませんので、その財源のための努力をしようとしても、私が先頭に立っていかなければならんと思っておるところであります。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 まさに、固定資産税率を下げれば財源が減るわけでございます。そういった意味で、徴収率を上げるというのは唯一の方法じゃないかと思うんです。それで各事業所に、税務課長、市長の日程表を組まれて、現在、普通徴収になっている所は、やはり特別徴収のお願いに回る。そして収税率を上げることが一番大事だと思うんです。 何故そのようなことを言うかといいますと、例えば、今、外国から働きに来ている方が豊前にはたくさんいらっしゃると思います。その方が途中でやめていなくなったときに、税金は当然、滞納になっていく。或いは、特別徴収でないために、普通徴収だと普通納付ですから、自ら払わなくてはいけないんです。特別徴収であれば、給与から引かれるから自ずと徴収率は上がると思うんです。その辺、日程を組まれて市長を連れて行くという考え方は税務課長、どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 税務課長、答弁。 ○税務課長 仲敷国敏君 その件につきましても、いろいろ検討いたしまして、特別徴収については、企業にお願いしてまいりたいと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 課長ね。やはり市長にぴしっと言って、やはり課長が行って頼むより、市長と副市長が一緒に行って頼めば、トップの事業者は変わると思うんですね。そういう点、特によろしくお願いします。 それに付帯して、豊前市で公共事業を行う方々が、普通徴収の方もいらっしゃると思うんです。その方について、特別徴収を義務としたらどうでしょうか。 その点は財政になりますかね。よろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 法人でない個人の業者もいらっしゃると思います。そういうものについては、今後、検討してみたいと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非そのようになるように、よろしくお願いいたします。 続きまして、関係のない市民の方々が、関係ないといったら失礼ですけれども、何も携わってない方々の滞納者があらわれていると思うんです。そういった人達の対応として、例えば、市のいろんな補助金を交付したり、或いは、市から仕事を回すときに参加できる、或いは、補助金を交付する、そういったものに制限を加えるという方法もあると思うんですが、その点は如何でしょうか。財務課長、お願いします。 ○議長 秋成茂信君 財務課長、答弁。 ○財務課長 池田直明君 現在もそういう形で、一部補助金の制限等かけている部分もあります。ただ、全体でどういうふうな制限額まで可能かどうか、十分慎重に検討していかなければいけないというふうに考えておりますので、その件については、内部で再度検討してみたいと思います。 以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 市税だけじゃなくて保育料とか、いろんな問題があると思うんです。ただ、子供さんを預けているといういろんな問題があるので、一概に切ってしまうというのは難しいかもわかりませんが、そのような人の対策として、やはり厳しい態度で臨まなければ滞納は増えていくと思うんです。検討するということじゃなくて、やはり市からいくらかの補助金があるときには、初めからカットさせて頂きますよと。その分は市の方で頂きますよ、という念書を頂くぐらいの気持で取り組まないと、滞納は減らないと思いますが、財務課長、その辺はどうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 財務課長、答弁。 ○財務課長 池田直明君 現在もそういう形でやっている部分もあります。ただ、補助金によっては、そういうものにそぐわないものもあろうかと思いますので、十分そこは検討して、またお答えしたいと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非お願いします。というのが、やはり真面目に納税している方にとりましては、そういった税を払ってない人がはっきり分かりましたら、皆さん納税しなくなると思うんです。 払わなくてよければ私も払いませんよ、というような状況になると思いますので、強い態度で臨んでほしいと思います。ひとつよろしくお願いします。 税の関係でNPO法人とか、いろんな団体で収益を上げている団体があると思うんです。 そのような団体をはっきり調べて、今後、徴収を取るべき団体はぴしっと取る、そのような態度を税務課長、示して頂きたいのですが、その点どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 税務課長。 ○税務課長 仲敷国敏君 NPO法人につきましては、今、調査いたしておりまして、原則的にはNPO法人は非課税になっていますが、公益事業を行った場合は対象になるということになっております。 一応、NPO法人の決算等は、福岡県のNPOの推進協議会等で管轄しておりますので、そちらのほうの決算ものぞいてみたいと思います。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員 ○4番 榎本義憲君 NPO法人を隠れ蓑にして、私から言わせれば収益をごまかしているような団体もあるのではないかなと。調べてみないと分かりませんが、よく新聞報道でされています。 やはり、そういったものに対して毅然とした態度で、例え非営利団体と思われても、よく調査されて徴収されるのも大事なことではないかと思います。そこら辺をしないと、やはり税収は上がらないと思うので、是非よろしくお願いいたします。 それから、徴収というのは、1つの納税者から不満を聴く大事なシステムなんですね。 行政に対する不満とか、いろんな不満をおそらく徴収者に言ってくると思うんです。 そのようなものを十分意見を聴いて、市政に反映させるといった取り組みをされることが、豊前市の発展につながっていくのではないかな。滞納する人には何らかの原因があるんです。言い方は失礼ですけれども、お金があっても払わない。そこには行政に対する不満があって払わない。そういった声をよく聴くというのも、1つの豊前市を発展させる材料と思うんですが、市長、その辺で徴収係にそういった意見を聴くという係というか、専門官みたいのを配置するのは、どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 専門官というか、徴収を本気でしようと思ったら、担当は意見を聴きながら、ただ、聴きっぱなしでなく点検討等も要るだろうと思います。そこはやり方の問題、特にこのマスタープランの件で、全職員と膝詰めの勉強会をいたしましたので、よかったなと思っております。後は実務の中で、特に、税務の関係は大変だろうと思うし、私も直接チームと一員として話してみていきたいなと。そして点検していきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非頑張って頂きたいと思います。そこで徴収係と言えば、やはりつらい立場にあると思うんです。職員は、市民の皆さん方に徴収に行くわけですから、係員は、それなりの役職につかしてあげる。そして、また、そこの部署に行ったら、それなりのポジションに引き上げてやる。職員のやる気を起こさせるために、全員役職にしていくという制度は市長、どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 そこまでは、ちょっとあれなんで、役職、何が役職なのかと。係長以上は役職なのか、課長なのか、そういう制度上の問題、人事配置の問題等もありますので、今の指摘は検討してみましょう。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 人事に関することですから、深く言いませんけれども、やはり職員がやる気、行きたくないなという職場づくりじゃなくて、あそこに行けば、ちょっぴり頑張ったらいいことがあるのかなということも、私は大事じゃないかと思うんで、思い切った取り組みを是非お願いいたします。 次に、安心して暮らせるまちづくりについて、お尋ねいたします。 今、総務課長から区域を割ってということで、私に言わせればモデル地域かなと思うんです。区長とよくお話して実行していく。昨年度、尾家議員、吉永議員が、それぞれ質問されて、そのまま1年間経っているということは、悪い言い方をすれば放置しているのじゃないかな。努力はされているでしょうけれども、結果的にそういうことになっているのじゃないかなと思います。だから区長と年何回かお話もあるでしょうし、時々区長会もあるので、そちらのほうに行かれて、具体的にモデル地区をつくって、多少お金がかかるか分かりませんが、そういった取り組みは総務課長、どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 足跡がぬるいのは、私も反省しているところでございます。ただ区長の役員会もありますので、これはかなり頻繁に行なわれていますので、この中では、かなり突っ込んだ意見交換ができると思います。榎本議員ご指導のモデル地区ができれば、なおいいですし、非常に入り組んでおります行政区も、私も職員しておりまして分かります。そういう点を具体的に区長会に提言しまして、できる所、或いは、行政指導で消極的であればお願いしていくという姿勢も必要であろう。このまま意見を聴くだけでは、なかなか総論賛成・各論反対になりますので、もう少し行政指導でというのが議員の提言でしょうから、そういう点で怒られるのを覚悟で、区長会に切り込んでいきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非、早めに実現するようによろしくお願いいたします。 安心するまちづくりの関係で、壇上からの質問ではずしておりましたが、昨日の市長の答弁の中で、防災無線等の話については、来年度以降実施するという一定の評価できるご回答を頂いておりますので、予算もかかりますけれども、是非、実現するように頑張って頂きたいと思います。 それに関連しまして、生活困窮者の関係で昨年度こういった事件がありました。 家族3名の方が車の中、路上生活で半年以上した。市の市営住宅の申し込みをしたけれども、空きもない抽選も当らなかった。死のうかなとそこまで考えた方がいらっしゃいます。 ご相談にお見えになりました。なんとかならないのかな、議員なんとかならないですかというお話も聞きました。やはり行政というのは、厳しくするだけが1つの考え方ではないと思います。困ったときに臨機応変に対応してあげるのも、1つの方法ではないかなと思います。例えば、水害や火災にあったとき、そういった条例じゃなくて、ある程度、市長の裁量で市営住宅に入れる。住む所がなくて困ったら、一時的に市営住宅に入れてあげる、そういったことが、やはり暖かい行政ではないか。四角にはまったような行政をやるだけが、豊前市をよくするんじゃないというふうに思いますが、その点について建設課長どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 建設課長、答弁。 ○建設課長 加藤久幸君 ご質問の中の生活困窮者ということは、住宅困窮者と理解させて頂きます。現実に議員が言われるような住宅困窮、公営住宅としての位置付けは、一応考えられないわけでありますが、特に、ご質問の中にあった住宅に非常に困窮して、先ほどありましたように死のうかということもあります。そういう場合に、市として一時的に、応急的に1、2戸住宅についてストックして、市の財政を考えましたところ、市の財政状況を含めて1つの案ではありますが、公営住宅法の耐用年数が切れた公営住宅の活用方法について、検討してみることも必要であると考えております。 それにつきましては、今後、上部機関・関係機関とも協議しなくてはいけませんので、努力していきたいと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 今、建設課長がご答弁頂きました。やはり市長の裁量になっている分があると思うんですね。やはり本当に困ったら暖かい気持で、建設課長、条例を最大限生かしてやれという気持で、市長、一言お願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 政治は、いろいろ言っても都合のいい人たちだけのためではありませんので、厳しく、そして急にいろいろ起こると思いますから、今言われた件も当然、行政が手を差し伸べて一緒に歩いていくという姿勢でいきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 市長、是非よろしくお願いいたします。建設課長、市長のそういった答弁ですので、優しい対応をよろしくお願いいたします。 続きまして、求菩提山の観光資源の活用について、お尋ねいたします。 壇上から1点、今後の求菩提山の活用について質問しておりましたが、答弁を頂いておりませんので、まず、その答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長 秋成茂信君 まちづくり課長、答弁。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 榎本議員の言われました求菩提山の観光資源の活用ですが、現在、県と連絡を取りながら、うちのキャンプ場の整備なんですが、キャンプ場のキャンプサイトの改築、バンガローの一部建替えや障害者用の対応として、バンガローの横に駐車場を整備することを県に今要請しているころです。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 整備関係の話ですが、市長、これは基本的に約3万人の観光客が毎年訪れるわけですね。豊前市民もいるでしょう。やはり、それでなくても岩屋・合河地区は過疎化になって、住む人もいなくなっていく、病院もなくなっていく、郵便局もなくなっていく、厳しい状況にあります。ここで何らかの手を打たなければ、益々過疎化になっていく、限界集落になっていくと思うんです。やはり求菩提というのは、大事な観光資源ですから、市が先頭に立ってやらないと、どうしてもよくならないと思います。 誰かに任していたんでは、何もならない。だから大胆に、さっき私は言いましたが、市の総合サービス型NPO法人、市が先頭に立って職員を派遣してでも、当分の間、職員を派遣して素晴らしいまちづくりを行っていく。軌道に乗ったら、それを民間に任せるという指導型ですけれども、市長、どうでしょうか、その辺。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 先日、寒田・鳥井畑線の会合をもちまして、昔よく知って親戚も多い所でありますが、50数名集まりました。しかも、きちっと会費を出して集まりまして、これからいろんな関係で協力していこうと。特に、そこには築上の町長もおられまして、極楽寺のほうからも道をつくりたいと言ってました。これはうちの合河・岩屋地区だけでなく、どこも詰の所は非常に厳しいことだろうと思います。トンネルができればいいなということもあるけれども、ただ、豊前市の求菩提の場合はつめで、しかし、卜仙・求菩提資料館・キャンプ場、かなりの人が来ますので、また、犀川や田川のほうにも可能性も出てきたので、今言われた点、ただ住むだけのNPOだけじゃなくて、1年中、人の出入りできるような知恵ですね。そういうことでの方向なのだろうと思っております。 幸いなことに求菩提資料館も、県も含みながら年中無休でありますし、卜仙の郷も一応指定管理者になっていますので、加えて公共的な施設がなくならないように頑張っていかなければならないので、今言った点、どのよう形にするのか、主体はどうなるのか、泥をかぶるぐらいの気持と運営をどうするか、ということになろうかと思っております。 今、ご指摘を受けながら検討してみたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 検討は是非お願いしますけれども、この総合型サービスNPO法人の設立というのは、行政が当分の間、先頭に立ってやらないと、人任せではうまくいかないのではないかな。やはり、そこに若者を定着させようと思ったら、それなりの施策をし、お金をつぎ込まなくてはできないと思います。そういった宣伝も1団体が行っていたんでは、なかなか実にならない。皆まとまって一緒にやれば大きな力になると思うんです。 現在、求菩提山の資料館の説明等、数人の方がやっているようですけれども、あくまでも来た人の関係の対応であると思います。或いは、ボランティア活動についても、来た人に求菩提資料館に電話をすればしてくれるのか、それとも、卜仙の郷に連絡すればしてくれるのか分かりませんけれども、そういうことじゃなくて、例えば、求菩提の公共施設の中にNPO団体をつくって、そこに連絡すればすべてOK、何人でも対応できますよと。 ボランティアの説明ガイド、観光ガイドの方々をお金がかかりますが、時々研修会等行って文化財の説明が誰でもできる、そういった体制づくりも必要だと思うんです。 行政がどう関わっていくかということが、基本になっていくわけですから、他人任せでは豊前市は市長よくならんと思うんです。検討するのは分かります。もう少し踏み込んで考えて頂きたいと思いますが、市長、如何でしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今のキャンプ場等は、商工会議所の観光文化協会がやっています。あそこで総会をし、ただ、ずっと常駐していない面が、キャンプ場の土地ということです。やはりそうなると地元の方、求菩提は岩屋の方ですが、中心になろうかなと思っております。 今の今、ご質問を受けまして、じゃ、こうしてこうやろうと出ませんけれども、少なくとも反面教師として、観光文化協会がありますので、それでは伸びがないだろうと思いますので、では、それに代わり、それを包含するような地元密着の組織をどうするのか、市が何処まで絡んでどうするのか、ということになるのではなかろうかと思っております。 今、言われた件につきまして、よく検討してみたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 よろしくお願いします。これは参考までですけれども、そういった団体をつくられて、例えば、郵便局にかわるコンビニ的な金融機関を、公共施設の中に置くというのは非常に抵抗があると思いますが、これはNPOに任せて大胆に行う、或いは、都会の方々が、今田舎に来るのが流行ですので、そのような方々に宣伝して来て頂く、宿泊して頂くと、いろんなことで交流が深まると思うんです。そういった取り組みを進めていかなければ前に行かないと思いますので、是非、考えて頂きたいと思います。 また、小さい質問を何点かさせて頂きます。現在、求菩提のほうまで市バスが何便か往復されていますね。ところがその市バスには、求菩提まで行く観光施設がいろいろあるわけですが、何もガイドがない。春秋たくさんの方が犬ヶ岳・求菩提に訪れるわけですが、例えば、次は千手観音前です、といわれの説明をする、次は、迦陵頻加の前ですとか、如法寺前ですと、昔から、どうしてこの施設ができたかという説明をするのも、観光の1つの手だと思いますが、その辺の検討は総務課長、どうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 バスの場合、停留所の案内と料金に表示しています。すべてのバスが最新式の放送ができる施設をもっているわけではないんです。15人乗りのバスにはございません。 そういった件については、コストがかかりますので、正直申しまして独立採算になっていますので、その問題をどのようにしていくのかという問題があります。金がある程度、担保できれば、それは技術的には難しい内容ではなかろうと思いますので、専門業者に相談してみて、コスト的にどのくらいかかるのかということも検討して、具体化に向けて市バスが有効的な観光案内になればいいと思いますので、やってみたいと思います。 また、1つには、臨時便はシャクナゲの時期とか、導入していることについては、お答えしておきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 岩屋線というのは、昨日の質問で黒字になっているとお聞きしております。そういった重要な路線で沢山の方がいられますので、その辺を考えてされたらいいんじゃないかなと。観光地に行けば何処もやっています。この文化施設は何なのか、豊前市民でも知らない方はいらっしゃると思うんです。そういった説明をすれば、通学する子ども達にも、この地域の文化のいわれなどの説明ができて、歴史の勉強にもなると思うんです。そのようなことから是非、検討するのではなくて取り組みをして頂きたいと思います。 続きまして、タクシーの運転手、その他の方々に対して、ボランティア活動の要請をして頂いて、タクシーで求菩提山に行く方もいらっしゃると思うんです。そういった方々を集めて、ボランティア活動の講師と言いますか、そういった説明をする考えはどうでしょうか。まちづくり課でしょうか。よろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 まちづくり課長、答弁。 ○まちづくり課長 福丸和弘君 現在はそういう取り組みはございませんが、今後、検討していきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非やって頂きたい。ガイドの育成は大事なんです。やはりタクシーに乗ってガイドして頂ければ、ここにも行って、あそこにも行ってと、言い方は悪いですけれども、余分な収入になってくるのではないかなと。1日ガイドをすればタクシーに乗ればいくらですよと料金設定して、良心的に表示しておいて、求菩提山まで行く運賃は1日いくらです、と宇島駅前にガイド料は要りませんとか、そういったことも1つのPRになると思うんですね。そのような活動というのは、行政がより積極的にすることが大事だと思います。 市長、その辺はどうでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 先般、横手市に行きましたら、今言われたように駅前に待っているんですよ。 市のNPOだろうと思います。連れて行って全部説明してくれました。地域によっては、今言われたのを、ものすごく積極的にしながら観光するということをしております。 個人的になって大変恐縮ですけれども、4月30日に同級会を求菩提の卜仙の郷でしましたときに、行き帰り同級生の東京から来た人に、これは岩洞窟ですよとか、蔵春園ですよと説明したら、ものすごく喜んだんですよ。豊前市出身でも知らなかったということで、最後に、大富神社さんの感応楽まで見ましたけれど、今言われたことは、少し勉強とレッスンがいると思いますが、そう金はかからないで意欲を持ってやれるいい提案ではなかろうかと私も思っております。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非、実現して頂きたいと思います。それから、現在、岩屋地区も大分休耕田が多くなっていると思うんです。そういった問題を解消するために、あそこは棚田がかなり有名ですが、その地域の休耕田になってる農地を、もっと有効に利用して、都会の方々やいろんな方々に呼びかけて利用して頂き、そこで特産品をつくってそれを販売する、そういったシステムづくりも非常に重要ではないかと思います。 最初から言っているように、今こういった市の指導型のNPO法人を立ち上げてやらなければ、ばらばらではなかなかうまくいかない。市長が言われるように部分的には、いいな、いいなということで実施したとしても、これは人が定着する材料にならないと思うんです。やはり是非、再度、NPO法人の立ち上げを真剣に考えて頂きたい。 市長、その辺の決意表明を是非して頂きたいので、考え方を再度お願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 ご質問している榎本議員も、1歩から、ひとつ加わって頂ければと思っております。 私の決意表明の前に。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非、そのメンバーに入れて頂きたいと思いますが、NPO法人の役員となりますと問題がありますので、一参加者として積極的に参加させて頂きたいと思いますので、市長からできたよという返事を、いち早くお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。 求菩提山の最後の質問させて頂きますが、求菩提山は、現在、台風等の影響でかなり荒地になっています。見るからちょっと悲惨な感じがするんです。そういったものの解消のために、土地を買うことは非常に問題があるかも分かりませんが、国の文化財の指定になったので、だんだん購入ができるという噂も聞いています。手がつけられる所から購入されて、針葉樹から落葉樹にかえて秋には非常にもみじ、かえで等が美しいよと景観づくりをされたらどうか。或いは、河川敷の部分に、そういった広葉樹を植えて、散策道路をつくられてはどうかという、NPOとは別に行政として、そういう取り組みをしたらどうかということをお聞きしたいと思います。教育委員会でしょうか、よろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 教育課長。 ○教育課長 寺光正博君 求菩提山の台風等の跡地については、榎本議員が言われるように、できるだけ景観的に広葉樹等を植えるように指導しております。それから、森林組合と話し合ってそういうように進めております。それから国が買い上げた場合等についても、そういう方向で進めるようにしております。また河川等の景観ですが、私も地元ですので、そういう方向で機会あるごとに皆さんに話はしております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 是非、求菩提山の景観を守るために、土地はなかなか人が手離なさないと思いますが、是非、美しい景観づくりのために努力して欲しいと思います。 1つ忘れていましたので、求菩提山の文化財の説明、或いは管理人等、嘱託職員が2年ぐらいで交代されていますかね。その辺よく分かりませんが、文化財の説明というのは長い経験と、いろんなキャリアが必要だと思うんですね。その辺で、2年交代で職員を替えるというのは人事に関係するので、市長が考えることでしょうけれども、豊前市の求菩提を宣伝するために職員は少し長めに雇用する。そして、その方々を将来、豊前市のそういった文化施設の案内役になっていくという意味での雇用を考えて頂いたらどうでしょうか。 人事ですけれども、市長、その点よろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 普通一般の嘱託は2年ですけれども、今、言われた文化財関係は5年と、少し長めにしております。今、言われたことも相当専門的になる面がありますし、現実は、そういう状況ですが、もう少しきちっと整理・整頓していきたいと思っております。 ○議長 秋成茂信君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 よろしくお願いします。いろいろ言いましたけれども、基本的には求菩提山をどうにかしたいといった気持であります。そのことは豊前市の産業の発展になると思っています。 私も市長から言われましたので、是非そういった団体に呼んで頂いて、一緒に手をとって豊前市をよくしようじゃないですか。共に頑張りましょう。以上、終わります。 ○議長 秋成茂信君 榎本義憲議員の質問を終わります。 次に、尾家啓介議員。 ○15番 尾家啓介君 質問をさせて頂きます。まず、第1番目、豊前市財政について、団塊の世代と呼ばれ戦後の成長期を支えた人たちが、60歳の定年退職の日を迎え、第二の人生へと足を踏み出しています。豊前市役所に勤務した職員も、多くの方が既に退職して市役所を後にしています。市当局も、補充の職員採用をぎりぎりにしぼっています。最大22億円あった人件費が、18億円を切るところまで計算ができるようになりました。豊前市財政に好ましい影響を与え、経常収支比率も好転の兆しを見せています。しかし油断は禁物です。 今後の市財政は、高齢者関係の医療保険・下水道会計・京築地区水道企業団を含む水道会計などへの一般会計よりの繰出しを避けることができません。多少の余裕ができても、経費削減に努め、市債の発行を最小限にして、公債費比率の引き下げを財政運営の第1に据えてきたと思います。豊前市財政運営についての考え方を、事務方トップである副市長の答弁を求めます。 次に、限界集落と高齢者対策について、戦後の農地改革で農地が細分化され、耕作者の所有となりましたが、国の高度成長期とともに、若い人が働き場所を求めて市外へ出て行きました。残った人たちも高齢になっています。市内には家屋敷・田畑・山林などの資産はあるが、収入の少ない老人が増えています。私の居住する隣組も限界集落です。 そこに下水道が布設される計画です。どの家もかつては籾を干した農作業場・朝晩の野菜をつくる小さい畑などを屋敷内に持っています。下水道の加入金は、住宅密集地に比べ2倍から3倍の金額になります。老人の1人暮らしでは、加入したくても加入できないと困っています。その他、収入が余りないのに、資産にかかる固定資産税、国民健康保険料の3割など、負担が社会的弱者に過重にかかっていると思います。収入の少ない高齢者に限って、免除措置を考える必要があると思います。答弁を求めます。 次に、郵政民営化により、山間地の簡易郵便局が、各地で経営が成り立たず閉鎖が相次いでいます。担当官庁は事態を憂慮していると新聞で報道されました。 豊前市の岩屋地区で、唯一住民のための金融機関である簡易郵便局も、経費の負担で経営の危機に直面しています。過疎化が進む地区で絶対に必要な機関です。一旦閉鎖に追い込まれると、再び簡易郵便局をつくることは非常に困難であると同時に、地区住民の生活に大きな不利益を生じることになります。岩屋地区にとって必要不可欠な機関である簡易郵便局を存続させるために、行政が手を差し伸べる必要があると思います。 これは私の次に、地元の岡本議員が質問いたしますので、私の答弁は行政が手を差し伸べる必要があるかどうかだけ、ご答弁頂きます。 第3に、一般競争入札の目的について、公共工事の入札における談合は犯罪であるとして、談合防止を打ち出した適正化法の施行に合わせて、豊前市は、条件付一般競争入札制度を試験的に導入しています。導入したその目的は、1つ、談合は犯罪であるとの認識。1つ、談合の防止。1つ、不良・不的確業者の追放。1つ、地場の優良業者の育成であります。平成20年4月以降の公共工事の入札件数は22件であります。そのうち19件は指名競争入札で、一般競争入札は3件であります。19件の指名競争入札の落札率は95.6%であり、従来どおりの透明性のない談合入札と推定せざるを得ません。 3件の一般競争入札は、6月2日入札の予定価格2268万円の工事は、70.37%の落札率、7月7日入札の予定価格1365万円の工事は、70%の落札率、7月28日入札の予定価格4483万5000円の工事は、70.02%の落札率で、いずれも最低制限価格で競合して、くじ引きによる落札であります。条件付一般競争入札の落札率は70%、指名競争の落札率は96%であり、誰が考えても正常ではありません。 談合防止を推進する行政側の方針は、完全に無視されている常態です。このままでは地場優良業者の育成どころか、地場業者の倒産が相次ぐ恐れがあります。執行部の見解を求めます。制度の見直しをする必要があると思います。 1つ、最低制限価格の事前公表の廃止。1つ、250万円以上の工事を条件付一般競争入札とする。1つ、入札参加資格を1000万円以上の工事は、現在のA・Bランク業者とする。1000万円以下の工事は、参加資格業者全員とする。以上を提案します。 検討して早急に実施するべきだと思います。明確な答弁を求めます。 以上、壇上よりの質問を終わります。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 尾家啓介議員のご質問の中で、豊前市の財政について、そして、3番目の一般競争入札の目的については、副市長から。2番目の限界集落と高齢者対策につきましては、財務課長、そして上下水道課長、税務課長からの答弁といたします。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 私から、豊前市の財政運営についての考え方について、ご質問にお答えいたします。 平成16年度からはじまった三位一体改革により、臨時財政対策債を含む地方交付税総額は、4年間で約9億6000万円削減されております。平均すると、毎年2億4000万円が削減されたことになり、過去に例を見ない状況が続いております。この間、行財政改革を進め、平成18年2月には、新たな行財政改革大綱と、職員35名の削減を柱とする集中改革プランを策定し、更なる経費削減に取り組んでおります。 平成19年度決算においては、実質単年度収支が4年ぶりに黒字化し、団塊の世代の退職金問題も目処がついたところであります。しかしながら、少子・高齢化社会の中で、今後、予想される社会保障費の増大や、上下水道事業会計への繰出金の増嵩、また、引き続き予想される国の歳出・歳入一体改革に伴う、地方交付税の縮減などに対処しながら、将来世代への責任を果たし、持続可能な財政運営を可能とするためには、過度に市債に頼らない節度をもった規律ある財政運営が必要であります。 議員ご指摘のように、今後は公債負担にかかる指標等を念頭に、臨時財政対策債を含めた市債発行額の総量管理をしっかり行い、市債残高を着実に減少させることが、一層重要になると考えております。 続きまして、条件付一般競争入札の目的について、ご質問にお答えいたします。 一般競争入札は、地域要件・施工実績・配置予定技術者の資格や施工経験等を、入札参加資格条件として広告し、入札参加資格を有するものは誰でも入札に参加できることから、公正性・透明性・競争性が高い入札方式でございます。 平成19年度から、地元業者の参加を重視した条件付一般競争入札を、1000万円以上の土木一式工事で導入し、平成20年度からは、入札の事前に行っていた入札参加資格審査を入札後に行い、また、郵便入札方式により施行することで、公正性・透明性・競争性を一層高め、入札参加者の手続きの負担軽減及び入札事務の効率化を図っているところであります。 今年度実施した3件の条件付一般競争入札につきましては、議員からご説明がありましたように、いずれも最低制限価格による、くじ落札となり、誰が参加するか分からない一般競争入札の効果が現れていると考えられます。しかしながら、このような状況が続けば、過当競争による倒産や不良工事の発生、下請け業者へのしわ寄せによる公共工事の品質の低下に関する懸念等も起きてまいります。 議員より、ご提案のありました3項目につきましては、今後の入札動向を注視しながら指名委員会等で十分協議・検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 それでは、私から岩屋地区の簡易郵便局の存続について、ご質問にお答えいたします。 郵政民営化から10月で1年となりますが、全国的に簡易郵便局の閉鎖を危惧する声が報道されております。新聞等によれば、簡易郵便局の数は、全国で郵便局全体の6分の1に当る4296局にあがり、その1割が一時閉鎖状態になっているとのことであります。 市といたしましても、特に、過疎地の簡易郵便局を取り巻く環境は厳しさを増していると認識しております。岩屋地区の簡易郵便局は、現在、旧岩屋公民館の一部を利用して営業しておりますが、お年寄りが身近で利用する地域唯一の金融機関である簡易郵便局がなくなれば、地域へ計り知れないダメージを与えると思われます。行政といたしましても、何らかの支援が必要ではないかと考えているところでございます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 税務課長。 ○税務課長 仲敷国敏君 国民健康保険の高齢者に対する資産割の免除措置についてのご質問にご答弁いたします。本年度の地方税法一部改正に伴い、国民健康保険税に、後期高齢者医療制度支援金が創設され、税率等の改正が承認されました。この税率も改正前の税率を踏襲し、基礎課税額の所得割を9.5%から6.4%に、資産割を38%に据え置き、被保険者均等割を2万4000円から1万9000円に、世帯別平等割を2万7000円に据え置いて、後期高齢者支援金の税率に所得割の3.1%、被保険者均等割の5000円を振り分けたものです。付加限度額の改正に伴い、基礎課税額の医療分が、56万円から47万円に減額されましたが、後期高齢者支援金12万円が創設され、基礎課税額の医療分と後期高齢者支援金の合計額が、改正前より3万円引き上げられましたが、改正前の税率と改正後の税率はなんら変更はありません。 また、今回の改正により、県下各市並びに近隣市町村の資産割の賦課をしている団体を調査いたしましたところ、合併市町村は旧団体として、48団体中、豊前市を含め18団体となっております。 豊前市国民健康保険加入者の1人世帯の年齢65歳以上75歳未満で、資産割のみが課税されている世帯は144世帯となっており、医療分につきましては、均等割と平等割の合計額が4万6000円のところを7割軽減されまして、1万3800円の賦課、支援金分は、均等割5000円が1500円、国民健康保険の医療分と支援金部分の合計年税額5万1000円のところで7割軽減措置がされ、1万5300円となっております。 この1万5300円プラス3割が賦課されているところです。指摘の資産割の賦課をしない場合は、その資産割相当額を他の税率に上乗せすることとなると思います。 今後の国民健康保険事業の財政措置がどのように変化していくか。後期高齢者の医療費4割負担がどのように関わっていくか、75歳以上の皆様が、後期高齢者医療制度にいったことにより、国民健康保険事業の医療費が、どのように変化していくか等が不明であり、現在の見込ができない状況であります。 議員指摘の特例を設定している団体は、県下では皆無であり、独自の特例を設けると、財政調整交付金の算定に影響を及ぼすと思います。今後とも、豊前市国民健康保険運営協議会に図りながら、議会に相談していきたいと思いますので、議員のご理解ご協力をお願いいたします。以上です。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 私からは、限界集落と高齢化対策の中の公共下水道の受益者負担金について、お答え申し上げます。平成19年度末の処理整備面積は352ha、整備率48.2%、処理人口9000人、水洗化率は69.%です。今年度は主に千束地区の工事を行なっております。 お尋ねの受益者負担金は、事業費の一部を負担して頂くもので、すべての土地にへーベーあたり500円かかります。田畑については、宅地化されるまで猶予されます。 最近10年間、賦課された法人用を除く個人宅地及び雑種地の面積が、100坪以上の土地については、平均37%であまり変わりがないようです。 支払については、5年間20回分割して納めて頂くのが基本です。また、一括納付報償金制度もあります。現在では、約8割の関係者の方が、この制度を利用されております。 しかし、短期支払が難しい関係者については、期間延長等、相談に応じております。 現在も意見・要望のある関係者については、自宅に訪問して、よりよい選択で進められるようにしております。これからも公共下水道の整備促進により、地域の住環境整備を進めてまいりますので、どうか、ご理解・ご協力のほどをお願い申し上げます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 1つ確認しときます。今年の退職金は退職者が多いので、22億円になっているけれど、後2、3年して団塊の人は全部退職してしまうので、35人も減員になると18億円を切るぐらいの人件費で済む、計算できるというふうに理解していいですか。総務課長。 ○議長 秋成茂信君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 そのような理解で結構です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 昔22億円あったのが18億円切るまで計算できる、これは本当にいいことなんですよ。 だけれど、これはたった1回しかない。団塊の世代は2回も3回もないんだから。 これで出た余裕資金というのは非常に大切にしてもらいたいわけよ。少し余裕ができたら無駄遣いするとか、無駄遣いじゃないけれどね。少し余裕ができたら、ここら辺に使いたいとか、あそこに使いたいとか、言うんじゃなしに、これだけは本当に大切にして頂きたいということは、今、世の中は不景気になってきている。不景気になると、政府も県も地方もお金が入ってこないんですよ。政府にお金が入ってこないと、当然、地方交付税はまた減額されるわけよ。だから副市長が言われていたように、今までも三位一体改革で、地方交付税は減額されてきた。だけど、これから一層減額される恐れがある。だけど、7年ぐらい前の交付税と今の交付税と姿が違うんですよ。その辺どう思われる。 質問が悪いけれど、7年か8年前は、例えば、30億円地方交付税が入るとするなら、普通交付税が30億円入ったんですよ。そして、年末に特別交付税が2億円か3億円付いたわけよ。今は政府のやり方は違う。30億計算して入るんだなと思っていたら、普通交付税は24億、25億円しか入らないんです。そして年末に、どんぶり勘定の特別交付税を5億円もってくる。普通交付税はしぼられて、ぎりぎりいっぱい、しぼったやつで、特別交付税でちょこっと使い前出すというふうに変わっているので、交付税の仕方が本当に異常になっているけれど、財務課長どう思いますか。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 お答えします。特別交付税につきましては、交付税総額の6%というふうに決められておりますので、その辺の配分方法については、昔も現在も変わっていないと思います。 ただ、交付税の減り方については、16年から先ほど副市長が申しましたように、平均2億4000万円削減されてきておりまして、これは全く今までの歳出とは乖離するような状況であります。こういう状況が、今年度は地域再生対策費4000億円ということで、ちょっと右肩上がりになりましたが、議員が言われたように、今後も歳入・歳出一体改革を国の歩調に合わせて、地方の財政も改善するということですが、ただ、交付税は減っていくというふうに認識しております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 特別交付税の6%というのが守られてないでしょう。要するに政府の言うことは信用しちゃいかんのだから。現実が普通交付税は25億円しか入らんでしょう。特別交付税は5億円入っているでしょう。6%じゃないじゃないですか。要するに政府のやり方は、ここ2、3年、三位一体改革から普通交付税をきちっと締めてきて、そして地方がやっていくのを見ながら、どんぶり勘定をちょこっと特交をつけてやろうかと、そういうやり方に変わってきよる。飴と鞭を使いよるんじゃないかと私は理解しています。これはいいです。 それと、さっき言いましたように、団塊の世代でできた大切な財産は、1回しかないんでね。だけれど、今言うように景気が悪くなって交付税も減ってくると。その上、豊前市の場合、一般会計の繰出しが増えるんですよ。下水道会計・上下水道会計・高齢者の福祉関係を含めて、これは増えるのはしようがない。けれど、一般会計繰出しで節約できるのは、やはり下水道関係と上水道関係しか節約できないんですよ。高齢者福祉関係は節約できないんです。だけど、豊前市は悲しいかな、上水道関係、下水道関係は増えるんですよ。 昨日も広域の受水量、責任水量問題が出よったけれど、これはいきなり解決しようたってできない、長い間かかるんですよ。長い間かかれば、その間、豊前市は増えていくんだから、そこら辺をふまえながら、どうしても、今の好転するであろう財政の余裕を、しっかり管理してやっていきたい。そのために副市長が言われたように、公債費比率を下げて頂きたい。だから、臨時再生債とか、当然、今度出てくるであろう減税対策債、こういうのにごまかされることなく、公債費比率を下げる旨を第1の目的でやって頂きたい。 再度お願いします。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 今、議員がおっしゃられたとおり、財源確保のためには、市債の管理が一番だと思っておりますので、財源対策債等もいろいろよく検討しながら、後年度に備えていきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 先ほど、固定資産税の1.4、都市計画税1.5の不均一課税、私もそれはいいと思うよ。したいんですよ。だけれど、先ほど言うように豊前市は財政が悪くなるんですよ。 今少しよくなったからといって、2億5000万円出したら、お金がなくなるから、それはちょっとやめてほしい。だけど、合併のときに当然それが条件になるんですよ。 合併するとすれば。そうすれば、やはり合併のメリットと、それから、不均一課税を採用するデメリットと、市民がそれでもいい、合併したいと言えば、法定協議会なんかで決まってくれば、それはやむを得んと思うけれど、要するに、合併の法定協議会の中で、そういうのが合併の条件になって、市民が納得すればOKだけれど、その前に、その固定資産税を多少財政が余裕があるからといって、やるべきじゃないと思っていますが、総務課長どうですか。 ○議長 秋成茂信君 総務課長、答弁。 ○総務課長 相本義親君 政策の問題でありましてね。ただ私ども事務方で言えることは、入りが減れば出をどうしていくのか。入りに合わせて管理していかないと倒産します。そういった問題を総合的にどのようにやっていくかということについては、私どもいろいろシュミレーションを事務方で書くことができますので、最終的に議会や市長・副市長あたりが、政治的にどのように決断するのかということになろうと思いますが、私たちを取り巻く環境は、尾家議員のおっしゃるとおり非常に厳しい状況があるということについては、私も認識している1人でございます。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 次の質問をいたします。戦後、農地改革になって田圃が細分化された、ご承知のように。 そうすると、家屋敷と少しの田圃と、少しの山林というふうな家が増えたんです。 けれど悲しいかな、高度成長期になっていくと、若い人は都会に出て行ってしまって家に残った人も年寄りになって、今、お年寄りだけが住んでいる。だけど家屋敷があって少しの田圃と、山林があって収入は殆どないという老人がすごく増えているんですよ。 山の上から海岸線まで全部含めて。その割には資産があると税金がかかる、経費もかかる。私は沓川だけれど、沓川地区で困っているのは、下水道が入ってくるんです。入ってくると屋敷の中には、昔、稲干していた所もあるし、朝晩、味噌汁の実にするための小さな畑も家屋敷にあるんですよ。農家の作業場であった。そういうのがなくなって、その家があって屋敷があって、年寄りが1人か2人住んでいると。下水道が入ってくると、それが全部加入の面積になる。そうすると、お年寄りは入りたくても入れない。そこら辺、水道課長、理解できる。理解できるかどうかだけでいい。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 現在、千束地区を行っておりますが、尾家議員の指摘のとおり全地区、過去、調べて議員に報告した経緯がありますが、広さ的には、そう変わりないということで、さっき答弁いたしましたが、私は今やっている期間の延長等で賄っていきたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 だから、これが法律は制度が1通りで、しようがないじゃないかというならいいけれどね。これは条例をつくるときに、1戸当りいくらにするのか、へーベーあたりいくらにするのかと、やり方が2つあった。それを要するに、その当時、下水道をつくる所は人工密集地が多かったから、人口密集地を基準にしてつくったんじゃないかと私は思っているけれど、それは答弁いりません。 お隣の吉富は1戸当たりいくらですよ。それと下水道の範囲に入っていても、田圃は変化するまで待つわけですな。免除措置があるわけよ。だから私が言う籾干し場とか、朝晩の味噌汁に入れるような青物をつくる畑なんか屋敷内にある所は、田圃扱いにして、それを利用するまでは免除したらいいんじゃないかと思いますが、それはどうなんですか。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 現在も、本当に宅地内に畑をきちんと区画割りしてつくっている所については、その面積を測って猶予しております。最終的に形態が変わった時点で、負担を掛けるようにしております。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 田畑だけじゃなしに、昔、軒先に籾を干した場所があるわけよ。あれも再利用するときは掛けるけれど、それは屋敷の中だから、屋敷面積から除外するということはできないんですか。 ○議長 秋成茂信君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 畑等きちんと毎年作っておれば、それは免除というあれになるんですが、籾干し場とか庭等については、今のところ考えておりません。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 どっちにしろ、お年寄りをあまりいじめるもんじゃないんで、もう一度検討してくださいよ。それにしても対象は少ないよ。それを全部チャラにするんじゃなしに、それを利用して建物を建てるときは、また加入金をもらえばいいんだから検討してください。 それから、国保の資産割ね。全部7100万円だけれど、収入がないのに資産があるから資産割がかかる年寄りの分だけを、免除措置掛けても財政調整基金まで削られるようなことはないと思うけれど、うまい方法があるんじゃないかと思うけれど、どうですか。 ○議長 秋成茂信君 税務課長。 ○税務課長 仲敷国敏君 今のところ、うまい方法というのが、ちょっと思いつきませんが、税率等の改正とかについては、全税率等を考慮しながら相対的に応能割・応益割の原則を守っていかないと、今度はそのやり方によっては、低所得者の減額措置が適用できなくなる場合等が考えられますので、いろいろな試算をしてみないと、現在は、はっきり言える状態ではないというところであります。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 豊前市の国保は、大体、応能割・応益割を合法にするのができないものだから、所得割りを上げるわけにいかんから、資産割を高くした経緯があるんですよ。豊前市の資産割は高い。だから高いのに資産を持っている年寄りが増えたんです。だけど収入がない。 そこら辺を勘案してやらんならん。大体、豊前市は資産割を高くしたんじゃから。 それを年寄りが困るなら、それを引いてやるのが当たり前、該当者に限って免除してやるのが当たり前と思うけれど、どうですか。 ○議長 秋成茂信君 税務課長。 ○税務課長 川島和広君 その部分については、再度、試算等、検討させて頂きたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 それでは検討してください。簡易郵便局の件は、岡本さんが詳しく説明するでしょうから、前向きにいろんなことをお願いします。 2、3日前テレビかなんかで、簡易郵便局で困っているんですよ。だからコンビニかなんかで開かせるというのが出ていたけれど、あれは人口密集地の話で、過疎地の話じゃないから、それを間違えないようにして、ご答弁頂きたいと思います。 それから、一般競争入札の目的について、お尋ねします。談合防止、談合防止といって談合していると認めるわけにいかんしね。けれど、宮崎県でよくテレビに出たがる知事が出たですね。あれが出て格好よく200万円か300万円以上、一般競争入札します、とやったんですよ。だけれど、それを実行したけれど、なんか業者が倒産しかかっていると。だけど落札率は83%だと。だけど業者は倒産しかっている。一般競争入札をやめるんじゃないけれど、なんか発注する方法論を変えようじゃないかと話が出ていると思うけれど、やはり制度を変えても、運用を間違えると業者は倒産するんですよ。 それで、公共工事の経営が安定できる落札率は85%と言われている。それで経営が安定できると言われとるんですよ。そうすると豊前市の場合は、指名競争入札の場合は、今年もまた95.6%、これは95.6%と言うけれど、この中に建設の最低価格が入っているからね、実質96%越しているわけよ。 そうすると96%というのは、談合があるんじゃないか。これ副市長どうですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 談合ではないものと思っております。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 談合がないとするならね。今度、一般競争入札を3件、試験的に入れたわけですよ。 そうすると皆96%どころでなしに、70%で仕事できますと、これでペイしますと入札しとるわけですよ。建設課長、7月8日に指名競争入札に出した工事で、予定価格4400万円の工事、これは積算間違いないだろうね。 ○議長 秋成茂信君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 積算書に間違いございません。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 積算の間違いないのが、4482万5000円の工事が10社入ったんですよ。 一般競争入札に。それで9社が最低制限価格なんです。2990万が10社のうち9社ですよ。4400万の工事の入札に、10社が参加して9社が2990万円でペイできると、工事ができると入札したんです。これは前回、見積もりが間違いないとするなら、70%でペイできるんですよ。 ○議長 秋成茂信君 明確に分かる人が答弁してください。副市長。 ○副市長 後小路一雄君 一応、この価格につきましては、最低価格で工事しておるものでありまして、これで落札しておりますので、ペイできるものと考えます。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 そうすると、先ほどの96%落札は儲け過ぎということになる。さっき私が言った経営が安定できる落札率は85%ですよと。これは学者が言うので分からんけどね。そうして副市長は70%もペイできるんじゃないかと。そうすると指名競争入札で入っている96%はなんですかということになる。大体、豊前市は年間で約10億入札がある。 そして、じゃ70%と96%では26%差があるんですよ。2億6000万円のお金が計算が合わん。それを丸々全部70%に下げろとは言わんけど、なんか少しやり方を変えましょうや。ちょっと異常じゃないかという感覚はあるんですか、市長、どうですか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 今いろいろ論議の後に、地元優先の一般競争入札に、ようやくたどり着いたですね。 今ご提案でございますし、また、こちら自身も地元業者の状況も仕事がないので心配しているわけであります。今の提案、ぎりぎり検討してみておきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 市長に答弁願ったのは、この公共工事を地元で条件付でやるというのは、目的はなんかと言ったら、やはり一番目的は不良・不的確業者の追放ですよ。談合屋の追放。 そして地場の優良業者の育成が目的なんですよ。だけど、今までのやり方を放置しておくと、地場の優良業者の育成どころか、業者をつぶしてしまう。だから、不良・不適確業者を確実に追放して、地場業者を育成するというやり方に徹底すればいいんです。 そのためには、さっき提案した3つね。これは確実に実行して頂きたい。 その辺、副市長、どうですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 ご提案頂きました3点につきましては、今、実行しているものもあります。 今3件条件付でやっておりますが、今後いろいろ動向を注視しながら、いろいろな面から検討していきたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 尾家議員。 ○15番 尾家啓介君 今までも適正化法が施行されてから何年も経つので、それから、ずっと不良・不適確業者の追放、優良地場業者の育成と何年も言ってきた。そしたら検討します、やりますと言いながら、いっこうに進まない。そして試験的に入札してみたら、要するに目的と全然違う方向に走っている。だから指導力がないとは言わんけど、確かに制度が悪い。悪ければ変えればいいんですよ、直るまで。それで言うことを聞かんのは入れないんだから。 制度が悪いなら制度を変えてみながら、また悪ければ制度をまた変えていけばいい。 今のままの制度を私が見る限りは、一番の欠陥は、最低制限価格を公表しているから、これが問題がある。4400万円の工事に10社入れて、9社までは最低制限価格なんてそんな非常識な話はない。だから最低制限価格をはずすべきだと思う。 それから、1000万円以上というのは、これは試験的には通用するけれど、やはり本式に地場優良業者を育成するなら250万円とか300万円以上ですよ。それやっていかなならん。そうでないと意味ない。それと入札には、必ず参加業者を増やさなならん。 だから、そうかといって、1000万円以上の高い高額の所にB・Cランクの業者を入れるのは、現実的ではないから、やはり1000万円以下までの工事は、全業者入って、1000万円以上は、ある程度、資格を与えるというやり方で真剣に考えてやらんと、本当にこのまま放置しとくと、市長みたいに今から検討しますとしておるとつぶれますよ。 倒産が出るよ。倒産が出てからああ、しまったじゃ間に合わんのだから。 市長が言う地場業者を育成するなら制度を変えましょうよ。制度を変えて地場業者を育成して、そのかわり嫌な話だけれど、不良・不適確業者を追放してしっかりやって頂きたいと思います。最後にどうですか。 ○議長 秋成茂信君 副市長、答弁。 ○副市長 後小路一雄君 ご指摘の件につきましては、指名委員会等で十分協議して、前向きに検討していきたいと思います。 (「終わります」の声あり) ○議長 秋成茂信君 尾家啓介議員の質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 11時42分 再開 13時00分 ○副議長 中村勇希君 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行します。岡本清靖議員、お願いします。 ○3番 岡本清靖君 皆様、こんにちは。9月議会での質問を壇上にてさせて頂きます。 今日は4点について順次させて頂きますので、よろしくお願いいたします。本市としての簡潔なるご答弁をお願いいたします。 最初に、過疎化対策についてであります。自分の地元であります岩屋でありますが、平成9年に南部4校が統廃合され、学校が合河地区に移転いたしました。学校がなくなり、生徒は路線バスや回送バス等で通っております。今までのスクールゾーンでは、子ども達の姿がなくなり、挨拶もなくなり、寂しい地区になり、地域の力はなくなっているように思えます。少子化が進み高齢者が多くなり、1人暮らしのお年寄りも増え、限界集落の危機も感じられるようになりました。本地区、岩屋の公的施設、駐在所も統合になりなくなりました。学校跡地に地区活性化センターという大きな公民館が新築されました。 地区の公的施設は、活性化センターと簡易郵便局のみであります。前区長さんの計らいで市との交渉の中、旧岩屋公民館を取り壊すことなく、岩屋簡易郵便局をその中に移転して頂き、また岩屋公民館が老朽化していたために、自分の資金を380万の改造資金で中をあたって再出発をされました。また、土地の賃貸契約で、年間に6万円の借地料の支払と電気・ガス等の自己負担も要しております。 高齢者が多くなっている中、今、合河・岩屋まで足を運んでの金銭の出し入れができない当地域に、なくてはならない金融機関であります。地区民は誰もが願っているわけでありますので、本市としての中山間地の過疎化を図る上での減税・免税を必要とするところでありますので、ご答弁をお聞かせください。 次に、市営バスと高齢者の関係についてであります。市営バスの運行には、市当局に対しましては大変ご苦労様でございます。平成9年度に小学校統合により、生徒達も二豊交通さんに任され、平成14年度に豊前市バスと移行しておりますが、昨日より、爪丸議員と尾澤議員による豊前市バスについての質問がなされております。 私の質問も重なる所がありましょうが、よろしくお願いいたします。 山間部では、バスの運行がなければ、お年寄りの足が閉ざされてしまいます。ましてや現在、飲酒運転ができなくなり、代わりにバスを利用して市街地まで出て行く方を見かけます。私もその中の1人でございます。昨日よりの質問で、1700万円の赤字と言っておりましたが、バス路線はなくてはならない機関であり、継続して頂きたいと思います。 今や70歳以上の方が高齢者マークをつけて運転されておりますが、80歳以上の人でも自家用車に乗られている人が多いようです。私も話をお聞きした中で、家族の中では心配されている家庭があります。そういうのも車に乗られて事故が起きては遅過ぎます。 本市としては、高齢者の方々に、免許証を警察署に戻された方に対して、バスの利用サービス、1年間無料という免税ができないものでしょうか。そういった施策はできないものでしょうか、お尋ねいたします。これからは、このような話が多くの人からあがってきた場合はどうなるか、お伺いいたします。 次に、現在、バイオ燃料を使ったバスを利用されていますが、軽油とバイオでは経費の面、走行距離の関係、また、車両1台の価格の違いをお伺いいたします。また、運賃の価格等もこのままでいかれるのか、お伺いいたします。 次に、鳥獣対策についてであります。市街地の人が、これらの話を聞くと嘘のように思われるでしょうが、山間地ではイノシシやシカによる農業の被害や、山林の被害が出ています。イノシシには稲やカボチャ・サトイモ等食べられます。シカにはソバ・シイタケ・お茶・山林の木の皮をむいたりして木の価値がなくなっております。最大に被害は拡大しております。地域住民の利用する単車や自家用車等にも当たる被害も出ております。 このような事態を本市はどのように受け取るのか、また、鳥獣被害を食い止めるためにこれからも徹底した仕事ができるのか、お伺いいたします。 今までに4件ほどの被害を聞いています。これは単車や自家用車の事故でございます。 中には、単車の現物も残っております。市としての積極的な答弁をお聞かせください。 最後に、市営住宅のあり方についてであります。上町団地建替えの準備段階に入っております。マンションということで大きな工事になります。大手の業者でないとやれない入札金額であります。だけど、豊前市としても、地域の業者が確立して皆さんが入れるような、そういった住宅関係の考え方もしてもらえればと思っております。 私が言いたいことは、豊前市では、京築檜がブランド化されております。その中で、これから市独自の土地を売却して家を建てられるといった施策の中に、京築檜、豊前市にもその京築檜があります。その京築檜を使ってモデルというものを作られるのではないでしょうか。全部を使って頂けるというのではありません。その中の一部でもいいです。 今や山村は崩壊の危機にあります。そういった人達のためにも、こういった形で市独自で考え方を練って頂きたいと私は考えております。 北九州地区では、北九州の木を使って家を建てるというPRや、モデルハウスができております。今までの京築檜のブランド化の流れに対して、どのように考えているのか、お聞きします。それから、これから京築檜はどのように育てていくのか、お聞きいたしますので、よろしくお願いいたします。これで壇上よりの質問を終わらせて頂きます。 ○副議長 中村勇希君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 岡本清靖議員のご質問で、市営バスと高齢者につきまして、総務課長。鳥獣対策と京築檜につきましては、農林水産課長。市営住宅のあり方について建設課長の答弁で、私は1番目の過疎化対策にサービス向上をについて、答弁させて頂きます。 過疎化対策にサービス向上の質問のうち、簡易郵便局の存続につきましては、午前中の尾家議員にお答えしたとおりでございますが、豊前市として今後、どのような支援ができるのか、他の自治体の状況を踏まえながら、対応等について検討してまいりたいと考えております。よろしくご理解の程お願い申し上げます。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 岡本議員から、ご質問頂きました市バスの中での高齢者対策について、いろいろご提言を頂いておりますので、そのことについてのお答をさせて頂きます。 この市バスにつきましては、昨日から多くの議員からご指導頂いておりまして、運賃とか路線の廃止とか、こういう重要な事項については、議会の判断、或いは、バス路線対策協議会の判断、これも議員もご存知だと思いますが、地元代表も出ております。 それから、豊前市地域公共交通会議という機関も、その上にできておりまして、昨日から答えさせて頂いておりますが、すべての同意が必要であります。そして、最終的に国に申請して国が審査するというシステムでありますので、市といたしましては、このバス路線を守っていくというのが、市の重要政策の1つと考えていますので、議員の皆様からいろんなご批判を頂くことのないように、少ない経費で最大の効果を挙げるのが我々の使命と考えていますので、ご理解頂きたいと思います。 まず、高齢者対策で市バスがもっている政策でありますが、65歳以上の高齢者の方々には、半年間乗り放題、どの市バスに乗っても何回乗ってもいいわけですが、1万7000円というフリーパス乗車券がありまして、これは非常に有利な制度になっています。 しかし、質問の無料化という問題はクリアしておりませんが、高齢者対策という件では市バスはこの制度がありますと、現在ある制度を申し上げておきたいと思います。 ご指摘頂いております高齢者の運転が、非常に危ないではないかといった方面で、福祉対策として考えられないのか、というご指導を頂いておりますが、ご案内のとおり、市バスはドアからドア、入口から入り口までということにはなりません。決められたバス停を決められた時間で走るように義務付けられていまして、自家用車の場合は、好きな時間に自由に自らの意思で運転をし、ドアからドアまで、かなり近い所までできるという利点があります。この点で今日、バスが競争力に負けているところであります。 そういう意味では、なかなか高齢者に自家用車をやめてバスに乗ってください、と言っても、そういうバスの不便さがなかなかですね。しかも決まったバス停しか止まりませんし、決まった所にしか行きませんので、そういう使いがっての悪さ、今日、岡本議員の地元のお年寄りも山に行ったり、田圃に行ったり、町に買い物に行ったり、病院もいろんな病院がありますので、バスはすべての需要を満たすことが出来ないという問題がありまして、ここで若干競争力に負けるかなと。 しかし反面、ご案内のとおりに、市バスは大量輸送ですから、環境に優しい、バイオになりますと、もっと環境に優しいということになりますし、ご案内のとおり市バスを開業しまして無事故運転を誇っております。そういう意味では、議員のご心配のお年寄りの事故等には、このバスに乗って頂ければ、事故の発生はかなり少ないのではないかと思われますので、こういった方面で、今後、沿線住民の高齢者の方にバスの積極的利用について、呼びかけしていかなければならんのじゃないかと考えておりますので、また議員も各方面での議会活動の中で、そういった住民の皆さんにバスの利点・欠点を含めてで結構ですので広げて頂ければと、市は責任を持って、こういった問題で、今後バス利用をできるだけ多くの方に訴えていきたいと。このことは市の責任ではなかろうかと考えております。 で、高齢者が免許を返納したら、1年間ぐらいは市バスを無料化できないかということでしたが、福祉政策としてのご要望については、十分、市の職員として耳を傾け検討する値打ちのある提言だと理解しますが、うちのバス運賃は、条例並びに先ほど申しましたようにバス路線対策協議会、或いは、交通会議、豊前市議会すべての同意がないと、そして最終的には、国の同意がないと変えることができません。 現状では、こういったものの理解と共感が得られるかという課題がありまして、そういう手続きが完了すれば、不可能ではないということで、今後、そういう各種会議にかけて岡本議員のご提言を真摯に検討していきたいと、お約束しておきたいと思います。 いずれにしましても、市民の安全と安心を守るのが、我々の任務だと考えておりますので、真剣にご提言について前向きに取り組んでいきたいとお約束しておきたいと思います。 また、バスについてのバイオ燃料についての説明をせよ、ということでしたが、このバイオ燃料は、いわゆるガソリンで言えばオクタン価が低いと言いますか、発火率が低いと言いますか、やや軽油に比べるとパワーが劣るということで、9割程度の力しか出ないと。 燃費になりますと、軽油に比べると2割ぐらいダウンすると。燃料消費量でありますが、これに投入しております軽油で走りますと、リッター9kmぐらい走りますが、バイオになりますとリッター8kmの燃費で走りますということになります。 今日、129円台の燃料が、今年1年で168円に推移しておりますが、このバイオ燃料は95円のまま据え置いていまして、現在、月額で比較して軽油で走りますと10万7520円かかるのが、バイオ燃料では6万6500円という燃料で終わっております。 ただ、全車にBDFが、要するにバイオ燃料が大丈夫だということでなくて、旧車両の初期に導入した三菱系の車はバイオで走ってもエンジンに問題はありませんが、今日は三菱がいろんなトラブルを起こしまして、うちは今、日野がほかに入っています。 この日野のメーカーの新式のエンジンは、燃やしてもらったら保障しません、困りますという指導を受けております。三菱の車が3台ありますので、この3台に少なくとも焚くことができますので、燃料の供給が安定的に入れば、市は喜んでバイオ燃料の導入を図っていきたい。 それから、バイオの専用車みたいのがあるのか。それから購入代金はどれぐらい違うのか、というご質問を頂いておりますが、BDF専用の車はございません。そういう特殊車両はつくっていないし、現在のところメーカーも積極的に、この燃料で走る車を進めていないというのが現状でありまして、まだ、この種の燃料についてメーカー側の対応が遅れているのではないかと思っております。 最後に、運賃については今のままでいくのか、どういう計画かということをお聞きしましたが、多くの乗客から喜んで頂いております。市の責任としては、これだけ市民生活が苦しい時代ですから、せめて市バスぐらいは、市民に優しい運賃をということで、経営努力で現有運賃で頑張るのが、市の職員の使命と考えていますので、改正する気持は、今のところ全くございません、ということをお約束しておきたいと思います。以上です。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 岡本議員のご質問のうち、鳥獣対策及び京築檜のPRについて、お答えいたします。 本市では、近年、イノシシ・シカ等の鳥獣が増え、農作物等の被害が増大しているところであり、有害鳥獣対策の一環として、防護柵やネットを設置し進入防止をしておりますが、最近、イノシシ・シカ等が地域住民の生活圏にまで侵入し、交通事故の発生等、住民の生活を脅かす事態が生じたと聞き及んでおります。 市としましては、鳥獣を寄せ付けない周辺環境づくり、捕獲や追い払い活動、有害鳥獣駆除等の充実を図るとともに、交通事故防止につきましては、豊前土木事務所及び関係部署と十分協議し、動物注意等の警戒標識等の設置を行ってまいりたいと思っております。 次に、京築檜のPRについて、お答えいたします。当市を含む京築地域で生産される檜は、京築檜としてブランド化されておりますが、近年の住宅建築工法の多様化や、木材産業の不振等により、近年そのブランドイメージが不明確になっております。 そこで県・関係市町・森林組合が主体となって、京築林業推進協議会地域材利用推進部会を設立し、地元建築士・工務店への販売促進PR活動や、地域住民による森林・林業体験学習の実施等、普及啓発活動を行うとともに、公民館・地区集会所等の増築・改築等のリニューアル対する地域材を提供し、京築檜の利用推進を図りたいと思っております。 本市におきましても、京築林業推進協議会及び豊築森林組合、関係町村等、関係機関と連携し、十分協議しながら京築檜のPRを行なって一層推進したいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 建設課より、市営住宅のあり方について、ご質問にお答えいたします。 現在、市では9階建ての高層住宅を建設中でありますが、高層住宅の建設のみならず住宅政策上、地域ブランドの京築檜を使った戸建住宅の建設の検討はできないか、とのご質問と理解させて頂き、お答えさせて頂きます。 議員ご質問の京築檜を使った戸建て住宅の普及につきましては、民間住宅の建設普及いかんに関わるところが大であると考えられますが、その普及の一助として、市営住宅における戸建て住宅の建設計画が将来浮上した折には、十分検討すべき事項と考えております。 具体的には、京築檜に関わらず地場が産出した木材は、幅広く使用する建物設計を考慮することであると考えておりますし、建設に当りましては、地域ブランドの京築檜や地場産木材等も合わせてPRすることも必要と考えております。それには品質の差別化を図り生産地と品質が保証できる仕組みづくりも重要ではないかと考えられます。 戸建て住宅の建設については、今後、住民ニーズや社会の状況変化等に合わせて十分浮上も考えられます。その節には、ご指導とご協力のほどお願いをいたします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 限界集落ということで過疎化になることで、今、市長から話がありましたが、本当の最適の突っ込みは財務課長、もう一度よろしいでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 午前中も尾家議員さんよりご提言を頂きました簡易郵便局については、郵政民営化する前から、特に、過疎の郵便局については、合理化のしわ寄せがくるのではないかと危惧されておりまして、結果としても、そのような状況になっております。午前中も申しましたように、全国で400を超える簡易郵便局が閉鎖に追い込まれているということであります。また、一旦、閉鎖に追い込まれますと、それを再開するのは非常に困難だという状況が、他の地域ではあるようです。そういう状況を踏まえて、現在、旧岩屋公民館の一部を6万円で貸しております。これは簡易郵便局といえども公的機関ではありません。今は民間の一企業でありまして、減免するというのは現在では難しいということでございます。 そういうことで、また実態はこれをどのように取り扱っていいのか、私ども勉強して、どういう方法があるのか、岩屋地域の皆さんともご相談しながら、やはりこういう大変な状況を踏まえて検討していきたいと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 財務課長の今の話、大変ありがとうございます。積極的にそういった考え方で前向きにいって頂きたいと思います。やはり岩屋も過疎化・限界集落と、本当に何地区かはそういう形ではないですけれど、全体的に考えるとそういう形に入っていると思います。 ですから、榎本議員が言われたごと、これから岩屋地区が一番大事なんです、求菩提山からしたらですね。やはり私も豊前市を代表する者としては、求菩提山が一番大事な物だろうと思います。その岩屋をできるだけ行政としても、いろんな面でして頂きたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 次に、市営バスの件であります。市営バスは私も利用しております。この中の職員の方で利用されている方はありますか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 定期を買っている者も若干名いまして、私どもも、例えば、卜仙あたりでいろんな会議等ありまして、乗れる場合はバスを利用しようということで、ただ、卜仙は無料の車を持っておりまして、これを頼んだりということで、それも利用しておりますので、どうしても市バスの場合は有料で、ここから行くと500円ほど片道かかりますので、無理には頼めないということもありますが、市の職員にも、もう少し利用方法について、お願いする時期に来ているのかなというふうには考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 先ほど言ったように私はバスの利用者であります。私は乗って頂くに際して500円。今いろんな協議会の中で話し合いして解決しなければ、料金改定はできないということになっておりますが、八屋まで下って、やはり400円が適当ではないかという自分の考えです。全体的に距離からしても、そんなに違わないと思います。合河までで400円。 それから下が300円、200円、100円になっていますが、私としては400円ぐらいが、適当な金額ではないかと思っておりますが、どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 料金の問題は、このバスを走らせるときにいろいろ論議を頂きました。つつみ隠さず話しますと、料金について、当初は安い料金の提供をということで論議しましたが、料金を下げて経営を悪化させるよりも、料金は西鉄よりやや安ければいいんじゃないかということで、昨日も答弁しましたが、西鉄より25%安い運賃で設定しております。 但し、岡本議員がご指摘のように、うちは100円刻みですから、100円の次はすぐ200円になります。西鉄の場合は20円、30円で刻みがありました。そういう意味では、一部かなり割引が大きい地域と、割引額が小さい地域。例えば、八屋駅から乗りますと大西まで100円で乗れます。これはかなり長い距離が100円で乗れるわけです。 その次は、横武の公民館に行きますと200円になります。山内に行きますと300円になります。改定幅が100円刻みですので、非常に不利益な部分もあるわけでありまして、そういう矛盾は感じていますが、今のところバスの運賃を変えるということになると、いろんな手続きがいりますということについては、先ほどご説明したとおりでございます。 そういう意味では、うちは回数券、これは3000円で35枚でしたか、100円券で提供しております。それと子どもさんに対しては、バス路線対策協議会の論議を頂きまして、日本一安いバス定期券ということで、高校通学の子どもさんたちに沢山乗ってもらうということで、今でも日本一を誇っていると思います。相当安くしております。 そのようなことで、今日の生活から見たときに、やや高いのではないかという負担感があることについても私ども承知しておりますが、上げるにままならず、下げるにままならずという現状でありまして、今のところ今の運賃体系で、ご辛抱をお願いしたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 分かりました。それでフリーパスの基準が何処まであるのか、地域的には。それをお伺いいたします。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 先ほども答弁いたしましたが、年齢が65歳以上でありますれば・・・ ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 ちょっとすみません。手を挙げて乗られる方があるわけでしょう。そういった関係をわかっていますか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 失礼申しました。フリー乗車で手を挙げて乗せる所は、どの範囲内かということですね。それは横武より上を一応対象にしておりますが、ご案内のとおりに、うちのバスの場合はお年寄りがバスに乗る場合、大体、交通ルールとか分からなくて、手を挙げさえすればすぐに止まれるというふうにお考えになるので、乗っているお客さんの心配がありますので、安全を確保し、後続車が後についてない場合は、横武より上については止めてもいいよと。 かなり早い所であれば、例えば、体の不自由な方等は、千束より上、バイパスより上は体が不自由で危険性がないと判断する場合は、運転手の判断で止めて乗せてあげてくださいと指導しています。原則としては、横武より上が理想であるよと日々指導しております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 私が乗り合わせた中で1回そういうのがありました。その人は合河から乗りました。 バス停でなくて中間からぽっと手を挙げて出てきたんです。運転手が、ちょっと頭カッカになってしまって、こんな所で止めたらという言い方で、すみません。ここはこういうことですよといういい方で、お客さんに対して言ってくれればいいだろうけれど、自分のほうがカッカなってしまって、お客さんはどうにもならないような感じで、そういったことがないように、そういったフリー乗車ができる所が、大体、何処から何処までということで聞いたわけですが、横武から上ということなら、やはり合河もその範囲に入っていますから、そういった関係で、運転手さんたちにも指導をよろしくお願いいたします。 ああいった形で、私もそういった言葉を耳にすると不快感がありまして、他に乗車がなかったからいいだろうと思うけれど、周りに乗車されている方が多かったら、不快感があると思いますので、その点は指導して頂きたいと思います。 それから、高齢者の関係で免許の関係がありましたが、運賃が安くならない形で取られますと、私の親もフリーパス券、回数券も買わせております。それで乗車させて病院なんかに行かせております。けれど92歳になりますので、1人で自分で行くと言いますので行かしておりますが、やはりそういった形で、バスの利用が高齢者でもできるということは、やはり皆さん見守ってもらいたいという形もありますし、地域の方で、バスの利用は、いろいろな面で利用してくださいということは、私からも言いたいと思います。 これから先すみませんが、よろしくお願いいたします。 続きまして、京築檜の関係でございます。この京築檜がどのようにして生まれてきたのか、課長、ご存知でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 ちょっと勉強しておりません。すみません。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 京築檜が一番いいというのは、昔は節があって一番悪かったんです。土台材という形で力が持つから、下のほうにもって行けという形なんです。だけれど、京築檜は今は手入れができて色がよい、香りがよい、そういった形でブランド化を進めております。 地域のブランド化は豊前市が遅れているんです。逆に外部の方が素材を買われて、外部の人が関東や関西に持っていって、京築という名目で売っているんです。だから、それを地元でできないのかというんです。だから市営住宅にそういった形の中で1本でも2本でもいいから、そういった使い方を、そして山林の所有者の方に還元ができるような考え方を持って頂ければと、私は思うんですけれど、どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 住宅には低廉価格というのがありますが、戸建ての住宅に地元産を使うということは、非常に大事だと思っております。そういうことは、今後必要が出たときには考えていきたいと、そういう住宅も今後必要ではないかと考えております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 じゃ、モデルハウスなんかつくるような形というのは考えていますか。 ○副議長 中村勇希君 建設課長。 ○建設課長 加藤久幸君 私が答えていいかどうか分かりませんが、トレードマーク、ここは何処が違うんだよという木自体の差別感も必要じゃないかと思います。今、私は調べていますが、国交省が本年度から、地域木材住宅市場活性化推進事業というのがはじまっています。 これは普及推進・担い手の育成・企画開発・その他事業を咬合した優れた事業に対しての補助金という形で、そうした組織づくりを生かしながらPR等考えて、その手伝いができればと思っております。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 山林の一番大事な所は標高の高さもあります。豊前市の中では、山林の面積は60何%ですから、だけれど、植林されている人工林は上でないと駄目だと思います。 大体200、300、400が本当の木の樹質のためには、一番いい標高差なんです。 そういった中で最適は岩屋地域、そういった形になると思います。やはり榎本議員も言われたごと、求菩提山周辺になると思います。そういった中で観光開発も考えながら、史跡も考えながら、やはりそういった形で山林を守っていく。森林組合とタイアップしながらでも、そういった形で前向きに新しい、いいブランドをつくりあげて頂きたいと思います。 どうかよろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 山下 正君 今、岡本議員のご指摘のとおり、やはり地場にある木は地元で使うのが一番いいし、この地域においては、この地域の木材が一番いい、強いということは聞いております。 それにつきましては、今後、森林組合・県・関係機関等とも十分協議しながら、豊前市のみならず京築地区全体としても、推進を図ってまいりたいと思っております。 よろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 岡本議員。 ○3番 岡本清靖君 ありがとうございました。今日は、4つの関係で質問させて頂きました。 これでもって私の質問を終わらせて頂きます。よろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 岡本清靖議員の質問を終わります。 次に、鎌田晃二議員。 ○2番 鎌田晃二君 皆さん、こんにちは。通告書にそって壇上より質問させて頂きます。 まず、最初に、文部科学省が監修し、学校保健会が作成した学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインが、今年4月以降、全国の教育委員会・学校などに配布され、アレルギー疾患のある子ども達を、学校や園でどう支えるか、という観点での取り組みを現場に促しております。 同ガイドラインは、文部科学省のアレルギー疾患に関する調査・検討委員会が、平成19年4月、全国の公立小・中・高校を対象として行った調査を元に、学校におけるアレルギー疾患への取り組み推進に向けた方策を提言したことを受けて、同報告書に盛られた共通理解に基づく取り組みを、具体的に示したものと位置付けられています。 アレルギー医療の現状を患者の視点から見ると、医療機関を選択する情報もなく、たまたま受診した医師の資質によって、治療や、その後の生活が大きく左右され、学校生活などで著しい生活の質の格差を生んでおります。学校、地域などで適切な治療につなげる連携体制の構築が急がれております。 具体的には、学校・幼稚園・保育園などで、健康診断や学校中心に疾患を理解し、自己管理を可能にする健康教育の実施、更に、医療機関での喘息の治療を受けているにも関わらず、度々、呼吸困難、発作を起こす、何時までも体育の授業に参加できない。学校行事に参加できない。医療機関を受診しているにも関わらず、アトピー性皮膚炎が好転しない。 増悪・警戒を繰り返す。食物アレルギーで食べられるものが殆どない。食物アレルギーで重い症状。アナフィラキシーを繰り返すなど、適切とは言えない医療を受けている子ども達を、専門医療機関につなげるシステムを構築する必要があります。 先の文部科学省のアレルギー疾患に関する調査検討委員会の報告書によると、学校が各種の取り組みを行っている、と答えた割合は、かなり高いものの、実際にアレルギー疾患で悩んでいるお子さんを持つお母さんたちに聞くと、実際とは違う、こんな対応をしてくれていないという声が多いのが現状です。いかに立派なガイドラインができても、実際にそれが学校現場で実行されなければ意味がありません。 そこで、豊前市におけるアレルギー疾患の有病率の実態をお聞きします。 中でも重い症状であるアナフィラキシーを起こす子どもたちは、どれくらい入るのか。 このアナフィラキシーというのは、ある抗原で免疫を得た生態が、同じ抗原の再需要によって、ショック症状を起こすというものであります。例えば、蜂にされて、その後もう一度さされるとショック症状を起こすといったものが、これに当ると思います。 そして、基本的なアレルギーの疾患に対する対策の方針をお聞きします。喘息アトピー性皮膚炎、食物アレルギーは、自席より再質問させて頂きたいと思います。 2点目に、子育て支援について、お聞きします。ファミリーサポートセンターではシルバーに委託し、子どもを預かってもらうサービスがありますが、どのくらい利用されているのか、お尋ねいたします。その他、通告書に書いたものは自席より質問させて頂きます。 3項目の市バスについては、3人の議員が質問されました。私を含めて4人になりますが、今までの答弁を参考にしながら自席より質問させて頂きます。 4項目の緊急通報システムについては、体の悪い独居老人の方が、ボタンを押して救急車に来てもらうというシステムのことですが、何人の方が申し込みされているのか。 また、申請をしたら、どのくらいで設置して頂けるのかを、お聞かせください。 以上、壇上での質問を終わります。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 鎌田晃二議員のご質問で、自席からという特定もあるようですが、一応、答弁書を予定している方は言ってほしいと思います。 1番目の学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインにつきましては、教育長から。2番目の子育て支援、そして、4番目の緊急連絡通報システムは福祉課長。 そして、市バスは重なりますが、総務課長からの答弁にいたします。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 鎌田議員のアレルギー性疾患の有病率につきまして、お答えいたします。 喘息につきましては、豊前市内の小学生の9.6%。中学生で6.5%。アトピー性皮膚炎は小学生4.1%。中学生4.6%。食物アレルギー小学生1.4%、中学生2.8%。 アナフィラキシー小学生0.1%。中学生0.2%という病率であります。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 子育て支援ということで、ファミリーサポートの件で、ご質問頂きました。 ファミリーサポート事業は、平成19年度より育児の援助を受けたい者及び援助を行いたい者を会員として登録し、育児の援助活動を行い、子育て家庭の仕事と育児の両立を支援する事業ということで、19年度から始まっております。 この事業は、豊前市においては、シルバー人材センターのほうに委託しております。 手続きとしましては、まず、会員登録を行い、預けるほう、要するに依頼される方の協力会員と、預かるほうの方と契約を結んで預けることができます。対象となる子どもは、生後6ヵ月以上の幼児から、小学校6年終了時の児童でございます。対象者といたしましては、市内在住の者となっております。利用時間は8時から20時までで、1時間あたりの単価は880円で、市が2分の1、440円を補助しております。 19年度利用実績は、述べ11人で92時間、市の助成額は4万480円であります。 続きまして、緊急通報の関係でありますが、一応、高齢者対策ということで、この事業を行っております。1人暮らしの高齢者等に対して、急病・事故等に対する不安感の解消を図り、福祉の増進に資する事業となっております。対象者は、市内に在住し、概ね65歳以上の1人暮らしの者で、虚弱等により緊急事態の発生が予想されるもの及び重度の身体障害者に貸与するとなっております。システムとしては、緊急ボタンを押せば消防署に直接つながり、相談ボタンを押せば在介の介護センターにつながるようになっております。 この緊急システムは、一応、1市3町で共同運営されております。設置台数は全体で660台。うち豊前市に設置台数は、平成20年6月末現在で165台となっております。 ご質問がありました設置希望の待機者は、一応45名となっております。この中で実質的に必要性の高い方は、4名程度ということになっております。19年度の緊急通報の件数ですが、全体で102件、誤報が89件、救急が13件、本市の場合は通報が14件、誤報が11件、救急が3件ということで新規に5台購入しております。 以上のように、通報件数はあまり多くありませんが、ただ、必要性の薄いと思われる方の申し込みが非常に多い関係があります。その関係で、消防署の交換機の容量及び誤報の状態を見ながら、今後、対応していきたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 それでは、自席より質問を続けさせて頂きます。まず、学校のアレルギー疾患に対する取り組みについて、お尋ねします。喘息が9.6ということで、中学校が6.6%ということであります。喘息に対する対策は、どのようにしておりますか。 まず、喘息は今、我慢の治療から発作を起こさない治療へと変わっております。 例えば、ほこりが舞う装置とか、動物の飼育係は免除するとか、後、運動・修学旅行などの各種の行事における配慮、こういったものがされている一方、体育の授業は参加不利と決めてしまわず、運動誘発喘息も起こりにくくなっていくということで、運動をさせている所もあるようです。どのように対応しているでしょうか。 それから、アトピー性皮膚炎はどのように。豊前市はプールが余りありませんので、なかなか少ないかも分かりませんが、それでも4.1、4.6%ということで、自治体によっては温水シャワーを保健室に設けている所もあるようですが、豊前市の取り組みをお聞かせください。よろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 まず、アレルギーの実態把握でありますが、来年から小学校に入るという子どもは、11月ぐらいに就学時健康診断を実施しております。その折に保護者にアレルギーがあるかないか、どういうアレルギーかということを尋ねて書いてもらうようにしております。 また、学校にあがった子どもにつきましては、毎年、小学校・中学校も健康診断をしております。事前調査表という中に、アレルギー或いは、日常生活で気を付けなければならないことを保護者に書いて頂いております。 また、緊急時の連絡カードというものがありまして、これも小学校・中学校で何か病気になったとか、或いは、大怪我をしたといった場合に、家庭の保護者のほうに、緊急に連絡しなければならないようなことについての連絡カードを書いて頂いていますが、その中にも体質や食べ物や薬などのアレルギーがあるかないか、あればどういうものがありますかということで、事前に把握しております。 学校で、どういう指導をしているかということでありますが、やはりアトピー性皮膚炎の件で、非常に激しい子どもについては、学校に温水シャワーを付けるようなことを、保護者と学校と教育委員会で話し合って付けたことも過去にはあります。その他、喘息の子どもには、掃除のときマスクを付けるとか、或いは、ほこりが立たないように掃除するとか、発作時はどういう対応したらいいかということを、家庭と担任、或いは、養護教諭と連絡を取り合って、どういう対応をしたらいいかというのは、1人ひとりによって違うと思いますが、対応はさせて頂いております。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 学校は薬等は預かっているんでしょうか。それとも対応がバラバラだと思うんですが、豊前市では、薬を預かって飲ませるということをやっているでしょうか。 喘息の薬とか、預かる学校もあるようですが、なかなか自己管理という所もあるようですが、豊前市の場合は、薬は預かっているでしょうか。預かって先生が飲ませるという対応をしているでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 そこまで具体的な情報はもっていませんが、先ほど議員がおっしゃいました学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン、これです。これが各学校に行っていますので、教育委員会といたしましても、9月から、この中身についてよく精査して、この中に学校生活管理指導表とアレルギー疾患用のサンプルが示されています。これを使って、その子どもと担任だけの情報の共有じゃなくて、学校全体の職員の情報の共有として、そういった学校の中で生活管理を必要とする子どもと、必要としない、自分で薬を飲めば分かる、よくなるという子どももいますので、そういう指導表が必要な家庭については指導表を配って、学校医なりの指導を受けた上で、学校での指導ということにしようと思っています。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 食物アレルギーのことをお尋ねします。この児童は全国に大体33万人、重いアナフィラキシーですけれども、1万8300人と言われております。そして、平成14年、15年で637件のアレルギーの症状を引き起こしたケースが報告されており、その中の50例が、命を脅かすアナフィラキシーショックを起こしたということです。 それで、豊前市は確か0.1%だったですね。中学校が0.2%ということでしたが、このショック症状を起こしたときに注射しますね。アドレナリン自己注射というのを。 この管理というか、自分では打てない子どもの時に、豊前市ではどのような対応をされているのか。救命医師法というのがありますが、医師法被害の刑事・民事の責任についても人命救助の観点からやむを得ずという形で、現在は、職員の責任にならないで不安をなくして、緊急な時には、この注射を打つということがされていますが、豊前市は、どのように指導されているでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 先ほど発生の割合を申しましたが、アナフィラキシーは、小学生で学校が違いますが、1人ずつ2人います。中学生で1人います。こういう言葉は、ガイドラインを読んではじめて知ったわけですが、先ほどから議員がおっしゃいますように、いろいろなショック症状、血圧が低下するとか、或いは、意識の低下とか、或いは、脱力を来たすような場合は、アナフィラキシーショックと言われて、大変重篤な状態になると聞いております。 その子どもが、今、在籍している学校でどのようにしているか、そういう注射をどういうふうに管理しているか、それを保護者と、どういうふうに連絡を取り合っているかということについては、後日、調べて学校に適切な指導をしていきたいと思っております。 今は、豊前市内の小・中学校には、AEDがすべて設置しています。また、各学校には、この指導の仕方、扱い方を勉強した職員がいますので、仮に、そういう状況になったときには、こういったものを使って救急・救命ができるのじゃなかろうかと思っております。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 では、アナフィラキシーのショック症状のときには、注射を打つか打たないかというのは、まだ、豊前では、きっちりとした指導はないという具合に理解いたしました。 このアレルギー疾患で、アトピーとか特に皮膚が汚いとか、いじめの対象になっている場合もあります。しっかりと病気の説明をしたり、友達への支援をお願いしたりして、共感をもって健康教育を行って頂いて、学校に共感する心を育てていって頂きたいと思います。この質問は以上で終わります。 次に、子育て支援について、お尋ねいたします。先ほど、ファミリーサポートという形で、11人の方が92時間ということでしたが、若いお母さん方にこの話しても、なかなか知らない方ばかりで、その説明をずっとして回るような形になっていますので、このPRを、440円というのは、調べても、おそらく日本で一番安いのじゃないかと思います。 こういったものを利用して頂いて、子育てに頑張って頂きたいと思います。 2番目に、保育ママ制度について質問いたします。保育ママ制度というのは、保育士や看護師などの資格を持った人が、自宅などで0歳から2歳児の子供を預かる制度であります。保育所と同じく、親が共働きで面倒を見れないといった子供を対象にしています。 保育者は、1人で3人まで預かることができて、保育時間は1日8時間ということです。 メリットとしては、暖かい家庭的な環境の中で、子どもが保育を受けられるという利点と、保育所の待機児童の解消を図るという利点があると思います。2000年に、国の補助事業としてスタートしまして、現在では、7億3000万円の予算がついております。 豊前市も、この制度を導入されたらどうかなと、どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 今、議員さんのご質問の関係につきまして、勉強不足で大変申し訳ありませんが、保育ママ制度は、平成18年に児童福祉法が改正されて、生後2ヵ月から3歳未満児ということで、法が制定されたとお聞きしております。その点につきましては、一応、先ほども議員さんがおっしゃられたように、待機児童対策ということになっておりまして、今、豊前市で保育所関係においては、待機児童はありませんので、現時点では、この制度は考えておりません。以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 待機児童がないというお話でした。6月議会でも同じ答弁でした。視察に千束に行ったときに教室が足りなくなるということで、教育長から、プレハブを建てるという計画を聞きまして、学童保育の今のプレハブの場所に建てるので、学童保育の所に移動するという話がありましたが、視察の時には、校舎が足りなくなる待機児童も必ずあります、ということで、移動の時に学童保育の今の施設を広げてくれないかという話がありました。 教育長、どうでしょうか。学童保育の今、千束はないという話ですが、確実にあるということを聞きましたので、教室が足りないのでプレハブを建てるという話をお聞きしましたので、そのとき移動させる際に、少し拡張して頂けないかという話です。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 あの時点では、来年度に入ってくる新1年生の数が、40名超すということで、プレハブを建てて対応しなければならないかなという話は確かいたしました。その後、新1年生が千束小学校に入ってくるだろうという子どもの数を調べた結果、40名を切るという状況でしたので、9月補正には、このプレハブを建てるという補正は組んでいません。 また、10月1日付で、来年度の新入生の数の予測が出てきます。そういった中で、また40名を超すということであれば、12月の議会、或いは、3月議会では遅いかも分かりませんが、そういったことを考えなければならないかとは思っております。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 それから、子育て支援センターのたけのこの更なる活用という形で、視察に行かせて頂きました。平日、何も行事がないときは平均2組ぐらい。多いときは7組あったと。 0のときも多々あるという話でしたので、近隣の住民の方もいつも早く終わって人も来てないので、他にも何か利用できないかという話も伺っております。 そこで、このたけのこの更なるPRをお願いして、なおかつ16時に閉館しておりますが、調べたところ16時に閉館という所は1件しかありませんでした。これを、できれば17時までという形にして頂いて、更なる活用をして頂きたい。それから、何故16時かという質問で、パートの方が16時までしか居れないということと、家に帰って、それから、ご飯をつくるのにちょうどいい時間だという返答でしたが、別に17時まで開いていても16時に帰ることができますので、その辺の改善をお願いしたいと思います。 これはもういいです。 それから、敬老祝金の廃止によって、子育て支援に、このお金を回すという話を聞いております。私が議員になっておらないときのことだと思います。いくら予算ができて、何処にどれくらいのお金を子育て支援に回したのか、金額でお答えください。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 前回、山崎議員さんに少し説明いたしましたが、大体、削減幅で2200万円程度あったかと思います。それについては、一部を19年度当初、出産祝金に2人目から10万円というのを新設いたしました。3人目から20万円ということでしたが、その分の追加に対して700万円ぐらい入れたのではないかと思います。 次に、子育てサポートセンターに100万円ほど予算をつけております。後、子育てに優しい市役所づくりということで、子育てガイドブックというのを作成等々して、それに60万円程度つけております。後、温泉の入浴券を65歳以上の方に配っております。 これは65歳以上の方が増えているということで、残りは、その所に充当したという内容になっております。それと、子育て学童保育ですが、これについても、年々措置人数が増えておりますので、それに400、500万円ほどで充てたかと思っております。 以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 じゃ、すべて子育てに使ったと理解していいでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 今申しましたとおり、一部老人の分ということで、入浴券のほうに400、500万円充当したということでございます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 家庭訪問などしますと、高齢者の方から苦情を言われます。そのとき説明するのに、子どものために使わせて頂きますという話で、そのたびに返答していますので、しっかり子育て支援のほうに使って頂きたいと思います。 続きまして、市バスについて質問いたします。本当に私も含めて4人、市バスについて質問が重なりました。ということは、本当に今、バスが転換期に来ているのじゃないかと思います。私の意見は皆さんとちょっと違いますので発表いたします。 各路線の1便あたりの平均利用者数を教えて頂きたい。それから、時間帯での利用者数が分かれば教えて頂きたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 うちはカウンター調査をやっていまして、バスの運転手にどのくらい乗っているのかについての、定期的なカウント調査をやっていますので、時間帯は、残念ながら的確に把握は困難ではありませんが、今、資料として持っておりませんので、後で出せるようにあれば出したいと思います。まず、どれくらいの1ヵ月の乗客数かについては調査しています。 19年度の1ヵ月の平均乗客数は、岩屋線で4407人、轟線で1755人、畑線で1439人、櫛狩屋線で736人でありまして、総トータル10万7500人、スクールバスが総トータル7600人、これはうち数になります。そういう状況であります。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 岩屋線が黒字ということで本当に驚きました。本当に頑張ってやっているなという思いもあります。豊前市バスは、昨日の答弁の中では、櫛狩屋線が1便当たり平均4人という形で答弁があったようですが、1便当たりでは分かりますでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 輸送量等が岩屋線でいけば16.1。轟線で8.8。畑線で9.1。櫛狩屋線で4という状況になろうかと思います。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 私も車を運転しながら、よくバスが通っているのを中をいつも覗き込むんですが、昼間はいつも乗ってないような状況で、岩屋線が黒字というのはびっくりしたんですが、これは通勤・通学とか・スクールバスとか、いろんな面でこういう収支になっていると思います。市バスは、昨日の答弁のとおり80条バスということで、78条と79条に移行されました中で、78条の3をちょっと読みますが、公共の福祉を確保するため、やむを得ないない場合において、国土交通大臣の許可を受けて、地域または期間を限定して運送の用に供するときとあります。ということは、公共の福祉の一環ですので、需要が乏しくても、その地域に人が住んでいれば運行しなくてはならない。 行政サービスが黒字である必要はないということです。しかし、行政サービスだから赤字で当たり前というのが皆さんの意識の中にあると、ものすごい怠慢な経営になっていくと思います。豊前市の場合は、なかなかいい経営であると思います。 昨日の質問の中に、22人の運転手をここだけ聞かせてください。管理人が4人という答弁がありましたが、4人は多いような気がするんですが、どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 うちは運転手・運行管理者を含めまして、いわゆる現職をリタイヤして定年退職した職員を雇用しています。当然、時間給で雇用しております。そういった関係で、1人の者に集中的に長時間仕事をさせるということをよしとしておりません。長いもので、1日6時間程度働けば必ず2日間ぐらいの休みを取らせると。それと、運転手並びに運行管理者、この団結権の問題もあるわけです。そういった問題で、賃金・労働条件改善等の問題もクリアしていかなければなりませんので、シルバー人材センター登録の運転手と、直営の運転手並びにシルバー人材センター経由の運行管理者と、直営の運行管理者というものを置いております。日々の業務は、市の職員が運行管理をやっております。 いわゆる、市の職員の時間外・祭日等について、バスの運行管理のために、運行管理者を充てると。当然、休み等の問題、或いは、突発的に家庭の不幸等もありますので、適正管理で行っていると自信を持っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 ここからが私の質問であります。私は今の78条の市バスは、そろそろ見直す時期が来ているのではないかというのは、これは福祉を目的と言ってもいいと思います。 小石原の私の友人のお母さんは高齢ですが、清田整形に通うのに小石原はバスが通っておりませんので、バイクでずっと通われておりました。膝が悪いので病院に通っていたんですが、子どもから止められていたんですが、タクシーで行ったらとてもお金がないということで、ずっとバイクを運転していたんですが、やはり事故を起こして足を骨折して、足を治しに行くところが骨折した。そういう話を私の同級生から伺いました。 その中で轟の方からも、こういうご意見を聞きました。乗らなければバス路線が廃止されるということで、用もないのに皆さんに乗って頂いて、八屋まで出てきているという話をお伺いしました。とにかく住民は廃止されるのは恐いという形で、このような連絡を取りながらやっております。そして、お年寄りの方が関節症等で膝が悪くて、黒土整形や清田整形に行きたいということですが、この市バスは近くを走っていなかったり、バス停も遠かったりして我慢するという形で、病院に行けない状態にあります。 これが今のバスのままでは、絶対に改善することはできません。そして、火葬場の近くの方からも、バスがないという話を聞きましたが、ここで提案したいのですが、こういった廃止代替バスが、こうやって固まって運営をされると、これを撤廃するとか、変えるのはすごく難しくなります。一度決まったらですね。 これを市長の決断で、今いろんな自治体が、こういった方の足を確保するという形で、昨日の尾澤議員がデマンドバス、デマンドタクシーの話をされていましたが、いろんな方法を使ったらどうかと私も同じ意見であります。 例えば、通勤・通学・スクールバス・コミュニティバスという形で、利用の多いときにこういったバスを運転し、日頃、市バスを見ても乗ってない時間帯には、このデマンドバスやデマンドタクシーを導入して、お年寄りが電話をかけて予約して、その人数集まってタクシーを運転するという形で、余所の自治体を見ても200円、300円で運営がされております。 これは問題的には、お年寄りが電話するという部分をクリアしなければいけませんが、それとセンターづくりにお金がかかりますが、将来を見通す場合には、市バスよりももっと福祉の充実も図れるし、このまま1700万円の赤字をするよりも、考え直す時期に来ているのじゃないかという思いがします。そして、コミュニティバスのいい所は、例えば、商店街とかに自由に止まって頂いて、商店で一定の金額の買い物をして頂くと、そこにバスのチケットを渡すという試みとかもいいと思います。 この78条バスをNGO法人に譲ることもできますが、コミュニティバスもNPO法人に任せても、そういった1項もあってもいいんじゃないかと思います。 それから、読売新聞の昨年12月31日に、運行補助金という形で、総務課長にご相談したところ、広域しか駄目だよというご返答でした。それで県に調べて頂いておりますが、読売新聞には新たな制度では、地域住民や事業者などで共同設立した協議会、豊前市にもあるようですが、路線を維持・活性化するプランを国交省に提出、創意工夫などが認められれば補助金を交付する。この場合の地域は、1集落から行政の枠を超えたものまで幅広く捉える、具体的には鉄道がある所はダイヤ変更、コミュニティバスや乗り合いタクシーの導入といった形で、問題は高齢者が多い過疎地、自治体などが旗振り役となって、高齢者を巻き込んだ協議会を設立、今あるようですから、赤字路線が次々に切り捨てられるというんじゃなくて、創意工夫をしながら、どうしたら住民の困った方々を救えるのかという観点からも、この市バスの見直しをやって頂きたい。 豊前市公共交通活性化計画という形で立ち上げて頂けないでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 議員のご提案は政策面の問題でございますので、事務方が踏み入るのは適切かどうか分かりませんが、多分、議員ご指摘のコミュニティバス、或いは、デマンドという形態は、21条バスのことをお指しになっているのではないかと思います。大体、民間の事業者が営業するバス形態が主でありまして、私どもの79条の2というバス事業と若干の開きがあるわけです。議員も今ご指摘頂きましたが、私どものバスはあくまでも路線が決まっておりまして、バス停もダイヤも決まっておりまして自由にすることができません。 昨日も答えましたが、80条は全国ではじめての許可でありましたが、豊前市内を自由に路線を変更できますという包括許可という、全国に先駆けて豊前市が貰った許可でありまして、これは今なくなりました。要するに、規制緩和から、また規制が入ってきたわけでありまして、うちは今79条の2というバスで運賃や時刻・ダイヤを変更するのは、非常に大変困難な厳しい規制の内容になっております。 それで、今のバス制度を見直して、デマンドタクシーやデマンドバス並びにコミュニティバス、そういうものを考えたらどうかということ、それから、国の補助金はどのように考えているのかということですが、基本的に理論的には議員がおっしゃるように、例えば新たな目新しい創意工夫した地域の活性化のために、いろんな事業を起こせば2分の1補助します、というふうに言っていますが、残念ながら、これは開かずの門です。 基本的には、その地域で走らせる事業については、それぞれの自治体で持ちなさいと。国は広域的な事業に対して、公共交通の使命を果たしていくというのが、国の原則でありまして、2分の1豊前市が準備をし、全国に先駆けて珍しいような事業をすれば、補助金を一定程度1、2年ぐらい、会議費とか、そういうものは面倒見てあげましょうということですので、今のところ、この事業はなかなかクリアが難しいのではないか。 それから、交通空白地帯は路線だけではないではないかと、そういうものはどのようにするのかという部分は、これは、また政策の問題でありますから、どのように考えていくのかについては、私どもも路線だけ守ればいいということではないことは、私どもに責任があることは承知しております。今後、検討していきたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 78条バスでは、豊前は厳しいという意見を申し上げました。例えば、清田整形、黒土整形は協賛金を出してもいいという話を伺いました。例えば、行く所といえばショッピングセンターですね。それから病院・学校等であります。だから1000円1口の協賛金制度を設けたりして、今、足が悪くてもバスが遠いから病院に行けないという方たちをフォローして病院に連れて行く。黒土整形では自分の所で車を出して送り迎えしております。 そういった費用を市に提供して頂いて、その代わりに充実したバス路線を病院の前までする。こういった市の職員たちが各病院に足を運んで理解して頂いて、抜本的にこのバス事業を見直す。今のままでは、本当にバス路線から外れた人たちの足は、我慢するかバイクに乗ってけがをするか、高いお金を払ってどうにかしていくか、このような方法しかありません。ここで抜本的な見直しといったものを提案したいと思います。 最後に、緊急通報システムのことで質問いたします。先ほど45名の希望で4名ぐらいが対象者じゃないかという答弁でしたが、私は、千束の知り合いが、心臓に病気を持っておりまして、私がまだ議員じゃないときに、こういう通報システムがあるよ、市にお願いしたらどうかという話をしましたが、電話口まで行けるし、日頃、簡単にどうもないわけですね。それで装置のお願いはしませんでした。そして心臓発作を起こして亡くなってから4日後に発見されました。こういった形で生命には順番がありません。 そこで、この45名が対象外であるというのを、早急に判断するのではなくて、例えば県営住宅の方からも相談がありましたが、高血圧で2度倒れている。けれど市にお願いしたら、1年待ちだと言われた。寝たきりの人から優先だと言われたと。私は1年もしたら死んでしまうと話していましたが、倒れた方、また過去に、そういった発作を起こした方等を、現在は電話口に簡単に連絡できるかもわかりませんが、過去倒れたことのある人を、この基準の中に入れるような方法はないでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 福祉課長。 ○福祉課長 戸成保道君 救急通報につきましては、今ご指摘のとおり判断基準が難しい点があります。 先ほど申しましたように、一応、独居の方、重度障害者を対象に、一応、申請書がかなり出ています。中には健康だけれど不安だから申し込みたいという方も結構おられまして、議員さんご指摘のように、一度、心臓病等で倒れて、今後、倒れる可能性があるということであれば、そういう点も考慮してまいりたいと思いますが、現時点で、病歴等を申請時に一応調査に行きますが、そういう話が聞けるかどうかということもありますが、おっしゃられるように、そういう点を、これから考慮していきたいと思っておりますが、一応、非常に誤報が多くて、豊前市で言いますと14件中、3件の救急ということでありまして、豊前市も台数は増やしたいと思いますが、消防署の対応が常に誤報で受けるということがありまして、なかなか台数を増やしてない状態でありますが、順番についてのご指摘の分につきましては、これから考慮する対象にはなろうかと思っております。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 1週間前に消防署に視察に行きましたときに、誤報にどのように対処されているのか、誤報が多いわけですから、通報システムを持った方に、1人介護人といいますか、担当者をつけておりました。それで誤報の時には、その方に行ってもらうとか、こちらから連絡が取れないときには、その方に行ってもらうという形で対応しておりました。 先ほど言いましたように、申請書の中に過去倒れたことがあるとか、そういった項目を1つでも入れてもらうような形で対応を願いたいと思います。よろしくお願いします。 以上で終わります。 ○副議長 中村勇希君 鎌田晃二議員の質問を終わります。 これより関連質問に入ります。関連質問は1人答弁を含め10分以内であります。 関連質問はありませんか。爪丸議員。 ○4番 爪丸裕和君 尾家啓介議員の関連質問をさせて頂きます。まず、上下水道課長。公共下水道の受益者負担金の件で確認ですが、先ほど答弁の中で、敷地内に現状が農地であるならば、その分については除外するという答弁をされましたが、1筆の筆の中が宅地であっても、そのようなことでやられるということですかね。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 免除じゃございません。猶予ですから必ず払って頂くようなことになろうかと思います。 そのかかる前に畑にしても駄目です。将来的にずっと畑として利用した経緯がなければ、訪問して、その辺は対処して相手と協議して、賦課するかしないかを決めております。 だから賦課をする前に畑ということで畑をつくっても、それは猶予の対象にはならないようになっております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 地目で判断されているのではないですかね。一般に敷地の広いお宅だったら、ちょっとした畑をつくっているわけですよね。その面積分は本当に猶予期間をおくのか。これは確かに農地は宅地化されるまで猶予ということは確かうたわれていますよね。 先ほどの答弁の中では、地目が宅地であるにも関わらず現況で農地であれば、それだけの猶予をするのか、そこの確認なんです。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 広い所は1反から1反5畝ぐらいある宅地があります。実際、現地に行ったら畑としてずっと利用している所が、1軒か2軒ですけれどもあります。それにかけるということになれば、やはり本人にも負担がかかろうかと思いますので、それが宅地化されれば、その時点で賦課したいと、そういうことで上司の判断・決済を頂いております。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 過去そのまま受益者負担金を払ったところが、その時点で現況が畑だったから、それを一応、猶予を与えるということで今から戻しますか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 それは申請があって、はい、そうですかというわけではありません。行って払うのが高齢者で難しいという所ですので、現状的に過去を調べた所もあまり、ございません。 それが荒れていたら駄目です。いくら農地でも、それをちゃんと毎年つくった経緯がなければ、私たちは対象にはしておりません。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 申し訳にくいが、うちは畑が結構あるんですよ。当時はそうではなかったと思うんですよね。スタートした時点では。あのときは議員になってすぐのときに、例えば、駐車場なんか最初に市長に質問した経緯があるけれど、やはり家を建てるんじゃないから、特に駐車場なんかは、農地と同様にお願いできないでしょうかということを、お願いした経緯があるんですよ。その時は駄目だということで、あくまで条例を引っ張ってきた経緯があるから、宅地でも、そういったことは当時知らなかったんですが、スタート時点からそうだったですか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 それについては、やはり負担が大きくなるわけですね。個人の宅地で300坪も500坪もあればですね。やはり、そういうのは上司と相談していくらかでも猶予です。 将来的には払って頂くということです。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 市長が、特別と認めた場合というのが、当然うたわれているでしょうね。ちょっとその関連ですが、課長が言われたように500坪も600坪もあるような方がおられるわけです。こういったときに、条例設定は可能なのかどうなのか、その辺は。 へーベー500円としたら単純計算で、100坪のとき16万5000円程度ですね。だから、これが500坪もあったら80万円とか1000坪になったら160万円になるんですよ。どっかで頭打ちの上限設定というか、そういったものは可能かどうか。 ○副議長 中村勇希君 上下水道課長。 ○上下水道課長 川島和広君 設定の上限はありませんが、5000平方メートルを超えれば超える分については猶予という形が出てこようかと思います。最終的には、やはり払って頂くということになるかと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 それは猶予がいいことですね。それと財務課長、入札制度ですが、設計価格と入札予定価格の違いはどういうものですか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 お答えいたします。予定価格の決定方法については、地方自治法上には具体的な明記はありません。国の定めます予算・決算及び会計令というのがありまして、その中には、予定価格は、取引の実例価格・需要の状況・履行の難易度・数量の多寡・履行期間の長短等考慮して、適正に定めなければならないと規定があります。 また、一方で、建設業法の中には、原価に満たない金額を、請負代金に載せる基本契約を締結してはならないという1項もありまして、後、設計金額の一部を正当な理由なく控除するものについて、厳に慎むようにというような通達もきております。 当市において、予定価格を設定する場合は、以上申しました制約等十分考慮いたしまして、工事案件ごとに工事の箇所の状況とか、工事の施工方法、工事の技術的難易度等を十分考慮いたしまして、慎重に決定しているところであります。以上です。 ○副議長 中村勇希君 簡潔にお願いします。爪丸議員。 ○9番 爪丸裕和君 要は歩切りですね。率直に申します。歩切りはやってはならないと国の指導があります。当然、設計価格というのも、じゃ根拠なしに1000万円、2000万円の設計価格ができるかというとそうじゃないわけです。当然、ここの技術者出身は、川島課長と山下課長でしょうけれど、当然、県の積算価格というのがあるわけです。これは今、国交省と農林水産省と違いますが、その基準に、その中には例えば、掘削する床掘りのそのリューべというのは、何百円というのは漠然と出ているんじゃないわけです。 1日の8時間の労働時間の中から算出されて、すべて、そこにうたわれているわけなんですよ。その根拠の元に設計されて、それが仕上がってきたものが設計価格である。 本市は、それを歩切りすることによって、それを入札予定価格にするということは、今一般競争入札を導入した上で、私はフェアーでないということを申し上げておきます。 副市長、如何ですか。やるんであれば、当然、歩切りは国はやるなと言っているんですから、その元で闘わせるのが筋と思いますが、答弁を求めます。 ○副議長 中村勇希君 副市長。 ○副市長 後小路一雄君 いろいろ国から、そういう指導もあるようですけれども、これにつきましては、非常に難しい問題もございます。ちょっと検討させて頂きたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 爪丸議員。 ○4番 爪丸裕和君 できるだけフェアーに闘わせるようにお願いいたします。終わります。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。吉永議員。 ○17番 吉永宗彦君 午前中の尾家議員、午後の岡本議員の関連で、岩屋町における郵便局等について、お尋ねいたします。答弁しておりましたのは財務課長でしたので、財務課長からとりあえずご答弁頂きたいのですが、近年、本当に岩屋町を中心とする過疎問題が、非常に大きな課題になっております。それも年々過疎が進行し、特に気になる公共的なサービス機関が、次々に廃止されたりすることによって、町内皆さん方の不便、そして生活自体に及ぼす影響も日々大きくなっております。こういう状況の中で、岩屋町の皆さんから要望書が7月に市長宛に出されていました。 これは先ほど頂きましたので、この内容を読まして頂いていますが、簡易郵便局が運営のために、多額の自己資金も含めて改築費等を支出しながら、地域のこれ以上の過疎化が進むことに、歯止めをかけていると言っても過言ではないような、お仕事をしているという状況がありますので、是非、これについて執行部の答弁がありましたが、検討中ということですけれども、この岩屋町における過疎化の歯止めの関係、岩屋町に限りませんが、これはもう、そう長く日を見て考えるような課題ではないと思っています。 特に、要望で言われていますのは、豊前市に支払っております使用料、土地代金の貸付料を検討して頂けないか、ということのようでありますので、状況判断によって、最高責任者であります市長の裁量に委ねられるわけでしようが、あえて財務課長にご答弁頂きますのは、やはりこういう喫緊の課題について、市長のみならず幹部職員の皆さんが、一元的な考え方を持たなければ、なかなか進めないだろうと思うからです。 それぞれ、まちまちのお考えがあるかもしりませんが、対応するのは極めて重要だという認識から、一元的に考えておく必要があろうと思いますが、あえて財務にお願いしたいと思います。この要望に書かれております主旨については、申し上げる必要もありませんが、できるだけ早い段階で、ご要望に沿うように結論を出せる問題かどうかについて、ご答弁頂きたい。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 先ほどからお答えいたしておりますが、特に、過疎地の簡易郵便局を取り巻く環境は、大変厳しいものがあるということについては、私ども認識は一致いたしております。 これにつきましては、地元の区長会とも十分ご相談を頂きまして、早い段階でできるだけ前向きに検討したいということで、先ほど報告したとおりですので、よろしくご理解頂きたいと思います。以上です。 ○副議長 中村勇希君 吉永議員。 ○17番 吉永宗彦君 お二人の答弁、とりわけ岡本議員さんの先の質問・答弁と余り変わらない、その丸写しのように思います。豊前市は、海から山間地まで、こういう形態のまちでありますが、豊前市の文化というのは、求菩提山の修験場の思想を受け継いだ文化ではないか。 つまり豊前市住民の心のうちにあるDNAの中には、求菩提山を源流とする文化が脈々と脈打っていると言う人もおります。それだけに、豊前市における現状の過疎化進行状況については、豊前市こぞって、これに歯止めをして求菩提山文化を大切にする。 午前中、榎本議員も求菩提山に大変熱を入れて語られていましたが、ある意味で私も同感であります。そういう豊前市の過疎化の象徴的な、この岩屋谷、求菩提谷の過疎化に懸命に歯止めをかけて、地域の極めて不便な状況の中でも、必死に働き生きていこうとする住民の皆さんのご要望でありますので、是非とも、これは1日も早い前向きな決断をして頂ければと私も思っています。 この要望書は執行部に出されておりますが、後ほど議長ともご相談して、議会でも、この主旨をどう生かしていくのか、ご相談してみたいなと思っておりますので、あえて市長答弁は頂きませんが、どうぞ市長も含めて、積極的に前向きな協議を進めて、できるだけ早い段階で安心して頂けるような方向を示して頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。渡邊一議員。 ○11番 渡邊 一君 私は、榎本議員さんの固定資産税の引き下げについての関連で、市長さんにお尋ねいたします。市長のご答弁の中で、本当に心強い合併を見据えた、要するに1000分の14をにらんだ意欲のある答弁だと、私は高く評価したんです。それに関連ですけれども、尾家議員の質問の中にもありましたが、今4億円ぐらい財政がよくなったという話でしたね。これは団塊世代の退職者が出たということが、大きな要素だと理解してよろしいでしょうかね。そうだとすると、これは合併の行政改革によるメリットは、かなりのものが想像できると、そのとき思ったんですよ。 だから、なんとしても、合併は一生懸命やろうという市長の意欲が感じられて、本当に嬉しかったんですが、その関連で、この辺の自動車産業の定着に、非常に大きな役割を果たすであろう周防灘沿岸開発の推進組織が出来上がっているように新聞に載って、ちょっと前に会議があったようですが、その内容を、お知らせ願いたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 8月の終わりに行橋で、今、会長が行橋の市長でありますが、前は周防灘臨海線道路推進協議会でしたが、今は名前が、周防灘湾岸線道路建設推進協議会と変わりました。 ただ東九州もしている、また海岸もするのかというようなことを言う人もいますが、もう30年ぐらいしていますが、継続してやろうというような方向になりました。 もう中座するということじゃなくて。それ以上のことは、まだ新しい動きがあれですが、特に、一番、山国川の中津から吉富からの道ですね。この関係の先が不透明になっているかなと思っています。 ○副議長 中村勇希君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 私は、今こそ、これを大きく推進する時期だと思うんですよ。おっしゃるように、東九州縦貫道が、まだはっきりしてないときには、これはやはり同じような路線を2本つくるということで、かなり抵抗が建設省にもあったと思います。ところが東九州縦貫道は、全部目安がつきました。ご承知のように、ここでは用地買収が個人的に入ったと思います。 ということは、全部予算の目安がついたということですよ。そうなってきますと、やはりこの辺を工業地帯で定着させるためには、産業道路がどうしてもほしい。 中津とダイハツとトヨタ・日産を結ぶきちっとした産業道路、それで、この辺が大きく伸びるかどうか命綱みたいな道路だと思います。今、声を大にして、ちょうど自民党の総裁選挙が明日から始まります。22日に決まります。総理大臣が24日に、おそらく決まるのじゃないでしょうか。福岡から大きく麻生先生が、今、産声を上げようとしています。今ここで声を上げるベきなんです。 ですから、是非ひとつ市長、あらゆる知恵、あらゆる人間をしぼって、これに邁進しようじゃありませんか。そのためにも、合併は非常に必要だと思いますので、もう1回、力強いご答弁をお願いします。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 西の方は築城基地がありますから、それをどうもぐるのか、上のほうに行くかですけれども、問題は、一番やはり中津から吉富が100億円かかりますから、それを大分県は厳しいようですが、福岡県がフィフティ、フィフティ見るということですので、吉富の位置がポイントだろうと思います。 ○副議長 中村勇希君 渡邊議員。 ○11番 渡邊 一君 もう1回、築城基地の問題が、ちょっと弊害になるような気がしますが、なに大したことありませんよ。 ○副議長 中村勇希君 申し上げます。よろしいでしょうか。固定資産税の件に関する関連質問でありましたが、今まで聞いていましたが、ちょっと関連とはなってないようなので、湾岸道路に。 渡邊一議員。 ○11番 渡邊 一君 そうですかね。産業道路がこういうことにつながるんですよ。こういう仕事にね。 若戸トンネルが上から載せていくんですよね。半分出来上がっているというんです。 築城基地をもぐるなんか、わけないと思います。頑張りましょう。以上です。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 鎌田議員の関連質問をさせて頂きます。先ほどから、執行部の答弁では、市の行政の仕事を随分とシルバー人材センターに委託されているという話がありました。 確かに、個人であればシルバーであれば、言い方は悪いですが、安上がりにあがるとかいったことでされているのじゃないか。確かにシルバー人材センターの方々は、経験豊かな方で大いに利用するのは結構なんですが、行政があまりそこまで利用しますと、若者が育たないじゃないか、後継者が育たないじゃないかという心配が十分に考えられます。 行政の場合は、後継者育成で、もう少し考えて頂いて取り組みされるのも必要じゃないかと思いますが、市長、その辺どうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 ヤング人材センターという組織もあります。八屋のほうにですね。まだそっちのほうは余り活躍してないようですので、頑張ってもらわなならんなと思っていますし、当然、若い人は、今、有効求人倍率は1.0を超えましたので、なかなか人の問題は厳しい面があるけれども、もっともっと馬力を出して頂きたいということで、先ほど言った組織も活用していきたいなと思います。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 そうですね。そのようにして頂かないと、本当に若者が豊前に帰りたくても仕事がないということが起こると思うんです。確かに行政は、私が勝手に思っているのかも分かりませんが、安上がりのためにシルバーに頼んでいるのではないか。そういったことは民間ならまだしも、行政の場合はやめるべきだと。極力、若者の育成のために、市長を中心にして頑張って頂きたいと思います。 それから、もう1点お伺いします。ふるさとサポートセンターというのが、先ほどご答弁の中で100万円のお金を出しているという話を聞きました。何処の課が、どういった仕事をされているのでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 ふるさとと言ったかどうか、ちょっと覚えてないんですが、子育てサポート支援事業ということで、ご答弁したつもりだったんですが、訂正させて頂きます。子育て支援で、それについてはシルバーに委託している事業で、シルバーの方に一時預りをお願いするという事業であります。以上です。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 その事業費が100万円ですか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 当初予算で100万円を付けております。20年度も100万円付けております。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 どういった仕事を主にされているのですかね。 ○12番 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 一時預りした場合に、時給あたり880円だったでしょうか、はっきり覚えてないんですが、その2分の1を市が助成するという事業でございます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 榎本議員。 ○4番 榎本義憲君 先ほどの話と同じで、やはり全てがシルバーなんですね。やはり、これは根本的に市の執行部が中心になって改めて頂くのが、大事じゃないかなと思います。 私の聞き違いだったんでしょう。そういうことであれば、それなりに必要なんで大丈夫だと思いますが、その辺は今後、十分考えて頂いて取り組みをよろしくお願いします。 終わります。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 榎本議員の関連で質問いたします。ちょっと恥ずかしい話ですが、もしありましたら結構ですので。施設の案内役という形で育てていきたいという話がありました。 それで、もしこういうことをやっておりましたら結構です。豊前市検定という形で、豊前市の歴史とか観光の案内という形で、小学生から何歳でも結構ですが、よく琵琶湖検定とか、各自治体でやられております。例えば100点満点中、90何点の人は1級とか、そういった形で80点以上は2級、という形で取り組んでいる自治体がありますが、豊前市はされているでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 史跡ガイドボランティアの組織はありますけれども、そういう検定制度を設けた上でのボランティアにはなってないじゃないかと、検定をしているとは聞いていません。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 それでは、こういった文化施設の案内とか、また豊前市を詳しく知って頂いて、観光名所といったものを郷土に詳しい方に問題をつくって頂いて、福祉センターかどこかで試験を募ってして、合格者には何らかの市長からの話があるとか、また、検定1級の方は、ガイドとしてお願いするとか、そういった形で豊前市自体を知って貰う意味でも、ものすごくいいことじゃないかと思いますので、こういったことをやられてはどうでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 釜井市長。 ○市長 釜井健介君 今やっているのが、市の美術展には絵・書画・写真・彫刻に応募して賞状を渡しています。今、議員が言われた件は、まだいってませんので、写真も絵も相当、地元で描いていますので、ちょっと市民展も5回になりますので、加えてやれるかどうか検討してみたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 鎌田議員。 ○2番 鎌田晃二君 3日ぐらいの前の新聞に載っていたんですが、我が郷土のこういった検定をすることによって、文化施設とか文化財、いろんな面を勉強して頂いて小学生5、6年の方が、かなり合格者が出ておりました。そういった形で、豊前市もこういった検定を導入してやったら、また楽しいんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。 (「なし」の声あり) それでは、これをもって今定例会の一般質問を終わります。 日程第2 議案第60号から議案第77号までを一括議題といたします。 議案に対する質疑に入りますが、今回は質疑の通告がありません。よって、これをもって質疑を終わります。 只今議題となっております各議案につきましては、お手元に配布の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 日程第3 意見書案第4号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。吉永宗彦議員、お願いいたします。 ○17番 吉永宗彦君 今議会ただ1つの意見書案の提案でございますが、お手元配布の資料、意見書案を一部朗読して提案理由の説明にかえます。意見書案の前段の文章の後半部分から入ります。 2009年度予算は、深刻化する地域間格差の是正と、公共サービスの充実に向け、地方財政圧縮を進める政策の転換を図り、地方税の充実・強化、国が果たす財源保障に必要な財源を確保することが重要です。更に、住民に身近な所で政策や税金の使途を決定し、地方分権の理念にそった実際運営を行うことができるよう、地方財政の充実・強化を目指し、政府に対して次のとおり求めます。3項目ございます。 1番、医療・福祉・環境・ライフラインなど、地域の公共サービス水準の確保と、地方分権推進に向けて国・地方の税収配分5対5を実現する財源移譲、地方交付税機能の強化により地方財源の充実を図ること。 第2、自治体間の財政力格差は、地方間の財政調整によることなく、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化により是正を図ること。 第3、地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を行うこと。 以上、意見書案の説明をいたしました。ご審議の上、採択頂きますようにお願い申し上げたいと思います。採決後は、内閣総理大臣ほか関係閣僚に意見書を送付ということになります。どうぞよろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑の方はありませんか。 (「なし」の声あり) これをもって質疑を終わります。 只今提案されました意見書案第4号につきましては、総務委員会に付託いたします。 申し上げます。以上で本日の日程は終わりました。 以上をもって、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。 散会 15時06分 |