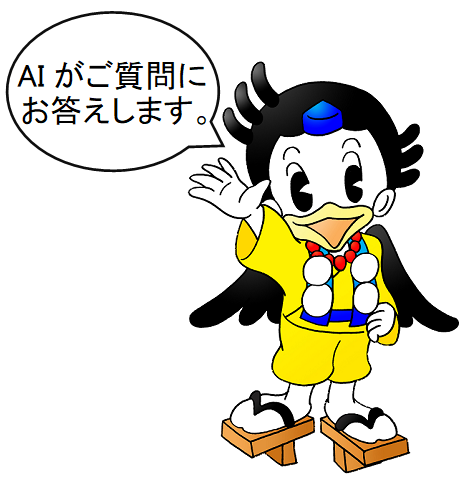麻しん(はしか)の流行について
令和7年8月以降、福岡県内で麻しんの発生が継続しています。
令和2年以降、麻しんの報告数は全国的に減少傾向が続いていましたが、令和5年以降、国外における麻しん流行に伴い、新型コロナウイルスの流行による人の往来の制限が解除されたことで、海外からの輸入症例が増加し、国内で感染を拡げる事例が見られます。
麻しん(はしか)とは
麻しんは、麻しんウイルスによる全身感染症で、空気感染(飛沫核感染)、飛沫感染、接触感染によって感染伝播します。麻しんは感染力が非常に強く、ワクチンを一度も接種していない等、免疫を持っていない方が感染するとほぼ100%発症すると言われています。麻しんの免疫がない集団に一人の発症者がいたとすると、12~14人が感染すると言われています(インフルエンザは1~2人)。
症状
感染すると約10~12日間の潜伏期間の後、発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが出現します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、稀に脳炎を引き起こし、重症化した場合先進国であっても1,000人に1人死亡すると言われています。
その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、数年から十数年後に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる知能障害や運動障害等が進行した後、数年以内に死に至る中枢神経疾患を発症することもあります。
発熱、咳、発しん、鼻水、目の充血等、麻しんに特徴的な症状が現れた場合は、医療機関に電話で連絡し、指示に従って受診をしてください。
※医療機関へ移動される際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。
治療
特別な治療法はなく、症状を軽くするための治療がなされます。中耳炎や肺炎などの別の病気に同時にかかってしまった場合には、抗菌剤を投与する必要があります。
麻しん患者と接触した後、72時間以内に麻しんを含むワクチンを接種することで、発症を予防できる可能性があります。
予防
麻しんは空気感染するため、手洗いやマスクでは予防できないため、予防接種が有効です。
MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では麻しんへの抗体が充分に産生されなかった方の多くに免疫をつけることができます。
定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合やご自身の免疫が不十分なことが判明した方はMRワクチンの接種をご検討してください。
【定期予防接種対象者】
・第1期/生後12か月~生後24か月未満(2歳になる前日)までに1回接種
・第2期/小学校就学前の1年間(年長児)に1回接種 (対象:平成31年4月2日~令和2年4月1日生)
【接種期間延長対象者】
国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、MRワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種が出来ない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。豊前市におきましても、国の方針に基づき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長します。
・第1期/令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方(令和6年度内に生後24か月に達した方)
・第2期/平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方(令和6年度の2期対象者)
・第5期/昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに風しんの抗体検査を実施し、抗体が不十分であった方。(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)
〈接種可能な期間〉
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
リンク
・麻しんの感染症発生動向調査:国立健康危機管理研究機構 感染症発生動向調査(IDWR)
・麻しん(はしか)とは:厚生労働省
・麻しん(はしか)に注意しましょう:福岡県HP