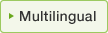ここから本文です。
為藤五郎
(明治20年2月1日~昭和16年7月4日)
教育ジャーナリスト。「教育週報」創始者。
|
比類のない教育ジャーナリストとして活躍し、初等中等教育者の灯明台「教育週報」を創始した。 氏は三毛門村(町)久松の貧しい農家に生まれた。父は勘来、母タケの次男。豊津中学に1,2番の成績で進んだが、1年生の終わりごろ、ちょっとした病気で退学した。明治35年、郡立准教員養成所を経て翌年秋、福岡師範学校に入学、1年生の寄宿舎生活でいわゆる師範生気質の悪弊を強く感じた。 4年生の時、早くものちの名ジャーナリストを思わせる文才溢れる評論、文学論、人物論などを中央の「中学世界」「文学世界」などに投稿し、多くの入選を果たした。 明治41年、東京高等師範学校図工専修科に入学した。同校を卒業して小倉師範学校に1年、鹿児島師範学校に3年在職した後、図工教師の職をなげうって上京した。すでに2児の父であった。 東京日日新聞の記者を経て、大正6年、博文館に入社、「中学世界」の主筆となった。これからは水を得た魚の如くジャーナリストの世界に氏独特の才能を発揮した。「中学世界」は4年後に発行部数が倍増した。 大正11年、博文館の当時日本一の総合雑誌「太陽」の編集長となったが、大正8年にはじまる母校の文理大学昇格運動の副委員長として東奔西走したため、在職1年で辞任した。昭和4年に昇格は実現した。 大正12年には「教育の世紀社」、翌13年には「児童の村小学校」の創設に参加し、14年、氏は生涯の大事業「教育週報」を創刊した。日本最初の週刊教育新聞で「飽くまで全教育者の味方となってその良港となる」ことを期し、初等、中等の新しい教育に関心をもつ者に情報と助言を提供し、まさに教育の民間パイロットの役割を果たした。 昭和16年、彼の没後も従兄弟十郎が戦時の困難の中に週報を守ったが、19年の出版整備によりその輝かしい歴史を閉じた。前後20年、947号を記録した。 氏の多くの論文や著作の主要なものはすべて外部からの教育の改革をめざしたもので、大正13年以後の政治活動もその中心は教育改革であった。13年、安部磯雄らと政治研究会を組織し、15年には社会民衆党結成に参加した。昭和3年以後、衆議院議員に2度出馬して惜敗したが、東京府会議員3期、東京市会議員1期当選を果たした。その後の活動を期待されながら55歳で病没した。
(本稿は豊前市史を転載したものです) |