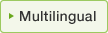ここから本文です。
久保晴
久保晴(1898~1985)
|
「久保晴」は俳号で本名は久恒貞吉。三毛門小犬丸生まれ。 地元俳壇では「鴎」「数の子」「我等」「新大陸」「俳句文学」「春潮」「めかり」等に所属。中央俳壇では「旗艦定位」「風流陣」に参加し、戦後「夏草」(山口青邨主宰)「若葉」「冬草」に参加。 「先帝祭句集」は昭和59年2月、久保晴が赤間神宮に奉納した自著句集である。昭和初期より戦前、戦中を経て戦後までの333の句は同氏の俳句道の集大成である。 一切は空即色木の実落つ |
|
|
芭蕉の俳句は生きた宗教であり、一条の道である事を教えてくれた。私の俳句は、神事を通じて始まり、神事は私の生涯修行の道場と。それかあらぬか「お祭晴」の別号までいただいたとか。 和布刈火や轉 (うた)た傾く峡(かい)の海 燃えさかるたいまつが関門海峡1200年の伝統を照らし出す旧暦の元旦にあたる未明、小雪の舞う海峡でワカメを刈る古代儀式「和布刈神事」が、かま、おけ、たいまつの炎が躍り燃え尽きるまで新ワカメを刈り神前に供える、そのときの句である。いまも和布刈神社境内に句碑として建てられている。 先帝祭句集を終え40日ばかり後、氏は俳句人生の生命を燃焼しつくされた。87歳。 |
|