 |
 |
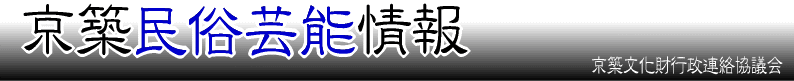 |
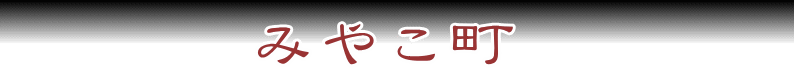 |
生立八幡宮神幸祭
(おいたちはちまんぐうじんこうさい) |

|
| ■起源 |
平安時代中期? |
| ■内容 |
生立八幡宮は神功皇后が三韓出兵の帰路、現社地付近の大村立屋敷に立ち寄られた際、生後間もない皇子・誉田皇子(のちの応神天皇)がそばにあった二子石を支えに立ち上がったという奇跡に因み、社を建てたことに始まるとされています。その後治暦三年(1067)に現在地に社が移されたことに伴い、年に一度旧社地に還御して神霊のみあれを行うようになったことから神幸祭が始まったとされています。
神幸祭は3日間からなり、初日は「御潮井採り」と呼ばれ神輿や山笠の清めや試し担きか行われます。2日目は「お下り」で神霊が神輿に移されて大村立屋敷へ渡御し、神事が行われます。このとき神輿に供奉する飾物としての山笠が動座し、馬場(神前の広場)は山笠衆の熱気で興奮に包まれます。夜は岩戸神楽が奉納され、「夜市」とよばれる夜の出店の賑わいも祭りの風物として知られています。3日目は「お上り」で神霊が神社へ還御されますが、このときにも山笠が供奉し、もう一度馬場が熱気で包まれます。山笠の動座終了後、神輿が神社へ還御し、祭典が行われて祭りの全日程が終了します。
この祭り第一の注目は、神輿に供奉して奉納される山笠で大きく曳山(2基)と舁山(6基)の2種類があります。その規模はいずれも縦方向12m・横5m・高さ20mほどで重量は3.5トンほど。この山笠を100人ほどの人数が全力で担ぎ上げ(あるいは曳く)ますが、その迫力は圧倒的で、担ぎ上げの気合の大声が馬場一帯に響き渡ります。 |
| ■交通 |
車 JR行橋駅から車で 約20分
JR 平成筑豊鉄道「犀川」駅から徒歩約10分 |
| ■文献 |
『犀川町誌』犀川町誌編纂委員会編 犀川町発行 平成6年 |
|
|
 |
| 【奉納日程】 |
| 場 所 |
日 程 |
奉納時間帯 |
備 考 |
| 生立八幡宮・禊場(今川河畔) |
5月第2日曜前々日
(初日) |
16:30 ~ 17:30 |
御潮井採り(神輿) |
| 生立八幡宮馬場 |
5月第2日曜前々日
(初日) |
18:00 前後 |
御潮井採り(山笠) |
| 生立八幡宮馬場 |
5月第2日曜前日
(二日日) |
15:00 ~ 17:00 |
お下り |
| 大村立屋敷御旅所 |
5月第2日曜前日
(二日日) |
16:00 ~ 16:30 |
立屋敷神事 |
| 生立御旅所 |
5月第2日曜前日
(二日日) |
19:00 ~ 21:30 |
岩戸神楽 |
| 生立八幡宮馬場 |
5月第2日曜日
(最終日) |
15:00 ~ 17:00 |
お上り |
|
|
|
|
|
|
〒824-0121
みやこ町豊津1118
みやこ町教育委員会
Tel:0930-33-3114 |
  |
|
 |
 |