豊前市の岩戸神楽(大村神楽講)
(おおむらかぐら) |
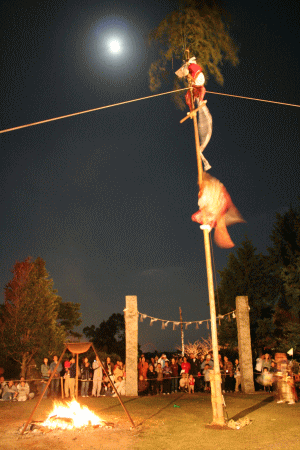
|
| ■起源 |
不詳 |
| ■内容 |
大富神社の社家、清原家によって伝授されたのが大村神楽です。その境内にある「大村神楽講百年祭記念碑文」には景行天皇の時代から神楽が奉納されていると記されていますが、それはそれとして、古く豊前の神楽は大富神社の相職であった清原家、長谷川家を中心に神職による神楽の奉納が行われていたと記録に残されています。その成立は少なくとも中世にまで遡り、社家神楽として盛んに奉納されていました。そして、明治一〇年頃に大富神社宮司清原司から、氏子である大村局九市、平木孫市、大久保新一などに伝えられ大村神楽講として発足したとされます。こうした氏子は、社家神楽の時代に神職が神楽奉納をする時にその補助者として奉納に関わっていた人物と見られ、「ホシャドン」と呼ばれていた人たちと考えられます。その後、大村神楽講の名は各地で知られるようになり、北九州地区を初め明治神宮や伊勢神宮、朝鮮半島にまで招聘され公演を行ったといいます。戦時中は一時その運営に苦労した時期もありましたが、昭和30年代以降は豊前を代表する神楽講として活動を続けていて、子ども神楽の指導を通じて若手の育成にも取り組んでいます。大富神社では毎年、正月元旦の日付が変わるとともに「湯立神楽」が奉納されます。燃え盛る炎の中で演じられる幻想的な舞は、まさに新しい年の初めを祝うにふさわしいもので、豊前の夜神楽を代表する光景です。 |
| ■交通 |
車 豊前市内へは、東九州道「苅田北九州IC」から国道10号線で50分 大分道「日田IC」から国道210号線で70分 |
| ■文献 |
|
|
|