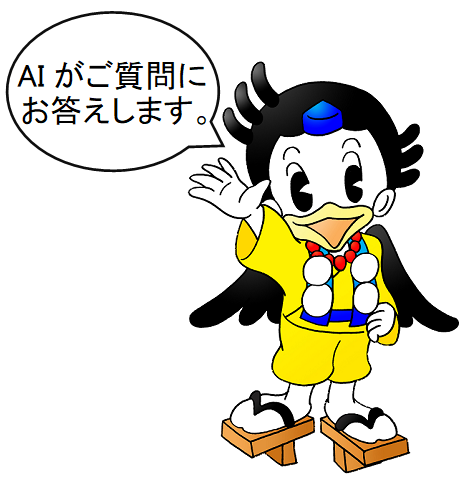議事録(平成19年3月13日)
| 平成19年3月13日(3) 開議 10時00分 ○議長 秋成茂信君 皆さん、おはようございます。 只今の出席議員は13名で定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 日程第1 一般質問、2日目を行います。初めに渡邊一議員、お願いいたします。 ○6番 渡邊 一君 皆さん、おはようございます。通告に基づき質問をさせて頂きます。 まず、最初に、吉富町との合併勧告を受けて、両議会で、合併協議会の設置議案を可決できました。合併に関しては、いろいろなご意見があると思いますけれども、新聞記事を見ますと、おおよそ市民の皆様方に合併の大切さ、何故、合併しなければならんのか、ご理解がだんだん進んでいるのではないかと思います。 と申しますのも、各新聞の記事を見ますと、豊前市議会が6日に議決いたしましたが、その翌日の7日の西日本新聞を見ますと、豊前市議会が法定協設置案可決、そして、市長はかねてからおっしゃっていますように、豊築は1つという理念に1歩進んだ、と大きな見出しで書かれております。なお、今度10日の西日本の朝刊には、9日の吉富町の議決に伴いまして、中家町長、前向き姿勢、そして、豊前市との合併問題前進と大きな見出しが出ております。これは、いずれも地域の方々の合併に対する気持を表しているのじゃないかと思います。 そこで、市長にお伺いしたいのですが、その中で、いろんな角度から議論していきたいという発言をなさっておりますけれども、いろんな角度ということを、もう少し具体的に市民の皆さん方に分かりやすく説明して頂きたいと思います。そして、豊築は1つに1歩前進したという意欲を、もう少しここで、今日は、幸いに傍聴席にもかなりの方がおられますので、披瀝して頂くとありがたいなと思います。そして、はずみをつけて頂きたいと思っております。 合併問題については、昨日もいろいろ議員の方がおられました。どういうことがよくなるか。例えば、古川議員の説明にあったように、今ここは自動車産業という形に取り組んでおります。その中で、新しい工業団地の増設は急務だと思います。それが合併の機運に大きく前進させなければならん。また、できると思います。担当課で県と、今かなり具体的な協議を進めているというような答弁でございましたが、10日の読売新聞ですけれども、県合併支援室では十分議論を尽くして欲しい。県としても協議の中で助言をし、合併後の財政支援をしていきたいというふうに記事が出ております。 この際に、いろいろなことを市長さんがおっしゃっていますように、いろいろな角度から、この地域が大きく発展を目指して議論を進め、県ともどんどん打ち合わせしながら進めていく今が大きなチャンスだと思いますので、是非、頑張って頂きたいと思います。 後は自席からの質問といたします。 次に、通告しております教育問題でございます。今、日本の国は、特に、安倍内閣になりましてから非常に学校が荒れている。そして、自殺その他が多い。悲惨な社会現象がある。大きく教育を変えないかん。特に、塾その他の問題の弊害も出ていることですから、公教育、小・中学校の教育をしっかり見直そうじゃないか。そのためには、教育委員会そのものの形骸化が今言われていますが、それをどうするかということも、大きな議論の対象になっております。そこで、教育基本法の改正の成立を受けて、私はこういう事件がありますので、これを紹介して市長の見解をお伺いしたいと思います。 福岡県教育委員会は、去る6日、筑前町の三輪中学校2年の生徒が、いじめを苦にした自殺問題で、1年生の担任教師48歳、指導、監督責任を怠った校長52歳を、それぞれ減給10分の1、1ヵ月間の懲戒処分にした。また、2年生の担任教師44歳と、教頭52歳を戒告としたという処分の発表がありました。処分が軽過ぎるとか重いとか、いろいろ議論はありましょうけれども、このいじめの問題で教育委員会が処分した。要するに何かの行動を現実に起こしたということは、初めてじゃないかと思います。 それが証拠に、記事の中で決定が遅れたことは、県教育委員会教職課は、前例がなく、処分の妥当性についての意見の整理がつかなかったとしている。いじめに対する初めての処分だと私は思いますけれども、市長の職務からは教育委員会は独立しているわけですが、今、教育委員会がいろいろ問題になっております。この処分に対して、市長は、どういう感想をもっているかということを、まず、お伺いしたいと思います。 次に、教育長さんにお伺いします。改正教育基本法が、昨年12月15日に成立して、22日に公布・施行ということになっております。そして、教育再生会議を安倍内閣に立ち上げまして、第1次報告書を1月24日に発表しております。 その中で、社会総掛かりで、公的教育再生への第1歩というふうに位置付けているようです。内容はゆとり教育を見直し、学力を向上する。そして、荒れた学校を再生し、安心して学べる規律ある教室にする。また、教育委員会のあり方そのものを抜本的に問い直す等々の提言がなされておるようです。そして、いじめ問題への対応として具体的には、教員免許更新制の導入、これは前から言われていることでもありますが、改めて、ここにはっきりうたってあります。 それから、今後の検討課題としては、教員免許を国家試験にしたらどうか。そして、学校週5日制の見直し等が盛り込まれているようです。それを受けて中教審で、今、喧々諤々の学校教育法改正案、教員免許法改正案、地方教育行政法改正案等の審議が始まっておるところでございます。この第1次報告を、教育長さんも既にご覧になっていると思いますけれども、まだまだ、これから国会にかかって決まるのには時間がかかると思いますが、この際、大きく教育を変えなきゃならんという認識は、国民にあるところだと思いますので、これを機に教育長としては、現場からこういう教育委員会であって欲しいんだ。 学校の先生は、やはりいい先生が欲しい、そのためにはこういうことが必要だ。要するに教育再生会議に現場の教育長から提言をするという気持で、それらについてのあなたのお考えをお伺いしたいと思います。 次に、担当課長にお伺いいたします。具体的に伺いたいのですけれども、荒れている学校現場と言いますけれども、豊前市ではどんなふうでしょうか。まず、中学校の荒廃が問題になっておりますが、ある中学校の卒業式に2、3年前ですが、刑事さんが卒業式においでになっていました。それから、最近、私の所のつつじ祭りをする神社に3、4人たむろして、中学生が拝殿の神殿の中に入って、たばこを吸いながら何を話しているか知りませんけれども、大体よからぬ相談をしているのじゃないかと思いますが、管理する地域の人達は本当に困っているということもあるようです。 それから、校内の荒れが中学校から低学年になってきて、小学校の高学年の生徒までが、先生に暴力をふるうということも耳にします。そういう、今、豊前市内の小・中学校の現状を具体的に説明してほしいと思います。 それから、学力向上にいろいろ県教育委員会もやっているようです。まず、最近は、福岡県と4県で学力調査したというのがありますね。その結果が、我が豊前市ではどんな結果だったのか。その辺を担当課長より説明頂きたいと思います。 以上、壇上において質問として、後は自席で細かく質問していきたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 それでは、渡邊一議員のご質問の中で、2番目の教育基本法関係の答弁を教育長、学校教育課長から答弁いたしますが、私はご指名でございますので、吉富町との合併の問題、そして、いじめに対する考えを壇上で、まずさせて頂きます。 今、議員が言われた点は、3月10日の読売新聞ですね。こういうふうに書いていると思います。既に6日、市議会が同設置議案を可決している豊前市では、釜井健介市長が県東部地域の発展のため、交流が深い吉富町との合併は必須条件、未来志向で様々な角度から議論すべきだと思うと意欲をにじませたと。この件を言っているだろうと思います。 様々な角度は、どのような点かと言いましたら、私としては4点あるだろうと思います。 まず、第1点が、財政問題、これは今、全国何処も財政が大変であるし、税収の厳しい所は合併しようが、しまいが大変な状況であり、本年度の予算は組めても、来年から組めない所は、全国すごい数の自治体になると思います。 お隣の吉富町は、今から30年前、不交付団体、九州でも一番金持ちの町でした。 吉富製薬は素晴らしい馬力でよかったんですが、最近は、なかなかそうじゃない時点もあるわけで、イメージとして、吉富は財政がいいぞというのが相当変わって来ておりますので、吉富の財政状況は本当にどうなのか。豊前市の財政の状況はどうなのか。この財政が厳しいから合併という国の方策を受け入れながら、自前で頑張っていこうということでございますので、まず、財政の問題について、とことん議論していきたいと思っております。 2番目は、福岡県の兼ね合わせでございます。福岡県の一番東の端が吉富、その横が豊前市、今まで行政の光が一番当たらない所、言い方は悪いんですけれども、築上郡の当豊前市は、福岡県のチベットということを、筑豊の人から言われるようなことがあったわけですけれども、今、自動車150万台の推進の中で大きく変貌している中で、大きな所につく前に一番身近な所と腕を組む。それに福岡県が、がっちりと3つ目の腕を組む。 これが豊前市と築上郡の幸せのために、一番いいだろうと思いますので、この点の県を絡めての議論、これが2番目でございます。 3番目が、今、吉富と豊前は13ぐらい、いろいろ共同事業をしております。 中学校もそうです。ごみも八屋のほうに持ってきております。そして、広域消防も勝山から大平・吉富まで一緒、豊前市が中核でございます。そして、介護保険で適応教室や13ぐらい一緒にしているわけでございますので、お互いの行政の中で、吉富との共同作業が大きなポジションを占めておりますので、この件につきまして、今は合併したらどうなのかという議論をしていくべきじゃなかろうかと思っております。 4番目として押えたいのが、合併新法における対策は講じられるのか。これが吉富として一番欲しがっている1番の課題は、中津から吉富にかかる山国川の橋の関係でございます。そして、もう1つ、中心街の道路を全部つなぎながら、新しい町の変貌を吉富は考えているわけでございます。 豊前市は、今、一番欲しがっているのは工業団地、特に、豊前東部工業団地の下の方は吉富の土地を持っている方もおるわけでございますので、是非、この合併新法における対策は、特別に講じられるかということを、いろいろな角度から追及していこうと思っております。後いろいろありますけれども、この4点が、今、私が思い浮かべるところでありますので、渡邊議員はベテランでございますので、また、ご指摘・ご質問して頂ければと思っております。 次に、いじめ問題でございます。筑前町の処分、大変重く大変厳しい状況、先生方も萎縮するような状況かなと思っておりますが、ある面は、1つの区切りかなと思いますが、もう一方としまして、我が豊前市も10年前に角田中学校の問題で、3年ぐらい苦労しました。しかし、一応、親御さんの、ご理解・ご了解のもとに、いじめのない教育を進めていく。そして、市民啓発をしていくということで、今、年に1回、2回の集会もして続いております。そして、また一番大事なことは、市議会の皆さんと1年間、苦しい思いをしながら、角田中学校のいじめ問題の解決のために、この場で決議をして、親御さんの方もひと安心していることが、終わりまして8年になるわけでございます。 このいじめ問題は、何処でも誰でも起こることでございます。行政当局者として逃げることなく、子ども達のために立ち向かっていき、優しさをもって、そのような町が一番これから望めるわけでございますので、これは是非、県下いろんな関係のご相談がありましたら、豊前市の経験を申し述べたいと思っております。 以上、私の壇上からの答弁にいたします。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 渡邊議員のご質問に回答を申し上げます。議員がおっしゃるように、第165回臨時国会におきまして、改正教育基本法の成立がありました。それを受けまして、文部科学省は関係法令の改正及び基本方針の企画・立案等に着手しています。文部科学省の大臣の諮問機関であります中央教育審議会は、3月10日に教育職員免許法、地方教育行政法、学校教育法の3法の改正案について、文部科学省大臣に答申したところでございます。 これからの国会で審議されるわけでございますが、正式に法改正がなされれば、豊前市教育委員会といたしましては、法に従い諸施策を実行していきたいと考えております。 最初に、ゆとり教育を見直し、学力を向上するということを申されましたが、今から約20年ほど前の臨時教育審議会でも、このことについて論議されていました。今度は、ここで、ゆとり教育を見直すという形になっているわけでございます。随分と教科書のページ数も薄くなりましたし、学習する時間数も学校5日制で少なくなりました。 従いまして、学力を向上するということになりますと、いわゆる、学習時間数を増やさなければならない。今の5日制の中で増やすとなると、例えば、夏休みを少し少なくして授業時数に充てるとか、或いは、5時間で授業が終わっているのを6時間目までするとか、ということなどが授業時数を増やすという形では可能ではないかと考えております。 国では、今の授業時数よりも10%増やすようなことも考えているようでございます。 その10%というのが、今申しました夏休みとか、或いは、放課後の時間を有効に使うとかいうようなこともあろうかと思います。 それから、学校を再生して、安心して学べる規律ある学校ということでございますが、先般2月5日付で、問題行動を起こす児童・生徒に対する指導について、という通知が文部科学省から県教委に来て、県教委から地教委にあったところでございます。先日の校長会で、その文書の中身は、各学校長宛に配布したところでありますが、大きくは、1つは、生徒指導について、先生方1人ひとりがきめ細かな指導を行って、積極的に教育相談やカウンセリングに当たるということ。また、児童・生徒の規範意識の醸成のために、各学校はいかに暴力行為等に関する、いじめや暴力行為等に関する決まりや対応の基準を、はっきりとしたものをつくって、保護者や地域に公表し理解や協力を得る。特に、校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性のある場合は、学校だけで抱え込むことなく警察に通報し、その協力を得て対応するということが、生徒指導上では大事であるというふうに通知があっております。 2つ目には、出席停止制度というものがありますが、これを活用するということであります。出席停止は懲戒行為ではなくて、学校の秩序を維持し、他の児童・生徒の教育を受ける権利を保障するための措置でありまして、教育委員会や学校は、この制度の主旨を十分に理解して、日頃から規範意識を育む指導や教育相談を行う。また、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童・生徒に対し、正常な教育環境を回復するために必要と認める場合には、教育委員会は、出席停止制度の措置を取ることを検討する。これが最終的な手段と考えております。この措置の運用に当たっては、教師や学校が孤立することがないように、校長や教職員、教育委員会や地元・地域のサポートによる必要な支援がなされるように十分配慮すること。 大きく3つ目には、懲戒・体罰について新しく見解が出されております。 1つは、身体に対する、なぐる、蹴る、長時間立たせるなど、肉体的苦痛を与える行為は体罰である。これは従来から変わっていません。けれども、教員や他の児童・生徒に対する暴力を正当防衛として制止する。教室の秩序維持のために、室外での別の指導を受けさせることなども許容されるとしております。 授業中に携帯電話ですけれども、通話した場合は、携帯電話を一次預かることも認めています。何を体罰とするかの文部科学省の見解は、はじめでありまして、教師が体罰の範囲を誤解して萎縮することがないようになるものと考えております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 学校教育課長、答弁。 ○学校教育課長 鈴木正博君 荒れている学校現場の現状ということで、ご質問がありましたけれど、現在のところ小学校、中学校の報告にある限りではありません。しかしながら、全国では17年度、小学校の校内暴力は2017件、中学校は3937件と報告されております。 議員お尋ねの校外での問題行動ですけれども、これは市民の方から何件か通報があります。通報があった時点で、私どもが現場に行きまして調査しまして、その内容において、それぞれ近くの中学校については、校長に連絡して指導するようにしております。 それから、警察にも通報いたしまして、パトロールして貰うように何時も言っております。 それから、学力調査のお尋ねですけれども、確かに、4県の統一のテストを毎年行っております。それについては、10月に行って、先月末報告がなされております。その結果については、県内で小学校については標準ということであります。中学校は若干、県内では上を行っているようであります。来年からは、県統一のテストは廃止されまして、全国学力状況調査ということで行われるようになっておりますし、先日、参加の方向で教育委員会で決定しまして、県には報告しております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 時間があまりないので、あれですけれども、2、3お伺いしたいと思います。 まず、市長がおっしゃいましたように、我が豊前市も不幸にして8年前、いじめによる自殺を体験しております。そのときの教育委員会の対応というのは、どうだったんだろうかなと心配しています。それを教訓にして、今、教育委員会が少し活性化したかなということを心配しておるんですよね。その時は、学校の管理に携わる、それから、担任の先生とかに対しての何らかの責任を取る人がというのは、教育委員会では議論があったのかどうか。それを今、問われているわけですね。 教育委員会が戦後、民主的だということで、アメリカさんから出てきた制度だと思いますが、私はこの制度は立派な制度だと思います。権力から独立して、子どもを伸び伸びと教育する。いろいろの権力、圧力に屈しない教育委員会というのは、最初は、確か選挙で選んでいたですね。今は市長が議会に相談して任命しておりますけれども、その教育委員会の活性化を促したいと、私は思いますが、議事録は今どうなっていますでしょうか。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 教育委員会は、定例的には、毎月上旬に1回開いております。必要であれば臨時に開いております。議事録につきましては、学校教育課長のほうが記録をとりまして、それを次の会の最初に、前回の話の内容の記録したものを読み上げて報告しております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 それは、教育委員会の中だけの話ですけれども、一般の例えば、私たち、それから一般市民の方々が、教育委員会の議事録を見たいということになったら、どうなりますか。 ○議長 秋成茂信君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 原則は、教育委員会は公開でありますので、今まで公開で傍聴に見えた方はいませんけれども、必要であれば見たいということであれば、それは公開いたします。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 今、教育長から、いろいろ学力向上についての話も頂きましたけれども、概ね中教委が出そうとしている答申に従おうというお話だったと思いますが、そういう理解でよろしいですかね。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 3月10日の答申の中に、文部科学省の意図する指導、或いは、勧告などが、県教委、或いは、市教委まで届かないということがあるので、その点については、賛否両論の併記をした形で答申をしております。けれども、私は市の教育行政において、文部科学大臣の教育委員会への指示、或いは、勧告等については、ごく限られた場合に限ったり、或いは、内容に歯止めがかかっているのであれば必要である、と私は考えております。そうしないと国民、或いは、市民から頂いたお金で施策を決定して実施していって、そのことの結果が責任を取れないというふうに思っております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 出席停止の問題も大きく問題になっているところですけれども、小学校・中学校ですから、私らの子どもの時には、謹慎というのがあったと思います。今、公教育では、出席停止は殆ど今まではなかったですね。 ○議長 秋成茂信君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 私が教育長になってから、或いは、教員生活の期間で、私がいた学校では、出席停止という措置はあっていません。これは、いわゆる問題行動を起こした場合の出席停止でございます。インフルエンザにかかったとか、或いは、伝染病にかかったとかという場合は、勿論、出席停止はございます。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 私は、このいじめというのは、人間として一番げびた行為と思いますので、出席停止を含めて何らかの躾をきちっとするということは大変大事なことだと思います。 それと同時に、歴史的に見ても人間のいじめというのは直らない。人間だけでなしに動物界すべてにいじめというのは、ずっとあると思います。そうしますと、いじめられる子ども達に、自殺までせんで何か抜け道と言いますか、そんなものはないだろうかと。 例えば、赤ん坊の時は痛かったり、寒かったり、いじめられたり、腹が減ったりしたら大きな声で泣くんですよ。そして親に訴えるわけよ。だから、いじめられる子が大きな声で泣くような、そして、親にかわる学校の中で訴えられるような、そういうものをいじめの世界がなくならんとするなら、そっちをもう少し真剣に考えるべきだと思いますが、それについては何かご意見ありませんか。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 特効薬はないと思いますけれども、やはり早期発見、早期対応ということでございますが、早期発見をする上で、子ども達が何らかのサインを出すと言われていますが、そのサインをいかに敏感に受け取れるかと、それが教師の力量でもあろうかと思います。 いじめは子どもだけでなく、大人の世界でもあるわけですけれども、それに対して、それを乗り超えられるだけの気力と言いましょうか、考えと言いましょうか、体験と言いましょうか、そういったものが学校教育の中、或いは、社会教育の中、家庭教育の中で、大人が指導したり、教えていかなければならないことではなかろうかと。 今の子どもの数が少なく、兄弟も少なく、生活体験も非常に少のうございますので、何をするにしても、すべて初めてでございますから、自分に自信がもてない、親に迷惑をかけたくない。自殺というのは、一番親に迷惑をかけることでありますので、そういった点も子どもに教えていく必要があろうかと思います。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 私は、早期発見の知らせを、子どもにどうやって設定させるかということです。 発見されれば、あなたがおっしゃったことはできると思いますが、要するに、泣いてこいという分かりやすい話をすれば、それを思いきって泣きなさいと教えないかんし、誰に向かって泣いていいか分からんような子どももおるでしょうが、それらの発見のためにどうすればいいか。例えば、担当の教師を置くとか、校長先生の所に何時もこられるような雰囲気をつくるとかあると思います。その辺のところを考えて欲しいと思っております。 それから、先ほどの校外の問題ですが、現場に行って警察とも連絡をとりながら、最後は学校長に伝えると。校長から指導してもらう。学校の中の指導の方法はどうなっているのかを、お伺いいたします。 ○議長 秋成茂信君 学校教育課長、答弁。 ○学校教育課長 鈴木正博君 それぞれの学校に、生徒指導の担当の先生がおられます。それを中心に生徒指導については行われております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 えらい答弁がそっけないけれども、もっと具体的にどんな指導をしたのか。 生徒指導なり校長がどんな指導をしたのか。そこまで教育委員会が把握していますか。 全部どんな指導をしたのか。どういうことがあったか。その辺のところをきちっと私は把握してほしい。そして、再発を防止せないかんのですからね。子どものためにも大変なんだから。警察事件にでもなったら、その子の一生の問題だから、どんな指導をしたのか。これを教育委員会がチェックして、教育委員と一緒に、学校現場は子ども達を救っていかなならん。そこまでやっていますか。 ○議長 秋成茂信君 学校教育課長。 ○学校教育課長 鈴木正博君 指導を学校でいたします。学校から報告を一応求めています。何故かと言いますと、市民はこの前もありましたが、特定の人間をどういう人間で、どうしてほしいということを言うわけですが、実際には、特定の人間を特定することはできませんけれども、そういう市民からの求めがありますから、教育委員会としても、具体的な話を持ち込みまして、学校側に全校、それからクラス、そういう指導を求めて指導の結果は、そういう人間はいなかったかどうかという報告を一応求めております。ですから、具体的にと申しますと、そこまで細かくはありませんけれども、ただ報告を求めております。 ○議長 秋成茂信君 渡邊議員。 ○6番 渡邊 一君 報告を求めるだけじゃなしに、それを教育委員会の中で問題を取り上げて、それを議論する。それが公表されるような形で、そこまで行って、初めて皆さんが知ることになりますから、特定する必要はないと思います。そういうことはやまるのではないかと思います。 いずれにしましても、教育の問題というのは、これからでございます。確かに、学校現場も荒れていることは事実ですし、学力が落ちていることも事実です。いい先生が欲しいなということも皆さんの共通の念願です。この改正を機に、我々豊前も教育問題にしっかり取り組んでもらって、これからの子ども達に明るい教育をして頂きたいと思います。 それから、市長にお伺いしますけれども、今4つの問題をお話し頂きました。 例えば、財政問題の中に、昨日、尾家議員が話しておりましたが、職員の団塊の世代で今度かなり辞めます。しかし、合併が実現すれば向こうの職員との関係も出てきます。 そういうものを合併することによって、首長と三役は1人ずつで済むわけですからね。 それから、課長も1人で済むわけですから、かなりの生首を切るわけにいきませんけれども、人員の削減で、大きく財政問題に寄与すると思います。それらは何のためにするかと立ち向かわなければなりませんが、もう少しそれらで、豊前市も新しく青少年のための措置を、今度、新しく2歳以上ですか、要するに福祉、それから、昨日、宮田さんでしたか本当に今、医者に行けないという人が増えていますね。 国民健康保険を取り上げられて、勿論、支払いせんほうが悪いでしょうが、それぞれの理由があるでしょう。それらも同じ市民ですから、どうやってうまく命を尊ぶかということを、そういうものに振り向けるための合併であると思いますので、この合併を勇気を持って、とにかく成し遂げなならんという不退転の決意で頑張って欲しいと思います。 それから、豊築が1つになった時に、この辺が教育特区と言いましょうか、教育環境が素晴らしいなと、それだけで人が集まってきますからね。活性化につながると思いますので、合わせてそういうことも考えながら合併を推進してもらいたいと思います。 以上をもって、時間切れですから終わります。 ○議長 秋成茂信君 渡邊一議員の質問を終わります。 次に、山本章一郎議員。 ○11番 山本章一郎君 私は、この議会で2つの項目について、教育長に、お尋ねしたいと思います。 最初に、自動車生産拠点づくりについて2、3点お伺いいたします。 1点目は、工業用地を急いで確保しなくてはならないと思いますが、今後、何社ぐらいの企業立地や拡張を考えているか、お聞かせください。また、どのくらいの工場用地の面積が必要とされているかについても、お答え頂きたいと思います。 工業用地の確保には、相当額の財源も必要と思いますが、財政面の負担はいくらぐらいかかるのかについても、お答え頂きたいと思います。ダイハツのエンジン工場が、久留米のほうに進出したとのことですが、企業誘致の競争も激しくなると予想されます。 迅速な対応が求められていることですので、市長の思いをお聞かせ頂きたいと思います。 2点目は、150万台生産拠点に欠かせないのが、工場で働く人材であります。 人材育成の場を職業訓練センター、青豊高校、企業が自ら運営する人材育成のための専門学校があると思います。ここに対する支援・協力を考えていると思いますが、更なる支援・連携・協力をお願いしたいところでございます。市長の考えをお聞かせください。 先日、武見厚生労働副大臣が来豊した際、職業訓練センターに立ち寄り実情を見て帰ったところでございます。国は、再チャレンジの政策を積極的に進めています。正社員になれるような技術を身に付けるために、職業訓練センターは有意義な場所だと思います。 訓練の中身や機材の強化も必要かと思います。ニートやフリーターを減らし、活力みなぎる市に1歩でも前進できればと思います。 県立の青豊高校の存在も、地域の人材育成には重要な存在だと思います。総合学科高校として誕生して、様々な進路を選べる存在の学校であります。まだ、その成果は未知数の所もありますが、小学校・中学校の義務教育と高校教育の連携協力が必要と思います。 地域に定着し、将来の地域を担う人材を育成のために、青豊高校は役割りを果たさなくてはならないと思います。義務教育と中等教育の連携・協力の考えを市長、それから教育長にお答え頂きたいと思います。 もう1つの人材育成の場として専門学校がありますが、この学校によっては、運営がうまくいってない所もあるように聞いています。この辺にも行政からの支援が必要と思われますが、市長の考えをお聞かせ願いたいと思います。 また、心配事も発生してきております。企業の進出や拡張が進めば、外国人労働者に頼るしかないと言われています。そのような方向になるのか、お聞かせ願いたいと思います。外国人居住者が過度になれば、地域の治安や教育が荒廃するという声があります。心配はないのか、お答え頂きたいと思います。また、外国人労働者に頼るとき、今、市内に何人か外国人労働者がいるように聞いております。 先月、市長は、中国の友好都市である通山県を訪問したとのことですが、豊前市との連携でコンピュータの学校ができている、どのように利用されているのか、お聞かせ願いたいと思います。また、通山県から日本に働きに来ていた人たちが、どんな暮らしをしているかについても、土産話を聞かせて頂きたいと思います。 質問の2項目は、中山間地域の活性化について、お尋ねいたします。 今年、合岩小学校の卒業生が、クラブ活動を中学校に進学してからも続けたいということで、千束中学校に入学するということですが、この原因は、中山間地の高齢化・少子化が進んだためと思います。そこで、現在の高齢化・少子化がどれぐらい進んでいるか、具体的な数値をもってお知らせ願いたいと思います。 市長は、今議会の冒頭の所信表明では、林業・農業の活性化策を述べられていましたが、地域から子ども達の声が聞こえなくなり、村もなくなる予感もする地域があると、そんなふうに私は思いますが、中山間の活性化策をお聞かせください。 また、今度、中山間地の活性化のために大きな影響を及ぼすのが、東九州道の完成だと思います。盛土工法を採用すれば人の交流、物の交流が分断される危険性を含んでおります。集落の中を東九州道が通るために、区を分断される地区も出てきております。 市民の暮らしが、今まで以上に住みやすい地域になるような努力が必要と思いますが、住んでいる人たちの心配を解消できる対策を、お聞かせください。 以上、2項目にわたりまして壇上からの質問を、ひとまず終わらせて頂きます。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 山本章一郎議員の一般質問に対し、自動車生産拠点づくりの中の工場用地等の今の動きにつきまして商工水産課長、そして、人材育成につきましては学校教育課長、中山間地域の活性化についての東九州自動車道の関係につきましては、都市計画課長からの答弁で、私は、壇上から自動車産業の総合的な関係と、外国人労働者につきまして、また、中山間地域の活性化についての全般的なことにつきまして壇上から、ご答弁させて頂きます。 課長から、細かい今の状況を言える範囲のことは言うと思いますが、要は今、大体、完売しまして後、工業団地の造成をしなければならない。それも数年後のことでなくて、この2、3年のことでありますので、先般3月の初めに県の企業局、県議会議員とも相談しながら、今どうしていこうかということをしているところでございますし、4月には、県知事選、県議選もありますから、その後かなと思いますけれども、造成に向けてお願いを県にしているわけでございます。 市だけでは10数億円、20数億円、30億円のことになりますので、県のご協力ももっていかなければと思っておりますが、ともかくスピーディーにやれる小回りのきくような工業団地の造成をしていこうか、と思っておるところでございます。細かい答弁は、課長のほうからさせます。 この中で、外国人労働者、特に、通山県に行ったじゃないかということでございます。 昨年、通山県の方が5名、豊前市で研修生として働きまして、今2名働いております。 他企業の方では2つ、3つ、中国の人、フィリッピンの人が働いている状況があります。 特に、通山県の場合は、中国でも湖北省の中で、武漢の大きな町から100kmほど入った所でございますので、皆さん気持のいい優秀な方ばかりでございますので、これからも継続していくということで、お話をしているところでございます。 ただ1年の研修では何もできませんので、最低2年の研修をしながら、また、お互いに時代が大きく変わっておりますし、中国は、特に、ものすごく建設ラッシュですので、お互いがビジネスができるような形でやっていこうかなと思っているところでございます。 次に、2番目の中山間地の活性化につきましては、答弁書を書いておりますので、読まさせて頂きたいと思います。中山間地域の活性化について、2005年より、我が国の人口は減少局面に入り、今後かなりの自治体において、人口減少に益々拍車がかかると見込まれております。人口減少は地方に対し、都市部との経済格差の一層の拡大、地域社会の活力や集落機能の低下、耕作放棄地の増加や、森林の荒廃による自然災害の発生危険度の増大など、大きな影響を与えると予想されているところであります。 このような状況の中、当市の中山間地域の活性化につきましては、住環境の維持・向上や農林業の振興はもとより、中山間地域の豊かな自然や景観、歴史や文化、また、そこで生産される農林産物などを積極的に活用したグリーンツーリズムや、都市・農村交流により、多くの都市住民に地域の魅力を伝え交流人口を増やし、農山村に活力を与える施策を推進してまいります。合わせて、外部の評価や交流により、地域に住む住民が地域への誇りと愛着を深め、ひいては、豊前ブランド定着へとつなげていく情報発信を積極的に進めてまいりたいと考えているところであります。 以上、申し上げておりますけれども、特に、今、豊前の場合は、道の駅・卜仙の郷を通じまして、10年前は、外来のお客様は30万人でございましたけれども、今は250万人を超しています。これを農産林業の推進のために、もう一工夫しなければならない、頑張らなければならないと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 商工観光課長。 ○商工観光課長 後小路一雄君 私からは、議員ご質問の自動車生産拠点づくりの工業用地の関係で、ご答弁申し上げます。この工業用地の必要面積と財政負担でございますが、面積につきましては、ニーズによりまして増減いたしますが、1つの単位として10ha程度かなと考えております。 団地創設につきましては、面積が広ければ広いほど高いリスクを負うことになります。 平成5年より、福岡県の企業局が開始しました豊前東部工業団地の造成事業は、23.3haで、その中に公共用地を4.3ha、販売面積は19haあったわけですけれども、用地費・造成費を含め約45億円、加えまして公共用道路、工業用水関係の事業を含めまして、市の負担額が約14億円となっております。このようなことを勘案しまして、用地確保につきましては、候補地・面積等を示しながら福岡県に強く要望しております。 それから、外国人の就労者が、どのくらいおるかということでしたけれども、これにつきましては、私のほうは6月1日、毎年、調査をしておりまして、昨年6月1日、市内企業93社に調査依頼いたしました。その中で回答頂いたのが68社でございます。 その中の6社で、外国の方が53名就労しているということでございます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 学校教育課長。 ○学校教育課長 鈴木正博君 人材育成についての質問でございますが、義務教育課程における就労に対する支援としましては、総合学習の時間を利用しての職場見学や、市内の事業所への職場体験をさせることにより自主性・自発性・協調性を養い、働くことの意義を学習させることを目的としております。このような活動を通して、様々な過程を経験させることにより、豊かでたくましく生きることのできる資質や能力を育成しています。 中学校から、青豊高校への進学者はかなりの数にのぼり、今後もこの傾向が続くと予想される中で、今以上に連携を保ち、就職選択においては高校に対し、情報提供を行なうとともに、生徒1人ひとりに対してのきめの細かい指導をお願いする所存であります。 今後も、一層の学力向上を目指しながらも、就労支援については、全力で取り組んでまいりますので、ご指導をお願い申し上げます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 都市計画課長。 ○都市計画課長 竹本 豊君 都市計画課でございます。東九州自動車道の関連につきまして、お答えいたします。 東九州自動車道が土手になり、人の流れ、物の交流に大きな影響を及ぼす対策を聞きたいということでございます。当地にとりまして、40数年来の悲願でありました東九州自動車道の施工が、ご存知のように昨年2月に決定いたしました。 以降、豊前市では、建設推進対策協議会、また、校区ごとの対策協議会を立ち上げて、地権者をはじめ関係の皆様への周知徹底並びに測量調査の承諾、同意のための地元説明会を行なったところであります。9月には、測量調査範囲内435名の方々から、97%の同意を頂きまして、西日本高速道路株式会社により、測量調査が実施され、この3月時点で、測量の成果をもとに作成される図面ができつつあります。 具体的に、まだ、構造や高さ等の内容が示されておりませんので、土手がどうとか、或いは、橋梁がどうとかいう詳細部分については、現在、お答えができません。ただ他所の高速道路の事例を見てもお分かりのとおり、地形、標高、勾配等で多少の差異はございますけれども、切土・盛土になるのは確かでございます。これは高速道路が、80kmから100kmの高速走行されますので、高速道路は安全面からも、道路構造上からも、平面交差をつくらないというのが原則ですので、やむをえない面もあると思います。 市道等の高速部分につきましては、必ず立体交差になるわけであります。従いまして、平野部につきましては、盛土工法はやむを得ないということで考えております。 盛土によっては、結果的に集落を割るという箇所も数箇所出てまいります。まもなく測量の成果をもとに作成される図面が出ます。それをもとに、地元設計協議を行なう予定にいたしております。その場で高さの問題とか、県道・市道等の交差部分の取り付け、或いは、側道の問題、集落の環境を勘案しつつ可能な部分につきましては、できるだけ影響が出ないような形で検討を加えてまいりたいと思っております。 一般的にインフラ整備を行う際は、100%いい面ばかりではございません。多少の影響も出るわけでございますが、地域振興、或いは、公共の福祉の増進等いかに折り合いをつけながら高い見地、総合的な判断から事業を断行していくわけでございます。 現状では、供用開始が、平成26年ということで計画いたしております。高速道路の完成によって、飛躍的に、この地域の利便性がますというふうに考えております。ここにはいろいろご意見もございましょうけれど、東九州自動車道の早期の完成に向けて、福岡県、西日本高速道路株式会社、豊前市が今一体となって頑張っておりますので、一層のご理解・ご協力をお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長 秋成茂信君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 それでは、中山間地域の高齢化・少子化の現状について、お答えいたします。 中山間地域の高齢化でございますが、合河・岩屋の平成17年度の国勢調査の結果で申し上げますと、合河につきましては、65歳以上、現在41.6%となってございます。 5年前の調査に比べまして3.1%の増ということでございます。 岩屋につきましては39.4%、これも前回に比べまして4.3%の増になっております。少子化の関係でございますが、今から10年前、合岩小学校については128名いた生徒が、18年では63名まで減少していると。合岩中学校につきましては、平成10年が92名、現在の18年は44名という現状でございます。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 それでは、自席から再質問させて頂きます。 自動車の集団拠点づくりについては、昨日から、今朝も渡邊議員から質問がありましたので、今後は県と連携しながら、吉富町との合併も含めながら進めていくというやり方だろうと思います。それで当然、最初は100万台構想が150万台になり、工場用地それから行政の財政負担も当然増えるということでしょう。こういったことも含めて、吉富町との合併、企業の立地のしやすくなるような地域の活性化に向けて、市長の決意も十分に分かりました。どうか早い時期に素晴らしい工場用地ができて、企業を誘致できるような日を1日も早くしたいと思います。 それから、工業用地、財政面的な質問は、これで改めて市長の決意を頂かなくて時間もありますので、人材育成のほうに入りたいと思います。 現在、豊前市内に職業訓練センター、それから、中部高校の会館ですか、そこには人材育成が入るということも聞いておりますけれども、そういった所に、今ちょうど安倍内閣が再チャレンジということで、今まで、市が訓練センターに補助金を出していたと思いますが、その内訳を、今後、国庫補助の期待が持てるんじゃないかと思いますけれども、そういったことの要素があるのかどうか、お聞かせください。 ○議長 秋成茂信君 商工観光課長。 ○商工観光課長 後小路一雄君 豊前地域の職業訓練センターへの国の補助ということですけれど、これはございません。今、自動車関連で有効活用ということで、私の方からも、そういった講座につきまして、いろいろ要望しております。これは県の関係でシステムがございまして、そういったものであれば100%県から出るようなシステムがありますので、そのような講座の導入についても、お願いしておるところです。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 この前、先に副大臣が見えたとき、リフトの教材のある室で、リフトの免許を取得しておれば、企業に就職するときに給料が1万円ぐらい高いと、採用されるのに有利に展開する。費用は3万円から5万円ぐらいかかるでしょうけれど、そういうことで、企業がそういった講習をすれば、自前で育成費がかかるみたいですけれども、職業訓練センターで、自らが受講して資格を取得すれば、正社員になりやすいという言い方をしておりました。 それで、今ちょうど安倍内閣が一生懸命再チャレンジ、イノベーションという言葉で表現していますけれども、これは副大臣が国の施策のPRもあったんでしょうけれども、そういったことが市にできるのではないか。どんなメニューがあるか分かりませんけれども、大きな期待をするべきだろうと思いますし、積極的に県に頼るんでなく、中央省庁まで出かけていってもいいんじゃないかという思いがしました。 そのことで、これからも、いろいろカルチャーセンター的な講座もあるみたいで、実際に働く現場で、その資格なり発揮できる講座は、まだまだ必要とされてくるんじゃないかと思います。今までは、市内の中・小企業で、そういった地元の従業員の育成というか、資格の講習などできない人たちのために、豊前市があったのかなと思っていますけれど、これからは、そういう形で再チャレンジしようという人たちが、一定の訓練養成の資格を取るということが、1つは再チャレンジ、フリーターやニートが減少できる方向になるんじゃないかと思います。それで商工課長、もうちょっと研究されて、そういった国・県からの支援を受けやすいような方法を研究してください。お答えをお願いします。 ○議長 秋成茂信君 助役、答弁。 ○助役 渡邊賢二君 山本議員の質問は、先般、副大臣にお願いしたという件のようでございます。 これにつきましては、認定職業訓練助成事業、運営費における補助対象の算定において、現在は、市内の事業所においては、3分の2の訓練生がいなければ補助対象にならないというような状況でございます。ですが、3分の2の会員の訓練生というのは、なかなか難しいということで、これを2分の1にして頂きたいということで、17年に職業訓練所のほうも国に要望書を出しておるようでございます。ですから、そこらあたりについて、是正したいというようなお答えであったと思います。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 そういったことで、いろんなことを入れながら地域の活性化を図って欲しいと思います。 もう1つの人材育成の場、青豊高校と義務教育との連携ということで、先ほど課長は、今からも更に、連携を深めていきたいというお答えでございました。現在、青豊高校は、総合学科として運営されておりますが、この中に、以前は車の生産拠点が、まだまだ前に出てきてなかった時代のことでした。それが今感じているのは、折角のこういった拠点ができて、若い人材が必要とされてきて、工業科、溶接とか旋盤とかの実習する場を含めたような、そういった教科が青豊高校にも求められているのではないかという思いがします。 発足当時は、農業系の旧北高校が農業高校でしたので、その辺のつながりがあったと思いますが、この地域には、工業科がなかったということもあったでしょうが、これからは、工業科を修得した生徒が企業からみたら、そういった人材がいいとされる企業が出てくるだろうと思います。今から150万の拠点ができたときに、いろんな人材、それから、若い人たちが地域に接触する1つの要素だと思いますので、そういった考え方は、市の教育委員会なり、市長なりが、県の教育委員会、それから県に要望していくべきだと思いますが、教育長に、その辺について要望する考えはないか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 工業関係につきましては、京築管内では、苅田工業高校がありますが、青豊高校になりまして総合学科ということであります。豊前地域、或いは、豊前の東部地域の子ども達も、そういった工業関係の仕事につけれるような状況をつくり出すという意味では、県の教育委員会、或いは、県議会のほうに豊前市教育委員会として、そういったことは、教育委員会の中で話をして要請していきたいと考えております。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 是非とも、そういった要請をお願いしたいと思います。 もう1つ、先ほど市長から、中国通山県から日本に仕事に来て頂いた方々の人材としての評価は、大変優秀な人材だという言葉でした。そういったことも含めまして、この青豊高校の中に3年間のうちに、海外に留学ができるような仕組みをつくったらどうかな、という思いがしております。今、単一制ですし、2学期制をとっておるようでありますので、その3年間のうちの半年間、中国なり、韓国なり、ヨーロッパなり、アメリカなりに、そういったことができる高校ではないかなと思います。 これも含めて、今から外国人労動者が増えていく中で、やはり外国の文化とか風土とか、実際に行って生活してみて体験してみないと分からない部分、分かるスピードが早まると思いますので、そういった体験を高校の3年間のうちにできるということは、語学力も日本の中で勉強するよりも、実際に半年でも生活すれば、それ以上の成果は十分あがると思いますし、これも単位の取得に最もつながる早道かなと思います。 これで1年留年して、卒業までに高校3年が4年かかったよという人がおっても、地域としては貴重な人材になると思います。こんな考え方を私は持っていますが、市長はどう思いますか。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 発想と着想はいいと思いますけれども、通山県は高校があったかな。小学校のつながりはもっていますが、研修生、働く技量を得る研修になっておるところで終わっていますけれども、高校に来る、なかなか簡単じゃないと思いますけれども、やるからには、そこまで考えることかなと思っております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 是非とも、この地域の若い人たちに、いろんな夢を描いてほしいと思いますので、どうか頭の隅において、何かの機会に山本議員が、あの時あんなことを言いよったなということで、どこかの場で提案してみてください。人材育成については終わりたいと思います。 次に、中山間地の振興について、財務課長、先ほどの具体的な数値を少し聞き取りにくかったので、もう一度お願いしたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 財務課長、丁寧に分かりやすく答えてください。 ○財務課長 池田直明君 17年度の国勢調査の結果が出ております。それによりますと、合河は高齢化率65歳以上ですが、その人口が41.6%ということで、これは前回の調査に比べまして3.1%増えているということでございます。次に、岩屋につきましては39.4%、これも前回に比べまして4.3%増えているということでございます。 小学校につきましては、平成10年の結果でございますが、岩屋小学校が128名、平成18年が63名ということで、約2分の1に減っています。合岩中学校につきましては92名。平成18年が44名という結果になっております。以上です。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 今、具体的な数値を示して頂きました。これほどに高齢化率・少子化率が進んでいるのかなと思います。将来的には、昨日も中学校の統合の話が出ていましたけれども、当然、合岩地区から中学校がなくなる。そして、自動的に小学校がなくなるのかなという予感がしております。先ほど総務省は、後、何年か後に村がなくなる地域を発表したようでありますが、豊前市内は、そういった対象になってないと思いますが、小学校4校を統合したときにいろんな振興策を講じてきたところですけれども、なかなかそれは成果が上がってないと言いますか、活性化、賑わいはあるでしょうけれど、観光客、外部から入ってきた数は10倍以上になったよという言葉でしたけれども、そこで暮らす人達が、今からどんな暮らしぶりになるのかという心配はあります。 特に、高齢者化はどんどん進んでいけば、必然的に農林業の担い手もいなくなると思いますし、担い手がいなくなれば田圃も山も荒れるということになります。今ちょうど団塊世代が定年の時期を迎えまして、この前も親戚の人に会いまして、60歳になって退職して、嘱託で後3年間は仕事をするという話です。それで、この際、豊前に帰ってこようかなという思いがあるけれど、という声でした。 豊前から出て行って定年を迎えて、この際、生まれた所、育った所に帰ってきて、もう1つ、生まれた所に何か貢献したいという思いが多く声が聞こえます。こういった方達が帰ってきて第2の人生じぁありませんが、生きがいの場づくり、そして、今からの農業は半面勤、半面農業で、年金を貰いながら片方で農業をやりながら、それぞれ家計を支えていくというようなことがあると言われております。 先ほど、市長は農業振興に力を入れるという言葉でしたが、ちょうど定年を迎えて年金を貰う人達のこの10年間の労働力は、中山間地にもってこいの地域かなと。住みやすいという、今までデジタル社会の中で、ずっと頑張ってこられて、ふるさとに帰ろう、アナログの時代を思い起こそうという、ふるさと志向があるんじゃないかと思います。 こういった方達に帰って来やすくなるような支援策が、何か考えていないかなと思いますが、是非つくってほしいと思いますが、そういったメニューがあれば聞かせてほしいし、市が単独でやろうという思いがあれば、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 私も63歳になりまして、同級生はみんな帰ってきております。けれど、合河と岩屋には住まんですね、みんな。やはり遠いというか、山間部かなと思いますが、今、幸いなことに国道10号線から合河・岩屋あたりは、大体12から13キロで、1つの望みとして、東九州自動車道ができインターチェンジができた場合、随分、合河・岩屋は近くなるのじゃないか。それと、もう2つあるんですが、津民・豊前線の開通、加えて鳥井畑・寒田の開通は、寒田の人からも鳥井畑と連携プレーをしたいという申し込みも来ております。 そうなると、かなり向こうの方に通り道ができるだろうと思っていますから、是非、横武ぐらいまでは、みんな住みそうだけれども、その上にどうかして住むために、道もできたら近くなるということですので、山本議員のご提案、特に、私の同級生は身近なものですので、よくご相談しながら、東九州自動車道の開通に合わせて、少し前からでも山間部の対策をどうしたらいいのか、ということを思っているところでございます。 ○議長 秋成茂信君 山本議員。 ○11番 山本章一郎君 是非とも、豊前市から、村がなくならないような施策を進めてほしいと思います。 もう1つ、東九州道の開通後、どんな影響が出るかということで、路線が決まって、測量が9割以上の同意を貰いながら進んでいるということでした。また、構造については、まだ設計協議がなされていないということで、答えが聞かれませんが、やはり、平野部に行けば水田があったり、水を管理するのに遠くなったり、水の配水・供給にも遠回りになったり、いろんなことが予想されますけれども、実際にその場がこないと難しいかもわかりませんけれども、こういった影響については、設計協議の段階で、十分な地元の声を伝えてほしいと思います。 後は、今まで道の駅で頑張ってきて、売上高も九州で2番目だったり、そういう嬉しい情報を聞いていますが、今度、高速道路が開通すれば、道の駅に寄る人が減ってくるのではないかという予測もされます。そういった中で、このエリアの中でサービスエリアができるのか。インターが鬼木にできてサービスエリアが、この近くにできるのかどうかわかりませんけれども、そういった計画があるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長 秋成茂信君 都市計画課長。 ○都市計画課長 竹本 豊君 先ほど申しましたように、平成26年度の完成を目指して、今、頑張っておるわけですけれども、高速道路をつくる、そもそもの目的は、便利に早く着けばいいということではなくて、やはり、この豊前市地域に、いかに観光客が増えたり、産業が起こったり、活性化ができるかということが、一番の目的でございますので、そういったことを主眼におきながら、今いろんな所と検討しているところでございます。具体的には、役所の中の各課を入れてハード部門、ソフト部門と分けて、ワーキンググループで検討しておりますけれども、その中で先ほど言われましたサービスエリアの関連も検討いたしております。 これは、西日本高速道路株式会社、或いは、国・県とのいろんな協議がこれからありますので、豊前市単独で、ああだこうだと言えない状況でありますが、できれば、そういう道の駅の代替機能として、築上町の椎田南インターチェンジから県境間に、サービスエリアを何とかできないかということで、今、1市2町で検討をしている状況でございます。 パーキングエリアにつきましては、旧大平村に計画されておりますが、そういったものをサービスエリアの機能を含めたものをつくっていこうじゃないかという検討をしているところでございます。 それから、インターチェンジにつきましても、観光客を増やすために、例えば、今仮称でございますが、ぶぜん・くぼてインターチェンジという名称にして頂いて、南部に観光地がありますので、そういった所に誘致したいという諸々の検討をハード部門、ソフト部門で検討しておりますので、できるだけ地域の活性化、悪影響を与えないようなことで頑張っていきたいと思っております。 (「終わります」の声あり) ○議長 秋成茂信君 山本章一郎議員の質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。 休憩 11時35分 再開 13時00分 ○副議長 中村勇希君 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行します。次に、村田喜代子議員、お願いします。 ○5番 村田喜代子君 皆様、こんにちは。傍聴の皆様、本当にお忙しい中をありがとうございます。 平成18年度の行政も、もう最後になりました。本当に早いもので、1年があっという間でした。その1年の間に本当に悲しい出来事等がたくさんあり、文教厚生といたしましては、本当に文教厚生というよりは、私自身、母親という立場の中から、さびしい思いがいっぱいさせてもらった1年でございました。でも、この1年をさびしいとか、つらいとか、悲しいというだけでなく、本当に子ども達がいい心をもった、いい感謝のもてる、そのような子ども達に育っていくことを願いながら、今日の一般質問をさせて頂きます。 今回は、第1項といたしまして、豊前市の活性化について、そして、2番目が、学校教育について、3番目が、子育て支援についての3項目を議題にいたしました。 豊前市の活性化といっても、特別のことではなく、まず、もって就労の場を持つことが最大のはじまりではないかと思います。雇用のない所には、人は集まってまいりません。 また、文化・芸術・自然の美しさのない所には人は集まりません。豊前市には資料館がありますが、特別の資料館でしかありません。資料館は、館長さんにしっかりお任せして、いい資料、また、外部からの方がみえるようにして頂けるようにお願いいたします。 まず、初めに、市長さんが施政報告の中で、職員の発想の転換をいたしますということを書いておりますが、その職員の発想の転換とは、どういうことかということを、まず、お伺いした上で質問させて頂きます。 豊前の玄関は宇島の駅だと思っております。今は車社会ですから、駅がなかなか忘れられておりますけれども、やはり玄関は駅と私は思っております。その駅にエレベーター設置の要望をいたします。高齢化が進み、バスが駅に入ってきて頑張っているのですが、車で送ってもらう方の中には、中津まで行き、エレベーターの必要性を訴える方々がいるということを知って頂きたい。エレベーターをつけるに必要条件の中の一番大切な乗降客の数、これが1日5000人ということで、条件に見合わないとのことでございます。 数を減しているのも、駅の階段の不便さがあることも否めないのではないでしょうか。 この最近、特急によく乗ることがありますが、2番線から1番線にくる最中、高齢者が荷物を持って上り下りする大変さ、また、身障者の不便さ、また、体の悪い方が1歩、1歩大変な思いで上り、下りていくのを見るにつけ、思わず知らぬ顔をしながら、その方の後を歩いています。やっと下りるのをみて大変でしたね、と声をかけると汗を拭き拭き、はあ、はあ、言いながら、ああ大変ですねと笑っていますが、その顔は苦しそうです。 横で奥様が困ったものですと、相槌を打つことも多々あります。駅のバリアフリー化の要望を特に要請したいと思います。 先日、武田良太後援会の中でも、私は最後に要望いたしました。また、議会が終わった後に署名を取って、どれだけの方達が要望しているのか、調べてみたいと思っております。 2番目に、豊前市の玄関の駅、松江・豊前・三毛門の駅の周辺の利用地を、どのように活性化に向けてお考えでしょうか、お聞かせください。そして、駅から商店街に向けての流れをどのようになされているのか。個人、個人の考えがたくさんあって、そして、年齢の差等で意見が随分と違うと思います。市民と市との話合が何度も持たれているようにあります。また、毎月のように商店主との話合があっているようですが、一向に駅前の活性化が見えてまいりません。車社会ですから、広範囲になっていくのは当然ですが、高齢化、また自主的、また効率的な自分の自治をつくるためには、豊前のまちづくりが一層必要なのではないでしょうか。 すこやか赤ちゃんの祝金も商品券であるのは、そのためではないでしょうか。 豊前の市民を対象にするだけでなく、外部より豊前の中を歩いてみるような企画が必要なのではないでしょうか。つつじ祭り、シャクナゲ、ヒメシャガ、川の清流、今からの若葉茂る里として、素晴らしい名勝をテレビ等いろんな所で放映し、また宣伝してみるのもいいのではないでしょうか。看板を立て観光名所を出してみては如何でしょうか。 駅前にも、そのようなことをお願いして、車中のお客から見える分かりやすい、そして、目から脳に焼きつくような奇抜なアイディアをもって、制作してみては如何でしょうか。 外部に向けてのアピールをしていってほしいのです。 この豊前市には、福岡・北九州・山口からも沢山のお客様が見えております。 そのお客様の中には、ストレスを大きく抱えて、そのストレスを豊前市の緑の中に捨てて帰るお客様もたくさんいらっしゃいます。特に、人口が減っている豊前、外へ向けてアピールできる観光名所を考えてください。また、今この席で教えてください。 山が栄えることによって、海が満ちたよき海になるように、町並みができることによって、豊前の流通が、自分の地域、豊前を栄えさせる、そのようなまちづくりを皆でしていきたいと思っております。 市長の施政方針に、市職員の意識改革を図ります。課題発見・計画・創造・他に働きかけ実行、よく聴き、分かりやすく説明、このよく聴きは耳で、そして心で聴く、チームワーク等、競争心に負けない活動ある人材の育成を努めてまいりますとありました。お客が少なくなるのは、商店主も考えることもあるかもしれません。市の行政と商店街主の話合をしつかりとして、その中に、女性を大幅に組み込んで話合をして頂くことを望みます。 4番目に、活力ある女性の方々の個性豊かさを生かした場の提供を、お願いいたします。 豊前市には、女性のネットワークがございません。安心して、よい意味での競争、そして話合いは大変に重要なことであると、私は思っています。何度か要望いたしましたが、なかなか頂けません。何時の時代でも、女性が元気な所は平和があり、また元気があり明るさがあります。安心して集える場所、拠点の提供はなされないものでしょうか。そこから、どのような知恵、行動が出てくるか分かりせん。市長の見解をお伺いいたします。 5番目に、10年と思っておりましたが、さっきの都市計画課長の話では、7年後ぐらいに鬼木・永久周辺にインターがおりてまいります。光陰矢の如しと言います。あっという間に、この7年、8年は経ってしまいます。インターができても、何もなければ車は素通りです。工場の用地、インターの下り口と、今から様々に変化する地域の顔が、そのままでは生きた地域づくりはできません。その時に乗り遅れないためには、早くから都市の位置づくりをしながら、農地は農地のみにせず、特区のような配置替えの構想をしていかなければならないのではないでしょうか。工場地も、ダイハツ・トヨタ等も、早やばやと150万台に向け、立地・稼動しております。 議会がある度に早急に県にと言っていますが、なかなか思うように実態が出てまいりません。市長のこのときの構想が、あの時あったからこそ今がある、と言えるようなものにして頂きたい。市長は、鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス、鳴くまで待とうホトトギス、鳴かぬなら殺してみようホトトギス、の3つのどれでしょうか。 2番目に、学校教育のことでお伺いいたします。学校教育の中で、今回、問題になりました給食の件でございます。これは、昨日、尾澤議員が質問いたしましたので簡単に略しますが、はじめからの経緯をお話ください。 大きい3番目の3項目で、少子化対策について、1昨年でしたか、私は、この7年の間に少子化の件を随分と質問させて頂きました。もう心が小さくなるほどの思いをしたこともございました。でも子供を育てるのは、1年、2年では育ちません。20年かかった中で、やっとひとり前の働きができてまいります。1昨年、市長に質問したことによって、全国何処も少子化はありますと言っております。豊前だけではございません、というお返事を頂いて、私は大変に腹もたち、がっかりいたしました。 でも、市長の今回3月の施策方針の中では、少子化は社会の成り立ちにも影響を及ぼしかねない大きな問題であり、安心して子どもを生み育てることのできる環境を整えることは、国はもとより本市においても、長期的な視点をもって取り組まなければならない重要な課題であります。そこで、今年度から新たな少子化対策として、児童手当の乳幼児加算をはじめ、すこやか赤ちゃん出産祝金の2人目からの支給や、子育てサポートセンター機能の充実、放課後児童クラブの拡充を図ってまいります。また、地域・企業・行政などが連携・協調し、未来の担い手である子ども達の成長を、社会全体で支える仕組みづくりを進めてまいります、というお言葉を聞きまして、本当に嬉しい思いがいたしました。 やっと宝物だと分かってくださったと、厳しい言葉ですが言わせて頂きます。 その中で、今回、出会いの場というコーナーをつくってくださっておりますが、どのような企画でもっていくのか、どのような構想があるのか、教えてください。 2人目のすこやか赤ちゃんの祝金も商品券でしょうか。もし商品券ならば、期限の引き延ばしはできないものでしょうか。3人子どもがいたときと保育料の件でございます。 3人子どもがいたとき、学校に行っても最後の3人目の無料化にはならないのでしょうか。 学童保育の設置について、小人数の学校の学童保育は、なかなか10人の規格にはまりません。タクシーで利用しているお母さん方の負担を考えて、なんとか対策を立てて頂けないでしょうか。以上をもちまして、壇上よりの質問を終わらせて頂きます。 ○副議長 中村勇希君 古川議員。 ○3番 古川哲也君 今の村田議員の質問の中で、すこやか赤ちゃんの件につきましては、今回、議案に提出されていますので、事前審議になると考えております。その辺の答弁は差し控えて頂きたいと、執行部にお願いしたいと思いますが、如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 今、私も注意しようと思いましたが、すこやか赤ちゃんの出会いのことは、今回、議案上程されている案件でありますので、あまり深くはということになりますので。 市長、答弁、お願いします。 ○市長 釜井健介君 村田喜代子議員のご質問の中で、答弁書を課長が用意している所は、各場所から答弁をさせてください。豊前市の活性化へ向けての施政活性化は、商工観光課、都市計画課長、人権課長、学校教育に対しては学校教育課長、子育て支援につきまして、今、微妙な発言もありましたが、福祉事務所長の答弁を自席からになりますが、私からは部分的でありますけれども、ご指名の中のご質問ですから、この場で、まず答えたいと思います。 1番目が、市職員の発想の転換、意識改革の件でありますが、私が所信表明をこの場所で申し上げた点を読んでみましょう。もう一度ですけれども。 バランス感覚のある市政運営を行ってまいります。更に、1歩踏み込み市職員の意識改革を図ります。課題発見、計画、創造、他に働きかけ実行する、よく聴き、分かりやすく説明、チームワーク等、都市間競争に負けない活力のある人材の育成に努めてまいります、という発言をしたと思います。どういう意味かと申しましたら、まずいのが現状維持、どうかなるだろう、縄張り根性、足の引っ張り、こういうことだろうと思います。 それを変えていかなければならないのは、採算コスト計算の導入、未来志向、現状打破、結果よりもプロセス、こういうことじゃなかろうかと思っておりますので、村田議員のご質問のお答えにさせて頂きます。 もう1点は、徳川家康と織田信長、そして、豊臣秀吉のことで、鳴かなれば鳴かしてみせようホトトギス、鳴かなれば鳴くまで待とうホトトギス、鳴かなれば殺してしまえホトトギス、どれを取るかというご質問でございますので、3番目の殺してしまえということは、口が裂けても言えないかと思いますので、私としては、織田信長をとるのではなくて、豊臣秀吉と、事によっては辛抱も宝でございます。徳川家康を取ろうと思います。 以上です。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 私から、宇島駅のエレベーター設置について、村田議員のご質問にお答えいたします。 平成12年5月に、高齢者・身障者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の推進に関する法律が制定され、1日の利用者数が5000人以上ある地域については、平成22年までに、バリアフリー化が義務付けられました。これによりJR九州では、利用者数が5000人以上ある駅について、エレベーターの設置などバリアフリー化を、平成22年までに順次進めていく計画とのことでございますが、利用者数が1日平均3500人の宇島駅については、その対象駅になっていないということでございます。 次に、宇島駅・豊前松江駅・三毛門駅周辺の利用方法について、お答えいたします。 各駅に駐輪場を整備し、また宇島駅・三毛門駅には、駐車場を整備し、通勤・通学利用者の利便性向上を図っております。宇島駅につきましては、駅前広場や電車の見える公園が整備され、現在は、駅裏の臨海工業線の整備が進みつつあります。各駅周辺では、最近、民間による宅地造成やアパート等の建設が続いており、今後も駅周辺という利便性の高さから、住宅化が進むものと思われます。 また、利便性を高めるため、列車運行本数や、特急列車の停車本数の増加などを関係機関に働きかけてきた結果、3月18日のダイヤ改正により、下り2本、上り1本の増便が決定しております。引き続き、関係機関に働きかけていくとともに商業者・地域住民・行政などによる利用客の増加策や様々な工夫が、駅周辺や豊前市の活性化につながるものと考えているところでございます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 商工観光課長。 ○商工観光課長 後小路一雄君 私からは、駅から商店街に向けての流れを、どのようにつくるのかということにつきまして、ご答弁申し上げます。まず、商店街は魅力あるものでなければなりません。 今、駅前を中心に中央・二葉の商業者の方々は、毎週会議を開きまして、合併も含めまして、本当に熱心に商店街活性化に向けて努力されております。東八商店街ガンバロウ会事業も、これから徐々にその成果が期待できると考えております。 商工観光課としましては、空き地・空き店舗等の解決策を含め、TMO事業で対応していきたいと考えております。歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを目指し、そのことが駅から商店街に向けての流れをつくっていくと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 都市計画課長。 ○都市計画課長 竹本 豊君 それでは、都市計画課から2つございますので、まず、最初に、駅から商店街に向けての流れをどのようにしてつくるかということで、ハード的な面、都市計画課の観点からお答えいたします。現在、宇島駅裏では、街路の臨海工業線、これは県事業でありますが、この整備を行っております。これにより駅裏は2、3年後には立派に整備ができる予定でございます。 それから、駅前周辺でございますけれど、先ほど財務課長からありましたが、電車が見える公園、駅前広場などの整備、或いは、東八交差点付近の改良、県道中津・豊前線、八屋・千束線などの整備が終わりまして、随分綺麗になったところでございます。 更に、現在、上町・沓川池線の整備を続行いたしております。後は、これをいかにネットワーク化していくかということが大事になってこようかと思います。新しいまちづくり三法におきましては、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりというのがメインにうたわれております。中心部を持続可能で、賑わいあるエリアにする必要があります。長期的には、駅前周辺は、区画整理事業の取り組みが必要であろうかと思いますが、現時点では、いろいろ話し合いはなされておりますけれども、気運がまだ高まっていないと判断いたしております。まず、できる部分から身の丈にあった整備を行うのがいいのじゃないかと思っております。優先すべきは、ハードの前段ソフト事業になろうかと思います。 最近、当地域は、自動車生産150万台計画エリアに入りまして、自動車産業、半導体産業集積基地として、いろんな可能性を秘めておるわけですが、宇島駅前もやり方次第では、大いに、今から発展の可能性があると思っておりますので、点在する空地・民地を利用して民間活力を導入するとか、優良住宅の造成、衣食住近接、賑わい、利便、安心、安全のまちづくりを目指して、お互いが頑張っていかなければならないと思っております。 それから、宇島駅関係の利用客につきましては、まずは、利用客を増やすということが大前提になろうかと思っております。 それから、高速道路の関係でございますが、午前中、山本議員さんから質問がございましたが、今回、高速道路ができたときのインターの付近を、どのように考えているかということのお尋ねでございます。東九州自動車道、椎田南インターチェンジから宇佐インターチェンジの間は、昨年2月10日、国土交通大臣より施工に認可を頂き、3月31日に西日本高速道路株式会社で、この区間は事業を実施するということが決まりました。 豊前市域におきましては、大西の東側の久路土付近になるわけですけれど、豊前インターチェンジ、これは仮称でございます。これが計画されております。 東九州自動車道築上町から、宇佐市間28.3kmにつきましては、計画では、平成28年度の竣工でございますが、福岡県知事、大分県知事ともに2年前倒しして、平成26年までに供用開始をと言われておりますので、我々も26年までには是非ともということで頑張っているところでございます。 お尋ねのインターチェンジ付近の将来像でございますけれど、都市計画マスタープランにおきまして、豊前インターチェンジから国道10号線までの間、これは1130mございますが、この道路は、将来は県道になる予定ですけれども、現在は、宇島・久路土線の予定でございますけれど、この付近は、豊前市の新しい顔づくりゾーンというふうに位置付けをしております。新産業予定地として、新たな豊前の玄関口として整備推進する、豊前をアピールする産業の検討、展開、各種産業が展開できる用地の確保など、長期的な視点に立ち、高速道路供用開始、平成26年までに、将来計画を明らかにして、都市計画の用途指定等を行いたいというふうに考えております。 また、インターチェンジから、南側のアクセス道路の件ですけれども、こちらは山内付近までは、ほ場整備事業で、福岡県で道路用地創設、穴あけと言いますけれども、創設しております。南部地域には、求菩堤山をはじめ素晴らしい自然や文化財が豊富にございます。将来は、豊前・耶馬渓線というアクセスの可能性も秘めております。 観光地への誘導路、県境越えの道路としても、非常に重要な位置を占めますので、今後県等にお願いして、アクセス道路の整備をしていきたい。豊前インターチェンジの名称もできれば観光誘発の意味で、ぶぜん・くぼてインターチェンジなどとして、観光入り込み客の増加につなげてまいりたいと思います。 豊前市は、海あり、山あり、平野あり、遊・食・自然の里にふさわしく様々な潜在能力を有しております。整備のいかんでは、将来の展望が大きく開ける可能性がございますので、一層、民・官・一体関係機関、横断的な取り組みによりまして、振興を図っていきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 総務課長。 ○総務課長 相本義親君 村田議員の女性のネットワークの件で、豊前市の活性化に向けて、女性の活力ある方々の個性を生かした場の提供は出来ないかという、ご質問でございますが、まず、市長も答弁しましたように、こういった問題で大切なのは、私ども行政に携わるものの意識改革が遅れているということを、まず反省しなければならないのではないかと考えております。 そういった意識改革をしながら、具体的に、今後21世紀を迎えまして、特に、今日、食の安全や健康の問題、或いは、環境への関心等々が高まる中で、市の活性化を図るためには、男女を問わず1人ひとりが持てる能力を十分に発揮していくことが、一層求められているわけでございます。 しかし、豊前市は、農林・漁業とこういった産業が伝統的に続く地域でございまして、性別による役割意識も一方で強うございまして、議員ご指摘のように、女性の役割や能力が適正に評価されていない。或いは、地域での諸活動への参画へ、なかなか進まないといった現象がみられているところでございます。私どももはじめ男女を問わず、こういった問題を解決するためには、意識の改革と女性の積極的登用が重要であろうと考える次第でございます。こういった女性のパワーを更に生かしていくことが、議員ご指摘のとおり、今後の市の活性化につながると、私ども確信しているところでございます。 議員が申しましたように、女性のネットワークがないのではないかと。話し合える場を考えて頂きたいという要望でございますが、この要望につきましては、平成18年1月に豊前市男女共同参画審議会の役員から、このセンター設置の要望を頂いております。 私どもとしましても、教育委員会社会教育課と緊密に連携を取りながら、今後このような要望をどのような形で反映していくのか、考えていきたいと考えております。 また、活動拠点の要望につきましては、具体的に市民会館等を、そういう場に提供して頂けないかというご提言も頂いていますので、管理をいたします教育委員会社会教育課と綿密に協議を進めまして、早い時期に議員の期待に応えるよう、前進を図っていきたい決意でございますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 学校教育課長。 ○学校教育課長 鈴木正博君 議員のお尋ねの親子方式の給食についての経緯についてございますけれども、ちょうど1年前に18年度の第1回議会の中で、豊前市行政改革大綱というのを発表しました。 その中で、自主性・自立性の高い財政運営の確保ということで、7項目目にあるわけでございますけれども、その中に、学校教育課としまして2項目の事項があります。 1つは、小・中学校の統廃合を推進しますという件と、それから、10番目に、学校給食については、親子方式を検討しますという件があります。それとともに、集中改革プランというのが発表されております。その中で、それぞれ学校の統廃合と学校給食については、スケジュールが立てられております。統廃合については、一応21年度まで、向こう5年間は検討しますということになっております。 それから、学校給食については、21年度に実施しますという計画になっております。 こういう計画を立てた以上は、はっきり言って各課でできるかどうか検討しながら進めていくというのが、現在のそれぞれ自治体で行われている計画の進行と言いますか、進め方でございますから、当然、学校給食は、学校教育課としては、学校給食を、どういう具合に進めていくかというのは、検討するに値する項目だと思いますし、所属長会議の中でも推進するようにと言われております。それで学校教育としましては、親子方式、拠点方式を検討しながら説明会をしたわけであります。それが経緯でございます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 福祉事務所長。 ○福祉事務所長 入船 正君 すこやか赤ちゃん出産祝金の現金化、それに伴う祝金の支給期限の延長につきましては、明日の委員会でご審議頂くということで、答弁を控えさせて頂きます。 それでは、少人数の学校の学童保育の設置について、お答えします。放課後学童クラブ設置につきましては、国の放課後児童健全育成事業実施要綱の補助基準及び豊前市放課後児童クラブ事業設置要綱に基づきまして、児童数等の要件を満たした段階で実施しております。要件を満たさない上での市単独の設置は、現状では厳しいと考えております。 続きまして、就学児を含めた第3子目の保育料の無料化について、お答えします。 村田議員から、度々ご提案を頂いております就学児を含めた第3子の保育料の無料化について、現在の在籍児から試算してみました。今、市内10園の在籍児が約925名です。 就学児を含めた第3子以降の対象児が132名です。この132名の月額の保育料が、月平均1万8744円のトータルで、247万4000円になります。この年間12ヵ月で2968万8000円となります。国の徴収基準外の市の持ち出し分、約6531万2000円を加えますと、約9500万円ということになります。これに保育所の運営費7億821万8000円の市の負担分、1億1652万9000円を加えますと、市の負担分トータルは2億1152万9000円となります。この関係につきましても、市の現状から厳しいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 初めに、今、古川議員さんから、ご注意がございました。また、副議長からもご注意頂くところでございましたけれども、一応、案としてあがっておりましたので、私は詳しく聞こうとは思いませんでしたけれども、これも持続していくために必要なことだと思いましたので、質問事項の中に入れさせて頂きました。 では、初めに、宇島駅のエレベーターの件ですけれども、3500人ぐらいから4000人ぐらいの間ということでございますが、この条件に合わないからできないというんじゃなくて、高齢化が進んでるバリアフリー化を考えたときには、よく話し合って、このエレベーターを付ける必要性というのは、十分にあるのではないかと思います。 高齢者の大変さというのは、なってみなければ分からない。また、危険が伴っているということを絶対に忘れてはならないと思うんです。折尾の駅もそうでしたけれども、折尾の駅は若い方たちも沢山、大学もございますので、いらっしゃいますが、豊前市の場合は高齢者がたくさんいらっしゃいます。やはり、そういう面から考えたときに、せめてトップのほうまで行くぐらいの思いで気張って頂けないでしょうかね。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 お答えいたします。現在、JRのほうに確認いたしましたところ、5000人以下の駅のバリアフリー化は5000人以上整備しておりまして、それが終わった23年度から検討したいということで、その内容については、現在、白紙の状態だというお答えを頂いています。そういう状況でございまして、それを単独で豊前市ができるかどうかというのは、非常に財政的な負担もあるのではないかと考えております。それについては、また上司と相談して検討してみたいと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 23年度といったら私もちょうど・・歳ぐらいになりますので、本当に今、大変な思いをしていらっしゃる方たちの気持がよく分かると思います。本当に時々言われてというんじゃなく、そういう話合いを今、白紙の状態であるかもしれないけれども、話合いの中にもっていくということは忘れないで頂きたいと思います。よろしいでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 それにつきましては、今後、JRと、もう少し詳しい中身の協議をしていって、また上司と相談して対応を考えてみたいと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 疑似体験をしてください。課長は、まだ随分お若いですので、助役さんも、市長さんも60歳過ぎたお年の中で、やはり何かを感じるのではないかと思いますし、財務課長といたしまして、いろんな分野にまたがってまいりますので、お年を召した方、体の悪い方、そして病気を持った方、いろんな面で人の心がよく分かるのではないかと思いますので、1人でも結構ですから、少し重たいものをつけて歩いてみてください。 今日、お昼休みにちょっと話をしましたけれども、その中で人の心の分かる、若い課長が折角できたんですから、そういう所も日本一、長い橋も寒いときに行き、そして、はじまったばかりの、たくさん待たなければいけない条件の悪いときに行き、いいときばかり行くのじゃなくて、課長の仕事として、ひどい思いもしてみることも大事なことではないか。人の心の分かる課長で、何時までもいて頂きたいと思いますので、そういう疑似体験も1度やってみてください。私も60歳を迎えて、あの階段が本当に大変な思いをなさっているなというのが、僅かに分かるようになりましたので、なってみなければ、なかなか分かりませんので、駅の危険度ということも考え合わせた上で、疑似体験を望みます。 一度やってみては如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長、答弁。 ○財務課長 池田直明君 お答えします。今度、実際に体験してみます。以上です。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 生意気なことを言ってすみませんけれども、やってみてください。そして、宇島・三毛門・松江と豊前市には、3つの駅がございますが、駐輪場等、広場、いろんな面で利用しているということでございますが、この3つの駅の中に、豊前市を見せるものがないのではないでしょうか。駅に行ったときに駅があるだけ、工場があるだけ、という感じのようにしか見えませんが、私が言うのは、この利用価値という中に宣伝を入れては如何かと思うんですが、如何でしょうか。 ○副議長 中村勇希君 財務課長。 ○財務課長 池田直明君 先ほど、都市計画課長から説明がございましたが、駅裏の臨海工業線の整備が2、3年後に整うということでありまして、この駅裏の開発につきましては、現在、その駅と道路の間に開発公社が用地等抱えております。今後この道路の整備に合わせて、工法も検討していかなければならない時期に来ているという中で、議員が先ほど提案されていました看板等の設置も、この中で検討していく課題だと考えております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 駅から見えるというんじゃなく、駅から勿論、見えなければなりませんが、駅からとともに電車の中から見えるぐらいな奇抜なというか、本当に豊前市にこんな素晴らしいのがあるんですよ、ということが分かるような、そういう宣伝をして頂きたいと思います。 商工観光課長、お願いします。 ○副議長 中村勇希君 市長、答弁。 ○市長 釜井健介君 これは、はっきり申しまして三毛門駅は、かぼちゃ、そして、日本で初めての消防団の事務所も併設していますから、便所もよくしました。宇島駅は、近々、豊前の出身者であります倫理研究所の丸山先生の立て札を建てようと思います。それと天狗の湯の関係のプラットホームがありませんので、少しうらぶれているけれども、少し綺麗にしていきたいなと思います。問題は、豊前松江なんですけれども、今ご相談しているのが、この駅は古い材料で、三毛門は豊前市のものですが、豊前松江はJRのものですよ。でありますので今の駅を、もうちょっと品をよくしてやってみようかなと。そこは松江・角田の人と相談して、おこしかけのブランチ地点というのはどうかなと。おこしかけの地点は本当は角田なんですよ。今の道の駅は、ちょっと離れている所でございますし、そういうご相談も今少ししております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 JRの場合は、JRに使用料とかは、いるんですか。 ○副議長 中村勇希君 助役、答弁。 ○助役 渡邊賢二君 JRの所有地については使用料はいります。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 では、3駅がございますので、しっかりと、この豊前を外の人に見せる戦いをして頂きたいと思います。そして、本当に市の職員の意識改革を、という素晴らしい市長の答弁をお伺いいたしましたので、本当に心を入れ直して頑張って頂きたいと思います。 時間がどんどん過ぎてしまっていました。 まず、私が一番聞きたいのは、学校教育のことなんですが、やはり給食の件もそうですけれども、P連のほうとしっかり話合ができてなかったということに、大きな問題があったのではないでしょうか。実施する以上は、そういうところの話合をしっかりしながら行って頂きたいと思います。昨日の話では、まだしないんですよね。教育長の話では、当分ということでしたけれども。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 昨日、お話しましたように暫くは棚上げにしたいと考えています。経緯は、先ほど課長から申しましたが、教育委員会側の説明資料が不十分であったということは、教育委員会としても大きく反省しております。現在、市P連から4項目にわたりまして質問状と言いましょうか、こういったことについて、データーを詳しく出して説明してくださいという要望があがっております。昨日も申しましたように、吉富町との合併問題も控えていますので、ここ1年ぐらいは、その合併状況を勘案して棚上げにしておきたいと考えて、また近いうちに教育委員会といたしまして、或いは、市としての回答を市P連のほうにしたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 本当に学校教育ですから、本当に慎重に言葉1つにしても、しっかりと慎重に皆さんを騒がせることのないような中で、1つひとつ行なって頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 さっき通告では抜かしてしまったんですが、総合教育の場において、子ども達の小さいときから、男女共同参画のあり方を教えていく気持はございますでしょうか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 このことは学校の教育課程の中で、国語の勉強からずっとありまして、道徳の時間もあります。その他に総合的な学習時間もあって、高学年になりますと、家庭科の教育の中でそういった家庭のあり方なども勉強もいたしますし、道徳の時間で、男女共同のことについても学習いたします。あらゆる学校の教育課程の中で、男女共同参画だけの教科はありませんが、いろいろな教科や領域の中で、いわゆる人権を含んでいる男女共同を含めまして学習、或いは、教育をしていきたいと考えております。 教室の中が、男女一緒になるということも、ずっと以前はなかった時代もありましたが、男女が一緒に生活している中で、お互いが助け合うということを学んでいると思いますが、より一層そのことについて、学校には話しをし、指導していきたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 男女共同参画を1つ間違えると、大変な世の中になると私は思っております。 1人の人間として生きていく権利を主張していくということは、大変大切なことであると思います。また、女性が働くようになってからは、なおさらでございます。以前にも何度も言っておりますけれども、先生方にも統一した中での子ども達に指導する。そして、1人の人間としての主張の権利の中には、本当に責任があるんだということを、社会を担っている僕達なんだ、私達なんだということを、心の中においていけるような指導をして頂きたいと思います。やはり次の時代をつなぐ子ども達の育成でございます。 また、今、核家族化が進んでいますので、生まれて死ぬという、そういう子ども達が一番大事な知らないところがございます。その中で尊んでいく、尊敬していく、そして、また感謝していく、そういうことを先生達が統一した中で教えて頂きたいと思っております。 時間がなかなかありませんので、あれですけれど、もう1つ感じたことは、誉め上手になって頂きたいと思います。教育長さん、市長さん、特に、豊前市の最高峰にいらっしゃる方です。子どもさん達が素晴らしいときは、本当に誉めて頂きたい。誉め条例をつくって頂きたいと思うぐらいな気持でございますが、如何でしょうか。この前の子ども天狗の時の子どものいきいきとした目を見て如何だったでしょうか。教育長さん。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 子どもに限らず、大人も誉められると嬉しいわけですよ。やる気が出るわけですよ。 そういう点では、北風を吹かせるよりも太陽政策でいきたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 是非、これから素晴らしいことに出会ったときは、誉めてあげて頂きたいと思います。 誉めることによって、叱ることができると思います。叱ることは虐待ではないと思います 本当に、その子どものことを考えたときには親はしっかり叱ります。近所の方もしっかり 叱ります。特に、そういうことについて、長として気をつけて頂きたいと思います。 いっぱい聞かないといけないことが残ってしまいましたが、これで終わります。 ○副議長 中村勇希君 村田喜代子議員の質問を終わります。 これより関連質問に入ります。関連質問は1人答弁を含め10分以内であります。 関連質問の方はございませんか。尾家啓介議員。 ○14番 尾家啓介君 学校教育に関連して質問させて頂きます。先日、報道で給食費の未納・滞納の問題が報じられていましたが、その総額の6割は、責任感と社会規範を守る意識の欠如だと報じられています。そこで教育長に質問ですけれど、教育現場、先生と保護者と児童・生徒それぞれの立場で、責任感と社会規範を守ろうとする意識が低下しているのじゃないかと思いますが、ご意見はどうですか。 ○副議長 中村勇希君 教育長、答弁。 ○教育長 森重高岑君 何処を基準にして、社会規範意識が低下しているか、人それぞれによって違うと思いますが、押しなべて、大人も子どもも人間力というものが、だんだん低下してきているなということは感じます。その人間力の中には、そういった規範意識も当然入っていると私は考えております。 ○副議長 中村勇希君 尾家議員。 ○14番 尾家啓介君 先ほど、学校教育課長が豊前市は幸いいじめがないと発言しました。これは喜ばしいことですが、けれど元気のあり過ぎる児童・生徒は何処の学校にもおるんですよ。 けれど学校の現場が、責任感と規範意識がピシッとしている現場での元気のあり過ぎる生徒と、社会規範と責任感が多少低下している所での元気のよ過ぎる生徒は、ちょっととらえ方が違うと思うけれど、教育長、その辺どうお考えですか。 ○副議長 中村勇希君 教育長。 ○教育長 森重高岑君 確か午前中だったと思いますが、問題行動についての文部科学省の指導があったという話をさせて頂きました。その中には、出席停止、生徒の取り扱い、或いは、体罰について、或いは、児童・生徒の問題行動の指導という大きな3つのことを申し上げましたが、その中に、先日の校長会では文書を示して、学校の中で研究・協議をして、そのことを地域や保護者、或いは、子どもにも伝える、公表するということを通して、今まで曖昧であった例えば、体罰に関する考え方の違いなども公表して、お互いに教職員も子どもも、或いは、保護者も地域の方も理解していくということで、だんだん規範意識が高まってくるのじゃなかろうかと考えております。 ○副議長 中村勇希君 尾家議員。 ○14番 尾家啓介君 表に現れたいじめじゃなく隠れたいじめ。今から起きるであろういじめの予防まで含めて、いろんな気を配って学校教育をして頂きたいと思います。以上、終わります。 ○副議長 中村勇希君 尾澤満治議員。 ○1番 尾澤満治君 村田議員の豊前市の活性化についての関連質問をいたします。豊前市に安心して住まれる住宅政策ということで、今日は新聞の広告で、保留地の分譲中という見出しが入っておりました。素晴らしいなと私は感心いたしましたが、これについて、どのくらいの地域で何万部、予算的には、どのくらい入れられたのか、都市計画課長、答弁をお願いします。 ○副議長 中村勇希君 都市計画課長。 ○都市計画課長 竹本 豊君 今回は、赤熊区画整理事業が、ほぼ面工事が終わりましたので、その関連。それと財務課の所管の点在する市有地の両面で、表が赤熊南、裏がその他の土地ということで、今朝、広告が入っていたと思います。エリアとしましては、行橋、中津の一部、豊前・築上ということで、7万2000部ぐらいをとりあえず今回、入れさせて頂いて反応を見ようということで考えております。 豊前市内で、既に一部保留地の分譲をしておりますが、やはり市外から住んで頂くというのが、区画整理事業の目的でございますので、やはり行橋とか、周辺の方々にPRして住んで頂こうと、人口増にもつながりますし、また先ほどの駅の利用客の増とか、そういったことにもつながってきますので、今後も引き続き2段、3段ということで売っていきたいと思っております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○1番 尾澤満治君 素晴らしいことだと思いますが、これで先着分と公開抽選分という形がありますが、これでずるずるいってもあれだと思うので、短時間にたくさんの方が入って頂くという形でしていかなければいけないと。特に、若い人なんかも金額的にかなり高いと思いますが、できましたら、民間並みに分譲期間を決めてもらって、そして、土曜、日曜日のほうが、この火曜日に入れたというのが、僕は思うんですけれど、火曜日のほうが入りやすいと、安く入れるというのが考え方なんですけれど、金曜日とか週末に入れて貰って、そして、例えば1回でも分譲という形で職員が入っていって、オープンするような形で真剣に取り組むことが出来ないのか、お伺いします。 ○副議長 中村勇希君 都市計画課長。 ○都市計画課長 竹本 豊君 今日、入れたのは、週末は非常に他の公告がものすごく、遊戯関係とか商店街関係が入りますので、目立つと言ったらおかしいのですけれど、少ないときに入れようということで入れたのが本日になりました。それから、今後の計画ですけれども、とりあえず新聞折込をして、インターネットの発信をしたり、あらゆる機会を捉えて、例えば、医師会の役員会があったときには、病院等にお願いするとか、現実に歯医者さん等にもしておりますし、そういったことで、いよいよ行き詰った段階では、開発のデベロッパーあたりにも声をかけて、できれば2年、3年のうちに完売したいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○1番 尾澤満治君 1点あるのは、民間から見ると処分価格と書いているんですよ。行政から言ったら処分価格でしょうけれど、民間から見たら分譲価格とか書かないといけないので、処分価格というと何か誤解を招くような言葉じゃないかと思うので、そこのところは処分価格と書かないといけないのかなと思いますが如何ですか。 ○副議長 中村勇希君 都市計画課長。 ○都市計画課長 武本 豊君 これは国庫補助金、それから地元の皆さんの資金も入っておりますし、都市区画整理事業という一定の補助事業によって整備しておりますので、一応、処理の段階では、そういう表現でしていくと。それで民間の土地が、その中に結構ございますので、そういったものは価格にしても、販売の時期にしても、それは自由でございますので、保留地の市が所管をする土地については、そういう表現になっておるわけであります。 ○副議長 中村勇希君 尾澤議員。 ○1番 尾澤満治君 できましたら早くPRしながら、全部合わせると3億円以上のお金が入ってくるということで、財政面でもかなり楽になるし、他の固定資産税とか、いろんな税金も入ってきますので、これは真剣に早くする形で、今度は県営住宅も出来上がりますので、その後ではなかなか難しいじゃないかと私は思いますので、早くと。 市長、最後に、こういう形で、宮崎県の東国原知事じゃないんですけれど、豊前市も自動車産業が入ってきていますし、皆さんが注目されている地域だと思うので、どうにかPR隊というか、豊前市だというアピールできるような営業センスを持ちながら、やっていかないといけないのじゃないかなと思いますが、日曜日にも出て、早く売るのだというパフォーマンスするなり、そういう形で市長の見解を、企業もかなりこちらに誘致を考えている所もあるので、市長自ら率先して、中央に行ってPRという形でできるような形ができないか聞きたいと思います。よろしくお願いします。 ○副議長 中村勇希君 市長。 ○市長 釜井健介君 新北九州空港に、今、豊前街道という店を出しております。そこに新人職員を去年の4月に、道の駅にも勉強に行かせ、また、新北九州空港の店員にもさせまして、皆が俺の分野はどんな分野もするんだと。仕事はどんなことでもやるんだ、というふうにしなければならないし、そのために私が先頭に立って頑張りたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 他にありませんか。山崎廣美議員。 ○2番 山崎廣美君 山本章一郎議員の中山間地の活性化について、ということの項目の中で、環境・農地・水・環境保全対策、今回、取り組むことになっておりますが、当然、中山間地での今までの取り組みは中山間地事業があります。それと、平坦部の対策についての窓口が、区長さんということに話を聞いておりますが、これからの説明会なり取り組み、調整をどのようにやっていくのか、農林水産課長に、お伺いしたいと思います。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 大坪 勝君 この農地・水・環境保全向上対策ということですけれども、この事業につきましては、ご承知のとおり農林水産省におきまして、19年度からの新規事業でございまして、300億円という予算取りをしたという報道が出されていると思います。現在、これの取り組みにつきましては、昨年2月、農業者を対象として、最初に地域座談会、約140箇所の地域座談会において、この事業の取り組みが19年度からありますよ、ということで説明会を行いました。 その時点におきましては、農林水産省といたしまして、要綱等の整備がなされておりませんで、その折に県からは8月頃には要綱ができるということで、その時点で昨年の8月頃に、説明会を要綱ができ次第、皆様方にお知らせしたいということで考えておりましたが、今年1月9日に、農林水産省におきまして、国からの説明会に私も参加いたしましたけれども、その時点に初めて要綱の説明、取り組みの説明ということで、これはJAさん、市協賛で、生産組合長に説明。また、この事業につきましては、非農家の方も参加型ということで、今までの農地については、農業者ということでしたけれども、非農家の方も参加型ということですので、区長会長さん並びに地域の区長会の会議に出席させて頂きまして、この旨の説明をさせて頂きました。 それから、2月につきましては、農業の地域座談会におきまして説明会を行いまして、今後の取り組みを行っていきたいというふうに思っております。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○2番 山崎廣美君 一応、この対策については窓口と言いますか、当然、集落の中で区長が窓口ですか、それとも生産組合長が窓口ですか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 大坪 勝君 それには区長であろうとも、生産組合長であろうとも、その会議の中で代表者を募って頂くということですので、区長でも生産組合長、それ以外の方でもかまいません。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○2番 山崎廣美君 それじゃ、当然、それは、今の各地区で営農組合なり組織があります。それがない所は区長、もしくは生産組合長、営農組合がある所は営農組合という形の中でいけれるということですね。後ですね、当然、これは新しい事業ですので、農業者だけでなく、一般を巻き込んだ中で、その地域の活性化、いろんなものを皆さんでまとまってやろうというのが、1つの目的ですね。ただ、今、非常に厳しい農業情勢の中で、いろんな面で田んぼや畑が荒れたり、河川もそうですが、いろんな道路愛護的なものにも使われるし、幅広くこの事業は使えると思います。但し、中山間地については、今まで中山間地事業の中で5項目使われていましたので、それ以外の項目ということで、それ以外の項目でないと、この対策には該当しないということですので、なお一層、中山間地については、その以外の品目を設定しないと、反当4200円貰えないということだろうと思います。 だから、当然、考えて頂きたいのは、農業委員会もそうでしょうが、前回、廃田の調査をやったということの中で、今シルバーも不足しております。折角のいい事業ですので、この事業を有利に使って頂いて、当然、未整備でもあります。ほ場整備でもありますので豊前市が全体で取り組むようなシステムづくりを、行政の方から指導するべきだろうというふうに思っております。そこはどういうふうに考えておりますか。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 大坪 勝君 豊前市におきましては、まず、その事業の連絡網という形で考えております。 事務局といたしましては、農林水産課、建設課ということで双方で組織化しております。 その中で各課横断的な事業になりますので、議員が申されましたとおり農林水産課、建設課、農業委員会ということで、職員対応をやっていくということで、今、地区別の班の構成をして6班をつくっております。そして、一通りの説明会を終わっておりますが、まだ細部にわたって質問等で出席して頂きたいという地域要請がありましたら、その地区の班が、夜、土、日でも出向いて、説明会を行うということで行っております。 ○副議長 中村勇希君 山崎議員。 ○2番 山崎廣美君 但し、私が心配するのが、集落座談会の中の農家の声の中で、なかなかできにくいという面があったんですね。面積が何ヘクタール以上とか、その全体を取り組んだ内容ですので、そこはもう少し、そういう各組織を通じて説明会をやりながら、折角、今、厳しい農業情勢の中で、国がそういう事業を立ち上げて頂いたので、利用できる所は利用すると。貰えるものは貰うというような今からの農業施策をやっていかないと、当然、これは豊前市の第1次産業でございますので、農林水産業の見直しを当然やっていくという市長の声もありましたが、だから、そこは集落が中心になりますが、行政が力を入れて頂いて、主導型ということでやって頂きたいなと思っております。以上です。 ○副議長 中村勇希君 他にございませんか。村田喜代子議員。 ○5番 村田喜代子君 山本章一郎議員の中山間地活性化についての高齢化・少子化の現状と対策ということで、高齢化のことで、卜仙の郷、求菩提の付近を、そぞろ歩きするような対策とかの考えは全くないんですかね。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 大坪 勝君 卜仙の郷につきましては、農林水産課が担当ということで答弁させて頂きますが、卜仙の中には理事会というのがございます。その中で卜仙を中心とした散策、それと減反の時に景観としてヒマワリを植えたと、そういうものを散策して持ち帰ってもらおうとか、いろんな都市交流型の事業ですね。前回では2月24日ですか、3日間中心にして温泉祭りとか呼びかけをしております。また、地域のお年寄りが頑張って頂きまして、シャクナゲ祭りとか、壮年会と合流のですね。それと山の手、そういう組織の方が、いろんな農業体験もできるような形も生み出して、農産物の販売等も行ないながら、高齢者も頑張っております。また、それ等については支援をしていきたいと考えております。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 これが中山間層に当たるわけですね。この散歩道の中に、女性のいろんな特色を持った方たちが、何かお店とか、仕事を出したいという中には入らないわけですね。 岩屋、合河の人達でなければ参加ができないですよね。この今の話は。 ○副議長 中村勇希君 農林水産課長。 ○農林水産課長 大坪 勝君 その中山間地域の中に、合河に薬草グループというグループがございます。その方々は合河・岩屋だけでなく、いろんな方が参加して一緒に作業をされて、下の方と交流をもちながらという形の仕事もしていますし、そういうことで幅広く参加されています。 また、山の手展ということで祭りがございましたけれども、そのときも遊び工房におきましては、下の方が織物を持ってきたり、装飾を持ってきて販売したり、そういうふうに交流型で活用して、地域の活性化につながるという考え方をもって事業を行ってます。 ○副議長 中村勇希君 村田議員。 ○5番 村田喜代子君 分かりました。そういう方達がたくさんいらっしゃいますので、また、その時は、ご相談にまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ○副議長 中村勇希君 他にございませんか。 (「なし」の声あり) それでは、これをもって今定例会の一般質問を終わります。 日程第2 議案第1号から議案第53号までを一括議題といたします。 議案に対する質疑に入りますが、今回は質疑の通告がありません。よって、これをもって質疑を終わります。 只今議題となっております議案第5号から、議案第21号まで及び議案第36号から、議案第51号まで33件を、お手元に配布の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 議案第1号から議案第4号まで及び議案第53号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。よって、本5件については委員会付託を省略いたします。 お諮りいたします。本日の日程は、これですべて終了いたしましたので、これにて散会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 散会 14時25分 |